兵庫慎司の『思い出話を始めたらおしまい』
第九話:有頂天と筋肉少女帯と人生を、リアルタイムで観れてよかった(前編)
月2回連載
第17回
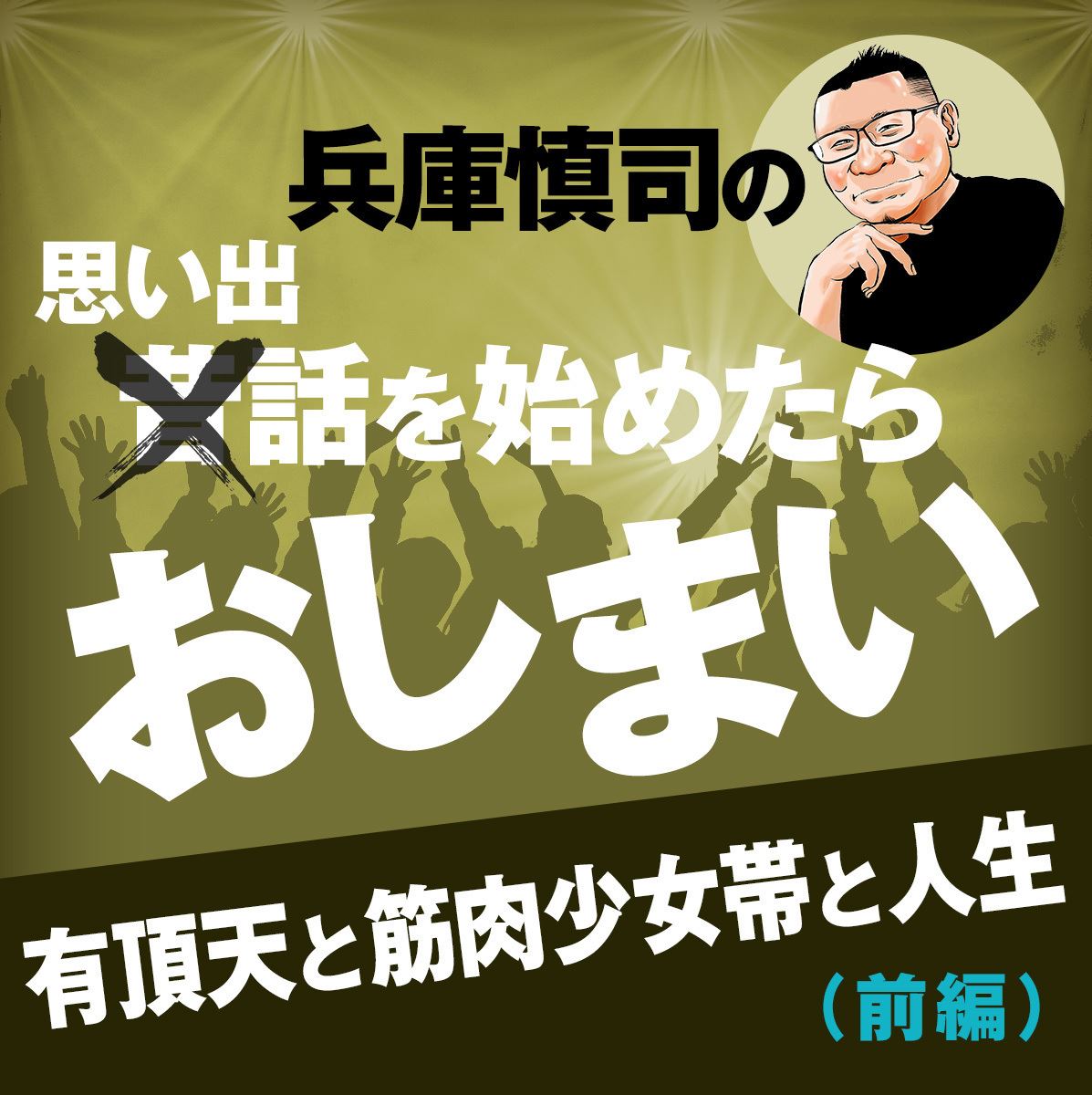
illustration:ハロルド作石
有頂天、筋肉少女帯、人生。
の、ナゴムレコードの3バンドのライブを、1980年代にリアルタイムで観ることができてよかった。と、後に何度も思ったし、今でもそう思っている。
有頂天はそうでもないが、筋肉少女帯は、後にインタビューやライブレポで、何度も仕事をすることになったし。つい最近も、このぴあ音楽で、
大槻ケンヂ×燃え殻の対談という仕事を振っていただきました。
人生の卓球と畳三郎が始めた次のバンド=電気グルーヴも然り、いや、それ以上に、仕事で関われる機会が多いし、長年にわたって。
このぴあ音楽でも、ライブレポート何度かと、「電気がフジロックを語る」という企画インタビューで、お世話になっている。
有頂天は高校生の時に広島ウッディ・ストリートで、筋肉少女帯と人生は大学生の時に京都BIG BANGで観た。今調べたら、有頂天は1986年5月13日で、筋肉少女帯と人生は1987年12月27日だったようである。
で。この二回のライブを観るきっかけを作ってくれた人がいた。「人」って何よ。いや、友達と言うほど近しくはなかったし、知人というほど遠くもなかったので、書きようが難しいのだ。ライブ一回だけだけど、一緒にバンドもやったし……そうか、じゃあ「バンド仲間」でいいのか。
そのバンド仲間は、僕と同学年だが、帰国子女で1年ずれたかなんかで、歳は1コ上の女の子である。高2の時、スタジオレンタルスズヤにたむろしている者同士として知り合った。スズヤのことは、この連載の第四話、「16歳の時に19歳の奥田民生を観た」の回で書いているので、ご存じない方はそちらをご参照ください。
当時僕は、頼まれるがままに、市内のあちこちの高校生のコピー・バンドでドラムを叩いていたが、内心は焦っていた。
周囲には、同じ歳で、つまり高校生で、オリジナル曲をやっていて、本気で活動しているバンドが、いくつもいた。市内の楽器店ふたつ(木定楽器とヤマハ)がそれぞれ年イチで開催する高校生のバンドコンテストの、決勝の常連になっているバンドもいたし、高校生なのに広島ウッディ・ストリートに出演できているバンドもいた。
CBSソニーのスカウトにひっかかって、育成バンドになっているバンドまでいた。これが、後にTHE STREET BEATSでプロになり(バンドがデビューする時に脱退したが、2年後に再加入)、POTSHOTやROCKN’ ROLL GYPSIES等を経て、現在JUN SKY WALKER(S)のサポートをしている市川勝也が、ベースを弾いていたバンドです。BRIXIONというバンドでした。
まずい。人に頼まれてコピーばっかりやってる場合じゃない。オリジナル曲で活躍できる、コンテストで勝てるし、ウッディにも出られるバンドを作らなければ。でも俺、曲、書けない。書けそうで、歌えそうな人、いないかしら。
という時に、僕が目をつけたのが、彼女だったのだ。その段階では、曲を書けるかどうか知らなかったし、バンドを熱心にやっている人ではなかったし、そもそも彼女の歌を聴いたことがあったかどうかも、今となっては記憶があやふやだ。
が、何か、「この人、いけそうな気がする」と感じたのだった。帰国子女で英語ペラペラだったのと、ちゃんと売りになるルックスだ、と思えたのも大きい。って、こういうのも今はもう怒られるんだろうな、ルッキズムとかで。
というわけで声をかけたら、乗り気になってくれたので、ギターとベースとキーボードを集めて、バンドにした。で、まずはコピーから、と、曲を決めた。当時大人気だった、シンディ・ローパーのファースト・アルバムから4曲と、奥田民生がやっていたバンド、READYの「PLEASE」という曲。で、スタジオに入ってみたら、彼女は歌える人だった。やはり。
そして、前述の市川勝也のBRIXIONが、市内の大きなホール(広島市青少年センター)を借りて、バンドがいっぱい出るイベントを打つというので、そこに入れてもらって、初ライブも決まった。
しかし。そのライブへ向けての何度目かの練習を、彼女がすっぽかしたのだ。理由は、美容院が混んでいたから。それにブチキレた僕は、「そんな奴と真剣にバンドやるのは無理」と、そのライブ一回きりで解散を決めてしまった。
そんなに怒らんでも。そりゃあ当時の美容院、予約していようが、平気で時間、押したりするよ。でもそこでキャンセルできないよ、高校生が。許してやんなさいよ。と、今になると思います。
そのようにして解散した後だったか、解散する前だったか忘れたが、彼女が「有頂天が広島に来る、観に行こう」と言い出した。
音楽雑誌の記事などで、有頂天のことも、ナゴムレコードのことも知っていたが、音は聴いたことがない。と言うと、当時出たばかりだった『BECAUSE』という作品を貸してくれた。ナゴムレコードではなく、宝島が立ち上げたキャプテン・レコードからリリースされた、黄色いデザインのやつである。
レコードではなく、もちろんCDでもなく(CDが本格的に普及し始めるのはこの2年後くらい)、カセットブックという形式だった。カセットテープに8曲入っていて、各曲の歌詞や、クレジットや、しりあがり寿が描いた『ピノキオ』というマンガが載った、ちっちゃい本が付いている。
聴いてびっくりした。こんなに意味がわからない歌詞、初めて。歌じゃなくてセリフが延々と演奏に乗っかっている曲もあるし、そもそも曲の構成も、イントロ→A→B→サビ、とかじゃなくて、次はどう展開するのかわからない。という、謎すぎる音楽でありながら、基本はちゃんと歌もので、ポップでもある。
混乱した。でも夢中になった。なんせ聴いたことがなかったので、こんな音楽は。テクノかな、ニューウェイヴかな、とも思ったが、それまで自分が知っていたテクノともニューウェイヴとも違ったし。
あと、しりあがり寿のマンガを読んだのも、この時が初めてだったかもしれない。なんで「ピノキオ」なのかというと、『BECAUSE』の4曲目に「ピノキオ」という曲が入っているからなのだが、『北斗の拳』のパロディで「ピノキオ」を描いたもので、これも衝撃的におもしろかった。というか、有頂天と同じで、こんなマンガ、読んだことがなかった。
そんなわけで、チケットを買い、ウッディ・ストリートで有頂天のライブを観た。日にちを鑑みるに、彼女と僕のバンドは、その時点では間違いなく解散した後だ。キレて辞めたのに、よく一緒に観たな。それぐらい、有頂天を観たい気持ちになっていたんでしょうね、僕は。『BECAUSE』を繰り返し聴くうちに。
で。ライブも衝撃的に良かった。演劇的な表情や動きをふんだんに取り入れた、ケラのパフォーマンスが、まず斬新に感じたし、メンバーもそれぞれキャラが立っていてかっこいい。
ギター:ハッカイとコウ、ベース:クボブリュ、ドラム:ジン、キーボード:ミュー、そしてケラの6人だった頃である。おお。何も見ずにメンバー全員の名前を書けた。というので思い出したが、こういう、バンドにまつわるメンバー名とかの情報を、好きなバンドも、そこそこ好きぐらいのバンドも含めて、やたらと暗記していた、当時の自分は。
音楽の情報を活字で得るのが好きで、どの音楽雑誌も隅々まで読んでいたので(それこそ広告ページまで全部チェックしていた)、自然に覚えたのだと思う。まさか音楽雑誌の会社に就職するとまでは、その時は思っていなかったが。
話を戻しますね。つまり、その時観た有頂天は、音源と同じく、ライブにおいても、それまでの自分が知らなかったものだらけだったのだ。歌い方、演奏のしかた、パフォーマンスそのものや、衣装やメイクやヘアスタイルまで含めて。
あと、演奏も、すごく上手く感じた。PAの出音の良さも含めて、「これがプロのバンドか!」と衝撃を受けた。
なお、近い時期に、同じウッディ・ストリートで観た爆風スランプにも、同じものを感じた。が、今考えると、当時の爆風と有頂天が同じくらいの演奏力ってことは、さすがにないと思う。爆風スランプ、当時のロック・バンド界隈の中で、圧倒的に上手かったはずなので。
ライブハウスで、至近距離で音を浴びたのも大きかったんだろうな。普段は基本、ウッディ・ストリートで観るのは地元のバンド、プロは広島郵便貯金ホールや広島東区民文化センターで観るものだったので。
広島郵便貯金ホールは、今の上野学園ホールです。東区民文化センター、今は全然やってないけど、できて間もなかった当時は、プロのバンドのツアーでもよく使われていたのでした。爆風スランプも、あとEARTHSHAKERも、ここでも観たことがある。以上、広島の人にしかわからない話だけど、一応書いておきました。
彼女の方は、有頂天に対してどんなリアクションだったのかは、隣で観ていたはずだが、あんまり記憶にない。「全然良くなかった」とか言われたら、さすがに憶えていると思うので、きっと僕と同じように、興奮して、喜んでいたんじゃないかと思う。
で。この1年半後に、彼女が有頂天をバックにライブをやっているのを観ることになるとは、その時は、予想だにしなかった。
次回に続く。
プロフィール
兵庫慎司
1968年広島生まれ東京在住、音楽などのフリーライター。この『思い出話を始めたらおしまい』以外の連載=プロレス雑誌KAMIOGEで『プロレスとはまったく関係なくはない話』(月一回)、ウェブサイトDI:GA ONLINEで『とにかく観たやつ全部書く』(月二〜三回)。著書=フラワーカンパニーズの本「消えぞこない」、ユニコーンの本「ユニコーン『服部』ザ・インサイド・ストーリー」(どちらもご本人たちやスタッフ等との共著、どちらもリットーミュージック刊)。


