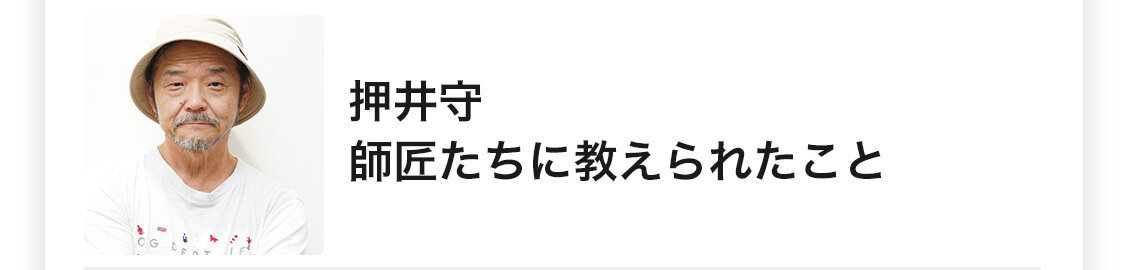押井守の あの映画のアレ、なんだっけ?
『ゴジラ-1.0』はご覧になりましたか?<後編>
月2回連載
第131回
Q.
『ゴジラ-1.0』がアメリカでの興行で成功を収めて話題になっていますが、押井監督は観ましたか? 世界的にもBBCが日本映画の成功とハリウッドの迷走と特集を組むくらい海外でも評判みたいです。製作費1500万ドル(山崎監督はそんなに出てないって否定してましたが)でハリウッドの超大作を超える興行成績をアメリカでは収めている点が話題になっているみたいです。
── 今回は『ゴジラ-1.0』についての後編です。アカデミー賞を獲得した特撮は確かにいいけれど、物語や設定のディテールが甘いとおっしゃっています。ひと言モノ申したいのは軍事的なディテールですよね?
押井 いろんな意味で甘いんだけど、とりわけ軍事系が酷い。もうありえないことの連続! 戦中なんて日本の対潜能力は世界でもサイテーの部類で、米海軍の潜水艦からやりたい放題でしたからね。
重巡の高雄はゴジラに遭遇して、至近距離で主砲の咄嗟射撃をしてたから納得ですが、最後の作戦でガスボンベを敷設してたのは駆逐艦の雪風と響だったかな? ゴジラの潜伏する海域で2隻だけで行動するのはほとんど自殺行為でしょう。大和の海上特攻より無謀です。史実でも残存していた海防艦や駆潜艇を動員して、ゴジラを牽制するために爆雷散布くらいはしてほしかったですね。
── 最後に主人公が乗るのは日本の戦闘機・震電ですが、あんな脱出装置ついてたんですか?
押井 あるわけないでしょ! 射出座席を搭載なんて、あの時代では無理です。米軍にすら戦中にはなかったんじゃないかな? ドイツ軍にはあったとは言われているけど、真偽のほどは分からない。
どちらにしろ震電にはなかったし、そんな装置を搭載することも不可能でした。事前にキャノピーを吹き飛ばすこと自体ハードルが高いし、そもそも射出座席そのものが研究段階だったんです。ちなみにキャノピーを自分で開けて飛び出すことは可能だけど、操縦席直後のプロペラに接触して死亡する可能性が高いです。むしろ震電はそうした自力脱出にはもっとも向かない機種だっただろうし、だからこそ射出座席が必要な戦闘機だったと思いますけどね。史実ではプロペラを火薬で吹き飛ばしてから脱出させるつもりだったようです。
── 押井さん、今調べたら震電、めちゃくちゃかっこいいですね。プロペラが後ろにあるんだ。

Photo:AFLO
押井 軍オタの間では震電、とても人気が高いんですが、残念ながら試験飛行で数分間飛んだだけです。にもかかわらず人気が高いのは、とにかくカッコいいから。日本機にしては珍しくデザインが素晴らしいんですよ。
試作中に終戦を迎えたから、あるいは実用化されなかったから、などという意見もあるようだけど、基本的に実用化できなかったであろう理由がたくさんあったんです。特にエンジンの冷却に関しては、当時の技術では解決不能だった。
米軍も同じ先尾翼形式の「アテンダー」という戦闘機を開発し、液冷エンジンを採用することでこの問題を解決しようとしたものの、結局うまくいかなかったといわれている。イタリアにも同様の試作機がありましたが、こちらも実用化していません。この先尾翼という形式は、おそらくジェットエンジンを搭載することでしか実現できなかったんですよ。
── 震電、ちょっとポチャっとしていてサンダーバード2号みたいじゃないですか?
押井 だからSF的な機体なの。私だって大好きですよ。プラモ小僧だった私は、震電が1000機、2000機あればB29をばったばったと落としてくれたのにって思っていましたからね。
でも、エンジンも機体もプロペラも追いついていない。不可能だらけの機体。あの頃に登場した「幻の名機」と呼ばれる機体のほとんどはそんな感じ。幻というより実用不可能な機体を作っちゃった。ドイツもそうだった。大戦末期のドイツの幻の名機も使いものにはならなかったですから。
にもかかわらず、どこかに1機残っていて、整備の天才的なおじさんがいじくって飛べるようにしたというわけだからね。しかも30ミリの機関砲がついている。どこで手に入れたんだろうと思うし、弾だってそうです。そもそも進駐して来た米軍が震電のような実験的な機体は残らず持って帰ったんだから。機関砲の隠匿なんて許してくれないし、できるはずもない。
そもそもで言うともうひとつ、主人公がすぐに震電を操縦してたでしょ?
── 特攻隊の生き残りだから戦闘機の操縦はできるんだと解釈してましたが、違うんですか?
押井 違います。飛行機は機体が代わるごとに操縦方法が異なる。にもかかわらず、すぐに操縦していた。
終戦からブランクがあるだけじゃなく、彼のような末期の特攻隊員は技能未熟者ばかりだった。離陸はできても着陸はできないというパイロットがいっぱいいたんです。まあ、着陸は必要ではなかったんだけどさ、彼らには。
※続きは無料のアプリ版でお読みください
取材・文:渡辺麻紀
撮影:源賀津己

『押井守の人生のツボ2.0』
東京ニュース通信社
1760円(税込) 発売中
質問はこちらのフォームからお寄せください!