川本三郎の『映画のメリーゴーラウンド』
『12人の怒れる男』から陪審員制度の話へ。ワイルダーの『情事』…日本製『12人の優しい日本人』…最後は意外な映画につながりました。
隔週連載
第64回
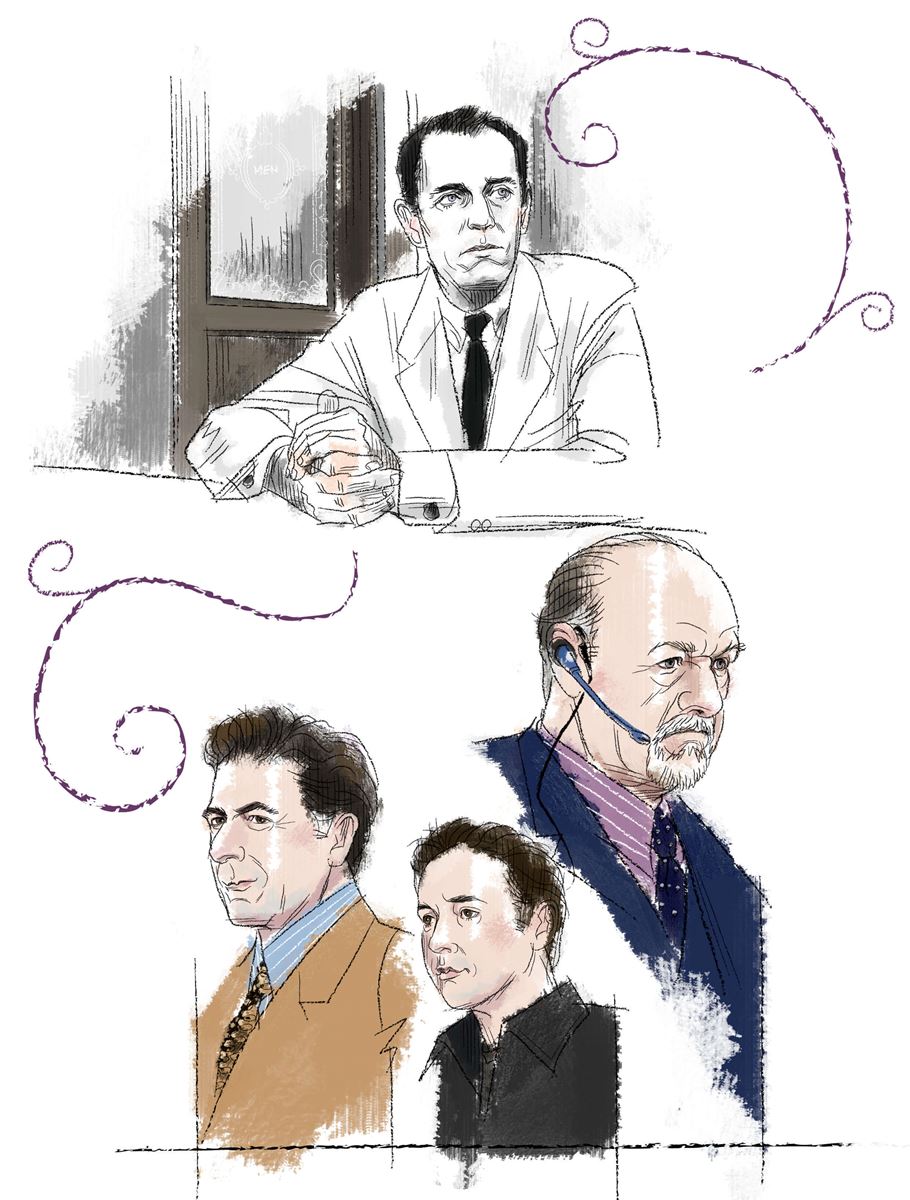
日本では、1959年に公開された『12人の怒れる男』(57年)は、なんといっても日本人に、アメリカには陪審員制度というものがあることを教えくれたという意味で重要な映画。
日本でも、昭和3年から昭和18年まで陪審制度があったが、この映画が公開された当時、そのことはほとんど語られなかった。日本ではうまく機能しなかったためかもしれない。だから、中学生の時に、『12人の怒れる男』を見てはじめて、アメリカでは普通の市民が人を裁くのだと知って驚いたものだった。
また、イギリスでもやはり陪審員制度があることは、『12人の怒れる男』の1年前に日本公開されたビリー・ワイルダー監督の『情婦』(58年)で知った。いうまでもなく、アガサ・クリスティが自らの短篇『検事側の証人』を舞台用に脚色した作品をもとにしている。
タイロン・パワー演じる仕事らしい仕事をしていない伊達男が、裕福な未亡人を殺害した容疑で逮捕される。法曹界の大者チャールズ・ロートンが弁護を引き受けることになり、みごと無罪を勝ち取る。
『12人の怒れる男』では12人の陪審員の全員が男性だったが、『情婦』では3人ほど女性がいる。彼女たちが美男のタイロン・パワーに同情したのかもしれない。
余談だが、この映画、ミステリとしてひとつ疑問がある。チャールズ・ロートンは、検事側の証人マレーネ・ディートリヒが、夫以外の男を愛している手紙をさるところから入手し、それが決定打となって、タイロン・パワーは無罪になるのだが、検事はなぜこの手紙の相手である男を探し出そうとしなかったのだろう。単に検事の怠慢か。


