佐野元春を成立させるクリエイティブのかけら
自身のレーベル“DaisyMusic”の設立と The Hobo King Bandとの傑作『THE SUN』
全14回
第11章

2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件。世界中に衝撃が走り、多くの命が犠牲となった。
ショックだった。何かが「試されている」と感じた。アーティストは日頃から人が感じない危機感を大なり小なり感じていると思う。特に詩人はそうだ。目の前の事象に言葉を与え、表現することによって、現実をどう乗り越え、凌駕していくのか。表現者として「何か音楽にしてみろ」と言われたような気持ちだった。
自分のソングライティングは不可解な現実と直面したときの本能的な結果だ。森の中で熊が目の前に現れた人間に対して「ガオー」と威嚇する、それと同じだ。
佐野はその日の夜のうちに「光 -The Light」を書き上げ、翌日には自身のスタジオでレコーディングを行い、同月18日に公式サイト“Moto's Web Server”から配信をスタートさせた。12日間限定の無料ダウンロードに約95000のリスナーがアクセスした。
iTunes StoreもSpotifyもなかった時代だ。曲を書いてすぐ配信というアクションはまだ一般的ではなかった。しかしやろうと思えばできる時代になっていた。
普通、新曲ができたらそれがレコードになって店に並ぶまで3ヵ月かかる。けれどこの曲についてはそこまで待っていられなかった。できるだけ早くコミュニティのみんなと意見交換をしたかった。そこで急遽、売り物ではなくパブリックドメインとしてオンラインで公開した。
ただ厳密に言えばこれは契約違反だ。契約レーベルの許可なくそうした行為をするのは許されない。話し合いの結果、「期間限定なら」ということになった。僕はレーベルの判断に感謝した。
そこで気づいたのは、これからのポップ音楽の役割についてだ。今起こったことをすぐ曲にしてすぐにファンに聴いてもらう。ポップ音楽にもそんなダイナミズムが必要な時代になっていた。そこで果たすポップ音楽の役割は決して小さくはない。僕はそう思った。
これまでの章でも触れてきた通り、佐野はインターネット時代の到来と、音楽ビジネスが迎えるパッケージから配信形態への転換をかねてから予期していた。彼は『VISITORS』制作時の記憶を語る。
直感したのは80年代前半。ニューヨークにいたころ、アルバム『VISITORS』のフロントカバーにも写っているコニーアイランドの海を見ているときだった。「NEW AGE」という曲のリリックを書いていたときのことだ。そこで一瞬、僕は未来を垣間見たような衝撃を感じた。それは地球という森が細かくはりめぐらされた通信網のようなものでつながっているイメージだった。ものを作る時代から情報の時代へ。自分は今その端境(はざかい)に生きているんだとリアルに感じた。
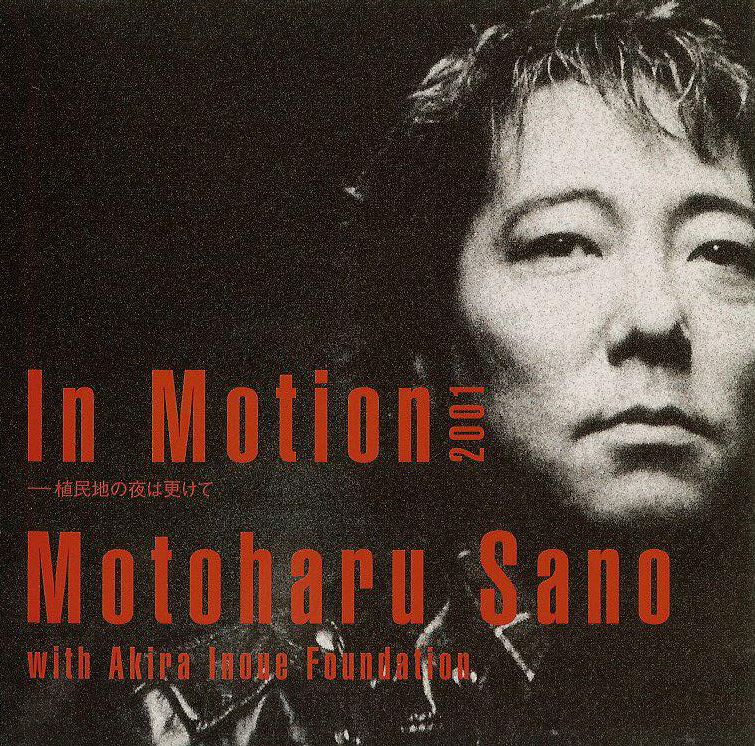
同月21、22日、佐野は神奈川県鎌倉市で井上鑑とのコラボレーションによるスポークンワーズセッション「In Motion 2001 -植民地の夜は更けて」を開催している。井上のスポークンワーズセッションはこれ以降も継続され、2017年にはニューヨークにおけるポエトリーリーディングのイベントも共にしている(※その模様はNHK BSプレミアム放映のドキュメンタリー「佐野元春ニューヨーク旅『Not Yet Free -何が俺たちを狂わせるのか』」で放送された)。
スポークンワーズと言って、自分がパフォーマンスするとき、聴き手がどう思ってるかはよくわからない。はっきり言えるのは、これも自分の音楽表現のひとつだということだ。
スポークンワーズは、日本では“詩の朗読”といった狭いカテゴリーに押し込められてしまっている。「非現実的な人が夢見がちな思いをしゃべる行為」といった誤解から、表現のポテンシャルが発揮されないまま、永らく放置されている哀れなアートフォームだ。それはたいていの場合、読み手に“ビート”が内在しないからではないだろうか。
自分がこのアートフォームに触れたのは、50年代ビートの作品を経験したときのことだ。アレン・ギンズバーグやジャック・ケルアック、ウィリアム・バロウズ。60~70年代の日本の詩人たちでは諏訪優さん、白石かずこさん。彼らのリーディングパフォーマンスを見て「いつか自分もこの列に加わるだろう」と予感していた。
しかし80年代になって、日本ではこの手のリーディングパフォーマンスはすっかり衰退してしまったかのように見えた。そこで新しい時代の表現が必要だと思い、『ELECTRIC GARDEN』(85年)という作品を出した。デジタルビートに言葉をフロウさせた、その後のヒップホップ表現につながる最初期の作品だ。
2017年にニューヨークでスポークンワーズのライブをやった。観客の反応も悪くないので続けていきたいと思っている。

2004年4月、佐野はシングル「月夜を往け」のリリースを最後にEPICレコードから独立。自身の新レーベル“DaisyMusic”を設立した。7月には同レーベルから記念すべき第1弾オリジナルアルバム『THE SUN』をリリースする。ディストリビューションを担当したユニバーサルレコードCEO(当時)の石坂敬一氏は、レーベル発足のパーティーで「「Rockというのは音楽の一ジャンルだが、Rock & Rollというのはスタイルであり、生き方だ。そして佐野元春はRock & Rollを体現してきた人。そんな佐野元春にふさわしいビジネスを展開していく」という名言を残した。
時代の波に押されて音楽業界は低迷していた。EPICレコードのよき友人たちとの決別はつらかった。何と言ってもデビューから24年もの間、並走した仲間だ。レーベルを離れたときは感謝の言葉しかなかった。同時に、自分は独立レーベル“DaisyMusic”を新しく立ち上げた。ファンやユニバーサルレコードの支援もあって心強かった。レーベル発足時のスローガンは「Let’s Rock and Roll!」。ここからまたはじめよう、そんな気持ちだった。
前作『Stones and Eggs』を佐野のソロとカウントすれば、佐野とThe Hobo King Bandにとっては『THE BARN』以来7年ぶりのオリジナルアルバムだった。佐野は最高のバンドサウンドをアルバムに収めるために奮闘した。
『THE SUN』の制作にはいつも以上に力が入った。レコーディングの期間ものべ4年という長い時間がかかった。いつリリースできるんだろうという不安を抱えたままの制作だった。ちょうどこのころThe Hobo King Bandに新メンバーの入れ替えがあった。キーボードにDr.kyOn、ベース井上富雄、ギター佐橋佳幸、そこにドラムス古田たかし、サクソフォンに山本拓夫が加入した。第二期The Hobo King Bandのはじまりだった。
彼らとのセッションは楽しかった。何よりバンドは脂が乗り切った状態だった。第一期The Hobo King Bandのオルタナティブ・カントリーロックから発展して、第二期The Hobo King Bandでは、ジャズ、R&B、ポップの要素が加わった。ジャムバンドの傾向を強めていき、ライブには常に多くのファンが足を運んでくれていた。僕らはライブに明け暮れ、レコーディングのための資金を貯めた。
この時期に「Sail on」(※後に「君の魂 大事な魂」と改題)という曲を書いた。ファッツ・ドミノに代表される50年代のニューオリンズ的なピアノ様式にモダンなポップ風味を加えた曲だ。僕はこの曲が大好きだった。「口ずさむメロディーは愛、抱きしめる花はデイジー、時よ 静かに流れてゆけ」。たいへんな時期だったけれど、当時の心境をこのラインに込めた。
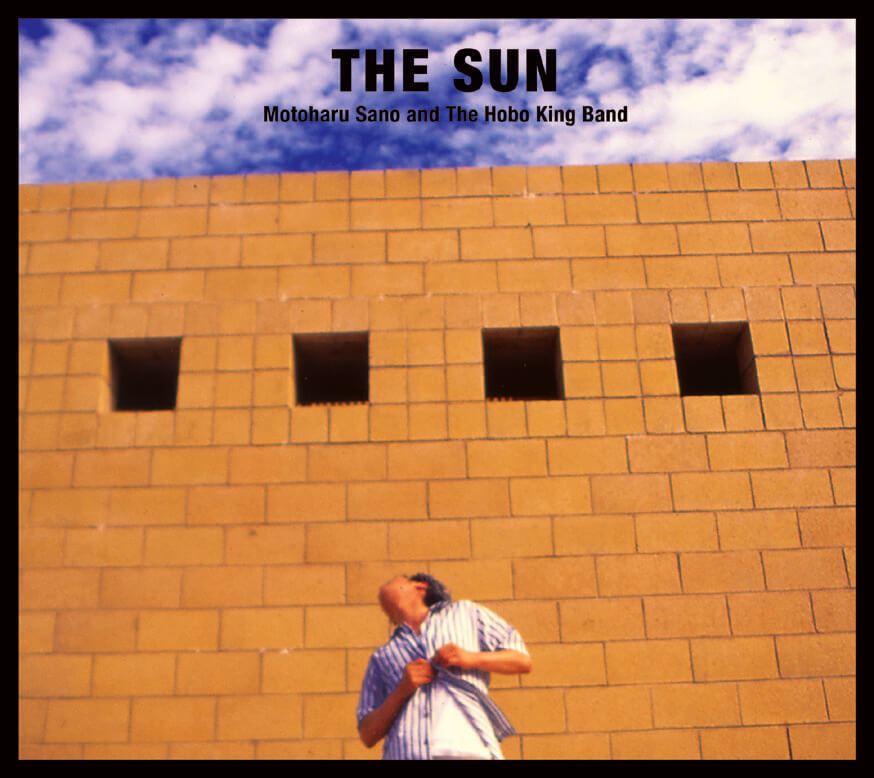
音楽シーンへの思い。阿吽のコミュニケーションと余りあるライブの経験値を備えたバンドサウンド。前章でも触れた『Stones and Eggs』の反省。様々な要素を背景に誕生した『THE SUN』は、この上なくみずみずしく、そして優しい傑作となった。
晴れて『THE SUN』が完成したときはうれしかった。The Hobo King Band結成以来、最高の傑作ができたという実感があった。自分のソングライティングの視点も変わった。成熟した世代の喜怒哀楽を支えるようなロック曲を書いた。大人たちのための、本当の意味での成熟したロックミュージックだ。The Hobo King Bandの技術力の高さがあったからできた音楽だった。
1曲目の「月夜を往け」とラストの「太陽」には、当時の佐野の思いが色濃く描き出されている。
「月夜を往け」と「太陽」には、EPICの友人たちとの長かった蜜月関係に惜別の念を重ねた。いずれも彼らへのメッセージであり、自分へのメッセージでもあった。
アルバム『THE SUN』はDaisyMusicからリリースしたが、ほとんどのレコーディングはEPICレコード在籍中に行った。だから気持ちとしては『THE SUN』までが僕のEPICイヤーズと解釈している。
『THE SUN』はその深みのあるソングライティングと卓越した演奏によって、国内では稀に、大人の鑑賞に耐えうるロックアルバムとなった。「レイナ」から「遠い声」、ラストの「太陽」へと続く美しい流れについても特筆しておきたい。本作に通底しているのは慈愛、そして博愛の精神だと言えるだろう。
そうかもしれない。その2曲は私的な情景を歌っている。特に「太陽」は子供のころから関心があった「神」をテーマにした。自分は高校がミッションスクールだったし、周囲にはクリスチャンが多かった。
しかし10代になると生意気にも哲学的な本を読みはじめる。虚無主義を説いたニーチェ、実存主義のサルトルだ。彼らは「神なんていらない」と唱えた。言ってみれば当時の自分は、有神論と無神論の間で引き裂かれていたようなものだ。〈God 夢を見る力をもっと〉という呼びかけから始まる「太陽」は、そのころのアンビバレントな自分をさらけ出した曲と言えるのかもしれない。
同時に、『THE SUN』は国が急速に保守化していく状況を重ねた思いもあった。「国のための準備」はその一端だ。アルバムのアートワークに日本の国旗をあしらって、そこに「我住む地を想う」と記した。韓国人の友人がここに反発した。彼は自分の意図とは違うところで『THE SUN』を聴いていた。言葉がやるせない災いを招く時代。自戒も込めて、表現者にとって厳しい時代が来ると直感した。
この傑作『THE SUN』の発表後、The Hobo King Bandとしての活動はいったん休止。佐野は新たに自分より一回り若い世代のミュージシャンを集めて、The Coyote Bandを結成。彼らを率いて00年代、10年代の充実期へと旅を続けていく。
この日、最後に聞いた。「現在の佐野さんにとって、神の存在とは?」。彼はこちらに付き合うかのような表情でこう言って笑った。
神? “Dog”のさかさまだよ。みんな、さかさまのDogを待っている。
取材・文/内田正樹
写真を無断で転載、改変、ネット上で公開することを固く禁じます
当連載は毎週土曜更新。次回は11月28日アップ予定です。
プロフィール
佐野元春(さの もとはる)
日本のロックシーンを牽引するシンガーソングライター、音楽プロデューサー、詩人。ラジオDJ。1980年3月21日、シングル「アンジェリーナ」で歌手デビュー。ストリートから生まれるメッセージを内包した歌詞、ロックンロールを基軸としながら多彩な音楽性を取り入れたサウンド、ラップやスポークンワーズなどの新しい手法、メディアとの緊密かつ自在なコミュニケーションなど、常に第一線で活躍。松田聖子、沢田研二らへの楽曲提供でも知られる。デビュー40周年を記念し、2020年10月7日、ザ・コヨーテバンドのベストアルバム『THE ESSENTIAL TRACKS MOTOHARU SANO & THE COYOTE BAND 2005 - 2020』と、24年間の代表曲・重要曲を3枚組にまとめた特別盤『MOTOHARU SANO GREATEST SONGS COLLECTION 1980 - 2004』がリリースされた。佐野元春 & THE COYOTE BANDの新シングル「合言葉 - Save It for a Sunny Day」iTunes Storeで販売中。
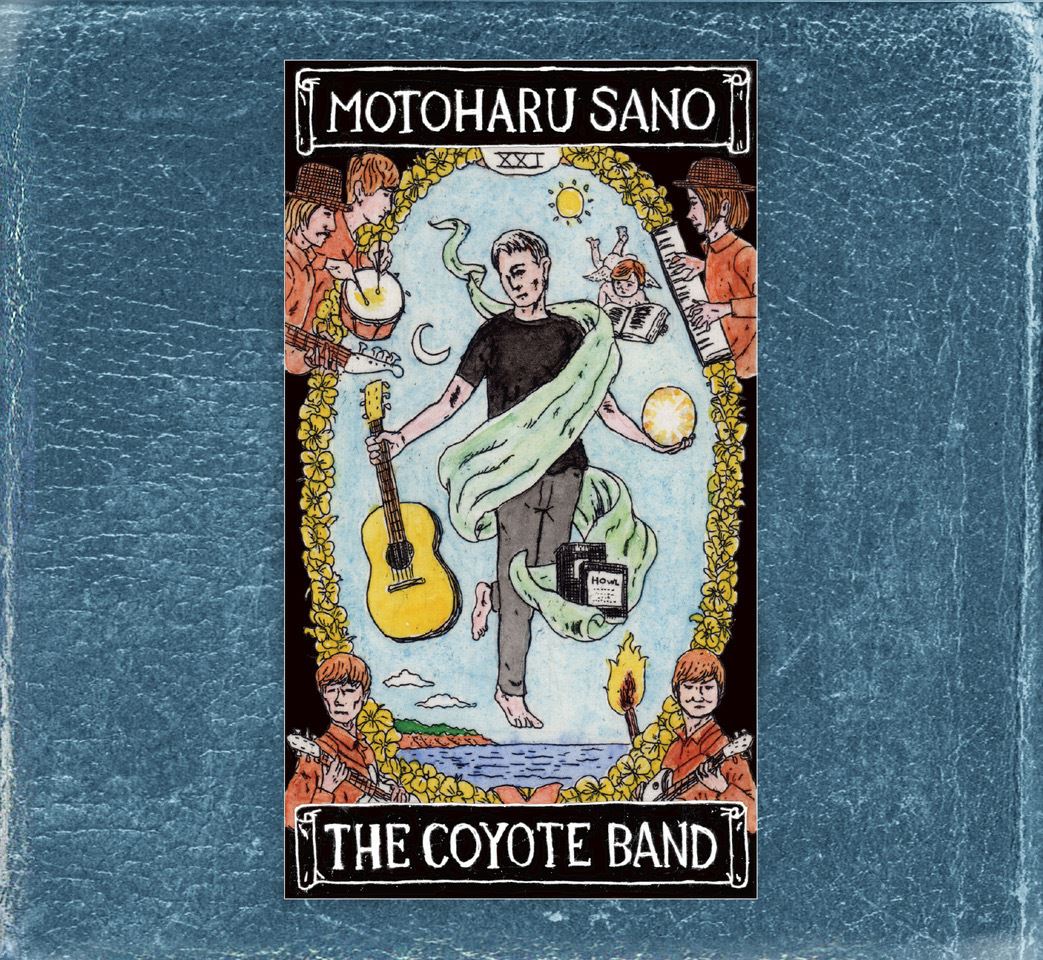
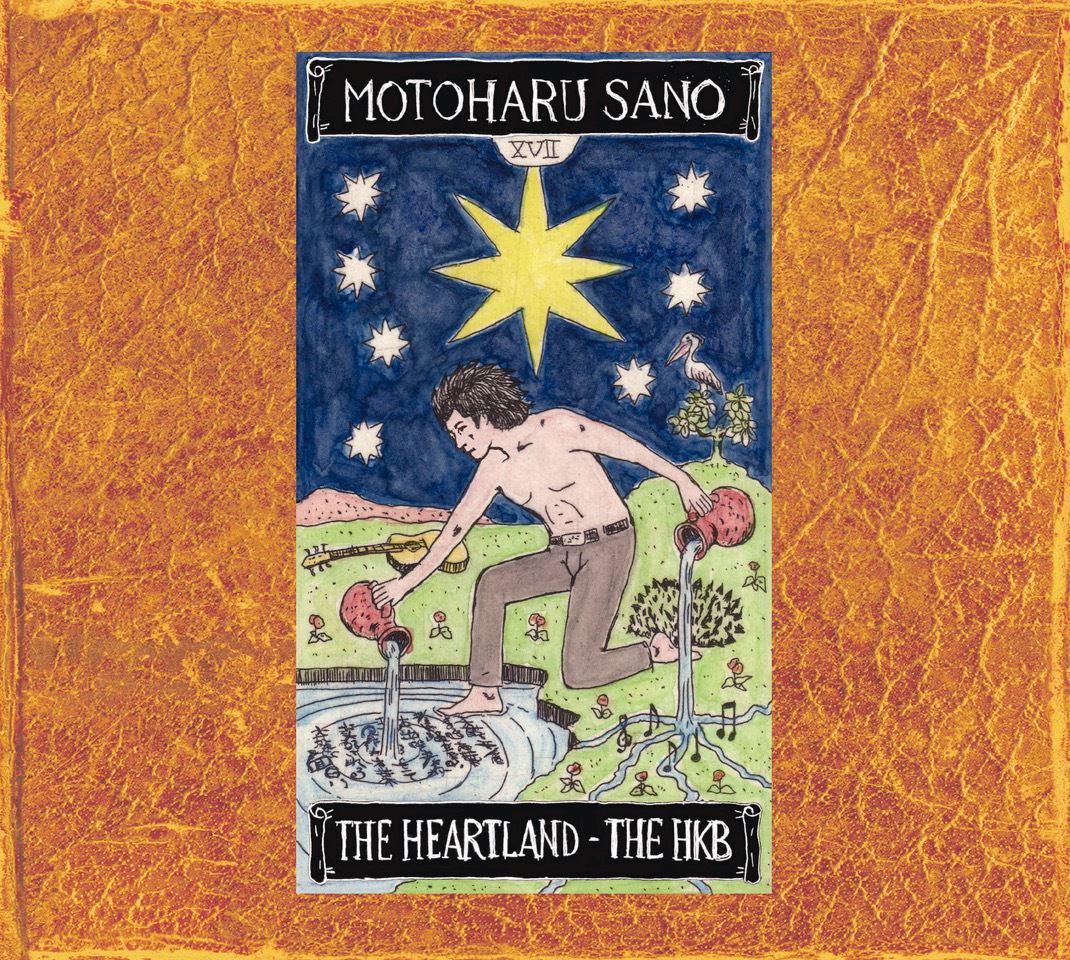
佐野元春 & THE COYOTE BAND TOUR 2020「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」
2020年12月13日(日)愛知・フォレストホール
2020年12月15日(火)東京・LINE CUBE SHIBUYA
2020年12月16日(水)神奈川・神奈川県民ホール
12月19日(土)京都・ロームシアター京都 開場17:00 / 開演18:00
12月21日(月)大阪・フェスティバルホール


