さやわかが語る、2015年の音楽文化と全体性「強度を一番先に取り戻したのはポピュラー音楽」
音楽
ニュース
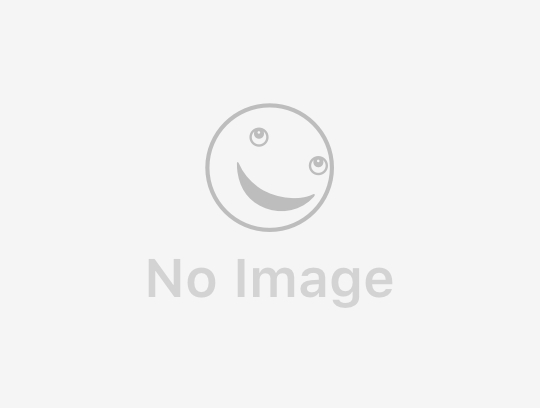
リアルサウンドでも執筆中のライター・物語評論家のさやわか氏が、2015年1月22日に新書『僕たちとアイドルの時代』(星海社新書)を発表した。同書は、さやわか氏が2013年6月3日に世に送り出し、大きな反響を呼んだ『AKB商法とは何だったのか』(大洋図書)に、ここ1年半余りの音楽シーンの情勢を踏まえて大幅に加筆・修正をしたもの。総選挙や握手会といったさまざまなシステムを作り出し、音楽チャートで注目を集める一方、激しい批判にもあってきた“AKB商法”にスポットを当て、その批判の妥当性を検証するとともに、これまであまり語られてこなかったその功績を浮き彫りにしたのが前書だった。今回の書籍では、刊行の後に起こった「恋するフォーチュンクッキー」のムーブメントや、世間を大きく騒がせた“AKB襲撃事件”にも言及、あらためてその理論の有用性を主張している。リアルサウンドでは今回、さやわか氏本人に登場してもらい、同書の狙いや主張についてたっぷりと語ってもらった。(編集部)
「アイドルは全体性をカバーしようとしている」
——今回の新書『僕たちとアイドルの時代』は、2013年6月に出版された前書『AKB商法とは何だったのか』に加筆されたものですね。この1年半の間に、前書で提示していたことが実証された手応えはありましたか。
さやわか:そうですね。『僕たちとアイドルの時代』は、前書を踏まえて「ほら、僕が考えていた通りになったよね」という本ではあります。新書化にあたって本のタイトルを変えた一番の理由は、前書で「日本はアイドルの時代だ」って書いたんですけど、いまはアイドルカルチャー以外にもそこで僕が「アイドルの時代」と書いたものが拡大しているので、そのニュアンスを込めたかったというのがあります。
——前書では、一般的にいう“AKB商法”への批判に対し、さやわかさんは異議を申し立てしていますよね。その異議の背景にあるのは、ポップミュージックはビジネスも含めて一体としたカルチャーとして捉えたほうがより有意義である、という考え方でしょうか。
さやわか:その通りです。ただ僕が言いたいのは、ビジネス側からポップミュージックを捉えましょうというだけの話でもないんです。まず前提としているのが、ポップミュージック以外のカルチャーであってもそうなんですが、全体性を見通すのは難しいということ。しかし一部の人々は、全体性がないにも関わらず自分の好きなもの、興味のあるものだけにしぼって、文化や社会全体を語ろうとする。しかしお互いにそういうことをやっていると、何が本当に重要なのか決められないまま、価値観のぶつけ合いになることがすごく多いんです。わかりやすく言うと、それはインターネット上での不毛な議論などに表れていますよね。漫画でもアニメでも映画でも「俺はあれが好きだ」「あれはダメだ」「あれが良いんだ」という、特に根拠のない水掛け論ばかり繰り広げられるようになる。しかし歴史を参照すれば、どんな文化にも価値を認められたものがあったと思うんです。でも特にアイドルの場合はそうした権威付けがされずにきたものだから、内部でも外部でも、とにかく「あれが好きだ」「これはダメだ」という不毛な議論に終始してしまう。僕が指摘したかったのは、そこなんです。
——なるほど、AKB商法への批判も倫理的なものに終始するものが多く、それはカルチャー全体を見通すものにはなっていない、という見方ですね。
さやわか:実際、僕がアイドルについて書き始めたのは06~07年頃のことなんですが、その時は編集者に「アイドルが面白い」と訴えても「さやわかさんはそういうのが好きなんですね……」と気持ち悪がられることのほうが多かったんですよ(苦笑)。要するに、僕が「アイドル好き」で、その人は「アイドル嫌い」という、好き嫌いでの判断ばかりがされたわけです。しかし、アイドルという存在が面白いのはそこでもあって、それだけ好き嫌いだけが横行する社会を前提として受け入れつつ、そこでなお「いかにしてポピュラリティを得るかが仕事」という人たちなんですよね。それはつまり、価値観を対立させるよりも、なんとかして社会全体をカバーすることを目指すという意味でもある。だからこそ、いまの社会を語る上での一つの鍵となり得ると思うんです。AKB48がまさにそうなんですけど、彼女たちは売上げを指標として使うことによって全体性をカバーしようとしていて、しかもチャートの売上げ順位やランキングのような構造を、自分たちの作品あるいは表現を届かせるためのインフラとしても使っています。倫理的な好き嫌いでそれを非難するよりは、そのことが今の社会にとって何を意味するのかを考えるほうがよほど有意義です。
——この本では、アイドルグループがチャートをジャンプボードにして、次の段階にいくルートが想定されていますね。
さやわか:そうですね。チャートで上位になって目立つことによって、AKB48のシステムはうまく循環してきたと思います。
——4章「AKB商法とは何だったのか」では、ここ2年くらいの新しい事象についても書かれていますが、さやわかさんが2013年までに立てた見立ての中で、特に予見が当たったと感じる事象とは。
さやわか:前書が出たのが2013年の6月で、ちょうどAKB48の総選挙があって、そこで指原莉乃さんが1位になりました。そして『恋するフォーチュンクッキー』がヒットした。これはもう、僕が書いた通りになったなと思いました。指原さんは恋愛スキャンダルがあってバッシングを受けたメンバーであり、またAKB48の中ではどちらかというとコメディリリーフとしてのキャラクター性を与えられている。にも関わらず、AKB商法の権化であるような総選挙という場で1位になることができた。つまりこれは、アイドルがかつてのようにスキャンダルを犯して失敗したらもうアウト、というシステムではなくて、違う仕組みが働いているというべきでしょう。また『恋するフォーチュンクッキー』は、曲としても非常によく出来ていて、それこそロック界隈のミュージシャンにも評価された。つまり「AKB48は握手券を売っているだけで、音楽性は伴っていない」という批判はもはや必ずしも成り立つものではありません。さらに同曲は、YouTubeなどを通じてみんながダンスする動画を投稿し、そのムーブメントが広がっていくという流れがあった。今のアイドルは疑似恋愛の対象として好きになる人を中心とした文化ではなく、曲の中身だけが重視されるのでもなく、そのアイドルがいて、その曲があることによって人々が繋がっていく、そういう文化になっているわけです。『恋チュン』のムーブメントは完全に狙って起こされたものだと思うんですけど、それがまるで前書で指摘したことをトレースするような仕掛け方だったので、我が意を得たり、と思いました。言い換えると、AKB48は現状を俯瞰した上で、次にどういう風にコマを進めていくべきかをちゃんと考えているユニットで、それを見事に当ててきている。だからこれは「だからAKB48はすごい」っていう話ですらなくて、今のポップミュージックの状況を踏まえたらこういうやり方がある、ということで、僕の本はそれを知ってほしいという気持ちを込めたものになっています。
「倫理的な批判よりも、歴史やシステムについての理解を」
——本書では2014年に起きたAKB48の握手会襲撃事件も取り上げています。その際には、やはり倫理観と結びつけられながらAKB商法までもが猛烈に批判された、と言及していますね。
さやわか:アイドルについてなにかネガティヴな事件が起こると、一部では「アイドルという文化そのものがよくないのだ」というところへ急に直結されてしまいます。女の子を無理やり働かせている、という風に捉えられがちだから、叩きやすいものなんですよね。特に2014年の襲撃事件の場合は、握手会という、いまもっともAKB48がうまく使っているシステムを突いたものだったからこそ、余計に反対派が盛り上がったとは思う。ただ、インターネットではやはり倫理的な批判が主であって、特に検証主義的ではなかったんですよ。つまり襲撃したのが誰で、その時の状況がどうだったかが注目されたわけではなくて、まず最初に言われたのは、「熱狂的なファンがやったんだろう」とか「あれだけ金を使わせているんだからそういう奴も現れるだろう」みたいな意見だった。要するに恋愛ストーカーまがいの事件だと思われたんですけど、事実は全くそうでなかった。でも、こういう見方をされるのは、AKBなど今のアイドルがまだまだ誤解されているせいですよね。そうすると、あの事件の本質がどこにあるのかも見過ごされてしまうでしょう。ただ、そこで僕が難しいと思ったのは、「事実はそうじゃないんだ、AKB48は潔白なんだ」と主張すると、自分まで価値観の対立に絡めとられてしまう。だからあの事件について、僕はそういう発言はできなかった。でも僕の本に答えは書いてあるので、読んでくれたらいいのになー、とはずっと思っていました(笑)。ああいう事件を期に、握手会を支える歴史やシステムについてちゃんと考えたほうが有意義だと思うんです。
——なにか問題が起こったときに建設的な議論ではなく、倫理的な闘争に発展してしまう。これを乗り越える手立てはあるのでしょうか。
さやわか:カール・シュミットっていうドイツの政治学者が、友敵理論——つまり政治というものが「あいつは敵か味方か」ということだけに収斂されていく——という考え方を示しましたが、僕はカルチャーについて書きながら、ずっとそれについて考えています。アレについて褒めているからこいつは味方、けなしているから敵、というのが際限なく進んでいくと、最終的には「敵だからけなさなければいけない」「味方だから褒めねばならない」という論理にまでなって、自分と価値観の合わない人と批判をぶつけ合うだけになっていくんですよね。それは本当に不毛。アイドルについても、「アイドルだからダメだ」というレッテル貼りをする人もいれば、「アイドルだから褒める」という人も出てくるわけじゃないですか。それは本当に文化について語っていることになるんでしょうか? 僕はそうは思いません。
——まさに剥き出しの政治があると。
さやわか:本書の中でトマス・ホッブズの「万人の万人に対する闘争」という言葉にインスパイアされて、「アイドルのアイドルに対する闘争」という言葉を使っているんですけど、それも同じ含意なんです。“アイドル戦国時代”といわれる状況は、私たちの社会の写し鏡のようなもので、それは闘争状態であってすごく危険なものだ、ということを指摘したかったんです。そして、それをうまく軟着陸させるようなやり方を、当のアイドルの中から探すことができるんだよ、ということが書きたかった。
——チャートというのは、観念同士がぶつかり合う状況に対する唯物論的な介入ではありますよね。
さやわか:そうそう。結局、価値観をどれだけ対立させたとしても、そこには抗い難く自分たち全体を規定している力が働いている、という話に持っていったわけです。そして、それを参照先とすることで闘争をするんじゃなくて、むしろ互いをつなぐハブとして有益に使うようなことができたらいいなと思っています。もちろんAKB商法的なものを使っているアーティストばかりが上位にいる今のチャートに、批判されるポイントはあると思うんですよね。「唯物論的介入をうまく利用しているんだよ」って言っても、それをしていない人にとっては「何言ってんだコイツ」ってなると思う。ただひとつ思うのは、僕が前書を書いた頃にはまだ「AKB48だけがそういう商法を使っている、だから許せない」という言い方が多かった。だけど実はジャニーズもやっていたし、EXILEも、ビジュアル系の人もかなりやっていたわけじゃないですか。AKB商法への批判が始まって、そうした売り方が可視化されたからこそ、そういうものを嫌いな人が「アイドルは許せない」じゃなくて、「そういう商法を使う人たち全般が許せない」という言い方になってきた。それはいまだに残念なことですけど、状況としては進んだのかなと思います。
——昨年11月、Mr.ChildrenがSexyZoneにシングル売上げランキングで負けるという象徴的な出来事がありました。本書では、SexyZoneの商法に対して批判が集まったけれど、とはいえミスチルもまた別の商法を使って売上げを伸ばしてきたバンドだということを指摘しています。(参考:SexyZoneがミスチルを抜いたCDシングルランキングをどう考える? さやわかが歴史的視点から提言)
さやわか:僕は1995年に『ROCKIN’ON JAPAN』が行った、ミスチルの桜井さんに対するインタビューをたまたま当時読んでいたんですが、それを読むとわかるのは、ミスチルこそ、一貫してどうやって売っていくかを考えてきたバンドで、とりわけタイアップを頑張って売れてきた人たちなんです。桜井さんの言葉には、「自分は大衆音楽に打って出るんだ」という強い決意があって、それ自体はすごく健全な考え方で、何も間違っていない。しかし、いろんな経緯があって、音楽シーン全体にアーティスト信仰みたいなものが根付いてしまった。これはミスチルが悪いわけではなくて、音楽が売れるということとアーティスト性みたいなものが乖離していった結果、逆に「売れない音楽を作っている人はアーティスティックに作品性を追求しているんだ」という奇妙な見方が出てきた結果だと思います。つまり、たとえば日本のヒップホップなんかでもまれに見られたような、ある種の清貧志向が台頭してしまった。するとミスチルなんかは「売れる音楽を作っているんだけど、決して売れるために作っているわけではない」という、すごく奇妙なロジックでほめられたりする。しかしポップミュージックであるというならば、それは本来ショービジネスの一環なわけで、やっぱりそういうほめ方はおかしいと僕は思っていました。ミスチルはタイアップで成功したからこそ、タイアップの手法を繰り返しているんですよね。「自分たちはタイアップでやってきたんだ」というのは彼らの旗印であって、それを伝家の宝刀としながらゼロ年代以降のAKB商法、特典商法とも戦おうとしてきたわけです。それは素晴らしいことだと思う。しかしそれがSexyZoneに敗れたというのは、タイアップ商法よりも複数枚+特典商法という商法のほうが現代にマッチしていたという意味だと思います。そうしたトレンドを知るためのものとして、チャートはちゃんと機能したと僕は捉えています。
——そうしたチャートの機能を捉えた上で、SexyZoneやAKB48を写し鏡として、ミスチルが純粋に音楽性を追求している、とする見方は訂正したい、と?
さやわか:それはどうしても言っておきたかったことです。一部のひとは、「いや、ミスチルのほうが音楽として良いんだ」とか「SexyZoneのほうが売れたのだから音楽的にも良いんだ」という形で友敵理論を押し広げていこうとするんですけど、どっちだって良いし、どっちが上という話でもないんです。単に今の時代がどうなっているかを計るものとして、チャートが機能すれば良い。それともうひとつ、この本でも指摘したことで重要なのは、本当に人が音楽性の高さを重視しているのであれば、じゃあ別に売れなくても良いじゃん、ということになっちゃうんですよね。たとえばオリコンチャートは、これまで一回も音楽性の高さについて計ったことはないんです。常に売れているかどうかを計っている。なのに、そのチャートのなかでミスチルが1位にならなかったといって怒るのはおかしいと思う。もし本当に音楽だけが大事なのであれば、自分の耳に心地よく響くとか、あるいは桜井さんが好き、ということだけで満足できるはずなのに、結局はポピュラリティを求めているわけですよね。
——良い音楽はチャート上でも高い位置にいるべきである、という考え方は昔から根強くあるように思います。
さやわか:これはすごく難しい問題ではありますよね。90年代の半ばですかね、ピチカート・ファイヴの野宮真貴さんが、「フリッパーズギターが『恋とマシンガン』でオリコンチャートに入ったときに、やっと自分たちの好きな音楽がチャートに入ったと思った」という話をされていたんです。僕はそれってすごく象徴的な言葉だと思う。自分たちの信じた「良い音楽」があって、それでオーバーグラウンドに打って出ようってことをハッキリ志向したのが、90年代のあの辺の人たちだと思うんです。つまり従来の音楽家は「大衆音楽は大衆音楽としてあるが、そうではないハードコアな音楽はこちら側にある」という形で自分たちの価値を主張していたと思うんですけど、90年代に「これで世の中変えてやろう」といって出た結果、今のアーティスト信仰みたいなものと結びつく結果になった。
——たしかに1995年に小沢健二が紅白出場を果たした時、それを一つの達成とみなす意見はよく聞いたし、私も納得していたように思います。一方でさやわかさんの本では、2000年代以降は紅白に出ることのカウンター性が、あやふやなものになっていったと指摘しています。
さやわか:そうしたカウンター性は、小沢健二さんみたいな人が紅白に出たり、『Hey! Hey! Hey!』に出たりした頃には、まだ成立していたと思うんです。しかし亀田誠治さんがプロデューサーとして出てくる辺りから何かが変わっていったように思います。亀田さんは対立軸などはあまり重視していなくて、オーバーグラウンドの領域で単純に良い音楽を作れば良いじゃん、ということを信じているように思うんですよ。別にそこに政治性みたいなものはなくていい。もしくは、シーンの内部から変えていければそれでいい。彼の仕事は椎名林檎さんのものなんかが有名ですけど、彼女の音楽もそうだと思うんです。彼女はカウンター性みたいなものを、キャラクターとしてまとってはいるんだけど、それはみんなに望まれる価値としてのカウンター性ですよね。結果として、そのカウンター性というのは言ってみれば「カウンターキャラ」として、キャラクター化したものでもある。それは時代の産物なんだと思います。そうした変遷を踏まえた上で、アイドルがなぜ面白いかというと、かつてのカウンターカルチャー的な物語をやり直そうとしたからなんですよ。つまり、ライブハウスから出てきて、インディのレーベルと契約し、その後はメジャーのレコード会社からCDを出して、それがオリコンチャートの上位に駆け上り、最後は紅白に出るんだ、みたいな。これは矢沢永吉の「成り上がり」みたいなモデルであって、そんなフィクション性の高い、泥臭いものはダメだ、という考え方が90年代後半からゼロ年代頭くらいまでは支配的だった。ところが、いまのアイドルなんかは、紅白に出たいとか、オリコンの上位に入ったらすごいとか、普通に言っちゃう。音楽性を追究しようという流れが退潮した後に、みんなが感動する音楽の物語、成り上がりの物語を再生産するアイドルというジャンルが盛り上がったのは、すごく面白いことだと思います。
「音楽は一番先に危機的な状況を迎えたが、一番先に独自の方法で回復していった」
——最終章では、そうしてシーンが盛り上がってくると、楽曲自体「も」良くなってくる、と指摘してますね。
さやわか:そのことは『AKB商法とは何だったのか』を書いた時には、まだ十分に可視化されていなかったから書くことはできなかったのですが、かなり重要なポイントなので慌てて書き足しました。つまり「アイドルは作品重視ではない」というのが前の本の結論だったけれど、「作品がなんでもいいのなら、逆に良質な音楽を作ったって構わない」という風潮が強くなってきた。「何でもいい」ところに「一番良い」ものを置くことができるようになったんですね。結局、それは音楽チャートみたいなインフラをうまく使えば、多くの人にきちんと作品を届けられるって言ったことと同時並行の動きとしてある。つまり、それを利用してお金を稼いでいれば、それだけ予算が使えるようになるし、そのおかげで良い作品を作ることもできる。だから「アイドルソングだからダメ」だみたいな言い方が通用しなくなった。むしろアイドル自身も楽曲のクオリティが高いくらいでは差別化できなくなってきたほどなんです。もうひとつ言えるのは、そういう風にアイドル界隈が良い曲を望んだことによって、楽曲提供側も「じゃあアイドルのための曲を作ろうか」と積極的になったんです。アイドルカルチャーに対する理解が深まって、それに当て込んだ曲を作るようにもなってきました。その結果、音楽を好きであることと、アイドルを好きだということが、矛盾しなくなってきている。そういう音楽ファンが増えている。僕はもともと音楽が好きなので(笑)、これは喜ばしいことだと思います。
——最後に今後の予測として、日本の音楽文化はどのように推移していくと考えていますか。
さやわか:この本の最初の方でも触れていますが、商品としての音楽の動向を追っていくと、00年代の中頃は音楽産業が単純に停滞していくのではないかと思われていたんですね。つまりゼロ年代を通して、CDがどんどん売れなくなっていった。それはインターネットのせいだ、違法コピーが蔓延しているせいだとか言われていたんだけど、同時並行した流れとして、フェスやライブが伸びてもいた。それはやがて注目されるようになって、今はライブ指向なんだと言われたりもしてますけど、じゃあその本質は何なんだと考えるべきですよね。たとえばフェスがどう流行っているかというと、やっぱり音楽を通じて人と楽しく過ごすということが大事にされているんです。前に朝の情報番組『ZIP!』でフジロックに行ってフェス飯を女の子3人で食べるという企画をやっていて、すごく驚いたんですよ。それってもう、音楽とは関係ないじゃないですか。じゃあ、そういう現象は音楽の敗北を意味するのかというと、そうではない。なぜなら、そうした空間は音楽がないと成立しないからです。音楽っていうのはすごく面白いカルチャーで、空間に常に漂うことができて、その場所にいる全員を束ねることが可能です。視覚のメディアだと全員を同じ方向に向かせないといけないけれど、音楽というのは勝手に耳に入ってくるものなので、どういう状態にあっても、その場にいる全員に、それぞれの形で与えることができる。その良さが今、伸びてきていると思うんですよ。そう考えると、たしかに音楽が売れなくなったっていう言い方もできるんですが、それでも映画にもゲームにも音楽は使われているし、ゲームの中で使った音楽をCDにすると売れたりもする。そんな感じで他のジャンルに、音楽は常につきまとっていて、むしろいろんなジャンルやいろんな人を結びつけるものになっている。そういう形で、音楽というのはすごく価値を持っているということに、今みんながようやく気付いてきているところだと思うんです。今は東京オリンピックの話で、AKB48が出てくるんじゃないかとか、EXILEが出てくるんじゃないかという話があります。その是非について、楽しみだとか許せないだとかいろんなことが言われていますが、少なくともそういう時に、彼らの名前が出てくること自体が、音楽にとってはすごいことなんだと僕は思います。
ーー最初のお話に沿っていえば、ポップミュージックがある種の全体性を回復しつつあり、それゆえに社会的な文脈のなかで取り上げられている、との見方もできます。
さやわか:ポップミュージックは全体性をカバーできなかったはずなのに、いつの間にかカルチャーの中心にあって、東京オリンピックで何かをやるとなったらAKB48やEXILEのような名前を出さざるを得ない。ポピュラー音楽が自分たちのハブとして機能していることを認めざるを得なくなっている。そこがやっぱり音楽の良いところだと思う。AKB48やEXILEが何を成したかというと、CDをバンバン売ってあちこちで人の目に触れさせたこと。それをウンザリするような話だと感じる人もいると思うんですが、言い方を変えると、彼らはそうして音楽を人に届けていったんです。今の時代——映画も文学も漫画も、細分化していって人々を繋げられなくなってきた時代——にあって、文化としての強度を一番先に取り戻したのは、ほかでもなくポピュラー音楽だったと思います。音楽はインターネット以降、一番先に危機的な状況を迎えましたが、一番先に独自の方法で回復していった。そう考えると、AKB商法と揶揄されたアイドルたちの方法論には、ほかのカルチャーにとっても学ぶべきものがあるといえるし、このやり方は是非を問われつつ、他のジャンルにもさらに波及していくのではないでしょうか。
(取材=神谷弘一/構成=松田広宣)
■さやわか
ライター、物語評論家。『クイック・ジャパン』『ユリイカ』などで執筆。『朝日新聞』『ゲームラボ』などで連載中。単著に『僕たちのゲーム史』『AKB商法とは何だったのか』『一〇年代文化論』『僕たちとアイドルの時代』がある。Twitter



 さやわか『僕たちとアイドルの時代』(星海社新書)
さやわか『僕たちとアイドルの時代』(星海社新書)