ピクサーの面目躍如は『インクレディブル・ファミリー』ジャック・ジャックの存在にあり?
18/8/14(火) 17:00
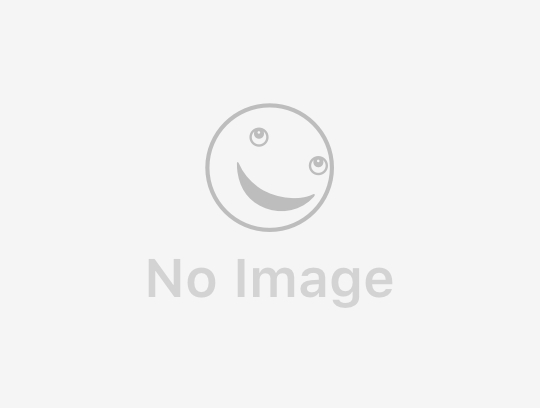
ピクサー社アニメの魅力は、なんといっても「擬人化」ということだと思う。虫の社会もウディ・アレン映画のように世知辛いのだな(『バグズ・ライフ』)、バケモノたちも会社のノルマと昇進競争にストレスを感じているのだな(『モンスターズ・インク』)、海を自由に泳ぐ魚も若年性認知症で右往左往するのだな(『ファインディング・ニモ』)というふうに、人間の社会生活の断面を、人間とは異なるモノたち(それは『トイ・ストーリー』のおもちゃたちのように、生き物である必要すらない)があざやかにかすめ取り、模倣してみせる。私たちの日々の悩み、日々の失敗談を、非人間が反芻してみせる。そうしたカタログがどんどん増殖するのがピクサー社の十八番であったわけだ。思えば、私たち人間にしたところで、十全に人間としての生を完璧にやり遂げているかといえば、まったく心許ないわけだから、ピクサーの非人間的モノたちによって私たちの生活信条やら世相やらが盗まれたことに、小気味よい快感をもたらされてきたということなのではないか。

前作『Mr. インクレディブル』から14年もの歳月が経過して、ふと思い出したように続編『インクレディブル・ファミリー』ができあがってきた。かといって1作目の14年後の物語というわけでもない。今回の第2作はあたかも長い空白などなかったかのごとく、前作のラストシーンから再開してみせる。実写の世界ではシリーズも長期化するうちに、「ウルヴァリンもずいぶんしょぼくれてきたぞ」とか「ブラック・ウィドウもだいぶオバサンになってきたわね」とか、そういうおせっかいな印象で観客があれこれと気を揉むことになる。そうした時間概念の不在は当然、アニメの強みだと言える。監督のブラッド・バードは言う。「僕はいつも頭の隅で(続編について)考えていたんだよ。だけど、他のことが頭のもっと大きな部分を占めていたんだよね。そしていつしか14年が経ち、“やばい! もうやらなきゃいけないぞ” と思ったというわけ(笑)。(時間がかかったのは)意図的ではないし、計算の結果でもない」。(劇場用プログラムより)

ピクサー社の第6作として作られた『Mr. インクレディブル』(2004)は、同社初の人間を主要キャストに据えた作品として話題をあつめた。同社第1作『トイ・ストーリー』(1995)でおもちゃを主人公に据えて以来守られてきた、人間とは異なるモノを扱うという伝統が、製作業務開始10年目にして途絶えたということになる。『Mr. インクレディブル』の発表当時、人間が主人公であることに対して少なからぬ違和感の表明が見られた。いわく「これでピクサーも普通の会社になってしまった」というような。ただひとつ補足するなら、『Mr. インクレディブル』はもともとピクサー社の企画ではなかった。ワーナー・ブラザース社のアニメ部門閉鎖にともなって、同社で製作予定だった『Mr. インクレディブル』は中止となった。しかし、監督のブラッド・バードとはカリフォルニア芸術大学で同窓だったジョン・ラセターの誘いがあり、『Mr. インクレディブル』の企画はピクサーに引き取られ、大学同窓のよしみのおかげでオクラをまぬがれた格好だ。
前作『Mr. インクレディブル』で提起された問題、そして今回の『インクレディブル・ファミリー』でも問題とされるのは、主人公のスーパーヒーロー一家の活動禁止処分である。スーパーヒーローが悪役退治の戦いの際に生じる人的、物的損害の問題は、『アベンジャーズ』シリーズ諸作の最近の主要テーマでもある。『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でメインテーマとして扱われた「ソコヴィア協定」は記憶に新しい。『アベンジャーズ』の超能力者たちが悪役を倒してくれるのはありがたいが、退治にかかる経済的リスクも甚大なものがある。だからスーパーヒーロー諸氏の活動も国連の管理下に置かせてもらいたい。その議定書「ソコヴィア協定」にサインするかしないかが、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』の問題の焦点となり、アベンジャーズ組織は、国連の決定に従うのもやむなしとするアイアンマン派と、おのおのの正義感に照らし合わせつつ活動の自由を保つべきだとするキャプテン・アメリカ派に真っ二つに分裂し、両陣営は仲間割れの兄弟喧嘩を起こすことになる。

一匹狼の集まりであるアベンジャーズの面々はともかくとして、Mr. インクレディブルにはだいじな家族がある。パパ、ママ、長女、長男、次男(赤ん坊)の5人家族であり、社会の制約を甘受しなければならない。驚いたことに上映時間のほとんどで、一家のパパであるMr. インクレディブルは対外活動の機会を奪われたまま、自宅で蟄居(ちっきょ)しつつ赤ん坊の世話に追われる。この難しい状況を打開しようと、破壊リスクの少ないママのイラスティガールだけが作戦に呼ばれ、単身活躍する。スーパーヒーローが主夫の役割を引き受けるという、アメリカ映画でも画期的な状況が生まれ、ゲッソリと衰弱しきったMr. インクレディブルの青白い顔色は、この映画でもっとも美しいものではないかと思える。本シリーズは、人間ならざるモノたちの「擬人化」プロセスを通過しない、いわばピクサー文化の傍系から始まった。しかしピクサー社の作風も近年は様変わりし、人間の冒険も扱うし、本家のディズニーや同業他社の作品群とあまり見分けがつかなくなってきたのは確かだ。「擬人化」プロセスの不在ゆえにかえって、Mr. インクレディブル以下、ここでの人間たちは不自由そうに見える。ヒーローも悪役もなぜか息苦しそうだ。楽しそうなのは、いささか人間離れし、バケモノじみた末っ子ベイビーのジャック・ジャック君だけだ。むしろ映画を陰らせるこの不自由さ、この抑圧を醸す逆説性こそが、ピクサー社の面目躍如なのかもしれない。

ところが興味深いことに、「擬人化」プロセスの直球勝負が、じつは同じスクリーン内に提示されもする。ピクサーアニメ興行の名物である併映短編、今回の前座作品『Bao』はわずか8分間のあいだにピクサーアニメの本質を突いてくる傑作だ。Baoとはおそらく中国語の「包」のことだろう。中華まんを食べようとした主婦の前で、その中華まんが蒸籠の中で動き出し、目鼻が現れ、手足が生える。虫でもない、バケモノでも、ロボットでも、魚でも、カウボーイ人形でもない。蒸籠の中の中華まんが生き始める。元来、生き物であるはずのないものが生きる。中華まんにガールフレンドができてデートに出かける際、主婦に悪態をついたりする。歩く消しゴムや、うなずいたりしゃべったりするランプシェードに心躍るという経験はおありではないでしょうか。そんな孤独な精神と背中合わせの豊かな空想の力が、8分間の短編『Bao』にみなぎっている。さらには子どもの親離れ、独立を黙って受け入れるしかない親の悲哀にまで触れている。
監督は中国・重慶生まれ、カナダ育ちの女性監督ドミー・シー(石之予)。ピクサー社初の女性監督であり、初のアジア人監督である。『インサイド・ヘッド』(2015)以降、ストーリーボードアーティストとして同社で働きながら、短編企画を上層部に提出し続けてきた。有望な中国市場を視野に入れた企画実現なのだろうが、その「擬人化」の空想力をもっと高めてほしいし、あっと驚くような、こんな予想外なモノたちが渋滞に巻き込まれたあげくに歌い出したぞ、というような映画的体験を、ドミー・シー(石之予)監督にはぜひ期待したい。
■荻野洋一
番組等映像作品の構成・演出業、映画評論家。WOWOW『リーガ・エスパニョーラ』の演出ほか、テレビ番組等を多数手がける。また、雑誌「NOBODY」「boidマガジン」「キネマ旬報」「映画芸術」「エスクァイア」「スタジオボイス」等に映画評論を寄稿。元「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」編集委員。1996年から2014年まで横浜国立大学で「映像論」講義を受け持った。現在、日本映画プロフェッショナル大賞の選考委員もつとめる。
■公開情報
『インクレディブル・ファミリー』
全国公開中
監督:ブラッド・バード
配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン
(c)2018 Disney/Pixar. All Rights Reserved.
公式サイト:disney.jp/incredible
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内





