『dancyu』編集長・植野広生が語る、“食の雑誌”を作り続ける理由 「世の中の食いしん坊を笑顔にすることが役割」
21/2/18(木) 8:00

コロナ禍で「食」をとりまく環境が大きな変化を余儀なくされた2020年。その年末に創刊30周年を迎えた『dancyu』は、「食」を扱う雑誌として確固たる地位を築き、食のプロを含め、食を楽しむ老若男女のハートをがっちりとつかんできた。
植野広生氏は、2017年4月に同誌の編集長に就任。食いしん坊を自負し、テレビやラジオ、読者との交流など、多方面で精力的に活動している。出版不況のなかにあっても好調な『dancyu』の誌面作りなどについて、大いに語ってもらった。
男女関係なく厨房やお店でいかに食を楽しむか
――植野さんはもともと『dancyu』ではライターとして参加されて、そのあとにプレジデント社に入社されて編集になったという流れなんですか。
植野:以前は日経ホーム出版社で、「日経マネー」という財テク雑誌を編集していました。その傍らで『dancyu』は創刊の1年後ぐらいから書き手として加わり、今から20年ぐらい前、当時の編集長に誘われてプレジデント社に転職したんです。それまでは「おいしかった」のシャレ、大石勝太というペンネームで『dancyu』や『週刊文春』で食の記事を書いていました。
――『dancyu』は「男子も厨房に入ろう!」を略したタイトルで創刊されましたが、コンセプトでずっと変わってないもの、反対に変わったものはあるんでしょうか。
植野:創刊したときは「男子も厨房に入ろう!」という言葉が成り立つぐらい、男の人があまり料理をしない時代でした。でも、今は男が料理を作るのは当たり前なので、男性も厨房に入ろうということはあまり謳っていません。男性女性関係なく、厨房、もしくはお店でいかに食を楽しむかというほうにシフトしてきていると思います。
創刊当時の号を振り返ってみると、男の趣味の週末料理みたいな特集がけっこうあったんです。今でもそういう特集はあるんですけど、大仰に構えるのではなく、ちゃんとおいしく、楽しく食事をしましょうという側面が強くなってきています。どちらがいい悪いではなく、30年間ずっと「今本当に美味しいもの、楽しい食事は何なのか」をその時点、その時点で考えています。そのときどきにみんなが楽しんでもらえるものを提案したいので、「うちはグルメ情報誌じゃなくて食いしん坊雑誌ですよ」とよく言っているんです。
――内容としてはクッキング・レシピとお店紹介、うんちく的なものをずっと核にされているんでしょうか。
植野:そのベースは創刊以来30年変わっていません。ただ、4年前僕が編集長になったときに、表紙の左上にある「食こそエンターテインメント」というキャッチを「『知る』はおいしい。」に変えました。食がエンターテインメントという考えは今では当たり前なので、ちょっとしたことを知るだけで普段の食事がおいしくなったり楽しくなったり、普段作ってる料理がもうちょっと上手になったりするよという意味で「『知る』はおいしい。」に変えたんです。
「食いしん坊」を打ち出した理由
――「食いしん坊」というキーワードは、植野さんが編集長になられてから大きく出されるようになったんですか。
植野:グルメというよりは、もうちょっと幅広く食を楽しみたい人たちに向けていろいろなことを提案していきたいので、「食いしん坊雑誌ですよ」と明確に打ち出すことにしたんです。食情報があまりなかった30年前と比べて、今は食の情報が氾濫しています。そのなかで、『dancyu』が何をやっているのかを明確な言葉で伝えなければいけないという思いもありました。「じゃあ食いしん坊ってなんなの?」ということでいろんな定義もしましたけど、僕が食いしん坊の代表として具体的なケースになることで、みなさんにちょっとでもわかってもらえればいいなと思っています。
特集テーマを決めるのは食いしん坊の空気
――食のおもしろさを毎号毎号、いろんな角度から伝えられてると思いますが、特集のテーマはどう決められているんでしょうか。
植野:テーマは基本的には僕が決めています。スタッフ達からの提案を受けて選んだものも含め、常に1年先ぐらいまでの年間ラインナップは用意しています。ただ、テーマを決めるにあたっていちばん大切にしているのは食いしん坊の気持ちなので、このラインナップを直前に変えることもあるんです。株式投資にはこの企業に投資したい、株を買いたいといった投資家心理を指標化したサイコロジカルラインというものがあるんですが、食の世界でも食いしん坊のサイコロジカルラインがあると思っています。世の中の動きや旬に関係なく、食いしん坊達が見てるもの、食べたくなるものがある。それを一番重視しているんです。
――それは世の中の食いしん坊からデータ収集するというよりはご自身の感覚で?
植野:自分がこれ食べたいなという感覚も大事にしていますが、飲み食いしにいった先で世の中の食いしん坊たちがどういう行動をしているのかも参考にしています。でも調査ノートを持って人が飲んだものや食べたものをリサーチするようなことはしません。そうしたデータの積み上げで出た結論っていうのは雑誌のテーマとしては面白くなくて、もうちょっと感覚的なもののほうが面白いと思うんです。
だから僕は誰かと一緒に飲食するとき、グルメライターさんや食の評論家といった食関係の人とは割と行きません。リアルの食いしん坊の感覚というのは、知識や情報が豊富な人たちの感覚よりも街のなかにあったりする。プライベートで特に一緒に飲み食いするのは、食とは関係ない世界の、食や酒が好きな人たちです。そういう人たちとふつうに飲み食いしてバカな話をしていると、感覚的に「ああ今やっぱりこういう感じだよね」となんとなくわかるんです。
――そうして食いしん坊のサイコロジカルラインを掴むんですね。
植野:データよりも漠然としたイメージを考えて、そのうえでテーマを決めていきます。ただ、読者アンケートの結果のような、スタッフに対して示す根拠はないので、代わりにこういうふうに伝えると読者がついてきてくれるよという方向性を示しています。このテーマならこういうコンセプトでやるときっと面白いよとか、食いしん坊に刺さるよとか。僕の役割としては方向性、目指すところを示すことがいちばん重要だと思っています。正解なんて誰にもわからないですし、スタッフが同じ方向さえ目指していれば、あとはもうみんなバラバラなことをやったほうが雑誌は面白いんですよ。
たとえば以前、羊の特集をやったときは「ちょっと羊に興味があるとか、羊を食べてみたいって人は一切対象にしなくていいから、本当の羊好きだけにあてて作ってね」と伝えました。結果その号は他に比べると売り上げが伸びなかったんですが、反応はすごくよかったですね。
紙媒体は特にプロがプロの仕事をしなければならない
――昨年来、飲食業界はコロナ禍の影響を大きく受けています。お店紹介をはじめ、誌面作りでも影響は出ているんでしょうか。
植野:かなり出ています。去年の春に肉料理の特集(7月号)をやったときは取材ができないので、半ば開き直りもあってほぼ1冊リモートで作りました。料理研究家の方にご自分で写真を撮っていただいたり、料理上手のカメラマンに料理作ってもらったりしたんです。ただ、これは僕としてはいちばんやりたくない手法でした。紙の媒体は他と比べ、よりプロがプロの仕事をしないと成り立たないと思っています。たとえばカメラマンだけでも和食が得意な方、洋食が得意な方、フレンチが得意な方などがいて、そういったプロ中のプロにプロの仕事をしてもらっています。でも、ステイホームでそれができなかった。雑誌の存在意義にも関わってくるようなことで、僕自身も改めて、紙媒体や仕事のあり方、編集者としてどう向かい合うべきかなど、いろいろ考えさせられましたね。
――苦肉の策だったんですね。普段の『dancyu』を読んでいると、とにかく写真も文章もおいしそうで、「食べたい!」という感覚になります。撮影でカメラマンに「これだけは守って」とお願いしていることはあるんでしょうか。
植野:カメラマンさんの場合は、きれいな写真より美味しい写真をということですね。思わず手が伸びる、食べたくなる、作りたくなるような写真を撮ってくださいとお願いしてます。たとえば真俯瞰で料理写真を撮ったらかっこよく見えます。でも、そこに箸とかフォークを持つ手が伸びるかといったら、伸びません。真上から食べる人はいないですから。客の目線で見たときに美味しそうに見えるかどうかが勝負なので、『dancyu』の写真は、基本目線なんです。
あとは、これは編集者の問題でもあるんですが、リアリティを持った写真を撮るようにとも言ってます。たとえば居酒屋で飲んでいる写真を撮るときに、お酒とお皿だけあるのか、そこにお箸もあるのかで、本当に飲んでいるように伝わるかどうかは大きく変わります。さらにはそのお箸は箸置きに乗っているのか、小皿に置いてあるのか、こうした割り箸ひとつで、その店のイメージや雰囲気、飲んでる人の感じの伝わり方が違ってくるんです。
僕の編集長としての仕事はリアリティのなさを解消していくことがけっこう多くて、違和感潰しと呼んでます。もしも載せた写真にリアリティがないと、読者に感覚で「なんか変だな」と思われます。そうなると本屋さんで手に取ってもらえても買ってもらえないんですよ。どんな仕事でもそうだと思いますが、一般の方の「なんか変」「なんか嫌」という感覚をいかに少なくするかは、売れるか売れないか、媒体として存続できるかできないかの大きな差になると思います。
――写真が語ることは決して少なくないんですね。ライターにはどのような要望をされてるんでしょうか。
植野:お店紹介だったら、ネットを見れば書けるような原稿ではなく、その店で実際に飲み食いをしないとわからないことを書いてほしいと常に思っています。うちは記事のためにいろいろな情報を集めていますが、どんなに信頼のおける方からの情報でも、必ずスタッフやライターさんと一緒に食べにいきます。読者である食いしん坊が実際に食事にいったときにどういうふうに楽しめるかという体験してくるわけです。
だから、どういう雰囲気だったか、どういう味わいだった、どういう楽しみ方をしたか、どういう説明を受けたか、具体的な情報を書いてほしい。もっと言うと「友達同士でワイワイ行くのに合っている」「上京してきた親御さんを連れて行くと喜んでもらえる」といった具体的なイメージやシチュエーションまできちんと伝えてほしいんです。
プロから教わるレシピは翻訳が重要
――レシピはプロから教わったものをちゃんと家庭でできるように編集されているそうですが、料理をしない読者もいれば、毎日料理を作る読者も多くいらっしゃいますよね。どのあたりのレベルに向けて、レシピを編集されてるんでしょうか。
植野:統一の基準とか初心者向け、上級者向けというのはまったく考えていないんです。編集として意識している『dancyu』のターゲットは食のアクティブ層です。記事を読んで、店紹介だったらその店に行く人や行こうと思う人、レシピだったら作る人、作ろうと思う人たちです。それはテーマや内容によってもかなり変わるので、毎回、このテーマだったらこのあたりに食のアクティブ層がいるなと考えるところにきちんと当てようと思っています。
レシピはこの食のアクティブ層、作ろうという興味のある人だったら誰でもできるようなものにしています。一般の方が絶対にできないものは載せないのが基準といえば基準ですね。かといって、完全に初心者用の誰でもできるものまで噛み砕くと、なんのためにプロに教わってるのかわからなくなる。プロに教わるのは、そこにプロならではの知恵とかコツとかノウハウがあるからです。そこをきちんとどう汲み取って翻訳するかが問題で、内容によってはコツとかポイントだけをしっかり紹介することもあります。あるいはプロの使う食材や出汁の取り方を載せたうえで、一般の方ができて、近い味に仕上げられる方法を書き添えることもあります。
雑誌が売れなくなった理由
――出版業界は縮小し続けているなかで、食を楽しむというコンセプトがしっかりあることが、『dancyu』の強みでもあるんでしょうか。
植野:こういうことを言うといろいろな人に怒られるかもしれませんが、なんで雑誌が売れないかといったらつまんないからなんですよ。『鬼滅の刃』や『ONE PIECE』はめちゃくちゃ売れている。それは面白いから、ファンがついているから売れるんです。うちの反省も含めて言うと、みんなけっこうまとまっていて、雑誌としての面白みがちょっと欠けてるかなと思っています。
『dancyu』のスタッフには「もっとぶっ飛んで欲しい」と言ってます。みんなが同じ方向さえ向いてたらいいので、特に若い人なんてどんどんぶっ飛んで、僕が驚くぐらいのことをやってほしいです。テーマを外さなければ何をやってもいいし、そのためだったらどんな人とも会える。この雑誌編集者としての最大限の面白みを活かせていないんじゃないかと思うんですよね。
今言ったことをできてるわけではないですが、『dancyu』は食いしん坊雑誌だというコンセプトが、レシピとかも含めてより現実的に今の世の中の食が好きな人にハマってるんだろうなと思います。そのベースにあるのは食いしん坊の気持ちやサイコロジカルラインです。だから、予約がとれない店、行列ができる店というのはほぼやらないですし、対価として考えて不当に高い店もやりません。そういう店は話題にはなるけど、ごく一部の人しか参加できない。『dancyu』が目指しているのはみんなが参加できるところ、食いしん坊全員参加型です。そうすることで読者がファンになってくれると思っています。
これからを担う編集者には何が必要か
――なるほど。ところで、スタッフ以外の方も含め、若い編集者の方達に求めることがあるとしたら、どのようなことでしょうか。
植野:とにかく編集技術よりも好奇心を磨いてほしいです。やはり編集者が多彩なる好奇心を持っていないと、なかなか読者に対して魅力を伝えることはできません。そのうえで常に「なぜ」という探究する感覚を持つことですよね。これは食の雑誌にかかわらず、「なぜ」と思ってそれをちゃんと聞いたり調べたりすることが絶対必要だと思っています。
好奇心に「なぜ」が加わることで独りよがりで終わらず、読者との共有ができます。とはいえ、当たり前のことはみんな「ふーん」で終わってついてきません。そうではなくて「あ、言われてみればそうだよね」という、その感覚がすごく微妙なんです。僕は1mm下の共有感と言っています。深すぎると「うーん、うーん、あ、そっか」とワンクッション、ツークッション出てしまうけど、1mmの薄皮の下ぐらいの潜在意識を掘り起こせれば「ああ、そうだね、ふだん思ってないけど言われてみたらそうだよね」となる。そこをいかに感覚として持つかは編集者としてすごく重要なことだと思っています。これができればたぶん何をやっても、どんな媒体でも面白いものができると思いますよ。僕もウェブの世界も見るようになったので、紙にしろウェブにしろ編集力を高めて、アホかって思われるぐらい雑多で爆発的に面白いことをみんなでやっていくと、メディアの世界が楽しくなってくると思っています。
2021年、『dancyu』はどうなる?
――『dancyu』も紙だけでなくウェブも展開されていますが、両者の住み分けは、どういうところを意識されてるのでしょうか。
植野:住み分けというよりは、別冊ムックなども絡めていろいろなリンクをしようと思っています。それぞれ別の媒体として存在しつつ、いろいろなものがリンクすることで「本だけではなくて『dancyu』のプロジェクト全体がなんか面白いね」とファンがついてくれる形が理想です。ですから、今後は、紙もウェブもリアルイベントも全部含めて、『dancyu』という世界のコンセプトをいっそう明確にして、ファンが集まるようにしたいですね。
――今後の話では、2021年はこうやりたいと決まっていることやこうなるだろうと考えていることはありますか。
植野:こういう大変な時期で、食の雑誌、媒体として何ができるかなと僕なりに考えたこともあるんですが、結局、今までやってきたことを続ければいいという結論なんですよね。『dancyu』は今日お話ししてきたように、何か難しいことや流行に左右されることなく、今何がおいしくて楽しいかということをずっと追って、それを提案してきました。だから、コロナに関係なく、同じことを続けるしかない。世の中の食いしん坊達を笑顔にすることが役割というか、ちょっとでも力になれればいいなと思っています。
また、コロナで不自由な思いをしたり、自由に飲み食いできなくなったりしたことで、本来の外食の楽しさや料理を作る面白さに気づきはじめた人が多いのではないのでしょうか。僕らだけでなくお店もそうかもしれないですけども、いい意味でシンプルに原点へ戻るような動きになるのではないかと思っています。
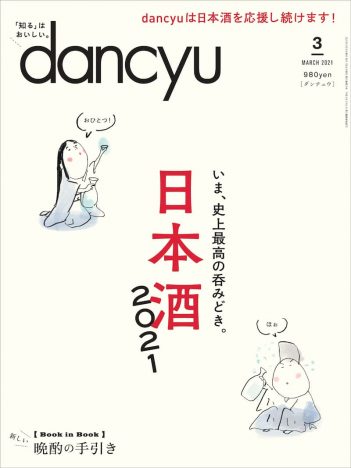 ■書籍情報
■書籍情報
『dancyu』2021年3月号
特集:日本酒2021
出版社:プレジデント社
発売日:発売中
定価:980円(税込)
サイトURL:https://dancyu.jp/read/2021_00004201.html
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内



