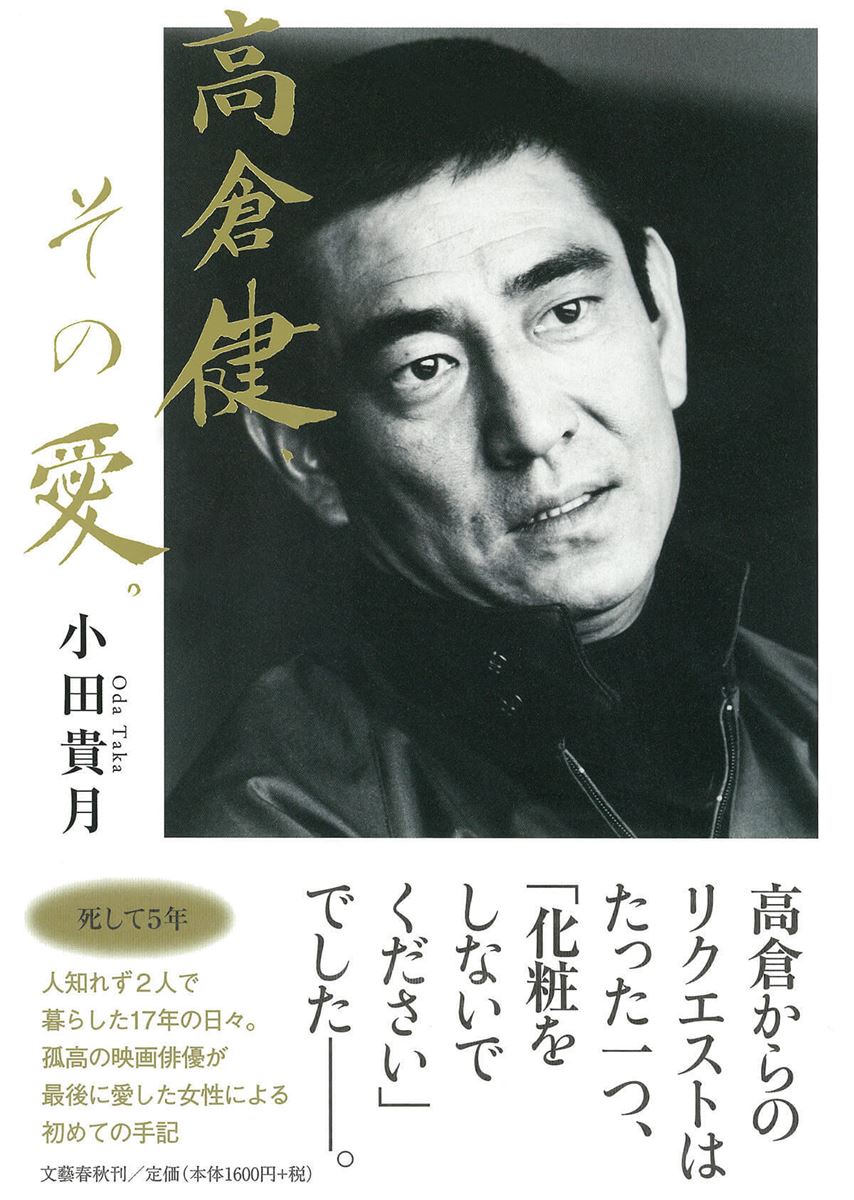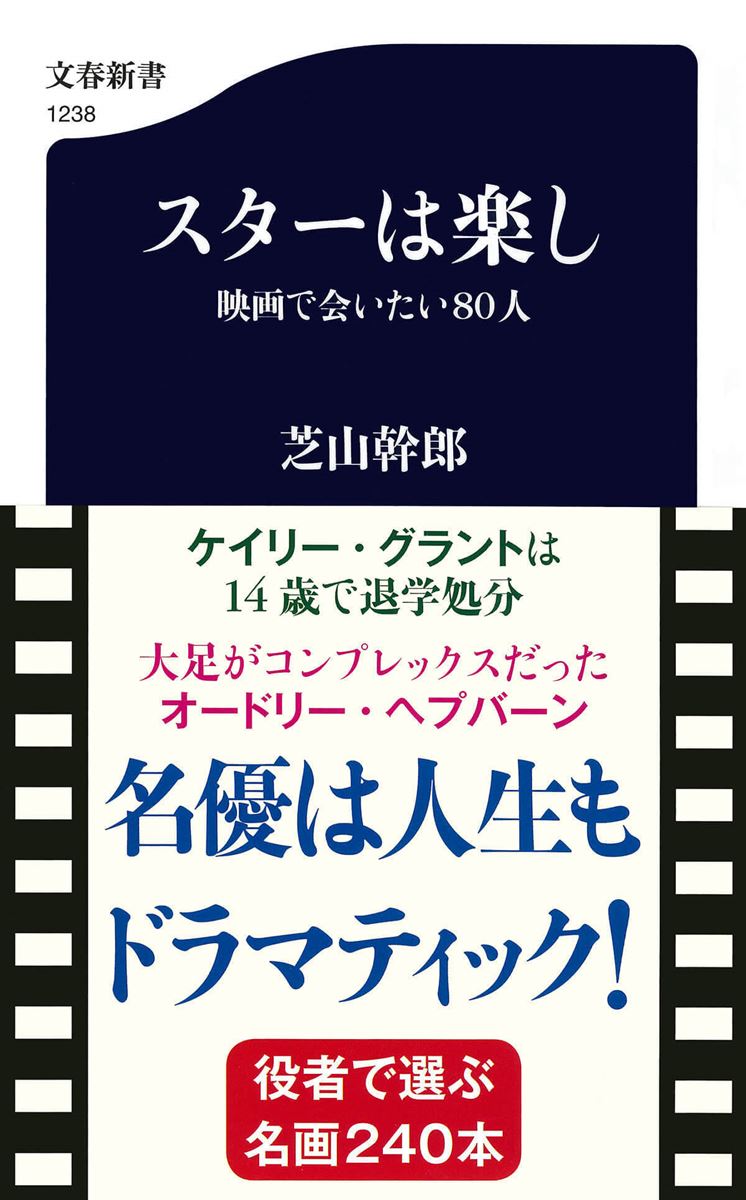植草信和 映画は本も面白い
映画通でなくても面白く読める! 伝説のプロデューサー関連本ほか
毎月連載
第30回
19/12/10(火)
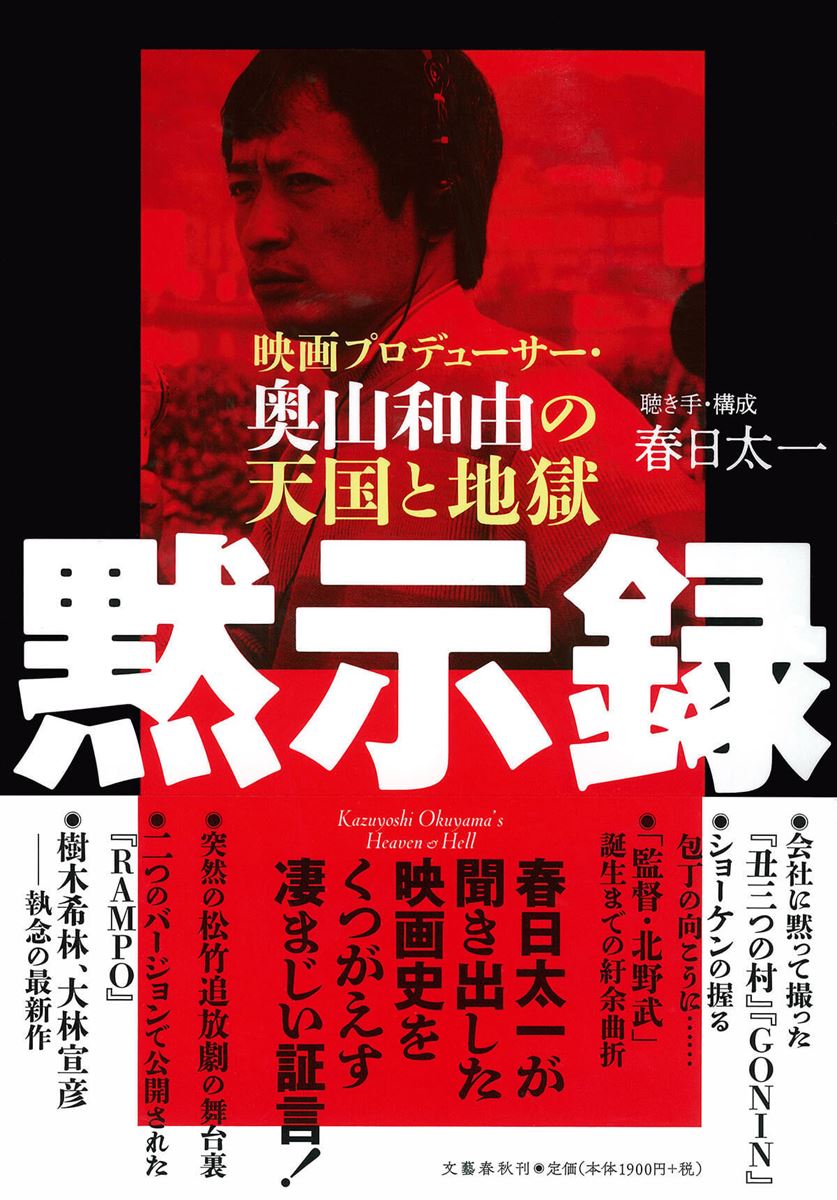
『黙示録/映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』
『黙示録/映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』春日太一著(文藝春秋/1900円+税)
出演者や監督で映画館に足を運ぶことはあっても、プロデューサーの名前で映画を選ぶ人は、まずいない。
映画関連書籍もそれと同じで、俳優や監督についての本は多いがプロデューサーに関する本は極めて少ない。我が書棚には永田雅一、城戸四郎、マキノ満雄、森岩雄、岡田茂、藤本真澄、本木荘二郎、児井英生、田中友幸、金子正且、俊藤浩滋、日下部五郎、伊地知啓(翻訳書ではダリル・F・ザナック、ロジャー・コーマン、ロバート・エヴァンス)の評伝・自伝・インタビュー集など、十数冊が並んでいるのみだ。
なぜプロデューサーに関する本は作られないのか。「売れない、興味がもたれない」と味もそっけもない答えしかないのだが、久しぶりに登場したプロデューサーの本『黙示録/映画プロデューサー・奥山和由の天国と地獄』は、映画にあまり興味がない一般の人でも面白く読める本になっている。
約40年間で100本以上の映画を作ってきプロデューサーの奥山和由に映画史家の春日太一がインタビュー。その帯文には「春日太一が聞き出した映画史をくつがえすすさまじい証言」とある。
13の章から成り、第1章の初プロデュース作『凶弾』から第13章『銃 2020』までの70本余の作品の成り立ち、それに関わったキャストや監督について縦横無尽に語りつくされる。
初対面の三船敏郎に出資させた『海燕ジョーの奇跡』、五社英雄監督と組んだ大作『226』、ビートたけしを監督に抜擢した『その男、凶暴につき』、今村昌平監督に二度目のパルム・ドール賞をもたらした『うなぎ』、才能に奉仕するのがプロデューサーの仕事だと気づかせてくれた深作欣二監督との『いつかぎらぎらする日』などの製作過程が克明に明かされる。さらに萩原健一、桃井かおり、樹木希林、ロバート・デ・ニーロらとの交流秘話が語られているのだから、面白くないわけがない。
奥山が格闘したのは映画作りだけではない。存亡の危機に瀕しているにも関わらず無為無策の旧態依然とした映画業界人への怒りから、改革にも挑む。
「堕ちていく組織にありがちな組織論と忖度だけで合議制をとっているご都合主義の映画作り」が許せない奥山は、松竹改革のために全重役を相手に孤軍奮闘する。
そしてあの「松竹追放劇」。第12章「追放―ある男の告白」では、一夜にして松竹を追われた役員会の模様が、ドキュメンタリー映画のようなリアル感をもって語られる。
人並外れた熱量を武器に映画作りに挑んだ男の語りおろし一代記。映画とは何かを、読む者に激しく問うている書でもある。
『高倉健、その愛。』小田貴月著(文藝春秋/1600円+税)
高倉健との17年間に及んだ私生活の一部を綴った小田貴月の手記『高倉健、その愛。』は2回の重版により累計発行部数が3万部に達した、と情報メディアSPICEが伝えている。
「僕は、貴より先に死ぬよ、多分……。順序から言えば、先だろ。そしたら……僕のこと、書き残してね。僕のこと一番知ってるの、貴だから」という故人の言葉が執筆の動機になったという本書は、序章「僕のこと、書き残してね」から始まり、4章で構成されている。
第1章「高倉健への旅のはじまり」では香港での最初の出会いから共に暮らし始めるまで、第2章「時を綯う」では高倉の日常生活、第3章「言葉の森」では出演作品、監督、共演者のこと、第4章「Takakura‘s Favorite Movies」では彼が愛した映画についてのコメント。終章の「樹影澹 あとがきにかえて」は、「澹は、風や波によってゆっくり動くさま。今、独り見つめる樹影澹に、高倉の気配や笑顔を重ねています」という文章で締めくくられている。
故人が私生活で何を考え、何を食べ、どんな映画が好きだったのかなど、著者に直接語った故人の“言葉”で浮き彫りにされていく。だが、読後、「肝心なことが語られていない」という隔靴掻痒感が残ったのは、なぜだろうか。
本書でなければ知り得ない多くのことが書かれているのは確かだ。例えば丹念に書き込まれている食事のこと。亡くなるまで欠かさず食べていたというグリーンサラダについて、中華料理、イタリアンのメニューなど故人の嗜好や作り方にかなりのページが割かれている。そうだったのか、健さんはこんな食べ物が好きだったのか…。
それはそれで興味深い。しかしそれよりも健さんファンが知りかったのは、「週刊新潮」をはじめとするメディアが報じる故人の実妹など小田家親族と著者の相克だ。
「週刊文春」(11月14日号)の『阿川佐和子のこの人に会いたい』で小田貴月と対談した阿川はその後記で、「貴月さんのお話を伺えば伺うほど、納得できたりできなかったりの繰り返しで、もやもやとした余韻がいまだ心の片隅に残っております」と書いている。
本書の読後感はそれに似ている。健さんが望まなかったであろう世俗の騒動に終止符を打つ本にならなかっことが、残念でならない。
『スターは楽し/映画で会いたい80人』芝山幹郎著(文春新書/1200円+税)
私事だが、映画AとBの両方を観たいけれど物理的にどちらかを選ばなければならないという事態によく直面する。そんなとき、昔は双葉十三郎氏の「ぼくの採点表」を、今は週刊文春「シネマチャート」の芝山幹郎の短評を参考に選択している。
AかBか、右か左か。その勝率は高い。当代きっての目利きである芝山の指摘は的確で狂いがなく、笑顔で映画館を出ることが多いのだ。
その芝山幹郎の新刊『スターは楽し/映画で会いたい80人』は、2006年から2018年まで月刊「文藝春秋」に連載された同名コラムから選び出された80篇に、「新書化に際しては、スターの肖像をスケッチするだけでなく、それぞれの代表作を三本ずつ、手短かに紹介した」(はじめに)。つまり240本の解説が“おまけ”で楽しめる本と、いうことになる。
登場する古今東西の映画スター80人を「名人」「怪人」「巨人」「妖人」「野人」「麗人」「才人」「奇人」の8つのジャンルに分類し、生い立ちやエピソードを交えてその演技や人間性を論じていく。
そのどれもが興味深く、面白く、読ませる。できれば全部を紹介したいのだがムリな相談なので、忘れ難いものだけを2篇ピックアップする。
「名人」篇のピーター・セラーズ。ビリー・ワイルダー監督と衝突して降板した『ねえ! キスしてよ』撮影中のこと。「彼は十七歳年下の(スウェーデン女優)エクランドに夢中だった。というより、若い肉体に溺れていた。“究極のオルガスムス”を求めたセラーズは、ポッパーズを服用してことにおよんだ。(中略)その副作用は劇甚だった。セラーズは三時間に八回も心臓発作を起こし、病院に緊急搬送された。一命こそ取り止めたものの、映画の降板は避けがたい。知らせを聞いたワイルダーは冷たく言い放った。『ハートアタックを起こすほどのハートが、あいつにあったのか』」。
「巨人」篇のジョン・ウェイン。『駅馬車』でブレイクした翌年「ウェインは危険きわまりない魔女に遭遇する。魔女とは六歳年上のマレーネ・ディートリッヒだ。ディートリッヒはウェインを釣った。『妖花』の共演で初顔合わせをした直後、ウェインを楽屋に招き入れた彼女は“いま何時かしら”と問いかける。ウェインは時計を見ようとしたが、それより早く、ディートリッヒはスカートをめくりあげ、黒のガーターベルトに結びつけた時計をしめしていた。“まだ早いわ。時間はたっぷりあるのよ”。誘惑完了」
その他、14歳で退学処分されたケイリー・グラント、大足がコンプレックスだったオードリー・ヘップバーン、14歳年上の女性に調教されたクラーク・ゲイブルなど紹介したい文章が山ほどあるが、こんな調子で書き出していったら、いくら文字数があっても足りない。
僅か1800文字で長年のキャリアをもつ名優たちの本質を抽出する、鮮やかな分析能力は名人芸だ。映画が楽しくなる一冊として超おススメしたい。
プロフィール
植草信和(うえくさ・のぶかず)
1949年、千葉県市川市生まれ。フリー編集者。キネマ旬報社に入社し、1991年に同誌編集長。退社後2006年、映画製作・配給会社「太秦株式会社」設立。現在は非常勤顧問。著書『証言 日中映画興亡史』(共著)、編著は多数。
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内