荘子itによる批評連載スタート 第1回:『Mank/マンク』から“名が持つ力“を考える
21/3/7(日) 10:00

0.荘子itは電気蝶の夢から覚めるがーーー 令和/映画の起床/批評
判で押したような「覚醒せよ」に、どれだけの意味があるのか。令和の時代にラッパー/トラックメイカーとして表現をし、そして今ここで映画の批評を始めようとしている荘子itにとって、それが問題である。
よしんば今こそ覚醒が必要であるとしても、それを直接的に言ってみせることを、徹底的に疑い抜く表現者や批評家が、もっといてもよいのではないか。荘子itはラッパーとして、耳に心地よいだけのアフォリズムやパンチラインやハッシュタグの怠惰さに敏感であるよう努めてきた。
現在、芸術や文化が立たされている危機とは、人々がそれを求めないことにあるのではなく、むしろ、誰もがそれを渇望していて、しかも、常にすぐそこにあるにも関わらず、その本当の姿を直視し、心から信じることはできないまま、「でもこれがそれだよね?」、と目配せし合いながら、担ぎ上げ温存していることにあるのではないか。温存も行き過ぎれば、さしずめ聖火リレーのように虚しい熱狂を生む。
そのような状況に、冷や水ではなく、coolならぬfoolな風を吹かせるために、この連載は書かれることとなる。「令月にして、気淑く風和ぎ」の令和の風紀を乱すために。儀式の火にくべる以上の異常な空気を送り込む。
芸術体験とは、主体が揺さぶられ、それ以前と以後では、世界が一変して見えるような体験であるに違いない。問題はその後だ。様々な形で美や崇高さに触れ覚醒した者も、翌朝には、それでも変わらないこの世界に改めて深く絶望し、どんなに素晴らしい表現や作品がこの世にあろうと、全ては無意味であると悟る。また同じ絶望を味わうくらいならこのまま目を覚ましたくないと思いながら眠りにつく。そしてまた目が覚める。真の「覚醒」などない、毎日ただ繰り返される「起床」に、なんの意味があるのだろうか。
荘子itの由来である荘子に倣えば、無意味はあるがままの様相として肯定される。しかし、本当の意味で無意味に耐えられるほど人は強くないのではないか。もし耐えられるように思えるなら、それは本当の意味で無意味と向き合うことを回避しているのではないか。荘子itが荘子にitをつけて、so嫉妬、so糞などのネガティブな意味を付与したのはそのような意識からだ。荘子のようになりたいし荘子はクソだ。荘子の胡蝶の夢も説話としては明晰だが、だからこそ無色透明すぎて、フロイトがes=itで名指したような余剰がない。
荘子itの夢はもっと不気味なものだ。それを直視することだけが唯一の誠実さだと信じる荘子itは、道家的達観を離れ、自らの凡庸さ、無知、醜態を晒しながら、わずかばかりの、だが確かにある意味を探求してみせ、真に良心的な道化たらんとするだろう。深淵な道教から愚直なストリートの思想(=路教)へ踏み出す余剰の一歩がitだ。令和の元号が『万葉集』からの引用であっても、元を辿れば中国オリジンであるように、荘子itは荘子から生まれたが、派生物はオリジナルに全て還元可能なわけではなく、むしろ余剰はそれ自体が独立した意味を持つばかりか、あまつさえ逆流して根源を侵食する。ジャック・デリダはそれを「代補」と呼んだ。
もはや大いなる「覚醒」はないにも関わらず、毎日のように「起床」することだけは変わらない。そんな状況での批評とはどのようなものか。無意味と戯れながら、ソムリエ的に鑑賞眼や哲学や美学を磨いていくことではない。そのような態度に荘子itは一切興味を惹かれていない。夢の中の胡蝶の羽ばたきが風を吹かせたバタフライエフェクトの結果として、現実に竜巻を起こし、夢を見ていた荘子itの布団を吹っ飛ばすような、虚構の果てでそれが自壊する運動を詳細に捉え、その意味を探究すること。それが本連載のテーマである。
1.『市民ケーン』から『Mank』への追想

『Mank/マンク』(以下、『Mank』)は、映画監督のデヴィッド・フィンチャーとその父ジャック・フィンチャーの親子が、「史上最高の映画」と名高い『市民ケーン』の脚本を書いた、映画史的には目立たぬ存在であるハーマン・マンキーウィッツ(=マンク)を題材に、ポーリン・ケール著『スキャンダルの祝祭』を下敷きに構想した作品だ。無名のまま亡くなった父ジャックが遺した脚本は、息子デヴィッドが映画監督として大成功しながらも、ヒットの見込みが薄い企画故に長年温め続けられ、ついにNetflix製作の後ろ盾を得たことで念願叶って映画化された。父の影響で映画を観始めた息子による、起源は極私的にして遠大な射程を持った本作を当連載第1回の批評対象としたい。
『市民ケーン』に冠される、「史上最高の映画」という誇大なコピー(英『Sight&Sound』誌で10年に一度批評家が選ぶランキングで50年連続1位、米映画協会の「アメリカ映画ベスト100」や仏『カイエ・デュ・シネマ』の「映画史上ベスト100」で1位などの実績がある)がいつから独り歩きし始めたのかわからないが、日本大学芸術学部映画学科監督コース出身の荘子itが学生時代、授業で『市民ケーン』を観させられた際にも教授から、「この作品は 、“史上最高の映画ランキング”の1位です」という不条理コントじみた前置きがなされた。今ならジャルジャルあたりがやりそうなネタだが、かつて、ダウンタウンの「お見舞い 世界1位」という、大病を患い死を目前に控えた子供役の浜田雅功を励ますために、「世界1位の男」役である松本人志がお見舞いにきて、「ぼくが世界1位だよ」と只管告げるだけのコントや、鈴木清順監督の『殺しの烙印』という、殺し屋の男が「殺し屋ランキング1位」を目指して、殺し屋ランカー同士でひたすら無為な戦いを繰り広げるだけの映画などで、それらの常軌を逸した不毛さに対するフェティシズムに目覚めていた荘子itは、大いに興奮した。

1941年の映画である『市民ケーン』を観た現代の学生の多くが、率直に退屈だと感じたり、一体どこが「1位」なのかと文句を言う気持ちもよく理解できる一方、荘子itは『市民ケーン』、ひいては、監督兼主演兼プロデューサーであるオーソン・ウェルズに魅了された。ウェルズのふてぶてしく不遜な「甘やかされた子どものような顔」(ポーリン・ケール)は、底の抜けた「1位」性を体現するに相応しい相貌だったからだ。むろんこのようなフェチは、全てのフェチがそうであるように倒錯していて、階級やランキングというものの根拠に実感が湧かない現代日本っ子が、その恣意的で権威主義的で、ナンセンスの織物のように見える世界の自動性をむしろ徹底する振る舞いによって冷笑(そしてその無根拠ゆえに際限なく哄笑)する態度だ。ポスト・モダン的主体の無根拠さへの痙攣的防衛反応であったのかもしれない。そのようなフェチは今では一抹の寂しさとともにだいぶ癒えてしまったが、若き荘子itの趣味趣向を著しく方向付けたことは間違いない。
最初はそのような不純な出会いだったが、映画とは不思議なもので、その後もオーソン・ウェルズの作品を色々観ているうちに本当に好きになってしまったし、多くのことを学んだ。映画は「夢」の隠喩で語られるが、必ずその余剰として「現実」の残滓を嫌でも鑑賞者に浴びせかける。それが冷や水となって、見世物小屋の観客は叩き起こされ、時には革命的な思想に「覚醒」してしまうことさえある。しかし、何度も「覚醒」を経験するうちに、それはルーティーン化し、観るだけでは満足できなくなり、次第に人は映画について語り出す。日々、「起床」するようにして、作品を見ては友人と語り合い、あまつさえTwitterやFilmarksで不特定多数のフォロワーに向けて自らのレビューを開陳する。より良い「起床」は「覚醒」に似ていて、その実それがまだ夢の中の出来事であっても、同じ夢の中でそれを眺める人々にとっては啓示として受け取られることすらあり得る。

映画学科を中退してラッパーになって数年、今になって『市民ケーン』を題材にした新作映画『Mank』が公開された。荘子itは、インストール済みのわずかばかりの映画史への知識を駆使するのみならず、様々な過去作の観直しや読書や検索を経て、本作の含意を汲み取る過程を大いに愉しんだが、むろんそのために必要とした情報を単に読者へ伝達することが目的ではない。本稿は、夢の正しい見方を提示するものではなく、いかにしてその外部に至ったかについて検討するものだ。夢の中で蝶になってひらひらと愉しみながら、その羽ばたきが瞬きとなって微睡みを晴らすような運動に寄り添うことが批評だ。だが、今現在夢の中にいるものが、どうして自ら目覚めようと/自らを目覚めさせようと思うのか。「覚醒」した気になって、『エヴァンゲリオン』の旧劇場版でもあるまいし、他者がいない世界で他者が必要だとひとりごちてみせてもしょうがない。「起床」は、ひらひらと舞ううちに、単なるエラーとして、たまたま訪れるしかない。
2.一文字違いの“Kane”と“Mank”の階級交差空想(cross-class fantasy)

Netflixを開いて、『Mank』の開始19分30秒過ぎ〜を再生してみよう。女の叫び声で起床したマンクは、ひどい二日酔いだ。叫び声の所在へ向けてフラフラと歩き出す。再び女の叫び声。辿り着いたのは西部劇(?)の撮影現場で、叫び声の主は女優のマリオンだった。1927年に『ジャズ・シンガー』が公開されて数年、いまだ映画はサイレントからトーキーへの移行期で、この現場で撮られているのも、どうやらサイレント映画のようだから、現場から離れた屋内で眠っていたマンクを起こすほどのマリオンの叫び声が録音されて劇場の観客に届くことはない。むろんサイレント映画の演技でも口パクとは限らないが、それにしてもそんな大きな声で叫ぶ必要はないだろう。マリオン曰く、「パパのアイディア」だそうだ。「パパ」とは、マリオンを愛人として囲っている大資産家ウィリアム・ハーストのことだ。ハーストの指示で、マリオンは今のうちから「トーキーに出る準備」をさせられているらしい(註:1)。

この、観客が決して聴くことのない叫び声でマンクは「起床」し、偶然にも撮影現場を訪れることになったわけだ。自明かつ必然とされてきた映画史に隠された裏側の物語に焦点を当てる本作を象徴するシーンといえるだろう。とにかくこの偶然の出来事を通して、相反する二人に思えるハーストとハーマンは出会い、あろうことか意気投合して親しい交流が始まる。より正確に言えば、権力者ハーストが、物怖じしない皮肉屋のハーマンを気に入って可愛がるようになったということで、それは非対称的権力関係を甘んじて受け入れたうえでの蜜月であり、ハーマン・マンキーウィッツは「オルガン弾きのモンキー」として飼われ始めるに過ぎない。だが、この階級交差体験が、やがて「史上最高の映画」の称号を得る『市民ケーン』の物語をマンクに書かせるのだった。

ある視点から、『市民ケーン』は、資産家ケーンという虚構のキャラクターを通じて、現実のハーストの実情を暴いた告発映画と目されてきた(註:2)。事実、現実のハーストは気に入らず圧力をかけて映画の興行を妨害した。また、『Mank』は、映画史においてオーソン・ウェルズの功績として知られてきた『市民ケーン』が、実はハーマン・マンキーウィッツの単独執筆によって生まれたものだと告発したポーリン・ケール著『スキャンダルの祝祭』を下敷きにしている。後に、この本における「ウェルズはほぼ一切脚本に関わらずマンクが一人で書き上げた」というケールの行き過ぎた主張は、より実証的なかたちで否定されている。

しかし、むろんこの二つの映画は単に「尊大な権力者を糾弾する」に留まる作品ではない。その側面もあるにせよ、『市民ケーン』及び『Mank』は、丁寧に読み解けば一方からの断罪的な告発映画ではないことが分かる。『スキャンダルの祝祭』においてさえ、「ウェルズとケーン、そしてマンク自身がよく似ている」ことが指摘されているように、彼らの関係は、(少なくともマンクからみて)自他の境界が溶け合っているようだ。コインの裏表のような二者が根底で共鳴する関係性は様々な文学作品、例えば、『Mank』の劇中で(史実でも)ウェルズが映画化しようとしていたコンラッドの『闇の奥』におけるマーロウとクルツや、フィッツジェラルドの『華麗なるギャッツビー』におけるニックとギャッツビー、さらに階級構造としては反転するがケルアックの『路上』におけるサルとディーンなどに通じる。また、『闇の奥』と同様にウェルズが長年映画化しようとしてついに実現できなかった『ドン・キホーテ』や、これまた『Mank』の劇中で引用される『白鯨』のような、「究極の片思い(=パラノイア)」の文学は、前述のような想像的領域における同一化をしたとて、厳然たる両者の差異は埋まらないという事実を示すものであるとともに、それらがマンクの側から饒舌に語られることで、やはりハーマンとハースト(≒ウェルズ)という裏表の関係にある二者の共鳴を示唆している。“Mank”と“Kane”はそれぞれ一文字違いで、両者の余剰である二文字を組み合わせると“Me”になる。

また、『Mank』がこのような「文学的な」想像力が隅々まで浸透した映画であることは、少なくとも『スキャンダルの祝祭』発刊当時の(現代ですら根強い)映画批評における「作家主義」が、「監督」(ウェルズ)に芸術性の拠り所を求めたのに対し、「脚本家」(マンク)の貢献を主張していることと切り離せない。フランソワ・トリュフォーの「詩的リアリズム批判」や、ヌーヴェル・ヴァーグ以降の映画批評や蓮實重彦的表層批評の文脈からみると、『Mank』作中でハーマンがマンクに対して言った、「これからはトーキーの時代だから文学が分かる脚本家が必要だ」という言葉はあまりに安直で「純映画的」ではないように思われる。だが、インターネットや、『Mank』を制作/配信するNetflix以降の時代の映像文化全体を見回してみれば、事態はそれほど単純ではないだろう。映画を映画館での上映やテレビの放映に合わせて観る時代から遠く離れて、PCやスマホのブラウザ上で、YouTuber/VTuber的な投稿映像や、リアリティショーやSNSにおける、筋書き(脚本)はないが、その代わり極めて直接的な欲望を刺激するエンターテインメントが、現実の人間をエージェントとして自然増殖する状況において、前述のヌーヴェル・ヴァーグ以降の「映画批評」や、ロラン・バルト的な「作者の死」を謳い上げ、表層やテクストそのものに徹底的に留まる態度(ヌーヴェル・ヴァーグ以降の「作家主義」も単なる現実の「作者」とは異なる、作品内在的な批評から遡行的に見出されるような「作家」を仮構する営為ではある)に、かつてのような現状批判力はない。現実が追いついて(行き過ぎて)しまったのだ。

『Mank』のクライマックスでは、マンクが自らの名を脚本家としてクレジットすることを要求してウェルズと対峙するシーンが、ハースト邸のパーティでマンクがハーマンと対峙した回想シーンと並行して描かれる。最終的にマンクは『市民ケーン』のクレジットを獲得し、アカデミー脚本賞を得る。マンクが唯一積極的に匿名の「オルガン弾きのモンキー」であることをやめて、映画史に「ハーマン・マンキーウィッツ」という名を作家として残したことは、彼の単なる功名心以上のものとして受け止める必要があるだろう。『Mank』劇中にも登場する映画プロデューサーのアーヴィング・タルバーグは、ウェルズに似て「若き天才(The Boy Wonder)」の名をほしいままにしたが、自らが手がけた映画にほとんどクレジットされていない。マンクとは打って変わって、「自らに与えるクレジット=信用になんの価値もない」と語る彼は、すでに充分すぎるほど「成功者」だったからそう言えたのだ。ここにも厳然たる非対称性があることは言うまでもない。対して、「ハーマン・マンキーウィッツ」や「マンク」という名が、映画史の置石として鎮座するに至ったことには極めて重要な意義がある。それは明晰な論理を越えた力である。そのことを語るために、次節では「固有名」についての議論を参照する。
※註1:直前のシークエンス冒頭のテロップに従えば、このシーンも1930年である。現実では、マリオンは女優としてこの時点で既にトーキー映画に出演しているはずなので辻褄が合わず、この設定は創作ということになる(むろん本作は、『スキャンダルの祝祭』の内容の是非を越えて、そもそも作劇上多くの部分で脚色が加えられている)。寝て起きたことで時代を遡ったと無理やり解釈できなくもないが、タイプライターを模したテロップがないため、本作の演出の原則上(例外はあるが)考えにくいだろう。いずれにせよ、あえてこのやり取りを抽出しその「起床」の意味に注目する本稿の趣旨は変わらない。
※註2:本作を現状の社会情勢に照らし合わせれば、フェイクニュースによる情報戦によって対抗馬を蹴落とし当選する共和党サイドを描くことで、何を批判しているか明白である。ただし、本稿で述べているように、本作は単純な民主党支持路線の告発映画ではない。インタビュー等で伺えるように、フィンチャー自身、いかにハースト達にとってもフェアに描けているかを重視している(参照:David Fincher’s Impossible Eye|THE NEW YORK TIMES)。
3.彼はなぜ“Herman”ではなく“Mank”と呼ばれるか
批評家/思想家の柄谷行人が『探求2』において行った整理に従えば、「固有名」が持つ注目すべき性質とは、「一般性」の中で「他ではない」と区別する「特殊性」ではなく、そのような体系の中での記述の差異に還元され得ない、「他ならぬこのもの」を直接に示す「単独性」である。
それ自体が柄谷「固有」の用法である「単独性」と「特殊性」の区別を短い紙幅で詳細に定義し尽くすことは本来難しい。あえて即席で感覚的に理解してもらうならば、例えば次のような説明があり得る。「豚」という「一般性」の中で、「一級ブランドの食肉用の豚」は、他の凡百の豚と比べて貴重なものであり、その意味で「他ではない」「特殊性」がある。それをあなたは美味しく頂くだろう。しかし、「ペットとして可愛がって育てた豚」は、多くの場合名前をつけるだろうし(そして実際に名前をつけたかどうかに関わらず)、「固有名」的な存在であり、それがどんなにありふれた豚であろうとも、「他ならぬこの豚」である以上、「単独性」を持ち、あなたはそれを食べることを躊躇うだろう。(余談だが、『豚がいた教室』という映画はこの点を議論し尽くす前に教育という名目で「他ならぬこの豚」を食べるという恐るべき結末が用意されていて、荘子itにとっての「トラウマ映画」である。)
さてこの概念を実際の作品に対してどう使えるか。『市民ケーン』というタイトルは、映画史(=「歴史」)において「単独的」な「固有名」であるが、その名をあえて記号として分解してみる。「(新聞王)ケーン」という特権的な「名」は、誰よりも成功を手にした男を表すので、人類一般の中で秀でる「特殊性」を帯びたメディアを賑わす記号であるとも言えると同時に、それに「市民」という「一般性」を表す普通名詞が冠されていることで、落差が生まれる。「並外れた成功者」(特殊性)のイメージを帯びたケーンもまた、多くの人々と同じく、一人の「市民」(一般性)である(『市民ケーン』の劇中でも、ケーン自らそのようなイメージのアピールとしてこれを自称するシーンがある)(註:3)。また、ケーンが死の直前に口にした“Rose Bud”という言葉も、少年時代のソリに刻印された文字のことで、あらゆる成功を手にした彼が最期に望んだのは、母親と過ごした少年時代の幸福な思い出で、結局それは他のどんな財によっても埋め合わせ難いものだった、というのが『市民ケーン』の基本的な感動惹起構造である(むろん、有名な「実は“Rose Bud”というのはハーストが愛人のマリオンの女性器につけたあだ名」というエピソードも描かれているので、この部分のフィクションとしての解釈は「映画的」に多様に開かれている)。そうして、記号やイメージが引き剥がされたところでようやく、ケーンという人物の「単独的」な有り様が映し出されるというわけだ。
柄谷の「固有名」の議論で重要なのは、「固有名」が、「話すー聞く」という対等な関係からではなく、「教えるー学ぶ」のような非対称な関係によって伝達されるということだ。それも、『市民ケーン』という「固有名」の伝達が、 デヴィッド・フィンチャーの場合は「父と子」の間であり、荘子itの場合は授業での「教師と教え子」の間であったりしたという具体的なことに限らず、原理的に、「固有名」の「単独性」は、同じルールを共有する間柄ではない関係によってしか伝えられない(柄谷はこのような形でのコミュニケーションのあり方を「命がけの飛躍」と表現している)。仮に、「固有名」を伝達された子や教え子が、それを元とは全く別の意味で理解したり使用したりしたとしても、元を辿れば、それが使われてきた固有の歴史性は残り続けるので、「単独性」は消えないとした。
「固有名」が記述に還元できないと言った通り、たとえ、「『市民ケーン』を書いたのはハーマン・マンキーウィッツ一人だった」(=『スキャンダルの祝祭』の主張)という命題や、反対に、「やっぱり『市民ケーン』はウェルズとハーマンの共同執筆だった」」(=『スキャンダルの祝祭』への反論)という命題が真であり、それ以前の『市民ケーン』に関する記述が訂正されたとしても、やはり『市民ケーン』の「単独性」は消えないということになる。
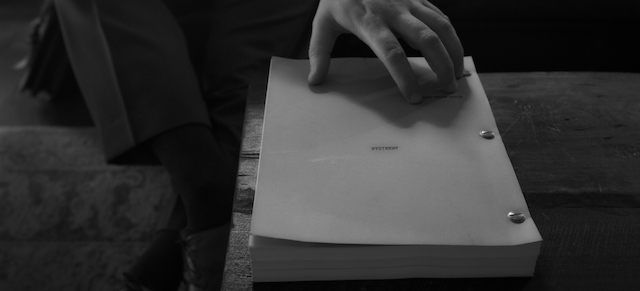
この議論については、柄谷の影響下にある批評家/哲学者の東浩紀が初期の著作『存在論的、郵便的』で批判的検討をしている。東によれば、このような、「固有名」がいくら訂正されようとも「単独性」を持つという議論には注意しなければならないと指摘した。東は本書を通して、一つの空虚な中心を前提とした否定神学的思考には批判的であり、「固有名」が「単独的」であると言う柄谷の議論を転倒させ、むしろ、「単独性」より、「固有名」が事後的に訂正可能であること(=「訂正可能性」)の方が、現実の(誤配にまみれた「郵便的」)コミュニケーション空間に開かれた議論としてより重要であるとした。その後の2000年代の批評が、比較的、「アーキテクチャ」や「二次創作的」なものを積極的に語る方向に向かったのはそのためである。また、より文学的な見地からは、ループものや可能世界の議論を経て、再帰的に一回限りのこの生を肯定するに至る過程を描き出す試みがなされた。『市民ケーン』もまた、他の様々な形でもあり得る可能性を帯びているからこそ、これだけ強い「固有名」として残り続けているのだ。
その意味で、『スキャンダルの祝祭』を下敷きにした『Mank』は、『市民ケーン』や「オーソン・ウェルズ」、「ハーマン・マンキーウィッツ」といった「固有名」の「訂正可能性」についての作品である。

しかし、果たして『Mank』の可能性はそれに尽きるだろうか。『市民ケーン』という作品の虚実交えた二次創作として、あるいは、単独的な映画史への批評的アプローチとしてのみ機能するのだろうか(実際、本作を手法的側面、例えば30-40年代オマージュに見える様々なギミック、タイトルロゴや音声や照明が、現代のデジタル技術でしかありえない仕方でアップデートされていることに注目し、「見かけ上はヴィンテージだが、実は極めてモダンな作りによる、古典的ハリウッド映画様式への批評」とみることができるだろうが、本稿の論旨からはずれるので割愛する)。
※註3:あるいは、“Citizen Kane”の企画当初のタイトルが“American”(アメリカ人)だったことから、「市民」という言葉を、単なる一般市民としてではなく、「アメリカ」という国の固有な歴史における「単独性」と理解することも可能である。(そもそも、「citizen=市民」という言葉自体が、国家に対して積極的に関わる「近代的主体」という意味で、単なる「民」や「大衆」とは定義的に異なるものであることには注意すべきだ)
ここでさらに別の観点で柄谷の固有名論に批判的検討を試みた議論を参照する。在野研究家の荒木優太は、文芸誌『しししし』(『草獅子』から改名)で連載された論考『柄谷行人と埴谷雄高』の中で、柄谷的な「歴史」ではなく、かといって東的な「二次創作」的な想像力に力点を置くのでもない形で、オルタナティブな議論を展開している。それは、「固有名」が様々な「別の固有名」に派生すること、即ち「異名」についてである。

マリオンとの出会いのシーンで、彼女はマンクをハーマンという彼のファーストネームで呼ぼうとするが、彼は自分をマンクと呼ばせる。
「Mr. Mankiewicz. Or shall I call you “Herman”?」
「No, please call me “Mank”.」
「Mank/マンク」とは、「Herman J. Mankiewicz/ハーマン・マンキーウィッツ」という名前のファミリーネームからとった「異名」である。むろん「オルガン弾きのモンキー」にかかっていて、ラストで自らを「自分で作った罠にかかったネズミ」、「逃げ出せないように自分で定期的に罠を修理してる」というマンクを象徴したアイロニカルなあだ名として受け取ることができるだろう。そのように理解すれば、マンクは基本的に負け犬であり、『Mank』は、持たざる者が権力者にわずかな一撃を食らわせ、自らの最高傑作のクレジットという形で映画史にかろうじてその名を刻んだという一点を示すに過ぎない。

だがそうではなく、「異名」とは、「固有名」が形成する大きな歴史や物語から見落とされ、忘れられていく「名の私生児」であり、『Mank』はそのようなヴァルネラビリティを伴った実存に徹底的に寄り添おうとした作品である。複数に派生する「固有名」とも言うべき「異名」は、「教えるー学ぶ」の伝達経路からして、「父ー子」や「教師ー教え子」のようなトップダウンの非対称性の形を取らず(かといって反転したボトムアップの形をとるわけでもなく)、“please call me Mank”のような水平なコミュニケーションによって、ある主体の意固地さによる非対称性を通して伝達される。
映画用に創作された人物であるシェリー・メトカーフの悲惨な事件によって、「覚醒」したドラマティックな瞬間に力点を置く読みでは見落としてしまうものとは何か。酩酊を繰り返しては、毎度ハッと「起床」するマンクの人生を、特異点ではなく、ある時間の幅を持った線の持続として示そうとしたところが本作の多義的な魅力である。ある人間の実存に真摯に寄り添って描くにあたって、その人生全体に対して肯定的であったり否定的であったりすることはできない。

ところで、本作には本来マンクと呼ばれる権利を持つはずの人物がもう一人登場する。史実においては、マンクよりはるかに「有名」である、ジョセフ・L・マンキーウィッツだ。彼は、劇中で描かれた物語の後、1949年と1950年の2年連続で監督賞と脚色賞を受賞する巨匠となる。ところが、『Mank』の序盤から中盤にかけては、マンクから「お前は俺の弟だから才能があると思われてる」と言われ、ファーミリーネームにちなんだ愛称は兄のもので、「ジョー」というファーストネームからとったあだ名で呼ばれている。だが最後にはマンクから、「マンキーウィッツという鳥だ」と呼ばれる。速記者のリタとマンクの会話だ。
「A rare bird thatー」
「ーa Mankiewicz.」
猿やネズミと違って飛べる彼は、その後マンクを遥か越えて「飛翔」し、「マンキーウィッツ」という名を特権的なものとして轟かせることになる。だが、繰り返し述べてきたように、あくまで『Mank』という作品は、飛べない方のマンキーウィッツについての映画であることによって、「マンキーウィッツ」という「固有名」ではない、「マンク」という「異名」を掬い上げるものとして、彼の人生の一点における「覚醒」ではなく、線的持続として繰り返される「起床」の有り様に寄り添って語られねばならない。
4.次回予告
今回は連載第1回として、『Mank』を足掛かりに、名が持つ力について書いた。荘子itという名やこの連載タイトル自体が、「固有名」をズラすことで生み出されたものであり、そのような名を弄ぶ想像力の根幹となっている思想を示した。次回からはより具体的に作品内在的に語り、様々な「起床」を試みていきたい。
■荘子it
1993年生。2019年に1st Album『Dos City』で米LAのDeathbomb ArcからデビューしたHip HopクルーDos Monosを率い、全曲のトラックとラップを担当。民族音楽やフリージャズ、哲学やサブカルチャーまで奔放なサンプリングテクニックで現代のビートミュージックへ昇華したスタイルが特徴。様々なアーティストへの楽曲提供に加え、ドラマ、映画の劇伴音楽、エッセイや映画評執筆など、越境的に活動している。
2020年3〜4月にかけてアメリカツアーを予定していたが、直前でコロナにより中止。その後、台湾のIT大臣オードリー・タンfeaturing曲等、精力的に楽曲をリリースし、7月24日に2nd Album 『Dos Siki』をリリースした。Twitter
■配信情報
Netflix映画『Mank/マンク』
Netflixにて独占配信中
監督:デヴィッド・フィンチャー
出演:ゲイリー・オールドマン、アマンダ・セイフライド、リリー・コリンズ、チャールズ・ダンス、タペンス・ミドルトン、トム・ペルフリー、トム・バーク
公式サイト:mank-movie.com



