『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』とは何だったのか 庵野秀明監督による“繰り返しの物語”を振り返る
20/8/26(水) 8:00
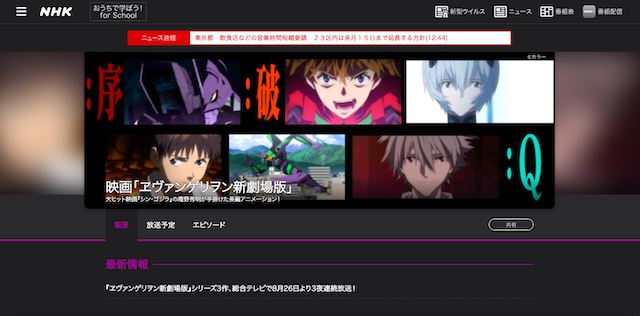
TVアニメの放送が1995年に開始されてから、その圧倒的な内容で熱狂的なファンを増やし、社会現象と呼ばれるまでになった『新世紀エヴァンゲリオン』は、1997年の春、夏に2本の劇場版が公開され、主人公・碇シンジの物語は終焉を迎えた。それから10年後に公開が始まった、同じ主人公を迎えて描き直す新たな劇場版シリーズが、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』だ。“エヴァ”の生みの親である庵野秀明監督自ら、制作スタジオ“カラー”を立ち上げ、ふたたびエヴァンゲリオンを世に送り出す企画をスタートさせたのだ。
しかし、シリーズは当初の構想を大幅に逸脱したものとなった。度重なる製作の延期や、合間に監督の『シン・ゴジラ』(2016年)への参加などがあり、新たな劇場版エヴァは、もはや第1作の公開より13年の月日が流れ、現在もまだ完結していないという、ほとんど監督のライフワークといえるようなものになってしまっている。それでも本シリーズの完結編になるといわれている『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が、東宝、東映、カラーの3社で共同配給となるという事実は、エヴァという作品がいかに多くの観客に待ち望まれた作品なのかということを、如実に示しているといえよう。
そんな『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズ3作品が、この度NHK総合テレビで3夜連続で放送される。ここでは、これまでに公開された新劇場版『序』、『破』、『Q』を振り返り、本シリーズが何だったのか、“エヴァ”とは何だったのかを、あらためてじっくりと考えてみたい。【※以降、TVシリーズ、旧劇場版、新劇場版のネタバレを含みます】
規格外のアニメ、TVシリーズと旧劇場版
そのために、まず振り返らなければならないのは、TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』と、“旧劇”と呼ばれるその劇場版である。最近、Netflixでこれら旧作が配信され、世界各国でふたたびエヴァに関心が集まった。あらためて鑑賞してみて思うのは、いま現在味わってみても、その面白さや革新性はずば抜けているということである。近年、アメリカの大作TVドラマシリーズが、映画作品を超えるようなスケール感と作り込み、斬新な演出などによって話題を集めているが、まさにいま、そのような作品の多くと並べて見ても遜色ないどころか、いまだに打ち勝てるほどの深さと広がりがあるのである。
アニメーションに限らず、作品というものは画期的な部分がひとつでもあれば、話題になり得るし人々の記憶に残るものとなる。だが、こと“エヴァ”に関しては、そのような次元を超え、時代を象徴し飛び越える作品にまでなってしまっている。それは、これまでのアニメの常識を覆すような新しい表現が、ひとつのシリーズのなかにいくつも存在するからである。
例えば、舞台となる第3新東京市という、建物や電線に囲まれた日本的な都市フィールドでの、エヴァンゲリオンと人類の敵“使徒”との対決。『ウルトラマン』などの実写特撮作品を意識した、細部にまでマニアックなこだわりが反映しつつ、庵野監督の信奉する実相寺昭雄監督や岡本喜八監督などを意識したアヴァンギャルドな演出や画面作り。さらには押井守監督作に見られる叙情的な都市の風景なども利用し、無数のカットによる素早い編集で見せていくという、庵野監督にしか表現できない極端な趣向は、圧倒的にユニークで斬新な魅力を作品に与えている。
他にも漫画やアニメからは、『デビルマン』や『機動戦士ガンダム』、『伝説巨神イデオン』などからの影響も見られ、ある意味本シリーズは、日本のオタクカルチャーを、監督の偏愛によって総合したものとなっている。しかし、それが単なる“よく見る使い古された表現”の羅列であることを逃れているのは、それらを常に超えようとする、鮮烈にして強い意志が存在するからだろう。
庵野監督は、かつて宮崎駿監督の『風の谷のナウシカ』(1984年)のスタッフとして、巨神兵のシーンを担当していた。本作の主人公である碇シンジらが世界を救うために搭乗する「汎用人型決戦兵器・人造人間エヴァンゲリオン」は、まさにその巨神兵の姿を連想させるとともに、人間には制御しきれない強大かつミステリアスな力を持っているという共通点を引き継いでいる。
さらにパイロットが試験管のような形状の「エントリープラグ」に乗り込み、それをエヴァの巨大な体内へと挿入し、まるで母親に胎児が守られているような状態になるという、グロテスクな機体の制御システム。くわえて、「福音」を意味する“Evangelion”という言葉が象徴するように、SF世界のなかに宗教的な知識の裏付けを与えることで、エヴァンゲリオンという兵器は、これまでのロボットアニメの常識を覆すほどの情報量がつめ込まれた存在となっているのだ。
観る者を魅了する、複雑な謎と設定の凄まじさはエヴァンゲリオンだけにとどまらない。エヴァが守る新第3東京市の地下には、使徒を倒すために組織された「ネルフ本部」と、広大な謎の大空間が存在している。使徒はその最深部“ターミナルドグマ”に存在するといわれる「アダム」に到達するために次々と現れる。この大空間の構造は、「マルボルジェ」や「コキュートス」など、いろいろな部分の名称が14世紀イタリアの詩人ダンテの叙事詩『神曲』の「地獄篇」から取られている。
また、“父親を殺し、母親と姦淫する”という呪われた予言を告げられた男子が、放浪のなかで予言の運命に導かれていくというギリシャ悲劇の戯曲『オイディプス王』からは、碇シンジと両親との関係を抽出しているように、本シリーズは、前述したように宗教をモチーフとし、歴史的な文献や文学などをベースとしている部分が多い。
『新世紀エヴァンゲリオン』を手がける前、庵野監督はTVシリーズ『ふしぎの海のナディア』を監督し、全力投球で燃え尽きた状態にあったという。その後の監督作を見ても分かる通り、そもそも庵野監督の作風は、破滅主義かと思うほどに作品に労力を注ぎ込み、その度に魂を抜かれたような状態になっているようだ。庵野監督は『エヴァ』までの期間に、特撮やアニメーション以外に、小説にも多く触れ、文学というものが、人間が生きる上でより普遍的なテーマを追求していることに衝撃を受けたという。その中には、登場人物の名前を『エヴァ』の主人公の同級生の名前に引用した、村上龍の『愛と幻想のファシズム』などもあった。
「ヤマアラシのジレンマ」などのコミュニケーション不全をテーマとした、きわめて現代的な問題を扱いながら監督は、『機動戦士ガンダム』の悩める主人公の構図も借りながら、“自分とは何か”ということを突き詰め、監督個人の実感と焦燥へと肉薄。TVシリーズの内容は限りなく純文学的で、同時に狂気をともなったコントロールが効かないものとなっていく。それを前衛演劇のような演出をとり入れて描いたことで、TVシリーズの最終2話は、アニメーション作品としてはかなり難解なものとなった。
しかし、それがさらに『エヴァ』の価値を高めることに繋がった。ロボットアニメとしての爽快さやカタルシスが欠如した内容は、それまでのアニメファンの一部には不満を与えたところがあったが、その一方でロボットアニメのような作品に全く縁のない人々が、ジャンルを超えた『エヴァ』の魅力に気づき、幅広く様々な観客が熱狂的に支持することになったのである。
プロデューサーの助力もあり、初めて自身が企画を立てて、話づくりも演出も好きにできるという好条件を手にしたことで庵野監督は甦り、そのチャンスを最大限に活かすことで、ついに『エヴァ』を前人未踏の領域に進ませたのだ。
そして、最終2話を描き直すというかたちで製作された旧劇場版は、Production I.Gのスーパーアニメーターらの力も得て、活劇としての魅力を大幅にアップさせるとともに、クライマックスへと至る流れでは、TVシリーズ以上に先鋭化した前衛表現に突っ込み、実写パートを用意したり、当時の製作スタジオのガイナックスが落書き被害に遭った写真や、インターネット上での監督個人を罵倒・脅迫するメッセージを画面に映し出すなど、監督としてやりたい放題の限りを尽くしている。
奇しくも、完結編が上映された夏は、師匠のような存在の宮崎駿監督の入魂の大作『もののけ姫』との同時期公開となった。そのネームバリューから、公開館数の多い『もののけ姫』は『エヴァ』とは比較にならないほどの動員を獲得したが、純粋に作品自体の新しさや、後世に与えた影響で考えるなら、『エヴァ』はさらにその上に到達したといえよう。
繰り返しの物語「新劇場版」
とはいえ、このように自分の全てをさらけ出した、破滅的ともいえる作品を、その後も安定して連発できるわけはない。宮崎監督が、世界的な映画賞を次々と獲得した『千と千尋の神隠し』など、その後も凄まじい傑作をものにしていくのに対し、庵野監督は実写作品を撮ったり、少女漫画のTVシリーズを手がけるなど、新しい表現を目指したものの、『エヴァ』に並ぶことができるような作品を送り出せずにいた。
そんな庵野監督が、新たなスタジオ「カラー」を自ら設立し、もう一度『エヴァ』をやるという。当初の仮タイトルは、『エヴァンゲリオン新劇場版 REBUILD OF EVANGELION』だったことから想像すると、いまだ熱狂的なファンの多い『エヴァ』をもう一度、ハイクオリティなものとして描き直すことを想定したものだったのかもしれない。しかし、この新劇場版シリーズの企画発表時には、大げさといえるほどの熱意が込められた、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』所信表明「我々は再び、何を作ろうとしているのか?」も同時に発表され、この内容から旧作のファンは、懐かしくもただならぬものを感じ取ったのである。
庵野監督はそこで、“「エヴァ」はくり返しの物語です。 主人公が何度も同じ目に遭いながら、ひたすら立ち上がっていく話です。 わずかでも前に進もうとする、意思の話です。”と語っている。
『シン・ゴジラ』で言われていた「スクラップ&ビルド」という言葉。破壊しては作り上げ、また破壊して作り上げる。『エヴァ』を繰り返し製作することで、都市が全く新しい姿を見せるように、そこにはアニメーションの世界をより新しい境地へと導く予感と期待が漂う。
旧劇場版『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』の劇中に、印象的な場面がある。“神と等しき存在”と同一化を果たす過程のなかにある碇シンジは、精神世界のなかで、幼児期の自身が公園を模した演劇の舞台にいる姿を見る。シンジは幼くして母親を亡くし、父親もそばについていない状況。夕闇が迫る公園に子どもたちの親が現れ、友達が家に次々と帰っていくなか、シンジを迎えに来る者は誰もいない。シンジはひとりきり、砂場でネルフ本部を連想させるようなピラミッドを完成させると、それを憎々しい思いで蹴り壊してしまう。だがしばらくすると、シンジは涙を流しながら、またピラミッドを作り始める。
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』
まさに、“REBUILD OF EVANGELION”という仮のタイトルに最も近いといえるのが本作であるだろう。TVシリーズ第6話までの内容を凝縮し、もともとのTV版のシーンを基に、作画し直したりエフェクトをくわえ、ディテール豊かなものとして、旧作を視覚的により新しいイメージに甦らせている。
とくに『序』が評価された部分は、旧作にあった特撮的なこだわりをさらに追求した箇所にあるだろう。TVシリーズでは「ラミエル」と呼ばれていた、正八面体の形状をした使徒が、3DCGによって鮮やかに形状が移り変わっていく様子は、明らかに旧作よりも心躍らせる表現となっている。一見、同じストーリーの繰り返しに思えるが、他にも、旧作からの微妙な設定の変更が随所にあり、主題歌に宇多田ヒカルを起用するなどの工夫も見られる。
とはいえ、筆者のように“新しい「エヴァ」”を期待して劇場に観に行ったものの、拍子抜けした観客は多かったはずだ。本作の新しさはあくまでも表面的な部分にとどまっていたからである。そして旧作のような極太の明朝体フォントの巨大な文字を突きつけるような攻撃的な演出にも欠けている。
だが、たしかに旧作の6話までといえば、旧作としても実験的な演出はまだまだ抑えられていた部分にあたる。その意味では、この抑制は当然といえるのかもしれない。何より、新劇場版から『エヴァ』に触れる観客のために、世界観をある程度オーソドックスに描いていく必要もあったはずである。
そのなかで最も物議を醸した点といえば、TVシリーズの終盤に登場するはずの人気キャラクター、渚カヲルが早くも登場し、意味深なセリフを口にしていることだ。
その内容から判断すると、どうもこの渚カヲルだけが、TV版で描かれたエピソードを知っているようなフシがあるのだ。今回の「新劇場版」の世界は、TV版や「旧劇場版」の世界と地続きにあり、何度も同じような出来事が繰り返されているのではないか。そして、渚カヲルだけがそのことを知覚できているのではないか。
それを裏付けるような描写として、TV版では青い色だった海が、「新劇場版」では赤い色に変わっているという点が挙げられる。TV版では赤い色が見られたのは北極海のみで、「旧劇場版」によって広大な範囲の海が赤くなったのである。つまり、「新劇場版」の世界は、「旧劇場版」の後の世界なのではないかということである。また「新劇場版」では冒頭のシーンにもかかわらず、映し出される山肌には、TV版第3話でエヴァ初号機が投げ飛ばされた跡のようなものまで見られるのだ。
これらの描写が、ただのデザイン上の変更に過ぎないのか、そしてカヲルのセリフはただのファンサービスに過ぎなかったのか、それとも深い意味があるのかについては、驚くことに13年経ってまだシリーズのなかで明らかにされてはいない。
もうひとつ、気になるのは、碇シンジがクライマックスの戦闘時に、人類全てを自分が救うような状況に対し、本当にこれが現実の出来事なのか疑問に思う場面が存在するという箇所である。このシーンでは碇シンジが線画を強調した“絵”として描かれている。これは、TV版最終話でも見られた表現。そのとき碇シンジは、“神に等しき存在”と同一化を果たし、世界のかたちを創造できる力を手にしていた。
ここから、「新劇場版」は、碇シンジが旧作の物語のなかで、もう一度やり直したいという願いのなかで生まれた、“都合の良い作りごと”なのではないかという疑念がわいてくるのだ。そのように考えれば、渚カヲルの謎にも説明がつくのではないか。もちろん、これらはそれぞれ推論のひとつでしかない。
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』
『序』『破』『急』。これは能など、日本の雅楽にある曲や物語の構成にあたる考え方であるという。『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』が、このような物語構成によって進んでいくのだとすれば、『破』は当初のリズムや雰囲気を大きく変えるべく機能する作品であるはずだ。
基本的には『破』も、『序』同様にTVシリーズのエピソードを描いていく。具体的には、7話から19話までと22話、23話の内容を部分的に抜粋するかたちである。だが、列車の線路が分岐するように、当時の人物の運命が、TVシリーズとは異なる方向に進んでいくのが見どころとなっている。
その変化の象徴となっているのが、新たなエヴァパイロット、真希波・マリ・イラストリアスである。いまだ謎の存在である彼女だが、マリがシンジの行動を眺めながら、「都合のいいヤツ」「匂いが違う」というセリフを吐くように、本作の碇シンジには、やはり本人も気づいていない、何か裏に重大な秘密が存在するように感じられるのだ。
『破』における変化の中で最も驚かされるのは、旧作では消極的で内省的な性格の碇シンジが、まるで王道ロボットアニメの主人公であるかのように、急に熱血的な面を見せるクライマックスである。そしてTVシリーズでは救うことのできなかった登場人物を救出までしてしまう。
この描写は、当時賛否の声が乱れ飛ぶ状況を作り上げることになった。『エヴァ』を通常のロボットアニメの文脈で楽しんでいたファンは、『エヴァ』がついに“アニメ”に帰還したという喜びや高揚感から絶賛する向きがあった。一方で、エヴァを文学作品のようなものとして楽しんでいたファンは、本作の展開が日本のアニメーション文化の枠に収まるようなものとして、いったん結論づけられてしまったことに落胆していたところがある。
『破』に満足したファンの一部から、次回作の上映後に観客みんなでTV版の主題歌「残酷な天使のテーゼ」を歌おうという呼びかけがSNSで飛び出したこともあった。この呼びかけは、声優がSNSで反対したこともあり立ち消えになったが、本作がとにかく多くの観客に刺激を与えたのは確かなことだろう。
この高揚感は、のちに新海誠監督の劇場アニメーション『君の名は。』の大ヒットにも繋がっているように感じられる。初期作品『ほしのこえ』を観れば分かるように、新海監督は『エヴァ』の多大な影響下にあるアニメ作家のひとりである。そして、少年や少女の紡ぎ出す小さな世界が、大きな物理現象や人々の命運を左右するような『エヴァ』的な状況を描き続けている。
『君の名は。』が若い観客を惹きつけた理由のひとつは、自分にも手が届きそうな恋愛の世界が世の中に多大な影響を与えたり、自分たちの背後には大きな運命が存在しているという、ダイナミックなファンタジーを提供したという部分である。裏を返せば、将来への不安のなかで、そのような頼れる大きな価値観を若い世代が求めていたということではないだろうか。
そんな構図を、庵野監督は『破』において、そのまま直球で描いたのである。しかし、これは乗り越えるべき“アンチテーゼ”であったことが、次の作品『Q』で描かれることになる。
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q』
『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』のなかで、現在最も最も興味深いといえる作品が、“序、破、急”の“急”をもじった『Q』だといえよう。予告編の時点では、「Quickening(胎動)」と記されていたが、碇シンジが真実や自分の生き方を求めて苦悩する姿から、この『Q』は、クエスチョンの「Q」の意味合いが強いのではないか。
本作で碇シンジが目覚めると、シンジは「あれから14年経った」と説明される。ミサトやリツコなどは年齢なりの姿になっているが、シンジやアスカ、マリやカヲルは14歳のままの姿を保っている。アスカはこれを「“エヴァの呪縛”」と呼んでいるようだ。
シンジはその後カヲルから、『破』のラスト(つまり14年前)に、シンジが「二アサードインパクト」という現象を引き起こすトリガーとなったことで、人間が大量に死滅してしまったという、ショッキングな真実を告げられる。
「僕がどうなったっていい。世界がどうなったっていい」と言っていたシンジ。その行動の結果、人間が大量に死んでしまったのである。そしてシンジは、爆弾が仕込まれた首輪をつけられ、ほとんど犯罪者として扱われることになる。これは、『破』のクライマックスを喜び、「シンジが成長した」と喜んでいた観客に対し、冷や水をぶっかけるような皮肉な展開である。
この展開に対する批判も多い。代表的なところでは、碇シンジは何も知らずに行動しただけであり、ミサトもそんなシンジの姿勢に共感すらしていたのに、いまさら犯罪者扱いするのはおかしいというものである。しかし、シンジには本当に責任が無かったといえるだろうか。
『破』のクライマックスで描かれている通り、ネルフの指令と副司令には、このような事態が訪れることはある程度予測の範囲にあり、むしろこの状況を好機ととらえている部分がある。対して、ミサトやリツコ、パイロットたちを含める、人類を救うために戦ってきた人々は、ネルフのトップに騙されていたことを悟り、反旗を翻している。
その意味では、シンジ自身も騙されていたということになるが、彼はその過程で、目の前の少女を助けるために、「世界がどうなったっていい」と、たしかに願ってしまっているのだ。これは、前述したような、個人的感情が世界の存亡にまでかかわってくるという構造が生み出す高揚感に対する、危機感の表明ではないのか。
シンジは、自分の頭で考えることをやめ、自分にとって都合の良い言葉にすがることで、またしても破滅へと突っ走ってしまう。そんな姿を本作のアスカは、「ガキシンジ」と呼んでいる。つまり、『破』において自分たちさえ良ければ他人はどうでもいいという感情や、大きなものに頼ることで責任を回避したいと願うシンジの感情は、幼児的だったという批判になっているのだ。
その後撮られた『シン・ゴジラ』では、第二次大戦において政府が根拠のない楽観によって、約300万人の自国民を死なせてしまったことを批判している部分がある。そして、現在もまだ政府の幼児性は変わらず、そのまま成長することなしには、有事の際に日本が同じことを繰り返してしまうということを示唆している。そして、このようなテーマが、『Q』にも色濃く投影されているように見えるのだ。このメッセージは、旧作にも見え隠れしていたように感じるが、本作によって明確な像を結んだといえよう。
『Q』が公開された2012年の時点で14年前といえば、エヴァの旧作が結末を迎えたあたりである。所信表明で監督は、「エヴァより新しいアニメはありませんでした」と語っている。この“14年”という言葉は、その頃より監督や我々は、前に進むことができていなかったということを暗示しているのではないか。そしていまだに旧作の“『エヴァ』の呪縛に”とらわれていると言いたいのではないか。
『序』『破』は、旧作のアレンジといえる作品だが、『Q』は物語の一部に旧作の引用が見られるものの、このようなテーマが反映したことで、これまでとは決定的に異なる新作になったといえる。その意味では、旧作の『エヴァ』の続きは、ようやくここから始まったといえるのである。
最終作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』
テーマの上で、やっと前進を見せ始めた「新劇場版」。だが、いまだにTVシリーズや、「旧劇場版」を超えるインパクトを持ち得ていないように感じられるのもたしかだ。それは、前述したような画期的な要素がまだそれほど顔を出していないからだろう。
しかし、旧作が本領を発揮し、庵野監督の表現の限界までたどり着いたのは、やはりTV版の最終2話であり、「旧劇場版」である。この最終作をどう描くかによって、「新劇場版」の『シン・エヴァ』は旧作の『エヴァ』に追いつくことができるのか、そして乗り越えることができるのかがハッキリとするだろう。庵野監督にとって、本当の勝負作が次回作なのである。13年かけたシリーズの出来がついに決定するというのは、おそろしくもエキサイティングだ。
そして、かつて『エヴァ』がアニメーションを変えたように、その次のステージにアニメーションを進ませるものになるのかも、ついに明らかになる。
■小野寺系(k.onodera)
映画評論家。映画仙人を目指し、作品に合わせ様々な角度から深く映画を語る。やくざ映画上映館にひとり置き去りにされた幼少時代を持つ。Twitter/映画批評サイト
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内



