skillkills、tricot、ZAZEN BOYS、54-71、MIYAVI……独自のリズムで日本のロックを更新してきた者たち
音楽
ニュース
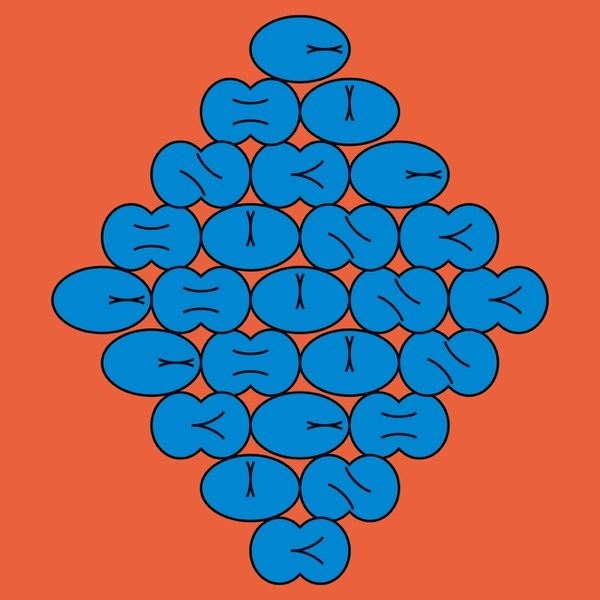
「四つ打ち好き」「横ノリよりも縦ノリ」「ミディアムテンポやブラックミュージックのような“ハネた”リズムは苦手」……俗に言われる日本人のリズム体質。80年代のバンドブームから今日に至るまで日本のロックといえば8ビートが主流である。縦ノリの8ビートでキックを効かせたテンポの速いロックナンバーはどのバンドでも人気がある。フェス文化が定着した2000年代、特に2010年代以降は“ノリやすい”、“沸きやすい”と言わんばかりの、ライブを想定したBPM(Beats Per Minute、テンポの単位)の高速化が進んだ。ただそれらはあくまで一般論であり、メインストリームの話でもあって、日本のロックのすべてがそうというわけではない。ちょうど最近リリースされた新譜の中で、そうした日本のロックのリズムに抗うような作品が2作あった。
(関連:LEO今井、人間椅子やZAZEN BOYSら楽曲で表現した新境地 ヘヴィーな音像を追求した理由を読む)
■日本のリズムに抗う新作
まずはskillkillsのニューアルバム『CHUNK』である。現在における日本のリズムの常識から最も遠いところにある作品と言っていいだろう。アンダーグラウンドでダウナーで、不穏な空気を漂わせている。それは、禍々しいことを歌っているというわけでも、楽曲が暗いわけでもない。どうノっていいのかわからないどころか、聴いているとなんだか不安になってくるような心地の悪いリズムだ。
“KING OF BEATS”を名乗る彼らの魅力は、その複雑で緻密に構築された不可解なリズムと規格外のビートである。楽曲の枠からすっぽ抜けていくようでちゃんと戻ってくる、つんのめってつまずきそうになりながらも一定のテンポを用いながらきちんと進んでいる……そう、彼らの楽曲に大袈裟な楽曲展開や突然の転調といった強引さはなく、自然を装いながらも歪なグルーヴを生み出しているのである。例えるなら、美しい日本語の文章であっても句読点やアクセント、イントネーションの位置をずらすことによって、文章を改変せずとも異国の言葉に聴こえたりするイメージに近い。その奇妙なビートに最初は戸惑いながらも、気がつけばどっぷりと深く沈められているのである。心地の悪いリズムはいつの間にか中毒性の高い心地良さに変わる。
もう1枚はインディーズシーンの女裏番長、tricotのメジャー初となるアルバム『真っ黒』。メジャーに行くと聞いた時、「満を持して」でも「今更!?」でもなく、なんとも言葉にできない複雑な感情を覚えたものだ。しかし蓋を開けてみれば、音楽面もマーケティング面でも申し分のない実力と実績のあるバンドにメジャーという強力な後ろ盾がつくとこうなるのか、と思わせる圧倒的なものを作り上げてしまった。「メジャーに行って変わってしまった」などということはこのバンドになかった。アルバム冒頭、「混ぜるな危険」のド真ん中のベースに右から斬り込んでくるギターと、ジェニーハイを経てすっかりミステリアスなフロントマンとしてのカリスマ性を得た中嶋イッキュウのアンニュイで婀娜めく歌、唐突に左から襲い来るキダ モティフォの慧敏な業、狂乱のリフバトルを耳にすれば、インディーズ、メジャーお構いなしに「勝った」と思わせてくれる斜め上からの爽快感。
変幻自在の変拍子、コピー不可能と言われるtricotだが、オリジナリティの真髄はその鳴らされるサウンドにあると思う。この手のオルタナティブロックバンドにありがちな、ジャキジャキとしたエッジ感がないのだ。リズムもアンサンブルも抜け目なく、体感上はシャープでタイトであるのに、耳をつんざく聴感上の嫌な鋭利さが存在していない。それはサウンドメイクといった表面的なものではなく、もっと本質的なところ、メンバー各々の腕と演奏力によるところが大きいだろう。飄々としていて素っ頓狂で、柔らかい耳馴染みの良さを持ちながらも聴けば聴くほど複雑で狂っている。歪んでいない、静かなるハードコアというべき攻撃性である。
こうしたリズムに抗いながら更新していくバンドやアーティストは、突然現れたというわけではない。日本のロックが発展していく中で、インパクトと共に大きな爪痕を残していった先駆者がいた。
■リズムに抗った先駆者たち
たとえば、54-71。ヘヴィなリフにラップというスタイルが主流だった90年代ミクスチャーロックの中で、隙間だらけのアンサンブルに一切の贅肉を削ぎ落としたシンプルでストイックなリズムと、極東を感じさせる奇天烈なボーカルが乗る異色のバンドだった。バスドラム、スネア、ハイハットという必要最低限のセットでリズムを刻んでいたbobo(Dr)はのちに、これまたロック界の異端児・MIYAVIとともに日本のリズムを更新していく。
向井秀徳という奇才も忘れてはならない。読経的でもあり落語的でもある、語り部というべきあの特異な節回しの歌と一体化したギター。ニール・ヤングや長渕剛といった、強烈な歌を歌うシンガーだからこそ生み出される独特のタイム感のギターストロークとカッティングを、自分のオリジナリティに昇華させた。
ZAZEN BOYSはそんな向井に寄り添い、絡みつくようなアンサンブルを持ったバンドだ。かのFreeのベーシスト、アンディ・フレイザーはバスドラムの軸から微妙にズラす“タメ”で魅了したが、ZAZEN BOYSは全員が絶妙な“ズレ”と“タメ”で聴く者を錯乱させていくのである。
■さらにリズムを更新していくバンド
現在、リズムを更新しているバンドはまだまだいる。不条理を抉っていく不安定なボーカルながらも、無駄のないシンプルなリズムが淡々と気持ちよく響くトリプルファイヤー。ハードコア、テクノ、ニューレイヴからトライバルの薫りまで漂わせる“スサシ”こと、SPARK!!SOUND!!SHOW!!はごった煮のミクスチャーながらも、日本のロックバンドらしいわかりやすさを持ったバンドだ。ボスニアをはじめとした世界各国の民族音楽を、“ウンザウンザ”とかき鳴らすバックドロップシンデレラは、今やフェスを中心としたライブシーンに欠かせない存在となっている。
こうしたリズムを自在に操っていくバンドに共通すること、それは“間合い”である。各楽器、音と音との“間”。音圧や重低音、音数の多さ……隙間を埋めていく派手なサウンドメイクが持て囃される中、あえて隙間を作っていく。それがグルーブとなり、心地良さになるのだ。弾かない鳴らさないカッコよさ、引き算の美学である。人間がいちばんリズムを感じ取ることが出来るのは、音が鳴っていない瞬間なのかもしれない。(冬将軍)

