ヨルシカの音楽が引き立てる、ストーリーの“輪郭と奥深さ” 映画『泣きたい私は猫をかぶる』から考察
音楽
ニュース
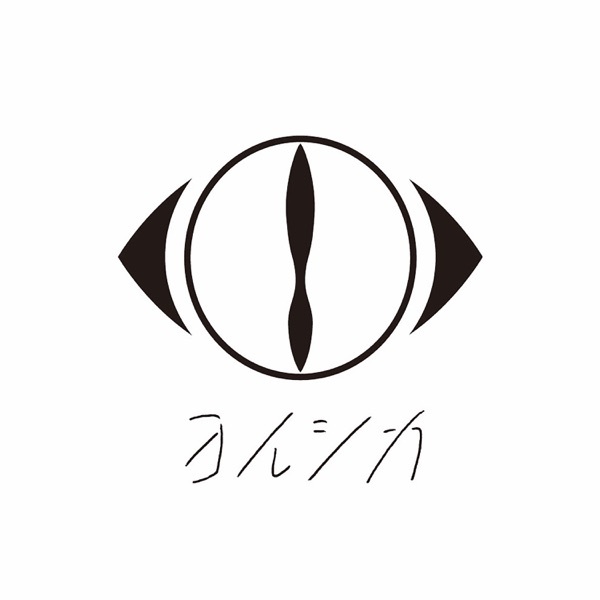
スタジオコロリドによる最新作『泣きたい私は猫をかぶる』が、6月18日よりNetflixにて全世界独占配信された。元々は6月5日に劇場公開を予定していたが、現在まで続く新型コロナウイルス感染症の影響により、劇場公開を断念した形となってしまった。とはいえ、新しいエンターテインメントを感じづらくなったいま、今作が無事に公開されたことをまずは喜ぶべきだろう。
佐藤順一と柴山智隆によるダブル監督体制となっており、脚本は岡田麿里、この時点でアニメファンはさっそく勘づくだろうと思う。恋愛、結婚と離婚、飼い主と飼い猫、家族それぞれの事情、個々人の感情、それぞれが重なり合いながら、人と人との距離感について丹念に描いている作品ではないかと、今作のタイトルを含めた予想は、おおよそ的を得ていた想像だと思う。
ヒロインである笹木美代は「自分が愛されるイメージができていない子」だと、作中にとある人物から言われる。他人との距離感をどのように捉えるか、それが彼女を悩ませることになる。作中では、その問題が現実のものとなってしまい、彼女はファンタジックな状況へと追い込まれてしまうわけだが、ここはネタバレとなるので書かずにいよう。
いうなれば今作は、「自分が周囲にどう愛されるか」というイメージ、そして「注がれているはずの愛情にどう気づき、受け取ろうとするか」という変幻を見届けるストーリーであろう。しかも笹木だけでなく、どの登場人物においても、それぞれに愛したい対象がいるにも関わらず、その距離感と愛し方が分からない、愛に不得手な人々として描かれている。特にそれは笹木美代の母親への描かれ方に表れているし、あっちの世界で登場する猫が発するセリフの中からでも、それは察することができると思う。
感情を象るヨルシカの音楽
本題へと移ろう。今回の記事における主人公は、ヨルシカである。
今作に、彼らは「花に亡霊」「夜行」「嘘月」の3曲を提供した。「夜行」のMVでは今作で使用された背景画を使って、オリジナルのMVを制作している。「花に亡霊」は今作の本編映像を使ったMVとなっており、文字通りにタイアップソングという側面が全面に出ている。これまでヨルシカのファンであった人からすれば、少し面食らうのかもしれない。なぜなら彼らは自身らのコンセプトに対して忠実であり、タイアップを手掛けるというイメージは結びつきにくかったからだ。
「何処までこちらの世界観で作ってしまっていいのかという心配をしていましたが杞憂でした。ファーストコンタクトで監督から自由にやってくださいと言われた時は心強かった」と語るのは、n-buna本人である。
ボーカロイドプロデューサーであったn-bunaが、suisとともに2017年に結成したヨルシカは、ミニアルバム、フルアルバムでこれまで4枚を発表している。『だから僕は音楽を辞めた』と『エルマ』は2作通じてのコンセプトアルバムになっており、n-bunaが描きたいストーリーを、音楽で語るというスタイル。音楽性は非常にシンプルなギターロックサウンドを軸に、エレクトロニカなども曲によっては披露している。
彼らを特徴づけるのは、suisの声色と歌詞によるものが大きい。幼少期から文学を嗜んでいたn-bunaは、恋であったり、寂寞であったり、怒りであったり、そういった心を押し潰さんとする切迫感や強い衝動のようなものを、うまく象ろうと言葉にしたためる。そういった言葉を声にするsuisは、曲調、歌詞、メロディラインの浮沈によって、少年のように、少女のように、フッと声色を切り替わって歌ってみせる。ミュージカルへ足繁く通っているという彼女の経験が、そういったボーカリズムにも繋がっているように思える。
ヨルシカは登場人物の心のゆらぎを巧みに表現し、聴くものの心を捉えようと試みる。『泣きたい私は猫をかぶる』は心の豊かな機微や揺らぎ、そこから胎動する人間関係を描こうとトライしていた。両者はほぼ同一のモチーフを選んでいる。手を組めば素晴しいものができるのではないだろうか。
今回の3曲に共通しているのは、いわゆるギターロックではなく、ミドルテンポかつチルなムードを醸し出していることで、suisのボーカル、ギター、鍵盤、ドラムの音がメインとなっている。映像から発せられるムードの邪魔にならないようにと念頭に置いたように思えるが、ここで重要なのは、この作品が発しているメッセージ性に対して、彼らヨルシカは声と言葉を用いて、輪郭を作ろうとしているところである。
セリフに呼応するような「夜行」
作中に登場した順に、この3曲を書いていこう。まずは本編で1時間を経過しようかというころに流れる「夜行」だ。
猫の太郎と、本作の主要キャラである日之出賢人が、雨のなかで人を探しはじめる時にこの曲は始まる。アコースティックギターのアルペジオ、雨音、歌いだされる言葉は〈ねぇ、いつかおとなになったら、僕らどう成るんだろうね〉、直後に日之出は「あいつどこに行ったんだよ……」と口に出し、猫は「ニャア……」と応える。人を探すなかで、日之出は思い出のなかでその人を逡巡し、「謝らなきゃ、ちゃんと帰ってくるよな」とつぶやく。その時にsuisは〈そっか、大人になったんだね〉と歌っているのだ。
登場人物のセリフ、情動の変化に対して、まるで音楽が呼応するかのように言葉をかけるのがよく分かる。ここ数年のアニメ作品において、劇中歌とシナリオの絡み方は非常に濃いものになってはいたが、登場人物の変化とここまでハッキリと呼応し合いながら、ストーリーを一つ前に進めるような演出は少ないし、ここまで丁寧に描いてみせたシーンはむしろ初めてだと言っていいのかもしれない。まるで、音楽が物語を進めたかのようであり、人の心を諭したように描かれる。
絵コンテが先にできたか、「夜行」が先にできたかは定かではないが、絵コンテのタイムシートとsuisの歌い出しを綿密に合わせたのがよくわかる。n-bunaはこの曲について、「大人になること、忘れること、死へ向かうことを夜に置き換えて書いた曲」とコメントしているが、まさにこのシーンを代弁しつつ、より大きいスケール感をもった曲となっている。
普遍的なメッセージを放つ「花に亡霊」、“大人になること”を描いた「嘘月」
「花に亡霊」は、今作の最終盤からエンドロールにかけて流れる楽曲である。今作の舞台となる季節は夏。「亡霊はつまり想い出なので、夏に咲く花に想い出の姿を見る、という意味の題です」とn-bunaはコメントしている。だが実際の使用シーンを見てみると、その意味の深さに気付かされる。
映画の最終盤で彼女は「一生懸命に好きにならないようにしていた。みんないらない、みんなカカシだって」と語る。いつか自分が愛されなくなるという状況に気づくことへの恐怖に違いないだろう。次に彼女は、「でも、やっぱり、みんないる。帰ったら、好きになってみる」と言葉を続ける。周囲に対して受け身となっていた彼女が、自分を省みて、自分を変えてみようと決心する本作のラストシーン。この次のカットから、「花に亡霊」が流れ始める。
曲の歌詞を全部読んでみると、様々に出会ってきたシーンを思い出として捉え、これからも忘れないように大切にしようと歌ってみせている楽曲である。
この曲を、今作に寄せて捉えてみよう。〈もう忘れてしまったかな/夏の木陰に座ったまま、氷菓を口に放り込んで風を待っていた/もう忘れてしまったかな世の中全部嘘だらけ/本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと〉という始まりの歌詞。実はここで想起できるシーンは、今作序盤のシーンと、日之出と笹木の2人が作中でどのように変化したかを物語るとある印象的なシーンと、2つをモチーフに描いたように読み解けるのだ。彼らがどう出会い、どう振る舞って、ラストに向けてどう変わっていったのかを、思い出として大切にしようという結び方に受け取れる。さらに、作品を代弁しつつも、作品から離れた上でもなお、強いメッセージ性を感じられる一曲になっているのだ。
「花に亡霊」が終わった直後、「嘘月」が流れてくる。「歌詞の節々に尾崎放哉の句を散りばめています」とn-bunaはコメントを寄せていたが、おそらく〈こんなよい月を一人で見ている〉〈底が抜けた柄酌で飲んでる〉の部分がそれにあたるだろう。
ここで一つ、すこし屈折した見方をしてみよう。「夜行」においてn-bunaは「大人になること、忘れること、死へ向かうこと」を夜に置き換えたと語っていた、それをこの曲にあててみてみると、「大人になる」もしくは「大人へと変わっていくタイミング」とみても良いだろう。
大人になったというように嘘をついては「猫をかぶる」自分、それは今作における笹木と日之出の在り方をモチーフにしているように読み解けるのではないだろうか。そういった見方を踏まえつつ、作中において笹木と日之出が、夜のなかでどのように過ごしていたかを見た方なら、とてつもなく沁みる歌ではないだろうか。
ストーリーを代弁するだけでなく、作品のシナリオ展開やカット切りといった演出効果にも、本作から離れてもなお強いメッセージ性を残す、そんな3曲ではないかと思う。この3曲が同時に収録されたアルバム『盗作』が、7月29日に発売となる。もとよりコンセプチュアルに作品作りに励む彼らが、今回の3曲をどのように自分たちのアルバムのなかに組み上げるのか、そういった部分を含めて、非常に注目すべきではないだろうか。(草野虹)

