Rhythmic Toy Worldの音楽は日々の希望であり続ける 3カ月連続配信シングルで歌う“同じ時間を生きている感覚”
音楽
ニュース
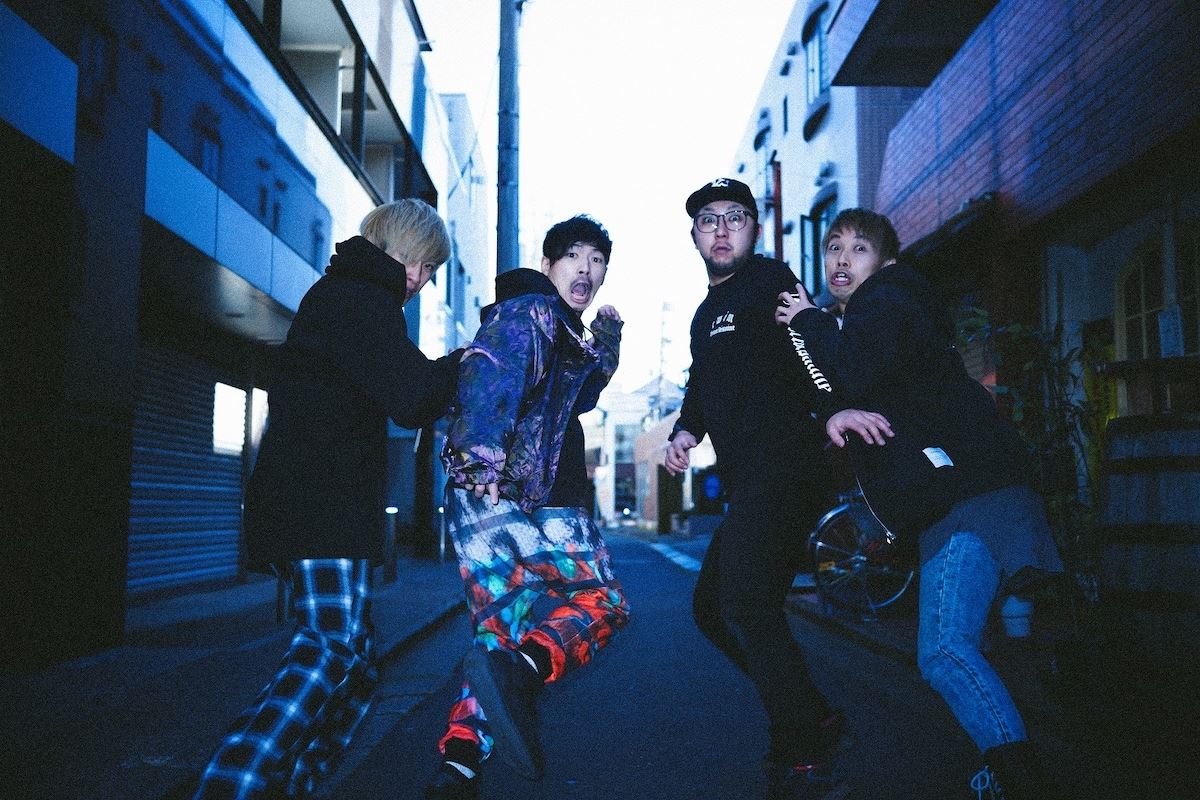
その奥にある作り手の姿がくっきりと目の浮かぶ歌だと思った。新型コロナウイルスの世界的な流行という、これまで経験したことのない事態のなかで、身近な人にすら会えない寂しさを感じ、押し付けられる正義感に違和感を抱きながら、それでも誰かと一緒に笑い合い、音楽を共有し合える未来を諦められずにいる。そんなコロナ渦で揺れる感情が、Rhythmic Toy Worldの3カ月連続配信シングル「VITE」「HAME」「CTOC」には、ありのままに表現されていた。これまでのリズミックの楽曲には、例えば、「フレフレ」や「ネバギバ」のように、ロックバンドとして明確に聴き手の鼓舞する意図をもったエールソングもあったが、今回リリースされるのはそういう歌ではないように思う。無理やりにポジティブになるでも、悲観的になるでもなく、この状況下に生きるひとりの人間としての感情がとても素直に歌われているのだ。
(関連:Da-iCE、新時代アーティストとして頭角を現したグループに ラファエル、EXIT、オーラル……各コラボに映る多面的な魅力)
まず、6月1日にリリースされた「VITE」は、これぞRhythmic Toy Worldという疾走感に満ちたキャッチーなギターロックだ。イントロで駆け抜ける岸明平(Gt)の開幕宣言のようなギターが一気に心拍数を跳ね上げる。過去の曲で言うなら、「輝きだす」や「僕の声」「いつか」といった、彼らのライブには欠かせないアンセムにも通じる楽曲であり、同時に、全曲のソングライティングを手がける内田直孝(Vo/Gt)の歌には、「未来」への揺るぎない信念を感じる力強さがあった。
タイトルの「VITE」とは、「速く、勢いよく」を意味する音楽用語と、英語で「噛む」を意味するbiteのダブルミーニングだという。〈噛めば噛むほどに味が出てくるよ/美味しそうだろ〉と、思うようにいかない人生だからこそ謳歌してやろうと不敵に歌い、〈人生ってやつは無限だ〉と、迷いなく言い切るサビの言葉が強い。これまでも数多くのエールソングを歌ってきたリズミックだが、ここまで強く叱咤激励するようなメッセージを吐くのは、実は珍しいことだと思う。おそらく「VITE」という曲には、それが必要だったのだ。バンドが止まることなく進んでゆくために、他の誰よりも、まず自分自身を強い言葉で鼓舞する必要があったのかもしれない。この曲について、内田は「手紙のようなもの」と言っていた。その宛て先は、リスナーでもあり、今苦境にいる音楽関係者でもあるだろう。それは、これまでにリズミックが歌ってきたような、聴き手と共に肩を抱き合って進んでいくような優しいエールソングとは一線を画すが、今この歌をバンドの意志として伝える姿そのものが私たちに勇気を与えてくれる、そんな 1曲だ。
「VITE」からは一転、7月1日にリリースされた「HAME」は、心の内側にあるダークな感情を抉るように吐露する攻撃的なロックナンバーになった。リズム隊である須藤憲太郎(Ba)と磯村貴宏(Dr)がボトムで激しく暴れまわり、重心の低い攻撃的なバンドサウンドをスピーディに鳴らす。メロディの言葉数も多い。「Rhythmic Toy Worldの最大の武器は何か」と尋ねると、メンバーは口をそろえて、「内田の歌だ」と言うが、この曲のようにそれぞれの楽器が存在感を主張する骨太なバンドサウンドも彼らの強みだ。生粋のライブハウス育ちである彼らの本気を感じた。
タイトルの「HAME」とは、くびきを意味する。牛や馬を引くときに用いる道具だが、転じて、自由を束縛するもののたとえとしても使われる言葉だ。内田はこの曲について、「社会につながれて、自分を押し殺して、自由に生きていけないことに対する憤りを吐き出した曲」というような説明していた。歌詞には、〈感覚的衝動煽った厚顔無恥な/現代TV Show〉〈正義は痛い病〉といった痛烈なフレーズが並び、社会に対する違和感を抱きながら、粛々と生きる「僕ら」の抑圧された感情が代弁されている。だが、単に不満をぶちまけるだけで終わらないのが、内田らしさだろう。〈「明日晴れたらどこへ行こう」/そんなくらいがちょうど良いのさ〉と、どこかに諦念を滲ませながら、決して明日を見捨てることはしない。泣いても、腐っても、必ず明日がくるという希望の描き方は「VITE」に通じるところがあり、やはり同じソングライターから生まれた曲だなと思わされるところだった。
8月1日にリリースされた「CTOC」は、変拍子を取り入れたパーカッシブなリズムが楽曲全体をリードする軽やかな楽曲だ。淀んだ気持ちを一気に掬いあげるような心踊る陽性のバンドサウンドにのせて、物語のように紡がれる歌詞がおもしろい。登場人物は「僕」と「名前のない少女」。夢の中で少女と会話を交わすことで、僕は最後にその正体に気づくが、それが何なのかという解釈は、リスナーへと委ねられることになる。個人的に感じたことを書かせてもらうならば、この曲はRhythmic Toy World流の音楽讃歌だと思った。それも、とても遊び心のある音楽讃歌だ。ドレミファソラシドの音階を一つずつのぼり詰めていくサビ。今回の3カ月連続リリースで貫いてきたアルファベット4文字のタイトルで、“シートゥシー”と読ませる謎解きのような仕掛けをヒントに聴いていくと、この曲からは、「なぜ歌が生まれるのか」「歌い続けていくことにどんな意味があるのか」「音楽とは何なのか」という、作り手の思想が浮かび上がってくるような気がした。
Rhythmic Toy Worldが鳴らす音楽は、ソングライターである内田のなかに渦巻く、未来への情熱、自分自身への葛藤、仲間への感謝といった感情を起点にすることが多い。インタビューでも、「歌詞は全部ノンフィクションでいきたい」という発言をしているとおり(参考:SPICE)、自分の体験を軸に音楽を生み出すタイプだ。そこに、須藤のベース、磯村のドラム、岸のギターが合わさることで、Rhythmic Toy Worldの音楽が出来上がる。そうやって、たったひとりの人間に芽生えた小さな感情だったはずの音楽は、やがてライブハウスで響きわたり、誰かの生きる糧になることもあるだろう。今、音楽はその役割を最大限に果たすことは難しい時期にある。だからこそ心から心へと想いを伝播していく自分たちの音楽の在り方を改めて見つめ直すことで、この歌が生まれたのではないだろうか。「CTOC」は、「音楽とは何なのか」という問いへのリズミックからの回答だと思う。
多くのアーティストがそうであるように、Rhythmic Toy Worldもまた、今年の2月以降すべてのライブがキャンセルになっている。昨年メジャーからインディーズへと活動の拠点を戻し、自分たちに似合ったやり方でバンドを続けていく決断を下したリズミックにとって、そのもっとも重要な基盤であり、これまで何よりも大切にしてきたライブハウスに立てないことは、かなりの痛手だったはずだ。彼らはよくライブハウスやそこに集まるお客さんのことを「宝物」だと言う。音源を出すときも、それをライブハウスで歌い続けることができるかを前提に考えることが多いと話してくれたこともある。そんなRhythmic Toy Worldが、バンド史上初めてライブがまったくできない状況下で作り上げたのが、今回の配信曲だ。聴けば聴くほど、その素朴さは必然だと思う。今は同じ空間に立つことは適わないからこそ、せめて同じ時間を生きている感覚だけは共有したい。この3曲にはそういう想いも託されているのではないだろうか。(秦理絵)

