デヴィッド・フィンチャー監督にとっての『市民ケーン』 Netflix映画『Mank/マンク』を解説
映画
ニュース

映画のオールタイムベスト企画があれば必ず名前が挙がり、“史上最高の映画”に最も多く選ばれてきた作品といえば、紛れもなくオーソン・ウェルズ監督の『市民ケーン』(1941年)のことだ。この、映画人なら誰もがうらやむ栄誉を欲しいままにする映画の脚本を執筆したのは、脚本家ハーマン・J・マンキーウィッツ。その愛称をタイトルにした本作『Mank/マンク』は、彼の生きたハリウッド黄金期の姿が語られる映画である。

だが、『市民ケーン』の主人公のモデルになったウィリアム・ハーストや、映画会社の経営陣、プロデューサーや俳優など、当時のハリウッドの人間関係が複雑に交差する内容は、一回で理解するにはかなり難しいかもしれない。ここでは、そんな本作の内容を整理しながら、何が描かれていたのかをじっくりと解説していきたい。
『市民ケーン』は、初めからここまで多くの評価を集めていたわけではなかった。アカデミー賞では9部門にノミネートされながら、受賞は脚本賞のみで、映画祭や映画館での上映に際しては妨害工作が行われたという。その理由は、この作品が実在の大富豪をモデルに、その生涯を皮肉たっぷりに描くという、かなり危険なものだったからだ。その人物、ウィリアム・ランドルフ・ハーストは、新聞、ラジオ、ニュース映画会社などを持ち、映画事業にも関わる有力者。そんな人物を揶揄したのだから、どんなに映画自体が素晴らしくとも、当時締め出しを食らったというのは当然の流れかもしれない。
だが、そんな映画がいまは映画史のトップに君臨しているのである。これにはやはり、公開当時押さえつけられていた不遇への同情や、製作者たちの反骨精神を賛美する意味もあったように思える。というのも『市民ケーン』は、とくに映画監督からの評価が高いのだ。もちろん同時に、25歳という若さで見事な演出力を発揮したウェルズの才能への賛辞や、撮影監督グレッグ・トーランドによる幻想的な映像、そしてハーマン・J・マンキーウィッツの文学的といえる重厚な脚本に価値を見出していることももちろんだ。なかでも脚本は、アメリカ文学の最高峰といわれる、F・スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』と比較しても、引けをとらない出来である。

本作『Mank/マンク』は、そんなハーマン・J・マンキーウィッツが、いかにして映画史上の傑作脚本を書き上げたのかを、史実を基に想像を加えながら描いていく。監督は、アーティスティックで娯楽性の高い作品で、ハリウッドの第一線で活躍してきたデヴィッド・フィンチャー。今回はNetflixでの製作で、キャリアのなかで最も渋いといえる題材に挑戦している。
もともと本作は、デヴィッド・フィンチャーの父親であり、新聞社に勤めていたジャック・フィンチャーが書いた脚本が基になっているという。デヴィッド・フィンチャーは、この作品を『ゲーム』(1997年)の後に撮る予定だったが、製作が開始されたところで企画は頓挫した。ハリウッドの内幕ものという、予算がかかる内容の割に題材が地味だという状況に加え、モノクロームで完成させるというフィンチャーの主張が、興行的に厳しいと判断されたのだろう。
『市民ケーン』が当時のハリウッドでも圧倒的に芸術的な大作であったように、表現を求めるクリエイターにとっての息苦しい状況は、現在のハリウッドも変わらない。その意味で、本作『Mank/マンク』は、デヴィッド・フィンチャー監督にとっての『市民ケーン』なのだといえるし、この、現代で最も風格が漂う映画を、配信業者のNetflixが製作しているというのは皮肉な事実である。
物語は、ゲイリー・オールドマン演じるハーマン・J・マンキーウィッツが『市民ケーン』の脚本を執筆する“現在”の時間と、彼が脚本にかかる前、カリフォルニア州知事選の期間にハリウッドで過ごした日々が“過去”の時間として、二つの時間が並行して語られていく。この構成は、まさに『市民ケーン』で、ケーンの死後の時間と、ケーンの半生が並行して語られていく試みに近い。そして、ベッドで酒ビンを落とすシーンなど、やはり『市民ケーン』にオマージュを捧げるような映像が、同じモノクロームで再現されている。
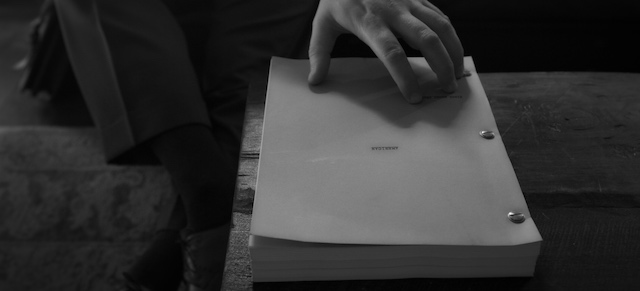
『市民ケーン』が、ケーンの発した最後の言葉“薔薇の蕾”の謎を追っていく一種のミステリーだとするならば、本作はハーマン・J・マンキーウィッツが、あのようなきわめて挑発的で攻撃的といえる脚本をなぜ書いたのかが解き明かされていく趣向となっている。もちろん、それは本作独自の解釈である。
背景に色濃く存在するのは、政治と映画の関係だ。1930年代の世界的な恐慌のなか、知事選では民主党の候補が労働者の権利をうったえていた。それを苦々しく思っていたのが、保守派の「新聞王」ハーストや、ハリウッドの映画会社の上層部だった。なかでも、映画会社メトロ・ゴールドウィン・メイヤー(MGM)の創始者の一人であるルイス・B・メイヤーは、スタジオで映画を作りあげるスタッフの賃金をカットすることで上層部の利益を確保するような人物として描かれており、彼のような人物にとって、大企業に不利な政策方針をとる政治家は邪魔なのだ。
そして、当時のMGMには“天才少年”と呼ばれる敏腕の若手プロデューサー、アーヴィング・タルバーグがいた。本作では、ハーストやメイヤー、タルバーグが、映画などメディアの力を利用して知事選をコントロールする様子が描かれる。なかでもショッキングなのは、ニュース映画において“やらせ”が行われるという描写だ。そこでは、大企業を優遇する政策をとっているはずの当時の共和党候補が、むしろ民衆の味方であり、貧困層から熱烈に支持されているかのように、事実を歪曲した演出が施されていた。この製作に関わり、ニュースを製作した人物は、深い後悔を感じて精神を病んでしまう。

かつてハリウッドの大女優ローレン・バコールは自叙伝にて、自分をスターダムに押し上げた恩人でもある名匠ハワード・ホークス監督が、スタジオの経営陣について、「ユダヤ人は金だけ出していればいいんだ」と仲間内で差別的にののしっていた事実を暴露している。ハリウッドの名だたるスタジオの創始者たちはユダヤ系であり、映画をつくる資金や大権は彼らが握っていた。
ホークス監督は、ハリウッドの歴史を代表する映画監督でありながら、このように口汚いものいいをしてた粗野な人物としても、当時の記録に記されている。荒野や草原でロケをした大スペクタクルの西部劇『赤い河』(1948年)の撮影時、知性派俳優のモンゴメリー・クリフトは、主演のジョン・ウェインとホークス監督が、あまりに粗野な会話を続けるために彼らを避け、孤独に現場で過ごしていたという。
しかし、なぜホークス監督は、経営陣を悪し様にののしっていたのだろうか。それは、資金を提供する者ではなく、自分のように実際に映画製作を指揮する“アーティスト”こそが、真に映画を生み出しているということを主張したかったからではないか。このようにハリウッドにおいて、資金を用意する者たちと製作する者たちの間は、歴史的にも分断されているところがある。
ハーマン・J・マンキーウィッツは、持ち前のユーモアで一時はウィリアム・ハーストに気に入られ、彼のそばでジョークを言うなどして、「面白い奴」と喜ばれていた。だが『市民ケーン』の内容がハーストや、その愛人で映画スターであるマリオン・デイヴィスを中傷するようなものであることが知れると、ハーストの息のかかった映画人たちから「身の程を知れ」「モンキーウィッツ」などとののしられる。ハーストが「オルガンを弾く猿」の話をすることも象徴的なように、ハーマンは実業家ハーストから猿回しの猿としてしか扱われていなかったのだ。

ハーストが別世界に生きていることは、彼の持つ邸宅の一つである“ハースト・キャッスル”を見れば一目瞭然だ。カリフォルニアの広大な土地に、動物園や飛行機の発着場ほか様々な施設が並ぶ。巨大な城は、『市民ケーン』では「ザナドゥ(桃源郷)」と称され、ケーンの富の豊かさを誇るシンボルとして紹介されるが、2番目の妻スーザンに「こんな場所、面白くも何ともない!」と文句を言われるという描写を、ハーマンは脚本に入れている。本作はその理由を、アマンダ・セイフライド演じるマリオンとハーマンのひそかな恋愛に結びつける。
演技力の拙さをたびたび世間から批判されていたマリオンだが、ハーマンは彼女に合った配役がされていないことを劇中で指摘する。これは、『市民ケーン』で、ケーンがスーザンをオペラ歌手に無理に仕立て上げようとした箇所に相当する。本作のハーマンは、彼女のことを真に分かっているのはハーストではなく自分だと言いたいのである。
そして聴き逃せないのが、ドイツでナチスが台頭しつつあることが分かる会話である。映画会社の重役たちは、まだその取り扱いを決めかねている部分があり、財力や政治力がありながら、国際問題、人権問題に介入することを避けている。ハリウッドの多くがそんなナチスの問題で及び腰のなか、ユニバーサル映画のカール・レムリや、ウィリアム・ワイラー監督などは、ドイツ在住のユダヤ人を移住させる事業を行い、そこにハーマン・J・マンキーウィッツも参加していたという。本作でもその事実が紹介されているように、ハーマンは人助けを行なうような優しい心を持っていたことが理解できる。

クリエイターとしてのプライドと矜持、プライベートな感情、そして正義の心。本作が到達する、ハーマンが『市民ケーン』を書いた理由は、これらが複合された、ハーマン・J・マンキーウィッツという人間の生き方や想いそのものだったのである。
そして本作に登場する、ハーマンの弟“ジョー”ことジョセフ・L・マンキーウィッツ(トム・ペルフリー)は、脚本と監督業で、この後『三人の妻への手紙』(1949年)や『イヴの総て』(1950年)など複数の作品で、アカデミー賞各賞を獲得し、ハリウッドの頂きに到達、全米監督協会の会長に就任することになる。ジョセフは若い頃の信念のままに映画界を民主的な方向に革新しようとし、映画人の思想を弾圧する「アカ狩り」に協力する保守派の大監督セシル・B・デミルと対立することになる。このエピソードは、ジョーもまたハーマン同様に正義を貫いた事実を示している。
とはいえ、本作『Mank/マンク』では、資本家からの手痛い反撃も描かれた。いかに正しい方向に進もうとしても、カリフォルニアの地を開拓し、映画製作の土台を作り上げ、人を集めているのは資本家たちであり、自分を含めクリエイターたちの報酬を支払っているのも資本家たちであることも事実なのである。ハーストが語る「オルガンを弾く猿」の話には、そういった意味も込められている。猿が何をやろうと、猿は猿回しの人間の手の内で生きるしかないのだ。本作が描くのは、このように資本主義社会における資本家と労働者の間の普遍的な関係でもある。

その意味で『市民ケーン』の物語とは、本作で映し出される、ハーマンが酒に酔った勢いで怒鳴り散らすシーンのように、弱い立場から放った、様々な感情が込められた叫びだといえる。そして、そのことを描く本作を撮ったフィンチャー監督もまた一人の映画人として、作品に自分の想いを込めているはずである。
本作『Mank/マンク』は、このようにハリウッドの現在と過去、クリエイターの現在と過去の感情が、『市民ケーン』という作品と『Mank/マンク』という作品自体を通して、重層的に構成されている。そしてハーマンの書き上げた『市民ケーン』は、ハーストという人物を通して自分という存在を間接的に物語に焼きつけ、フィンチャーはハーマンを通して、おそらくは自分自身を語っている。そして、この作品が自分自身だからこそ、ハーマンは脚本を書き上げた後に、ウェルズと戦ってまで自分の名前をクレジットすることを頑なに要求し、フィンチャーはその姿を描いたのではないのか。
映画は多くの人間の共同作業で作られる。しかし個人が生きた証を、自分の溢れるような情熱や主張を、思い切りぶつけることもできる。ハリウッドは簡単に変わらないし、強者は弱者をこれからも利用し、搾取し続けるのかもしれない。だが、そんなシステムに中指を突き立てるパンクロックのような魂を持った『市民ケーン』が、史上最高の映画として、多くの観客を魅了し続けていることは、多くのクリエイターたちにとっての希望になっている。本作はそんな事実もあぶり出しているのだ。
■小野寺系(k.onodera)
映画評論家。映画仙人を目指し、作品に合わせ様々な角度から深く映画を語る。やくざ映画上映館にひとり置き去りにされた幼少時代を持つ。Twitter/映画批評サイト
■配信・公開情報
Netflix映画『Mank/マンク』
一部劇場にて公開中
12月4日(金)よりNetflixにて独占配信開始
監督:デヴィッド・フィンチャー
出演:ゲイリー・オールドマン、アマンダ・セイフライド、リリー・コリンズ、チャールズ・ダンス、タペンス・ミドルトン、トム・ペルフリー、トム・バーク
公式サイト:mank-movie.com


