【峯田和伸ロングインタビュー】『越年 Lovers』撮影裏話や大好きな映画・音楽の話まで
映画
インタビュー

峯田和伸 撮影:稲澤 朝博
台湾のグオ・チェンディ監督が、感銘を受けた岡本かの子の短編小説集をベースに、年越しのマレーシア、日本、台湾の3組の男女が織り成す不器用な恋愛の行方を描いたラブストーリー『越年 Lovers』。
大晦日の山形が舞台の日本編に出演し、故郷の山形で、同じ山形出身の橋本マナミと山形弁での恋模様を味わい深く体現した峯田和伸を直撃!
撮影に入る前のプライベートの出来事から撮影の裏話、仕事のスタンス、大好きな映画や音楽の話までたっぷり聞いちゃいました。

インタビューは思いがけない告白から始まった
幼馴染みの太郎から「恋人の碧(橋本マナミ)から別れることになった」という報せをもらった寛一は、その電話をきっかけに大晦日の故郷・山形に久しぶりに帰ってくる。
ところが、太郎は不在。代わりに思いがけない形で、初恋の相手だった碧と数十年ぶりに再会することになるが……。
そんな数十年越しの恋を見つめた『越年 Lovers』の日本編で、主人公の寛一を等身大で演じた峯田和伸。そのインタビューは思いがけない告白から始まった。
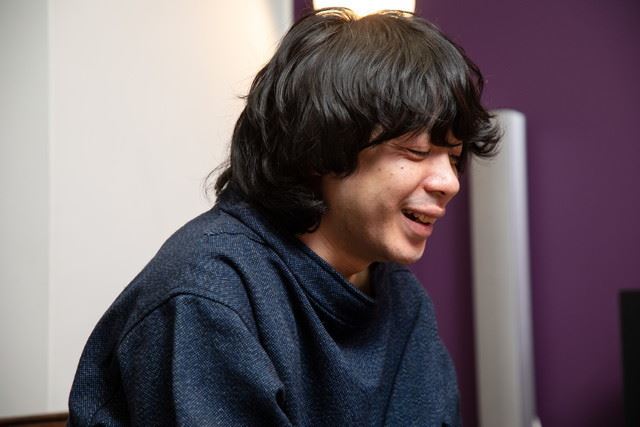
――今回のオファーを最初に聞いたときはどう思われました?
地元の山形に出向き、そこで撮影するということを僕はいままで経験したことがなかったので、山形出身の役者同士が山形弁のセリフを喋る設定にまずは惹かれました。
台湾の監督が撮るということにも興味がありましたね。それで「ぜひやりたい」と言って参加させていただきました。
――台本を読まれた印象は?
自分の中に100個ぐらい人格があるとしたら、僕が今回演じた寛一はその中にいた奴だったんです。
そういう奴じゃなかったらたぶん「ごめんなさい」って言ったと思うんですけど、自分の中にもあるキャラクターだったのでやれるな~と思いましたね。
――高校時代の初恋の女性に何十年ぶりかで会って、お互いに相手の気持ちを何となく知りながらどちらも告白しない、そのじれったい感じが可愛いなと思いました(笑)。
撮影に入る3年前にちょうど地元の同窓会がありまして。僕、いままで一度も同窓会に行ったことがなかったんですよ。
でも、40歳を記念して企画されたその同窓会に行かなかったら、たぶん一生行かないだろうなと思ったので初めて参加したんですね。
そしたら出席率もけっこうよくて、僕が小学校1年生から中学校3年生まで9年間、ずっと好きだった女性も来ていたんです。
――片想いだったんですか?
1回も想いを伝えたことはないです。その彼女が、同じテーブルの対面の席に座っていたんです。でも、ほかの人とは「久しぶりだね」と言ったり、「峯田、テレビで見てるよ」「ドラマ、見てるよ」とか言われたりして、けっこう喋ったんですけど、彼女とはひと言も喋れなかったんです。
もう大人なんだから、普通は「あっ、どうもどうも」っていう感じで打ち解けられるじゃないですか? でも、行けねえんだな~、俺と思いましたね。
――彼女も話しかけてこなかったんですか?
向こうもこなかったです。目も合わなかった。気配はもちろん感じていただろうし、いや、話しかけられるタイミングは絶対にあったと思うんですよ。けど、行けなかった。だから、まだ行けねえんだな~、俺と思って。
それで東京に帰って台本を読んでいたときに、あっ、あるわ、未だにこの行けねえ感じは俺にもあるわと思ったんです。

撮影裏話:山形弁での自然なお芝居
――そのリアルな体験も役に活きているんでしょうね。橋本マナミさん演じる碧との距離感も絶妙でしたが、橋本さんとは今回が初対面?
そうです。現場で初めてお会いして「よろしくお願いします」と言ったんですけど、もう最高でした(笑)。
――会う前のイメージと印象は違いましたか?
橋本さんも山形出身の方ですけど、“愛人キャラ”で知られている人だから、お会いする前は都会にすごく染まった、ちょっとスレたところもある人なのかな~という勝手なイメージを持っていたんです。
でも、実際の彼女は本当に素朴で優しい、裏表のない人で。うわ~この人とだったら気持ちよくお芝居ができるな~と思ってすごく安心したんですけど、実際、どのシーンもお芝居に集中してストレスなくできました。
――橋本さんとも山形弁での自然なお芝居ですね。
そうですね。でも、彼女は高校から東京に来ていたので山形弁を忘れているところがあって。
台本は標準語で書いてあるから読み合わせのときに山形弁に変換しながらリハーサルをしたんですけど、「峯田さん、このセリフって山形弁でどう言うんでしたっけ?」って聞かれることもあったので、教えてあげながらやっていました。

――この映画の山形弁は、映画用に多少分かりやすくしてあるんですか?
いや、けっこうネイティブ寄りです。訛りはけっこう強めだと思います。
――映画の最初の方に出てくる恩師の先生は地元の方ですよね?
そうなんですよ。役者じゃないんですよ(笑)。けっこうそういう人が何人か映っているんですけど、あの先生、セリフをけっこう与えられちゃって本番はガチガチでした(笑)。
でも、最高でしたね、役者が演じているのではなく、実際に笠智衆のような佇まいをした人ですから最強ですよ。役者は負けちゃいます。
撮影裏話:「あのシーンはよかった」とみんなから言われる

――ああいう人がいるとドキュメンタリーっぽい感じにもなりますしね。
この映画のメガホンをとったグオ・チェンディ監督が、もともとはドキュメンタリー映画で評価された人みたいで。だから、そういう要素もけっこう多いと思います。
クライマックスのふたりが揉み合うところも、引きだけ1発で撮って寄りの画を1回も撮らなかったので。
日本の監督だったら顔の寄りや手の寄りを撮るんだろうけど、引きの1発だけだったから、そういうところがこの監督っぽいと言うか、台湾の人の感性なのかな~と思いました。
――この『越年 Lovers』はマレーシア編、日本編、台湾編の3章からなるオムニバス映画ですが、日本編のエピソードも岡本かの子さんの原作「越年 岡本かの子恋愛小説集」「老妓抄」の中にあるエピソードなんでしょうか?
渋谷駅の階段を上ったところにある岡本太郎さんの大きな絵や、ふたりがコーヒーを飲む岡本太郎さんも通われていた「蔵王」という店名のロッジとそこに飾ってある岡本さんの絵に原作の要素がちょっと含まれているぐらいです。日本編のお話自体は完全に映画のオリジナルですね。

――橋本さんとのシーンはどこから撮影に入ったんですか?
順撮りって言うんですかね? ほとんどそれに近かったので、初めて会うシーンを最初に撮りました。
――寛一と彼の友だちが、雪で動けなくなった車をその下に服を敷いて動かそうとしているところに彼女がやって来るくだりですね。
そうです。パンツ姿になっちゃっていた僕がズボンを履き直しているときに現れて、見られた僕が「あっ!」ってなるあのシーンです(笑)。
――あそこで、寛一と友だちがどっちのジャンパーを車の下に敷くのかで言い合いになりますけど、寛一が「自分のはエレファントカシマシのジャンパーだから」って嫌がるあのセリフはアドリブですか?
いや、決まっていました。台本にはないんですけど、監督やプロデューサーと話しているときに「峯田さんは誰のライブに行かれますか?」って聞かれたから「エレカシですかね~」と言って。
それで「じゃあ、エレカシで行きましょう」みたいな感じで決まったんです。
――髪の毛もこの役のために短く?
と言うか、撮影がNHKの大河ドラマ『いだてん〜東京オリムピック噺〜』と重なっていて。
あっちが先に坊主頭で始まっていたんですけど、『いだてん』はそれほどメインの役ではなかったので、「坊主頭のままでよければ、空き時間を見つけて山形にも行けますよ」という流れで参加させてもらったんです。

――みなさんたぶん言われると思うんですけど、寛一が碧の作ってくれたお雑煮を食べるシーンがとてもいいですね。
みんな言いますね。インタビューを何度も受けてるんですけど、「あのシーンはよかった」って、みなさん言われます。
――ふたりの距離があそこでグッと近づきますけど、あれはどこまで演出が入っているんですか? 寝ていた寛一はいきなり起きて、何も言わずに食べ始めますよね(笑)。
あそこは本番も何回かやったんです。で、確か鼻水が出ていたので「紙を取ってください」みたいな芝居を僕が提案したと思います。
それで、ふたりの関係がちょっと溶け合うみたいな感じになったんですけけど、あのシーンはいちばんテイクを重ねたかもしれない。
――ピンクの毛布を途中で被り直すのも可愛くてよかったです(笑)。
監督が「OK!」と言った後に「もう1回」って言うじゃないですか? でもそれは、いまのはダメだったからもう1回ということではなくて、面白かったから違うパターンも見せてっていう感じだったんです。
やる度にお餅を食べなければいけなかったから大変でしたけど(笑)、さっきはこうしたから今度はやらないでみようとか、自分なりにいろいろ変えてやったのを覚えています。
――あのシーンでは、食べている峯田さんを見ている橋本さんの表情もよかったですね。
あのシーンはセリフはないけれど、ふたりがちょっとだけ近づくところだろうな~というのは橋本さんも僕も何となく意識はしていて。
「よかったですね~」って言ってくださる人がいらっしゃるということは、そのニュアンスが上手く表現できたのかなと思います。自分ではちょっと分からないですけどね。
僕、人が食べているシーンがけっこう好きなんです

――いや、素晴らしかったです。寛一にとっては至福の時間だったと思いますし。
僕も映画が好きでけっこう観るんですけど、僕、人が食べているシーンがけっこう好きで。
例えば韓国映画とかだと、ジャージャー麵をすごい音を立てながら食べるじゃないですか。イタリア映画だったら音を立てずにパスタを食べると思うんですけど、その食べ方によってその映画の性格が出る気がするんですよ。
そういうところがすごく好きで。今回もお雑煮をス~っとすする音だけで東北っぽい感じが伝わってきて、それがとてもよかったですね。
――寛一と碧が、玉こんにゃくと饅頭を目を合わさずに交換するところもよかったです。
台湾の人からしたら、“玉こん”は珍しい食べ物みたいで。僕が最初に食べている大福みたいなお饅頭も蔵王では有名なお菓子みたいですけど、外国の人って自分の国にないものを見つけると、何これ? 面白い。これを撮ろうという思考回路になるみたいで。
特に“玉こん”はあの形が珍しかったみたいで、「このまま食べるんだ?」みたいな感じで面白がっていましたね。

――橋本さんとの現場でのやりとりで覚えていることは?
今回は分かりやすい指揮者がいない現場と言うか、監督が日本語を喋れないということもあって、細かく「ここは、こうしましょう」という作り方じゃなかったんです。
バイブルは台本で、自分がそこから感じ取ったものを持っていって、現場でやって見せる。で、それを見た監督が面白かったら「OK」みたいな。だから、けっこう自由に動き回れた現場だったんです。
――外国の監督だと、コミュニケーションがとれなくて、やり難いところもあるのかなと思ったんですけど…。
監督がやって欲しいことは片言の英語で分かりました。でも、基本的に「これをやって欲しい」というよりは、「これはやらなくていいですからね」みたいなところでの会話だったような気がします。
――例えば、どんなことですか?
例えば、写真館の前を3往復するシーンのときに「3往復の途中で立ち止まるのは全然OK。任せます」みたいな。
それで、自分の気持ちのままにやって見せて監督が面白いと思ってくれたら「OK!」という感じだったんですけど、自分が思う、これはたぶんNGじゃないんじゃないかな~っていう芝居をけっこう自由にやれたと思っています。
――クライマックスの撮影はどんな感じだったんですか? バーっと歩いて行った碧が戻ってきて寛一を転倒させますが、あの一連は、女性の方が結局仕掛けたような感じに見えます。
この映画の3つのエピソードに出てくる男たちはみんなダメですよね。
女性をいきなりぶっ叩いたり、何を考えているのか分かんない男しか出てこないけれど(笑)、原作者が女性だから、どこかそこには女性目線もあるんでしょうね。
これが、例えば夏目漱石だったらまた違うと思うんですよ。どこか男目線で、玄関に毎日毎晩同じ女が立っているみたいな感じになっていたかもしれない(笑)。
でも、今回は登場する男たちがみんなディスコミュニケーションで、それに女性が振り回される。そこには、女性から見た男性の何か共通する印象があるのかもしれませんね。
『越年 Lovers』をどんな人たちに観てもらいたい?

――この映画をどんな人たちに観てもらいたいですか?
起承転結がはっきりとした、山あり谷ありみたいな分かりやすさはないけれど、自分の日常に近い人たちが映っていて、なんか、ホッとするような映画にはなっていると思います。
映画にはいろんな楽しみ方があると思うし、自分の日常とかけ離れたアトラクションのような世界を楽しむ作品もありますよね。
でも、一方には、好きな人に想いを上手く伝えられなかったりする、自分に近い問題を抱えた人が出てくる映画もあります。
この作品も、最近、あの人との関係が上手くいっていないなと思っていたり、何かの問題にぶつかっている人たちがちょっとでも前を向いてくれるような映画になればいいなと思っています。
役者という仕事の位置づけ
――ところで、峯田さんは音楽活動だけじゃなく、最近は役者の仕事も多いと思うんですけど、ご自身の中では、役者の仕事はどういう位置づけなんですか?
楽しいです。音楽は楽しいだけじゃない。と言うか、仕事なんですよね。
――お芝居も仕事ですよね。
お芝居の方は、仕事とあまり思っていない節がありますね(笑)。音楽の場合は作品を作るために、すり減っていく自分がいて。昔からやってきて、ずっとやって行こうと決めたことなので、これからもやっていくと思うんですけど、お芝居をやると、そのすり減っていく作業からちょっと逃れられて、やっと人間に戻れるようなところがあるんです。
――もう少し楽にできるわけですね。
そうですね。楽しもうって感じですね。音楽は楽しもうというのはあまりない。それ以上に重い、責任感みたいなのが伴いますけど、お芝居って監督に投げられるんですよ。だから、楽なんです。
曲を作って「歌詞できねえ!」って言って、追い込まれたときは「ガー」ってひとりで部屋で叫び声を上げているような日常とは違って、お芝居は脚本家がセリフを作ってくれるからすごく楽。
それで、観た人も喜んでくれるけれど、音楽ではそんなことにはならないですから。
――ちなみに、映画が好きでよくご覧になるって言われましたけど、どういう作品が好きなんですか?
どんな映画でも観るけれど、昨日観直したのは、クエンティン・タランティーノ監督の『ワンス・アポン・ア・イン・ハリウッド』(19)。去年は家にいることが多かったので、けっこうたくさん映画を観ました。DVDもよく買いますよ。
――タランティーノが好きなんですか?
好きです。大学生のときに初めてリアルタイムで『レザボア・ドッグス』(92)を観て、そこから新作のたびに映画館に行っています。VHSも買ってDVDも買って、デザインが新しくなった再発版のDVDも買ったりするから『パルプ・フィクション』(94)と“レザボア”は5、6枚持ってます(笑)。レーザーディスク以外は全部持っていますね。
――自宅はコレクションでスゴいことになってるんじゃないですか?
そうですね。いっぱいありますよ。スタンリー・キューブリックとかレオス・カラックスとか、好きな監督の映画のDVDはいつでも観られるように買うことが多いですからね。
――『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』も好きですか?
最高です(笑)。
――シャロン・テート事件を知っている人は悲しい結末になるんだろうなと思いながら観ていくわけですけど、あの映画ではそうならないところが………。
変えたんです、運命を。ブラッド・ピットとレオナルド・ディカプリオが演じたあのふたりが(笑)。

――そこがいいですよね(笑)。
最高! 最高! 事件を起こすチャールズ・マンソンを演じていたデイモン・ヘリマンの喋り方が、本人の喋り方にそっくりで。
実はチャールズ・マンソンは音楽家なので、アルバムも出しているんです。劇中のセリフにも出てくるんですけど、ザ・ビーチ・ボーイズのデニス・ウィルソンと仲がよくて、デニスが「チャールズ、オマエもアルバムを出そう」と言って、レコーディングをしているんですよ。
でも、それが果たされず、お蔵入りになっちゃったからチャールズがデニスにキレて「ハリウッド、むかつく! 人を殺そう!」となって。
シャロン・テートと夫のロマン・ポランスキー監督が住んでいた家をメンバーに襲撃させるんだけど、あそこはもともとデニスが住んでいた物件なんですよね。
で、そのチャールズ・マンソンのお蔵入りしたアルバムも、お蔵入りになったものの、再発運動が高まる中で音源が出ていて、めっちゃいいんです。
そのアルバムにはチャールズが喋っている声も入っているんですけど、あの俳優の喋り方や雰囲気はそのアルバムの声にすごく似ているんですよ。

どんな質問をしても、飾らない自分の言葉で真摯に答えてくれた峯田さん。
その山形弁の訛りも人間臭くて、周りを温かな空気で包み込むが、撮影現場の状況や監督の演出、自分の心の動きや演技プランを丁寧に、明確に振り返るあたりは流石!
柔らかな言葉の中に仕事に対する厳しい姿勢が伺えたし、アクセルを踏み込むように一気に饒舌になり、話が止まらなくなった終盤では映画と音楽が本当に大好きなことが伝わってきて、聞いているこちらも楽しい気分に。
『越年 Lovers』でも、そんな峯田さんの魅力を堪能することができますよ。
取材・文:イソガイマサト 撮影:稲澤朝博
『越年 Lovers』
公開中
ぴあアプリをダウンロードすれば、アザーカットが見られます!
ダウンロードはこちらから
フォトギャラリー(26件)
すべて見る
