「動物園は、いつの時代も社会の縮図」 文化史研究者が語る、“動物の権利”の歴史
音楽
ニュース
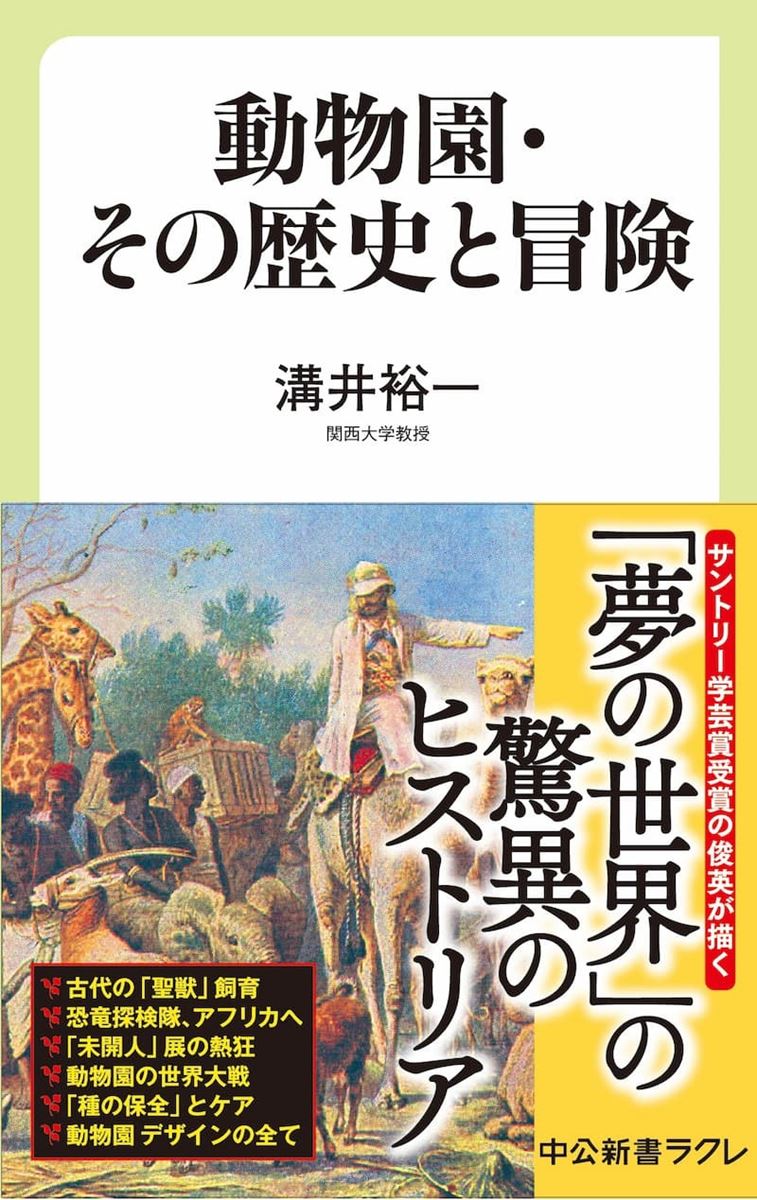
動物園は、あなたにとってどんな場所だろうか? 小さい頃に遠足で行った場所、学生時代にデートで行った場所、大人になって家族と行った場所、ひとりでじっくりと楽しむ場所……人々の身近にある動物園は、18世期末にヨーロッパにて誕生した。溝井裕一氏の著書『動物園・その歴史と冒険』(中央公書ラクレ刊)は、文化史という観点で古代から現在までの動物園の歴史を、園内の建物やデザインの変遷を辿りながら追った1冊。珍種を集めて展示する古代の動物コレクションから、動物園の前身とも言えるメナジェリー、そして近代における動物園の歴史を追った本書を読むと、動物園が人間社会と切っても切り離せない存在であることを痛感する。
今回、溝井氏には本書をより深く読むための詳しい解説を話してもらいながら、近年では動物福祉やQOL(quality of life)の充実が謳われるなど、目まぐるしく変化する動物観、そして我々人間との今後の関係についてさまざまに語ってもらった。(タカモトアキ)
人間の動物観の変遷を辿る
――まず、溝井さんが動物園と人間の文化史を研究されるようになった経緯を教えていただけますか?
溝井裕一(以下、溝井):もともと、独文出身で、ドイツの民間伝承について研究していました。『赤ずきんちゃん』を始めとしたメルヘンや伝説に出てくるさまざまな動物たちは第二の主人公といってもいいほど大切な存在で、メルヘンを通して人間と動物の関係を分析しようとしていたのですが、どうしても時代が特定しづらい。なおかつ、もう少し広い視野で見たほうがいいんじゃないかというところからテーマを探していた時に見つけたのが、「動物園」だったんです。
さらに、私がずっと気になっていたのは人間の動物観。人間が動物のことをどう思っていたのかということを重視して、できれば古代はこうで中世はこう、近代はこうだというふうに人間の移り変わりとリンクさせながら、動物園が一体どんなふうに成立してどう変化していったのかを、文化史的な視点から研究してみようと思ったんです。
――動物観に関してですが、本書にもあったように人間優位という考え方がキリスト教から派生していたことに驚きました。
溝井:確かに、重要なポイントですね。人間優位の考え方は、キリスト教徒の多いヨーロッパと関係が深い思想といってもいいのですが、日本人の多くはキリスト教徒ではないのにも関わらず、明治時代、西洋由来のものをありがたがって受け入れる過程で、無批判といってもいいくらい、知らず知らずのうちに身に付けてしまったものなんですよね。
――それ以前のメソポタミアやエジプトなどの古代文明では、動物は支配対象であった一方、人間にとって恐れや憧れを抱く存在で、ライオンに人間が生贄として捧げられていたという記述も印象に残りました。古代から中世の動物観についても詳しく書かれていますが、執筆されてどのようなことを感じられましたか?
溝井:なかなか一筋縄ではいかないものですね。人間というものは非常に複雑で、崇拝はしていても利用もするわけです。たとえばメソポタミアでは、ライオン狩りをして王の存在をアピールしたりもしました。ただ、古代においてはひたすら支配するべきという考えばかりではなく、自然に対する畏敬の念がまだ残っており、エジプト人は神々を表すものとして動物を扱っていたりもした。その辺りが古代文明の魅力だと言えるでしょう。
――ちなみに古代ローマでは、動物同士や人と動物を戦わせる催しがありましたが、中世以降のヨーロッパでも動物同士を戦わせるアニマルコンバットが実施されたりと、人間は動物を用いて権力を見せつけるようになります。
溝井:動物は、人間にとって自分の道具を代弁するために用いるものだった一面もあります。さまざまな時代を見るなかで重要なのは、動物園の中で扱われている動物の向こう側には必ず人間の姿がちらつくということ。例えば、アニマルコンバットが流行した近代ヨーロッパは、30年戦争という、ものすごく残虐な出来事が起こった時代でもあったわけです。
その次の時代で、フランスのルイ14世は動物たちを戦わせず、王がすべてをコントロールして理想の社会を作ろうとした。ルイ14世が持っていた動物園――メナジェリーと呼びますが――は、まさにそういったものだったんです。動物園は、いつの時代も社会の縮図としての一面があったのですね。その点、本書では動物園と人との関係を楽しむついでに、知ってもらいたかったところでした。
――近代ヨーロッパのメナジェリーを経て、1828年に世界初となるロンドン動物園が開園しますが、動物園というものは意外と歴史が浅いのだなと。だからこそ、今もなおいろいろな動物園で試行錯誤が続いているんだなということが実感できました。
溝井:動物園が本格化された19世紀は、植民地時代なんですよね。結局、異郷の野生動物を展示する動物園は帝国主義時代の産物であるわけです。ただ、19世紀から現代まで、ものすごい勢いで社会が変化してしまったので、動物園もその変化に適応するのが大変でした。
例えば、初期の動物園は不自然な場所――狭い檻の中――に動物を閉じ込めていましたし、第2次大戦前や戦後には動物ショーが流行していました。これらは今から見ればすべて不自然ですが、支配するという点においては一貫していました。つまり、動物に不自然なことをさせることによって、相手を支配しているのだという満足感を感じさせる部分があったということです。
その後、戦後の動物園が悪戦苦闘しながらやってきたのは、いかにして不自然さをなくすかということでした。狭い檻を撤廃して、動物ショーのようなこともしない。今もなお続いている挑戦ですが、できるだけ自然に近い環境にしようと変化しつづけています。
興行師バーナム、そして動物商カール・ハーゲンベックの登場
――近代の動物園を生み出した人物として、本書では映画『グレイテスト・ショーマン』の主人公のモデルとなった興行師バーナム、そして動物商カール・ハーゲンベックが挙げられていましたね。
溝井:2人ともいろいろ批判されるようなこともした人物ですが、バーナムもハーゲンベックも部外者でありながら、動物園の発展に存在感を示したことは高く評価しています。もともと、バーナムは見せ物をしていた人ですし、ハーゲンベックは動物取引を商売としていて人でした。そういう人たちのほうが幅広い視野を持っている。つまり、当時社会がはたして何を求めているのかを知っている人たちだったのです。おそらく彼ら、特にハーゲンベックにとっては、狭い檻での動物飼育を市民は喜んでいないらしい、動物園は体験型の施設であるべきということに気づいていたようです。ハーゲンベックはそのような視点から、広大な敷地で動物を飼う方法を生んで――成功したら批判されたりもしましたけれど――動物園に新しい時代をもたらしたといえるでしょう。
動物園や水族館が突きつける冷たい現実
――本書で特に衝撃的だったのは、戦時中の動物園についてでした。『かわいそうなぞう』のことはもちろん知っていましたが、日本だけでなく世界中で戦争によってたくさんの動物が犠牲になっていたというのは非常に辛い現実でした。
溝井:動物園や水族館が私たちに突きつけているいちばん冷たい現実は、支配する側が人間であり、支配される側が動物であるということです。日ごろ動物園や水族館で楽しんでいる時は、そういったことをあまり感じませんが、動物飼育は基本的にすべて人間の意思に任されているという実態があります。人間が危機に立たされた時、当然、人間は自分の身を守ろうとするものなので、動物と人間のあいだの溝がこれでもかというくらい、はっきりと見えてしまうんです。
――本書の中で、ドイツのノイミュンスター動物園の園長が、新型コロナウィルス流行によって「最悪のときは動物たちの間引きもありうる」と示唆していたことは、この世界も戦時中と同じように動物たちを過剰に振り回してしまう怖さを痛感しました。
溝井:衝撃的なニュースですが、どちらかと言うと注意喚起の意味を込めて、こういった恐れがあると敢えて表現したんだと思います。ただ、社会のサポートが失われた瞬間、ヨーロッパのような動物園先進国であってもこういったことを考えざるを得ないんだということは感じますよね。戦時中は総力戦に突入してしまったので、動物園は最悪の事態を迎えてしまいました。今、世界中の動物園は厳しい状況に直面していますが、コロナの流行がどれくらい長く続くのか、まったく予想はつかないので、状況が悪くならないことを祈るばかりです。
動物園は「自然以上に自然らしい世界」を作ってきた
――動物園でのさまざまな試行錯誤について書くなかで、いちばん興味深く感じたのはどんなことですか?
溝井:個人的にいちばん面白いなと思うのは、動物園のデザイン。建物を見ることによって、その動物園が動物のことをどう考えているか、動物に敬意をはらおうとしているのかは感じとれます。歴史的に見ると、かつては監獄のデザインに似た施設もあれば、ハーゲンベックが考えたようなパノラマ式のものもあり、最新型の野生空間に没入できるランドスケープ・イマージョンを導入したものもある。人間の無数のアイデアをいかに実現して、デザインするかというところは非常に面白いですね。
――最近の動物園の展示は、動物福祉を向上させ、なるべく自然や野生に近づこうとしているようにみえます。
溝井:大きな流れとしてそうですね。もちろん本物の自然というわけにはいきません。動物園は「自然以上に自然らしい世界」を作ってきました。けれども、それはあくまで人間がイメージした自然を形にしているのだということは忘れないほうがいいですね。
私たち人間は自然を楽しむ時、代用品や二次創作物で満足することが多いんです。例えば、水族館に行くと海に潜ったような気分になれる。動物園やテーマパークもそうですね。それは、理想化された姿だけで満足してしまうようなことでもあります。今の流れはもちろん誤っていないと思うのですが、そこから先に、動物がほんとうの自然に生息する姿を見てみたいと思わせることが重要だと思います。
――動物保全に対して、日本は後進国だと言われています。動物園の施設はまだまだ旧式のものが多いですが、動物福祉の充実が求められる今、飼育員さんたちが工夫を凝らしてQOLを向上しようと努力している動物園もたくさんあります。
溝井:この本を通して強調したかったのは、人間の動物に対するイメージ、つまり動物観が今、大きく変化しつつあるということです。動物の権利が言われ始めたのは1960~70年代辺りからで、その影響が直撃したのはアメリカの動物園でした。今は随分と改善されていますが、ヨーロッパ、そして日本の動物園もグローバルな流れを意識せざるを得なくなっています。動物福祉に無頓着でいることが、許されなくなりつつあります。
今はコロナ流行の影響もあって、外国人はあまり日本に来ていませんがいずれ戻ってくるでしょう。SNSによって写真や動画が瞬く間に世界へ拡散されてしまう時代ですから、国境はないものと考えていたほうがいい。その中で、日本はヨーロッパやアメリカ以上に動物福祉をしていますと胸を張って言えるようになっておかないといけないでしょうね。そして、そこでも重要なのは部外者の視点です。シビアな目で見ると日本の動物園はまだまだ改善の余地はあるでしょう。健全さを保つ意味で、一般の人たちの批判的な目は必要だと思います。
――動物園は、動物福祉、そして飼育環境においてさらに変化していかなければいけないということですね。
溝井:はい、変わらないといけません。
歴史を研究している立場からいいなと思うのは、動物福祉に気を配る一方で、古い飼育舎を残している動物園です。ロンドン動物園やアントワープ動物園では昔の飼育舎を保存ないし復元して、在りし日の姿を伝えています。そうやって歴史へのアクセスポイントを残しておくことで、動物園として奥行きが出てくるのではないでしょうか。歴史的な資料としての価値も大きいです。
――天王寺動物園にあるチンバンジーのリタとロイドの像は、まさにそれに当てはまりますね。
溝井:はい。チンパンジーに芸をさせていたというのは、苦い記憶でもあります。ですが、かつて行っていたことをなしとするのではなく、昔はこういうことがありましたと示していることは立派です。天王寺動物園では、例年夏に戦争と動物園の展示もやっていて、当時、殺処分があったこと見せています。そういった視点は良心的で、大いに評価すべきでしょう。
昔の自分たちはどうだったのか、だからこそこうしなければいけないんだということを、歴史を踏まえて考えている動物園は大丈夫です。なぜなら、広い視野でどうしなければいいかをわかっているからです。また、欧米における動物園、水族館の立場は非常に厳しい状況がありますが、だからこそ優秀です。それらの動物園は動物福祉に心を配っていることは見ていて明らかです。市民の意識がそうさせてきたといえます。
意識をアップデートするために必要なこと
――そうすると、私たち一人ひとりが動物に対する知識、意識を身に付けることが大切と言えますね。どうすれば、アップデートされていくと思いますか?
溝井:いろいろな人が発信して、動物園がそれを汲み取っていくという、循環が必要になるでしょうね。だからこそ、私も動物園の部外者ではありますが、書籍というかたちで発信していますし、動物園の人たちもさまざまな情報を発信している。ただ、一方通行ではダメで、発信を受けた人たちが動物園に見に来て、またいろいろな疑問をぶつけていくことで、双方向なものになっていくのではないでしょうか。
――本書にも書いてありましたが、動物園は必要ないと感じる人が一定数います。むやみに動物を増やすことには確かに疑問を感じますが、異国にいる動物を身近に感じて、その匂いや大きさなどが体験できる動物園はすごく貴重な場であるとも言えます。これからの人と動物園の関係性は、どうなっていけばいいと思いますか?
溝井:非常に難しいですね。シビアな言い方をすると、動物園や水族館は病院のように、絶対社会に存在していなければいけないものではない。……こんな言い方をすると、動物園を研究している私自身に跳ね返ってきそうで恐ろしいですが、だからこそ動物園は誕生時からずっと、自分たちの存在意義をアピールしていなければならなかった。戦争に協力した過去があるのも、そういう一面からなのですね。
動物園の存在というのはもともと非常に不安定で、大多数の人たちが動物園あるいは動物についてどう考えるかによって、未来が方向づけられるものなのです。例えば私は毎年、大学の講義のあとの学生たちに質問をします。今後、動物園は必要か、存在するとしたらどういう姿が望ましいかを書いてもらうのですが、年々動物園はなくてもいいという意見が増えています。ただ、すぐになくなってしまえばいいというわけでもない。それに、全員が動物福祉は必要だと答えます。だから、動物園の存在意義とは何かという問題は考え続けていくべきではないでしょうか。動物園という空間にしかない価値はあるはずで、デジタルで代用するのは難しいように思います。
――デジタルでの代用だけになってしまうと、先ほど話されていたように、自然とは異なる人間の理想型だけで満足してしまうようになるかもしれないですよね。
溝井:そうですね。今後取るべき道はとにかく動物福祉を手厚くして、個体数を多くしないこと。また、動物が精一杯、輝くような魅力的な展示法を取るべきでしょう。本書で紹介しているアメリカのウッドランド・パーク動物園は見事です。また、ヨーロッパとアメリカの動物園をまわって感じたのは、園内を歩いているだけで楽しいということ。動物のいる環境をただ歩いているだけですごく満たされた気分になるほど、緑が豊富で瑞々しい。個人的な意見を言うと、園内に緑を増やしていくことが大事でしょうね。大阪の天王寺動物園はその取り組みが顕著で、てんしばゲートから入ると緑がどんどん押し出してくるような感覚に浸れます。メインとなる展示も非常に優れている最新型の動物園でありながら、歴史にもアクセスできて奥行きがあるのでおすすめです。

溝井氏に聞くおすすめの動物園
――国内でほかにおすすめの動物園はありますか?
溝井:関東だと、よこはま動物園ズーラシアは体験型施設で興味深いですね。天王寺動物園のように、人間の視線を感じさせない展示方法をとっていることも重要です。見るという行為は支配することとリンクしていて、見られる側というのは支配される側でもあります。ですから、動物が隠れたい時には隠れられるようにしたり、動物が気づかないところからこっそり覗き見できる展示がある動物園はいいですよね。山口県のときわ動物園は、熱心に新しい展示に取り組んでいる未来型の動物園なので、ここもおすすめです。
――本書は動物や動物園が好きな人にとってすごく興味深い一冊ですが、そのほか読んでいただきたい方々はいますか?
溝井:コロナ禍でもありますので、日常を離れて過去のワクワクするようなエピソードに触れたい、冒険をするような感覚で旅立ちたいと思っている方に読んでいただければ大きな喜びです。戦争の話も出てきますが、全体としては楽しく読んでいただけるのではないかと思っています。冒険小説が好きな方、あるいは歴史全般に興味がある方にも読んでいただけると嬉しいです。
■図版出典一覧
1. 著者撮影
2. DʼAveline. ʻBackyard of the Royal Menagerie of Versailles during the Reign
of Louis XIV, 1643- 1715.ʼ Wikimedia Commons. 17 October 2020 <https:// commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ménagerie_de_Versailles#/media/ File:Versailles_M2.JPG>.
3. 著者撮影
4.秋山正美『動物園の昭和史― おじさん、なぜライオンを殺した
の― 戦火に葬られた動物たち』データハウス、1995年、246ページ
5.〜8. 著者撮影
■書籍情報
『動物園・その歴史と冒険』
著者:溝井裕一
出版社:中央公論新社
発売日:発売中
定価:920円(税別)

