ポール・マッカートニー、来日公演の“オールタイムベスト”に込められたメッセージ
音楽
ニュース
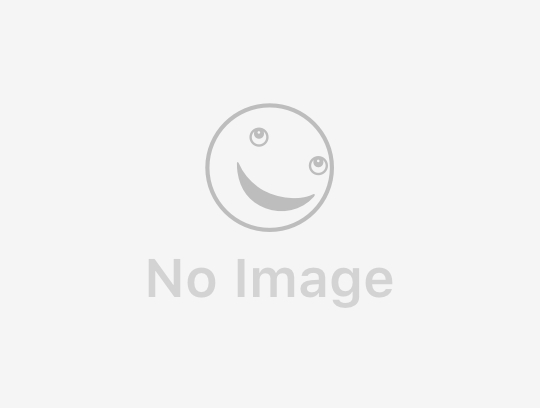
ポール・マッカートニーによる『フレッシュン・アップ ジャパン・ツアー2018』の幕開けとなった10月31日の朝。テレビを点けると、「とくダネ!」司会の小倉智昭さんがポールについて話していた。大ファンである西武ライオンズが(同時期に開催された)日本シリーズ進出を果たせなかったことを悔やみつつ、おかげで気兼ねなく東京公演に行けるとのこと。音楽について語っているときの小倉さんは、いつだって表情がキラキラしていて最高である。
それから数時間後。同ツアーの会場である東京ドームに足を運ぶと、同じようにキラキラした笑みをそこかしこで見かけた。その年齢層は実に幅広い。制服姿の女子高生に大学生っぽい集団、カップルや子連れの夫婦、重役クラスと思しきオジサマや、1966年のビートルズ初来日も観ていそうなご年配の客まで。はたまたポールやウイングスのシャツを着た正統派(?)のファンから、They Might Be Giantsのパーカーをわざわざ着てくる音楽オタクまで。クラスタの壁を超えて、いろんなタイプの人たちがポール見たさに集まり、写真をパシャパシャ撮っている。洋楽市場がどんどんニッチ化していくなか、そこには夢みたいな光景が広がっていた。これほど老若男女が広く集まるイベントが、他にどれくらいあるだろうか。
ポールは2013年を皮切りに、ここ数年はハイペースで来日しているが、ハッピ姿でやってくる度に社会現象レベルのフィーバーを巻き起こしている。この日も当日券こそ出ていたが、ほとんど満員と言ってよさそうな入りだった。もちろん、熱心なリピーターも相当数いるのだろうけど、念願の初ポールを観に来た人も少なくないはずだ。忘れられない思い出がある人もいれば、観光地を訪れるようなミーハー感覚で来ている人も、ポップの頂点を拝みに来た人も、つい最近ストリーミング経由でファンになった人も、一曲も知らないけど何となくついてきた人もいるかもしれない。
だからきっと、オーディエンスのなかには十人十色のポール/ビートルズ像があると思う。そういった期待、それぞれの人生の全てに応えるようなパフォーマンスを、ポールは見せてくれた。76歳を迎えた彼が、最新アルバム『Egypt Station』で36年ぶりの全米チャート1位に輝き、今もポップミュージックの最前線にいる理由をそのまま体現したようなステージだった。

ビートルズの「A Hard Day’s Night」、ウイングスの「Hi, Hi, Hi」で威勢良くオープニングを飾ると、「こんばんわ東京、ただいま!」と日本語で挨拶するポール。ここから「All My Loving」までは若干の予定調和っぽさも感じられたが、4曲目の「Letting Go」で、アリーナ席に現れたホーンセクションの演奏が入ると、アンサンブル全体が見違えるほど“フレッシュン・アップ”されたものになり、客席からも手拍子が沸き起こる。
このホーン隊が、今回のライブではひたすら冴えていた。『Egypt Station』から披露された「Come On to Me」でも効果てきめんで、楽曲にグルーヴをもたらしている。吹き荒れるブラスサウンドを耳にして、ウイングス全盛期の傑作ライブフィルム『ロックショウ』を思い浮かべたファンも多いだろう。あるいは、ここ数年ブラックミュージックが更新されていくなか、ブラスサウンドの魅力が見直されている傾向にあったので、そういう機運をポールも見逃さなかったのかもしれない。そして、さらに驚かされたのが、この曲のアウトロで「イェー、イェー!」と叫ぶポールの声。大ベテランが新曲でここぞとばかり、最高潮のボーカルを絞り出す光景は、アーティストのあり方として理想的だと思った。
ベースからエレキギターへと持ち替えてきたポールは、続く「Let Me Roll It」「I’ve Got a Feeling」でブルージーな展開を見せると、今度はピアノの前へ。妻のナンシーに捧げた「My Valentine」や、ソロ屈指の名曲「Maybe I’m Amazed」などを高らかに歌い上げる。重厚なギターロックからメロウなバラードまで。計算し尽くされたセットリストで客席の隅々まで支配してしまうあたりは、元祖アリーナロッカーの面目躍如だろう。そこから今度はアコギに切り替え、「I’ve Just Seen a Face」「Love Me Do」といったビートルズ初期のナンバー、はたまた前身バンド=The Quarrymen時代の「In Spite of All the Danger」まで飛び出すと、ここから先はポールの独壇場だった。

この日、披露された全36曲のうち、ビートルズのナンバーが半分以上を占めていた。それ以外も、往年の代表曲から近年のナンバーまで、オールタイムベストと呼んでも差し支えない構成である。伝説の通り、水を飲まないポールのステージはとにかくテンポがいい。おまけに曲間では、なるべく日本語でMCしながら、ひたすら会場とのコミュニケーションを図ろうとしていた。世界中の誰でも知ってるスーパーミュージシャンが、日本のファンのためにここまでやってくれるのだ。これでポールを好きにならないほうが無理である。
ここでふと思い出したのが、フジロックでのボブ・ディランだ。ディランはMCなんて一切しないし、わかりやすい形でヒット曲を演奏することもない。それでも、百戦錬磨のバンドによる演奏はひたすら素晴らしかったし、一切の無駄を省いているようで、アメリカ音楽の豊潤な味わいがたっぷり詰まっていた。それに、ディランはただそこにいるだけで最高にカッコよかった。渋くて偏屈で妥協せず、だからこそみんな憧れた、求められているディランの姿がそこにはあった。
それと同じように、ポールには誰もがヒット曲のオンパレードを求めているし、時折チャーミングにおどけてみせたり、愛嬌に満ちた人柄をみんな愛している。その期待に一挙一動で応えるポールもまた、最高にカッコイイ。かつて60年代には、海を越えてライバルと目されたビートルズとディランが、50年近くの月日を経て、己の表現を極めた姿をアピールしている。対照的なステージのようで、どちらも同じだけの何かを背負っているようにも感じられ、そう考えたら目頭が熱くなってしまった。
「Love Me Do」のあと、「Blackbird」を歌う前に「これは公民権運動についての歌です」とポールは説明していた。ケンドリック・ラマーが「Alright」でラップしているように、ブラック・ライブズ・マター以降の混乱が続くアメリカにおいて、この曲に込められたエモーションは現在も有効であるはず。ヒップホップを熱心にチェックし、近年は社会平和を熱心に呼びかけているポールのなかでも、きっと輝きを増している一曲ではないか。だからこそ、一際シンプルに演奏されたのが胸に響いた。
そして、ハイライトとなったのが『Egypt Station』からの「Fuh You」。ヒット請負人のライアン・テダーが手掛けたこの曲は、アルバム中でも群を抜いてモダンでキャッチーだった。新作から披露されたのはわずか3曲だったが、この曲を歌っているときのポールが、一番生き生きしていたような気がする。そこから「Something」「Ob-La-Di, Ob-La-Da」「Let It Be」などヒット曲が立て続けに披露され、「Live and Let Die」ではポールも耳を抑えるほど、火柱と花火が「バーン!」と鳴っていた。そして、大合唱の「Hey Jude」で本編は終了。

アンコールで、ポールはハロウィンにちなんでスカル・マスクを被って登場。「Yesterday」に始まり、「Helter Skelter」から『Abbey Road』のメドレーへと繋ぐ感動的な流れでフィナーレを飾った。映像では、「Golden Slumbers」「Carry That Weight」を演奏するあたりでイエロー・サブマリンが登場。海の中を泳ぎ回ったあと、アングルが空へ変わって、最後に「The End」を演奏し終えると、そこには大きなラブシンボルが映し出された。そこにも、ポールからの無言のメッセージが込められているはず。今の世の中を思うと、重たいものが感じられた。
そういえば、ポールがMCで、次の曲の背景だったり、ジミ・ヘンドリックスへの追悼、ジョン・レノンやジョージ・ハリスンとの思い出などを熱心に説明していたのも印象深い。どれもファンなら知ってそうなエピソードだし「なんでわざわざ?」とも思ったが、きっとポールは初めてライブを観に来た人や、若いファンに向けて伝えたいことがたくさんあるのだろう。
ここ数年、多くのロックミュージシャンがツアー引退を発表しているなか、76歳のポールは、今も新しいファンのために扉を開こうとしている。「最近は日本に来すぎだから」なんて言わず、ぜひ来年もツアーを開催してほしい。
(取材・文=小熊俊哉/写真=Yoshika Horita)

