TRF DJ KOO×守尾崇が語る、90年代J-POPとエイベックスサウンドが現代に伝えるもの
音楽
ニュース
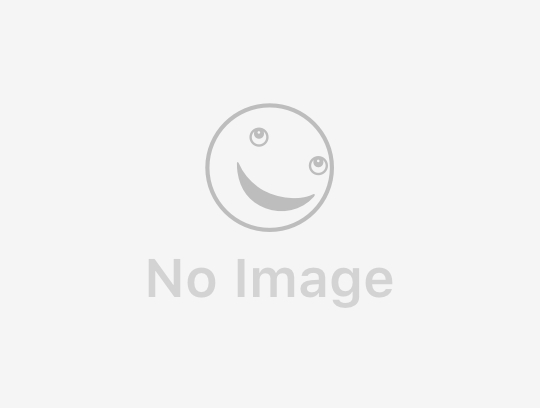
90年代を代表するアーティスト、TRF(※96年から大文字に)。90年代といえば、TRFが「CRAZY GONNA CRAZY」(158.7万枚)、「masquerade」(138.9万枚)、「survival dAnce ~no no cry more~」(137.6万枚)、「BOY MEETS GIRL」(128.5万枚)、「OVERNIGHT SENSATION ~時代はあなたに委ねてる~」(106.3万枚)などミリオンヒット曲を連発。他にもJ-POPシーンでは様々な名曲が誕生した。
いかにして90年代J-POPは生まれ、狂乱の時代を迎えたのか? なぜ当時の音楽は今もなお歌い継がれているのか? 曲の構造やサウンドに隠された秘密とは? 今回リアルサウンドでは、DJ KOOとTRFのサポートキーボード&マニュピレートを担当していた音楽プロデューサー、守尾崇(たかし)をゲストに迎えたトークを展開。90年代ヒット曲&ポップカルチャーの魅力を、二人に余すことなく語ってもらった。(ふくりゅう:音楽コンシェルジュ)
洋楽と邦楽の架け橋だったダンスミュージック
――J-POPの誕生を振り返ると、まず1988年にターニングポイントがあったと思います。ヒットチャートを見ていると87年までは演歌、歌謡曲、アイドルが強かったのですが、今のJ-POPに通じる流れが88年から89年の間で急速に生まれているんですよね。
DJ KOO:TM NETWORKの大ブレイクもその頃ですね。アルバム『CAROL ~A DAY IN A GIRL’S LIFE 1991~』のリリースもあったし。
――90年代J-POPの立役者の一人、小室哲哉さんはTMのシングル「COME ON EVERYBODY」で『第39回NHK紅白歌合戦』(NHK総合)へ初出場しています。KOOさんはtrf加入前、80年代半ばからリミックスチームThe JG’sをdj hondaさん等と結成。リミックス文化を牽引し、ディスコやファンク、ユーロビート文化を盛り上げました。
DJ KOO:それこそ、アイドルのリミックスなどもやってたね。
――小室さんも「Get Wild」以降、ユーロビート的な四つ打ちダンスポップでJ-POPのルーツを作られたと思います。ダンスミュージックの文化が、J-POPに繋がる礎を形成したと言っても過言ではないのかな、と。
DJ KOO:当時ってまだまだ邦楽と洋楽が分かれていた時期だったんですよ。その橋渡しがダンスミュージックだったのかな。日本の歌を歌謡曲からJ-POPに変えたよね。そのきっかけとなったのが、ユーロビートなどディスコやクラブから生まれたサウンド。まだ、J-POPという言葉はなかったんだけど、歌謡曲のメロディをダンスミュージックでアレンジしていくという発明でした。初めてDJのノウハウが、音楽制作に取り入れられた時代だと思います。
――それまでは時代を象徴するようなサウンド感がありましたが、90年代ってなんでもありというか。洋楽に特に顕著ですが、いろんなジャンルが増えましたよね。
DJ KOO:そうだね。その理由のひとつとしては、楽器などの機材の進化があって音楽の作り方に変化が起きたからだと思います。
守尾: サンプリングなどのDJ的なサウンドの作り方が多く取り入れられるようになりましたね。ジャングルなんて、ビートを早回しにして混ぜて作ってましたから。80年代でもMacとかを使えばできたんですけど、まだまだ簡単じゃなかった。その後、90年代に入ってわりと簡単に操作できるサンプリングキーボードが出てきて、ループを早回しにして乗せたりするようになっていくんです。trfの「Sexual in Gravure (JAZZY GROOVE MIX)」とか、ギターのカッティングはサンプリングの音ネタですね。
DJ KOO:音ネタだね。サンプリングの切り貼り。
守尾:カッティングも昔は人が弾いてたのが、サンプルをわざとサンプルらしく、人とは違う使い方をしてみたり。それが90年代的かな、と。
DJ KOO:それまではバンドの演奏力とかボーカル力勝負だったんですよ。でも、90年代はアレンジはじめもっとセンスが大事になってきました。
日本のレイヴカルチャーを牽引した小室哲哉とエイベックス

――実際、お二方とも90年代初頭は音楽制作とどのように向き合っていましたか?
DJ KOO:機材との戦いだったかな。デジタルレコーディングとか、新しい機材の導入とか。デジタルでできることが増えてきた分、勉強することも増えました。守尾君なんかはtrfの最初のホールツアー『trf TOUR ’94 “BILLIONAIRE ~BOY MEETS GIRL”』あたりで機材周りの大変さをくぐり抜けてきたよね。
守尾:そうですね。やっとライブでコンピュータを使っても安心できるようになってきた時代でした。94年頃はMacを使ってましたね。僕もステージの上で楽器を弾きながら。今は音自体を再生というか、要はレコーダー的な使い方で使っていますが、この頃はMIDIで楽器を鳴らして演奏してました。
――KOOさん、『trf TOUR ’94 “BILLIONAIRE ~BOY MEETS GIRL”』のツアーではどんなことを思い出しますか?
DJ KOO:小室さんがアルバムが完成して「1stツアーやるよ!」って言ったときに、スタジオでセットリストを書いてくれてことを覚えています。実際にtrfっていうダンスユニットがどういう形でライブをホールツアーで表現していくかなんて、まだ誰にも見えてなかったと思うんです。でも、小室さんの頭のなかでは完成されてたんですよ。
――trfもアルバムの中では多種多彩なジャンルの音楽にチャレンジしてきましたよね。そもそも所属レーベルであるエイベックスは、新しいサウンドへのアプローチが早かった。しかも、成り立ちでいうとそもそもインディペンデントなレーベルだったという。
DJ KOO:そうですね。90年代のジュリアナサウンドというかテクノサウンドをヨーロッパから引っ張ってきたのはエイベックスだし、そこの名残の派生で、アンダーグラウンドなダンスミュージックも使命感として網羅していたんじゃないかな。
――93年に、東京ドームで『AVEX RAVE’93』が開催され、trfも小室さんと出演されてました。The Prodigyもエイベックスからのリリースで、そのイベントに出演していたんですよね。お立ち台に溢れたあの狂乱の空間に。
DJ KOO:レイヴカルチャーを巻き込んで、色々一緒くたなイベントだったよね。プロディジーは当時、テクノとして認識されていたからね。この時期、すごい好きだったな。デジロックって呼ばれていたロックとダンスやテクノのミクスチャー感。プロディジーやケミカル・ブラザーズ(The Chemical Brothers)とかさ。最高だよね。
――去年、SNSで93年の東京ドームでのKOOさんと並ぶ小室さんの写真をアップしてましたよね。めちゃくちゃかっこいいビジュアルで。
DJ KOO:あの頃は、ビジュアルも混在してたと思いますよね。80年代からの流れのニューロマ(ニューロマンティック)とか、ハワード・ジョーンズとかニューウェーブみたいなノリとか。Jesus Jonesは、ハウスでミクスチャーでバンドだったよね。いろいろ混在している感じがtrfにはあったり、それが90年代っぽいよね。
――初期KOOさんのドレッドはJesus Jonesからの影響?
DJ KOO:そうです。小室さんがJesus Jonesのアルバムジャケットを見て、「いいね!」って言ったので次の日に。でも、当時はやってくれるところがなかなか無くて(笑)。それでやって家に帰ったら、奥さんにナマハゲみたいって言われちゃって(苦笑)。それくらいの思い切りがあったよね(笑)。
――守尾さんは、90年代初頭どのように過ごしていましたか?
守尾:僕はアマチュアからちょっとずつ仕事をし始めた頃でした。まだ20代前半ですね。YAMAHAのEOSというシンセサイザーが90年代に登場して、小室さんとそれでお付き合いがあり、大きい仕事をいただいたのがツアー『trf TOUR ’94 “BILLIONAIRE ~BOY MEETS GIRL”』だったんです。そのちょっと前のTMNの終了コンサート『TMN 4001 DAYS GROOVE』もデータ制作のお手伝いをやらせていただいてました。この頃、小室さんが作業している姿を後ろで見ていて。データ制作や音ネタを重ねたりしているのを「こうやって作るんだ!」って学んで。ここでの経験が、次の00年代に活かせたなっていう思い出ですね。
DJ KOO:まだシンクラヴィアだっけ?
守尾:色々使っていたと思いますが、僕のなかで小室さんは、エンソニックのVFXとかASRを使っていたイメージが強くて。今でも、音が太いって有名なシンセなんですよ。その後、mihimaru(GT)のレコーディングで、キックの音が細いなって時に、ASRでサンプリングし直して使ったことがありました。名器ですね。「WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント」はリズムがジャングルじゃないですか。あれは、ターンテーブル的な発想だと早回ししてやるのでビートが崩れないんですけど、小室さんは鍵盤で作っていたんで途中で拍の表裏がずれたりして新しかったなと。海外の新しいジャンルに、小室さんの手癖というかテイストが、上手く融合されて新しいサウンドが生まれていてすごいなと思っていました。
――世界で1番売れたであろうジャングルソングですもんね。“新しいリズム、新しいビートに、メロディアスなメロディを乗せるという方程式”に“メロディのセンスは日本人好み”というかけ合わせが、90年代のひとつの発明になりました。trfの場合は、それがテクノからはじまったという。しかも、アルバム1枚目『trf ~THIS IS THE TRUTH~』の際は完全に洋楽スタイルで、早すぎた感もありながら。
DJ KOO:これはもう、小室さんがレイヴを日本でやるっていう意味で、国内市場を全く考えてなかったですよね。レイヴっていうシーンを、日本で自分で新たに作るんだってことだったんじゃないかな。このときに<PWL>とタッグを組めたことは、trfにとって大きな成功へのアプローチになりましたね。
90年代〜00年代を席巻したTKサウンド

――エイベックスの邦楽アーティスト第1号なんですよね、trfは。改めて、結成時のエピソードを教えてください。
DJ KOO:アルバム『trf ~THIS IS THE TRUTH~』の制作途中に、小室さんと会ってスタジオに参加することになりました。でも、まだ当時は小室さん以外、誰もこのアルバムがどう完成するのかわかっていなかったと思います。当時は音を埋めていくアレンジが主流でしたが、ベースとキックとリズムのみでサウンドを構築していた感じで。そぎ落とされた少ない音で淡々とキックの四つ打ちがあるというか。
守尾:『trf ~THIS IS THE TRUTH~』は、攻めてますよね。当時小室さんが作っていたなかでも、かなり激しめのダンストラックに小室さんらしいメロディが乗っていて、すごく新鮮でした。
――あと、ユニークなのがディスコやクラブイベントとも活動が連動していたこと。
DJ KOO:あれは『TK RAVE FACTORY』っていうイベントを横浜ベイサイドクラブではじめたのがスタートで。感覚的にはイベントのためのCDというか、イベントのために集められたメンバーだったんですよ。今でいう『Ultra Japan』みたいなフェスというか、そんな感覚に近かったと思います。
――キックの強さへのこだわりや音の引き算。今から考えると、EDMのカルチャーにも通じるセンスですよね。
DJ KOO:このときに小室さんが話していて印象的だったのが「人数が多ければ多いほどリズムは伝わっていくから」という言葉で。「キックだけでも何万人もオーディエンスがいたら、それでノレるよ」と。とにかく、キックの音にこだわってましたね。
――いまこそ、アメリカのビルボードチャートへランクインするアーティストのキックへのこだわりは半端ないですよね。それこそ、trf初のヒット曲「EZ DO DANCE」は、実はとてもシンプルなサウンド構成だったりします。キックだけでノレるトラックになってるんですよね。ライナーノーツでも小室さんがそんなようなことを語っていました。
DJ KOO:キックとテンポだよね。BPM140だったらテクノやトランスのテンポ、BPM135だとちょっと哀愁のある長いメロが映える。当時は、裏打ちのハット16符がマストだったよね。
守尾:そうですね。
――「EZ DO DANCE」や「寒い夜だから」のヒットなど、いわゆる歌謡曲をダンスミュージックが飲み込んでいきました。安室奈美恵、globeなど、小室サウンドが広がっていく過程で、松浦(勝人)さん率いるエイベックスチームはTKサウンドを分析。作家チームを作ってEvery Little Thingや浜崎あゆみなどで、小室さん以外の作家でも結果を出し続けていきました。大文字以降のTRFももちろん。
DJ KOO:そこは、守尾君なんか特にそうだけど、クリエイターが大事なポジションになったよね。それまでの作詞家・作曲家というよりも、もっとサウンド全体を取りまとめていく感じで。
――90年代J-POPを振り返るうえで、そこが大きなポイントかもしれませんね。一方で00年代以降はトラックメイカーのカルチャーが当たり前になっていきましたが、90年代初頭はそんな感覚はなかったんですよ。でも小室さんや浅倉大介さんから、いまに通じるトラックメイカー文化、00年代以降にも通じるJ-POPが発祥したのかなと。
守尾:たしかにそうですね。そんな意味では、作家をチームとしてファクトリー的に束ねた松浦さんもそれを意識していたんでしょうね。
DJ KOO:松浦さんはもともとユーロビートの分析をしていて、どうやってJ-POPに活かすかについてよく熱く語っていました。あと、90年代のダンスミュージックって、あくまでDJがプレイするお皿であって、ライブ感までしっかり考えることはなかったんですよ。そこでtrfがホールでライブをやりはじめたっていうことはデカかったし。たぶん、サウンドを支えた守尾君なんか手探りというか。ライブで魅せるって大変なことだったと思います。
守尾:最初、trfのバンドはキーボードとドラムとベースだけで、ギターがいなかったんですよ。人間3人とコンピュータとtrfのみなさんっていう形で。そういう意味でも攻めてましたね。ドラムとベースで生のグルーヴをだして、あとは機械でいいじゃないかっていうところが、小室さんの中にあったと思うんですね。
――trf以降のダンスミュージックカルチャーは、ダンサーをパフォーマーとして目立たせていきますよね。ここでギターがいなかったことも大きなポイントだと思うんです。―あと、最近は世界的にもスパニッシュやアフロビートのセンスをポップミュージックに取り入れるのがスタンダードになってますが、この時期のTKソングってワールドミュージックのエッセンスを取り込んでいましたよね?
DJ KOO:そうでしたね。3rdアルバム『WORLD GROOVE』とか特に。小室さんって、いろんなタイミングでその後の伏線になるようなことを入れてくるんですよ。振り返ってみるとすごさを感じますね。
――90年代のミリオンヒット連発のタイミングにも実はものすごい実験的なことをやっていたと。
DJ KOO:「BOY MEETS GIRL」で鳴っているパーカッションも全部和楽器ですからね。映画『天と地と』のサントラを小室さんがやったときにも参加されていたパーカッショニストに仙波清彦さんっていう方がいらっしゃるんですけど、実際に現場に来て鼓(つつみ)とか鐘を叩いてくれて、パーカッシブにしたんですよ。
守尾:チャンチキ(金属製の打楽器の一種)みたいなのも入ってましたもんね。
「MY LITTLE LOVERは超ライバル」(DJ KOO)

――90年といえばほかにも、B’zやZARDをはじめとするビーイング所属アーティストのヒット。そして、トレンディドラマの主題歌ヒットから小田和正「ラブ・ストーリーは突然に」、CHAGE and ASKA「SAY YES」などが誕生しています。
DJ KOO:当時のドラマのヒット曲って今も変わらず歌えますよね。やっぱり、カラオケソングの存在って大きかったよね。
――あとは沖縄アクターズスクール出身勢の台頭ですね。2018年に引退した安室奈美恵さん、MAX、SPEED、DA PUMP、Folderなど。あと、ジャニーズでSMAPのヒットも90年代大きかったですよね。
DJ KOO:そうですね。あとは、90年代といえばヴィジュアル系。X JAPAN、LUNA SEA。それからバンド系だとイエモン(THE YELLOW MONKEYS)もいたし。B’zのギターの松本(孝弘)さんには当時、よく一緒に呑みに連れていってもらいました。
――どんなお話をするんですか?
DJ KOO:遊んでいるときは仕事の話はしないけどね。この間も松本さんの自宅へ行って、Rainbowとかマイケル・シェンカーとかのレコードを聴きました。あと、90年代といえばミスチル(Mr.Children)かな。小林武史さんがプロデュースしていたグループはどれも強敵でしたね。なかでもMY LITTLE LOVERは超ライバルでした。たしか『masquerade』を出した頃に、ミスチルとチャート争いになって……。ドリカム(DREAMS COME TRUE)のリリースもあったから三つ巴みたいな。
――THE JAYWALKなど、少し大人っぽい歌えるJ-POPヒットも90年代カラオケ文化を牽引しました。
DJ KOO:よくそれだけいろんなジャンルが収まる枠があったよね。それにglobeのアルバムも良かった。
――globeのアルバムのセールスが伸びたとき、KOOさんはどのように受け止めていました? 今だからこその質問ですけれども。
DJ KOO:いや、うち(trf)にもいい曲を書いてほしいなって(笑)。globeもいいけどtrfも忘れないでねって思ってましたよ(笑)。
――そうですよね。90年代のヒット曲の一覧を見ていて驚くのが、だいたいどの曲も知ってるんですよ。音楽マニアでなくても知ってるような曲ばかりで。時代を代表する文化として“音楽”があったことは大きいですよね。
DJ KOO:95年って、他の年と比べてもミリオンヒットがたくさん出た年なんですよね。その走りは、カメリアダイアモンドのCMタイアップだったのかな。その後、サビだけでも引っかかるような曲が作られていった印象もあります。サビ30秒間で良さが決まるとか、そんな発想の作り方は90年代に生まれたものかもしれませんね。CMで流れる部分だけ先に作っておくとか、当時よくありましたから。
守尾:そんな意味では、計算というとあまり聞こえがよくないですけど、どうマーケットで聴かれるかをちゃんと考えながら作りはじめた時期なんですかね。
DJ KOO:そういった作り方の技法がダンスミュージックは特にハマりやすかったのかもしれない。サビから始まってとか、ABCの構成で転調使ってインパクト出してみたいな。素材の切り貼りじゃないですけど、ペースト作業っていうのもハマってたんじゃないですかね。
――当時のエイベックスのカルチャーからは、リミックスへの強いこだわりを感じ取ることができました。trfも必ずリミックス集をアルバムとアルバムの間に出していましたよね。リミックスカルチャーを日本で広げたきっかけもエイベックスだったと言えます。
DJ KOO:ヨーロッパでは、シングルなどひとつの楽曲に対して当たり前にリミックスのバージョンが付いてますよね。僕らも楽曲によってはもっとダンスを意識したバージョンで聴いてもらいたいという考えがあって、リミックス集『HYPER TECHNO MIX』シリーズを出したりしていますし。逆にこのシリーズは、小室さんから任せてもらっていた部分があって。当時嬉しかったのは95年に出した『hyper mix 4』が100万枚超えたんですよ。リミックスアルバムがですよ。それは嬉しかったな。当時はまだ音先行というか、リミックスが持つ価値に今以上の意味がありましたよね。今は逆に音とMVがセット、MVありきな時代になっていて。リミックスでMVを作ることとかないもんね。
――そのような時代を経て、Spotifyをはじめとしたストリーミングサービスの時代がやってくると、アルバムよりも配信シングルで定期的に楽曲をリリースすることが大事になっています。リリース自体が宣伝となり、再び音で評価される時代になりつつあるというか。
DJ KOO:たしかに、どんどんリリースは増えていますね。今は、データのやりとりだけで作れちゃうし、サイクルが早くなってきているからリリース頻度を早くしたいんですよ。覚えてもらうためにも。
――データのやりとりの話でいえば、90年代当時はネット環境的に大変でしたよね?
DJ KOO:マスタリング作業のために海外にメールでデータを送る時、電話回線で送ってたからね。ISDNで。そこで、何時くらいに届くか逆算して、マスタリングの音をチェックしたりしてました。それってまだ10数年前の話だもんね。今と大きな違いだね。
――インターネットはいろんな流れがありますけど、日本でインターネットが広まったのはWindows95以降です。一般に少しずつ普及しはじめたのは97年、98年くらい。一般家庭での高速回線、ADSLが普及したのは2001年。ほんと、つい最近ですよね。
DJ KOO:不思議だよね。ネットが普及して音源データでやり取りする時代になって。いろんなコラボレーションもボーカルトラックだけ使ってどんどんやれちゃうし、90年代はPCでやるとはいえSSLのデカい卓を使って作業してたからねぇ。デスクトップで完成させる時代ではなかったから。
守尾:そうですね。あくまでオーディオは別で録ったものだったりとか。MIDIは使っていたけども……っていう感じで。
現代にまで根付く90年代J-POP

――90年代らしさって、守尾さん目線だとどんなキーワードになりますか?
守尾:僕はシンセが好きで音楽をはじめたので、シンセが自然に使われるような時代になったのが90年代だなと思ってます。それまでシンセって、ちょっと特殊な楽器だったんですよ。
――80年代は、まだマニアックなイメージがありましたね。全体的に高価でしたし。
守尾:80年代ってまだ「シンセですよ!」って使われることが多かったんですけど、90年代くらいからシンセといっても特別なものじゃなくなくなりました。技術が進化したことによって、普通に制作でもライブでも使われるようになって。上手く融合していった時代かなと思います。
DJ KOO:シンセで曲を作る時代だね。
守尾:80年代にYAMAHAのDX7がデジタルシンセのポピュラリティーを切り開いて。90年代でサンプリングがポピュラーになって、そこから先は大きく変わってないかもしれませんね。
――90年代ならではのサウンド、機材でいうとどんなものになりますか? 80年代といえばDX7というエポックがありました。
守尾:そういう意味では、冒頭で話しましたが僕のなかではエンソニックのVFXとASRですね。小室さんがよく使っていた印象もあって。あと、音ネタをけっこう使うようになりましたね。要はサンプリングCDのこと。そのなかに「ヘイ!」とか「ワオ!」とかオケヒットとかがいろいろ入っていて。そのサンプリングを曲のなかに散りばめるっていう手法が一番使われた時代かな。
――そういえば、trfも94年にサンプリングCDを出してましたよね。
DJ KOO:はい。『Preset Sound』っていう。本物の音をそのまま出して、「EZ DO DANCE」でもそうなんだけどトラックを聞くと、普通の人だとこの音をどうやって使っていいかわからないようなノイズとかまで入ってるんですよ。それは実際に小室さんが手打ちで作っていて。あと、90年代といえばJD-800だよね。
守尾:1991年に出たRolandのシンセですね。
――プリセット53番のピアノの音を、小室さんはレコーディングで好んで使ってましたよね。
DJ KOO:やっぱり、90年代を象徴する明るいピアノサウンドだよね。
守尾:あれが当時の小室さんのピアノですね。
DJ KOO:本物のピアノみたいなサウンドではないんだけど、シンセならではのピアノで、ダンスミュージックのビートにぴったり張り付いていく綺麗なシンセなんですよ。「BOY MEETS GIRL」でも使われてますね。「CRAZY GONNA CRAZY」もそうだし、あの当時の小室さんのデータを見たらベロシティが全部127だったの。
守尾:ガツガツですか。全開ってことですね。
――それは、どういう意味ですか?
守尾:MIDIだと数値で強さ(ベロシティ)が出るんですけど、それが1から127なんですよ。それが全て127ということは、もともとキラキラした明るいピアノなんですが、さらに全開の明るさで使っていたということですね。あと当時の話でサンプルネタ的なことといえば、篠原涼子さんの「恋しさとせつなさと心強さと」をよく聴くと歌と関係ない「ファ~」って音が入ってるんですよ。これを小室さんが作っているところを僕はスタジオで聴いていて。これどうなるんだろう?って思っていたら、歌が乗ったらこんな効果になるんだ……みたいな。意外と隠し味サンプルがいっぱい使われていた時代ですね。
――あと、90年代といえばファッションの面白さもありますよね。ファッションと音楽の距離感も近かったです。裏原文化や渋カジ、アメカジ。スニーカー、アウトドアファッションなど、いろんな流行が生まれた。音楽でいうリミックスカルチャーじゃないですけど、ファッションにもそんなセンスが重要な時代になりました。
DJ KOO:スポーツ系もね。プーマとか、アディダスとか絶対に昔は私服にはしなかったじゃない? それを考えるとスポーツメーカーとか、いろんなミクスチャーが起きたよね。そういえば、先日、『90‘s REVIVAL FASHION FES』というイベントのイメージキャラをやらせてもらって、DJやトークショーを行いました。TRFは昨年25周年を迎えたのですが、イベントに親子3世代で来ている方もいて、これはすごいことだなと感じましたね。今年は平成最後だから、みんな90年代を振り返ってくれるのかな? こうやって文化は続いていくのかなって。
――そのイベントのDJでは、どんな曲をかけたのですか?
DJ KOO:最近だとね(安室)奈美恵ちゃんの「HERO」から入って、それからglobeの「Feel Like dance」いって「愛しさとせつなさと心強さと」、「BE TOGETHER」、「EZ DO DANCE」、「survival dAnce ~no no cry more~」、「Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~」で、最後にアンコールでSMAPとかかけちゃう。90年代の曲って、かけただけで雰囲気がバーッて変わるんですよ。でも、音が90年代の音だとパワーにかけるので絶えずリマスタリングしてる。1回MacにいれてゲインあげてEQかけ直して。EDM感覚のパワーのある音でかけられるようにね。MIX CD作ってみたいよね。
――CMでも、90年代の曲がよく鳴ってます。
DJ KOO:ファンションも音楽も、海外にあったいろんなカルチャーを日本へ引き入れて、それを日本独自のものとして再構築してまとめあげていったのが90年代っぽい感じがするんだよね。振り返ってみて思うんだけど、90年代リバイバルの先っていうか、俺、最近、和のユニットELECTRIC SAMURAI REVOLUTIONを組んでるのね。日本舞踊とかをやっていて。日本の伝統カルチャーとDJで組んでるんだけど、もはや海外コンプレックスじゃないんだよね。日本のみんなで作ったものが、2020年に生まれてくるような気がするな。
ーーちなみに、90年代J-POPは、90年代アーティストに多大なる影響を受けたというあいみょんヒットの流れもありますが、いまもなお若いリスナーからも評価が高いです。
守尾:今日話してて思ったんですが、当時は国内で音楽活動をガッツリ頑張っていた感がありますよね。今は、海外に出ようとするアーティストが多いじゃないですか。それだけじゃなく、海外の流れもちゃんと取り入れつつ新しいものを作ろうっていうエネルギーに溢れていたのかなって、語っていてすごく思いました。いろんな要素がいい方向に作用していた時代だからこそ、多種多様なヒット曲が生まれたんでしょうね。
(取材・文=ふくりゅう/写真=池田真理)

