『妹背山婦女庭訓』ほか名作揃いで襲名と初舞台が満載の六月
ステージ
ニュース
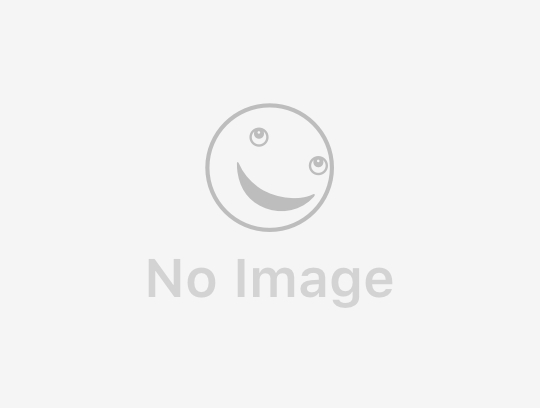
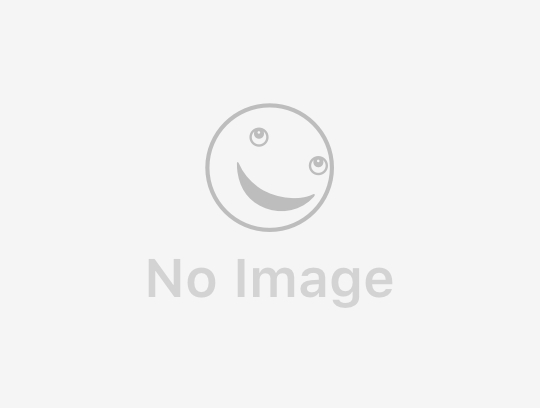
6月1日に幕を開けた東京・東銀座の歌舞伎座が、特別な賑わいを見せている。中村時蔵が初代中村萬壽を、長男の中村梅枝が六代目中村時蔵を襲名。さらに新時蔵の長男の小川大晴が五代目中村梅枝として初舞台を勤める。また、中村獅童の長男の小川陽喜が初代中村陽喜、次男の小川夏幹が初代中村夏幹を名乗り、初舞台。昼の部は片岡仁左衛門、夜の部には尾上菊五郎も出演しての襲名口上に、客席からは大きな拍手が送られている。
昼の部(11時開演)・夜の部(16時30分開演)は、それぞれ3本の上演。どれも見どころ満載なので、順を追って見ていこう。
まずは、腕の良い板前だが今ではスリに身を落としている正太郎に獅童、その幼馴染みでドジだが愛嬌のある牙次郎には尾上菊之助と、「歌舞伎座でがっぷり組んで芝居をさせていただくのは初めて」(獅童)というコンビによる『上州土産百両首』。名作『金色夜叉』でも知られる劇作家の川村花菱がオー・ヘンリーの小説「二十年後」を下敷きにして書いた、男同士の友情物語だ。2人の役どころはイメージと真逆といえそうだが、獅童は情に厚く男ぶりのいい正太郎を、菊之助は要領は悪いが一所懸命に正太郎を慕う牙次郎を好演。正太郎のスリの兄貴分・金的の与一の中村錦之助、正太郎が板前として働くことになる料亭の亭主宇兵衛の松本錦吾、岡っ引きとなった牙次郎の親分・隼の勘次の中村歌六と、人情も仁義も備えた男たちの佇まいも見どころ。味わい深いセリフの数々や、獅童と菊之助が客席を縫って歩く演出など、隅々まで楽しめる作品となっている。
続いては、華やかな舞踊『義経千本桜 時鳥花有里』。源義経(中村又五郎)と家臣の鷲尾三郎(市川染五郎)が都落ちする道中で、白拍子(片岡孝太郎、中村米吉、中村児太郎、尾上左近)と傀儡師(中村種之助)に出会う。かれらは旅の慰めにと芸を披露するが、その正体は……。義経主従の品格、傀儡師の滑稽み、白拍子たちの美しさと、多彩な踊りが魅力の演目だ。
昼の部の最後は、六代目中村時蔵襲名披露狂言『妹背山婦女庭訓(いもせやまおんなていきん) 三笠山御殿』にて、新時蔵が“女方の大役”として知られるお三輪を初役で勤める。
杉酒屋娘お三輪(時蔵)が、恋する烏帽子折求女(実は藤原淡海/萬壽)の裾に付けた苧環(おだまき)の糸をたどってやってくると、そこは権勢を誇る蘇我入鹿の御殿。途方に暮れるお三輪が、娘のおひろ(梅枝)の手を引いて通りかかった豆腐買おむら(仁左衛門)に尋ねると、求女は入鹿の妹・橘姫(中村七之助)と祝言を挙げるとのこと。さらに、橘姫の恋敵と気づいた官女たちにもてあそばれ、御殿への侵入を阻まれるお三輪。ついに“疑着の相”(すさまじい嫉妬を抱いた者の顔に表れるという悪相)となったお三輪の前に、漁師鱶七(実は金輪五郎今国/尾上松緑)が立ちはだかり……。
若手ながら品格ある古風な香りを漂わせる女方として、これまでも多くの演目で成果を示してきた時蔵。お三輪も冒頭のいじらしい様子から終盤の“疑着の相”まで、美しい所作と表情、厚みのある芝居で、観る者をグイグイと引き込んでゆく。令和の世にあって、歌舞伎の本格を備えている時蔵は貴重な存在だ。劇中口上の仁左衛門の言葉通り、大名跡を襲名して今後ますますの活躍を期待しているのは、歌舞伎ファン共通の想いだろう。
初舞台の新梅枝、陽喜、夏幹のほか、獅童は初役で名作に挑む
そして夜の部は、花形(若手俳優)が顔を揃える『南総里見八犬伝』から。おなじみ「八犬士」に中村歌昇、坂東巳之助、中村種之助、中村米吉、中村児太郎、中村橋之助、市川染五郎、尾上左近が扮し、「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の玉を掲げるシーンはワクワクする華やかさ。次世代を担う人気俳優たちだけに、ひと場面だけではもったいないと思ってしまったほどだ。
続いては、初代中村萬壽襲名披露狂言・五代目中村梅枝初舞台の『山姥』。山姥の萬壽、山樵峯蔵(実は三田の仕)の中村芝翫、源頼光の獅童が見守る中、怪童丸(後に坂田金時)の新梅枝、渡辺綱役の陽喜、卜部季武役の夏幹の3人が初舞台を勤めている。「山めぐり」を踊る新萬壽のしみじみとした味わいと、元気いっぱいに演じて立廻りまで見せる新梅枝との対比に、脈々と受け継がれてきた歌舞伎の歴史を感じる舞台。幼いながらしっかりと見得をする陽喜と夏幹の様子にも、場内の熱気が一段と高まった。劇中口上では、怪童丸に黄金の太刀を与える藤原兼冬役の菊五郎が、披露の役目を担い盛り上げる。
夜の部の3本目は、生世話物の人気作『新皿屋舗月雨暈 魚屋宗五郎』。気のいい魚屋の宗五郎(獅童)が、旗本の屋敷へ奉公に出した妹が手打ちにされたことを知り、禁酒の誓いを破ったことから起きた顛末を描く。今回が初役となる獅童は庶民の怒りと悲しみをにじませつつ、杯を重ねて次第に酩酊する場面ではコミカルさと人間の弱さを重ねて表現。宗五郎を取り囲む女房おはま・七之助、父太兵衛・河原崎権十郎、小奴三吉・中村萬太郎の温かさ。“殿様”磯部主計之助役の中村隼人の説得力も印象に残る。陽喜と夏幹は酒樽を届けにくる酒屋丁稚与吉と長吉に扮しての出演。「灘の生一本ですから、よぉく効きますよ」のセリフもはっきりと聞こえ、客席からは笑いと拍手が沸き起こっていた。
取材・文/藤野さくら
写真提供:(C)松竹株式会社
<公演情報>
六月大歌舞伎
公演期間:2024年6月1日(土)~24日(月)
会場:歌舞伎座
チケット情報:
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2451221

