細野晴臣が語る、『HOCHONO HOUSE』完成後の新モード「音楽の中身が問われるようになる」
音楽
ニュース
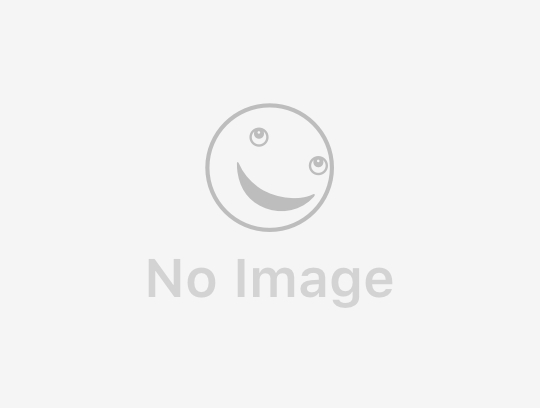
音楽活動50周年を迎えた細野晴臣が3月6日、ニューアルバム『HOCHONO HOUSE』(ホチョノハウス)をリリースする。1973年に発表されたソロ1stアルバム『HOSONO HOUSE』を細野自らがリアレンジ、新録した本作。前回のインタビュー(細野晴臣が語る、『HOSONO HOUSE』リメイクとサウンドの大変革「まだまだすごい音がある」)でも語られていたように、サウンドメイク、エンジニアリングを含め、大きな変化を実感できる作品だが、本人は「このアルバムはまだプロセス」だと語る。新たなターニングポイントとなるであろう本作『HOCHONO HOUSE』をフックにしながら、現在の細野のモードに迫った。(森朋之)
作家性を維持しなくちゃいけない
ーー『HOSONO HOUSE』のリメイクアルバム『HOCHONO HOUSE』が完成しました。まずこのタイトルですが、先日の中野サンプラザ公演で「あまりにも深刻に作っていたから、笑ってもらえるようなタイトルにしたかった」と話していましたね。
細野晴臣(以下、細野):そうなんですよ。自分をあざけ笑うというのかな。「何をそんなに深刻になってるんだよ」という。それは客観性でもあるんです。昔からひとりで妄想のなかで音楽を作っていたから、「独りよがりだ」と言われるだろうなという恐れをいつも感じていて。それに対する予防でもあるんですよ、客観性は。作ってるときはそうじゃないんですけどね。本当に独りよがりに作っているし、のめり込んでいますから。ミックスの段階、曲を整えるときに、そういう気持ちが湧いてくるんですよ。社会性が出てくると言ってもいいかもしれないけど、あまりにも標準から飛び出さないように気を付けようと。
ーー今回もミックス、マスタリングまで細野さんが手がけてますからね。
細野:ええ。いつも言うんだけど、男女の恋愛と結婚に似ているんです。曲を作っている最中は恋愛状態で、気持ち良ければいいっていう(笑)。曲ができるというのは、結婚して子供が生まれるようなもので、ちゃんと育てて、教育して、世に出さなくちゃいけない。それがミックスやマスタリングなんだけど、とにかく大変なんですよ。しかも1曲だけではなくて、10曲くらいありますからね。
ーーそれが“標準から飛び出さないようにする”ということなんですね。
細野:そうです。レコードの時代であれば、針飛びしなように作らなくちゃいけなかったし。以前はエンジニアにしかできない仕事だったんだけど、いまはそれをミュージシャンがやり始めた時代ですよね。もちろん、枠はあるんですよ。ポップスの枠のなかで、いかにベストを尽くすかというせめぎ合いなので。
ーー今回の『HOCHONO HOUSE』は、サウンドメイクの大変革のなかで制作された作品ですし、ミックスやマスタリングもいつも以上に難しかったのでは?
細野:そこは自分では評価できないというか、まだプロセスの途中なんです。完全にシステムが変わっているわけではなくて、ある部分は古いままで、ある部分は新しい機材を使っているので。もどかしさを抱えたまま制作していたし、難しいだけにおもしろいというか。まあ、苦労はしましたけどね。
ーー音質を決めるうえで、何か基準のようなものはあったんですか?
細野:これもねえ、難しい話なんですよ(笑)。基準はあってないようなもので、結局は主観に頼るしかないんです。もともと理論的にやってないですからね。「○ヘルツの周波数帯が」ということではなくてーーエンジニアはそういうやり方ですけどーー僕は耳だけで判断しているので。スピーカーやヘッドホンなど、いろいろなアウトプットの方法を試して、少しずつ整えて。部屋鳴りもありますからね。ここ(取材場所のプライベートスタジオ)はちゃんとしたスタジオではなくて、音がたまっちゃう場所もあるんですよ。いま僕が座ってる場所もそうで、ふだんは聞こえない低音が聞こえたりして。今回は全部ここで作りましたけど、課題はたくさんありますね。いまのシステムのなかでは最善を尽くしたけど、どうなんだろうな……。まあ、それは自分の問題なので、アルバムを聴く人には言いたくないけど(笑)。
ーー前回のインタビューでも、「音が変化するプロセスが出るアルバムになる」という話をされてましたよね。
細野:僕が聴けばそう感じる、ということですね。初めてアルバムを聴く人はそんなこと思わないだろうし。前回のときは、熱情にかられていたんです。その熱はいまもあるんだけど、去年は“グローバルサウンド”と自分で呼んでいた音にすごく興味があったし、テイラー・スウィフトの新作なども素晴らしい音だったしね。その音はまだ僕には作れないけど、作れたところで、ああいう音楽はやれないんです。やっぱり自分は作家性を維持しなくちゃいけない立場だから。グローバルスタンダードは存在するし、取り入れたいところもいっぱいあるけど、そのなかに入っていくわけにはいかないので。そういう気持ちで作ってましたね、『HOCHONO HOUSE』は。だから、やっぱり中間なんです。いままでの音とは違うけど、まだ途中。いまはそれだけでいいのかなと。
ーー「薔薇と野獣」が先行配信されましたが、その後、さらに制作のシステムは変わったんですか?
細野:いや、そうでもないんです(笑)。ほら(と機材を指さす)、見た目もそんなに変わってないでしょ。じつはね、新しいシステムも揃っていて、奥の部屋に置いてあるんです。なので、今回のアルバムでは使ってないんですよ。
ーーえ、そうなんですか?!
細野:ええ(笑)。新しいシステムは、ここじゃなくて、自分の家に置こうと思ってるんですよ。今回はここで作ったけど、ちょっと不便なところもあって。ここで作った曲をCDに入れて、車のなかでチェックするんですよ。「ここを直したい」と思っても、戻るのが面倒だから、翌日になっちゃう。家でやれば、すぐ直せますからね。それをやるのは、次の作品からなんだけど(笑)。
ーーやっぱり過渡期なんですね、いまは。細野さんのキャリアを振り返ってみても、「あの時期に大きく音が変わった」というタイミングが何度かあって。
細野:ソロアルバムを作るときは、変わり目が多い気がするな。たとえば『トロピカル・ダンディー』(1975年)もそう。レコードのA面とB面ではぜんぜん違うっていう、大変化の時期だったから。そういうことがときどきあるんだけど、この年齢になって、起きるとは思わなかった。楽しいけど、年齢的にフィジカルはつらいよね(笑)。
ーー制作にのめりこまないと、作品はできないですからね。
細野:うん。あと、時間との戦いもあったんです。ずっと先延ばしにしていて、「もうこれ以上は遅らせられない」という切羽詰まった状況に自分を追い込んじゃったから。
ーー細野さんにも締め切りはある、と。
細野:もちろんですよ。締め切りがないと、たぶん、今もずっとやってますよ(笑)。
今は“音のおもしろさ”が大事
ーー『HOCHONO HOUSE』の曲順は『HOSONO HOUSE』の逆になってますが、これはどうしてですか?
細野:『HOSONO HOUSE』は、「ろっか・ばい・まい・べいびい」という曲から始まるんだけど、今回はそこから始めたくなかったんです。その理由はよくわからないけど、気持ちが不安定だったし、同じにはしたくないなと。もうひとつは(『HOSONO HOUSE』の最後に収録されている)「相合傘」ですね。オリジナルには数小節のインストが入ってるんだけど、どうしてそうなったかというと、はっぴいえんどの最後のアルバム(『HAPPY END』1973年)に入れちゃったからなんですよ、曲が足りなくて。本当はソロアルバムに入れたかったんだけどなという名残惜しさもあるし、今回のアルバムは、その続きから始めようと思って。「『相合傘』という曲の続きはこうだったんだよ」ということですね。
ーーはっぴいえんどの『HAPPY END』と細野さんの『HOSONO HOUSE』はリリースの時期が3カ月くらいしか違わないですからね。かなり交差しているというか。
細野:そうなんですよ。そのなかで曲の算段をしなくちゃいけなかったから。「相合傘」は気に入ってたしね、自分でも。
ーーなるほど。リスナーにとっては“『HOSONO HOUSE』の楽曲がどうアレンジされているんだろう?”というのが一番気になるところだと思いますが、たとえば「恋は桃色」の場合はどうでした?
細野:これはねえ、いろいろ考えたんですよ。とにかく、カントリー色は出したくなかったんです。「ひとりで打ち込みで作る」って言いふらしちゃったのもあるし、この曲は打ち込みでいけるかなと。まずシーケンサーみたいな音を入れて、そこからアレンジしましたね。「住所不定無職低収入」もそういう感じですね。ただ、すべてを打ち込みでやっているわけではなくて、生ギターだけでアレンジできそうだったら、そっちを優先していて。そこは曲によるというか、もともと『HOSONO HOUSE』自体がそういうアルバムですから。「薔薇と野獣」と「恋は桃色」ではずいぶん違う世界だし、統一感を持たせなくてもいいのかなと。
ーー「パーティ」はライブ音源が収録されています。
細野:あれは1976年くらいの音源なんです。たまたま見つかった音源なんだけど、いまとあまり声が変わってないんですよ。当時は20代だったのに、おっさんみたいな声で(笑)。録音状態があまり良くなかったから、エディットしてますけど、ほぼそのままですよ。「住所不定無職低収入」も。デモテープをもとにしてアレンジしたんです。デモではひとりでギター弾きながら英語で歌ってたんだけど、『HOSONO HOUSE』はバンドでアレンジしてるから、デモとは雰囲気が変わっちゃうんですよね。「ひとりでやればこうなる」というのが、今回のバージョンですね。
ーー「冬越え」もギターと歌を中心にしたアレンジ。「終わりの季節」はインストバージョンです。
細野:『HOSONO HOUSE』のバージョンはバンドサウンドなんだけど、ライブではギター1本でやることが多くて、それに近いアレンジですね。新しい機材で打ち込みした曲もあるし、昔のアイデアを引用している部分もあって。行ったり来たりしながら作ってる感じですね、こうしてみると。「終わりの季節」は、メロディをとりあえずギターで入れてたら、それが気に入っちゃって、そのまま入れようと。最初から計画していたわけではなくて、行きあたりばったりなんですよ。1曲1曲、「どうやってアレンジしよう?」と難題を突き付けられながら制作していたいし、やってみないとわからなかったので。「終わりの季節」は歌詞が好きな人も多いんだけど、インストをカラオケだと思って歌ってもらえればいいかな(笑)。
ーー「CHOO CHOO ガタゴト・アメリカ編」「僕は一寸・夏編」などは歌詞も変わってますね。
細野:そうなんです。「CHOO CHOO ガタゴト」のオリジナルには〈こだま ひかり〉という歌詞があるんだけど、ちょっと古すぎるでしょ(笑)。いまやリニアの時代だし、アメリカ公演もあるから、〈大阪あたりで乗りかえ〉を〈シカゴ〜〉にしてみたり。まあ、ご当地ソングみたいなもんだよね。大阪で演奏するときは、〈大阪〉と歌いますよ(笑)。
ーー(笑)。“この歌詞、いまはちょっと歌えないな”ということも?
細野:ありますよ、それは。「僕は一寸」は大幅に歌詞を変えたんだけど、原曲は当時の風景のなかで書いているし、いまの気持ちとは違うので。『HOCHONO HOUSE』は去年の暑い夏の最中に作り始めたから、“夏編”にしたんです。何て言うのかな。松本隆と違って、自分の心情を歌詞にしているのでーーまあ、松本くんもそうかもしれないけど(笑)ーーそのときに感じたことを歌ったほうがいいんですよ。
ーー『HOSONO HOUSE』と改めて向き合うなかで、当時の心境を思い出す瞬間もありましたか?
細野:いやあ、それがぜんぜん理解できないんですよ。「若者の考えていることはわからん!」というか(笑)。音楽三昧だったのは確かだけど、アルバムに関しては、半分以上、参加してくれたミュージシャンに任せていたし。あとね、当時は制作にかける時間も少なかったし、お金もかけられなかったんですよ。エンジニアの吉野金次さんの機材を狭山の家に運んで、「とにかくこのアルバムを完成させよう」という気持ちだけで。だから、アレンジも生煮えっていうのかな。後先のことも考えてなかったし、「どうせ、すぐに消えちゃうんだろうな」っていう。こんなに長く聴かれるなんて、まったく思ってなかったです。
ーー当然、アメリカの音楽からの影響も色濃くあって。
細野:もちろん。The Bandの「Music From Big Pink」なんて「奇跡のような作品だ」と思って崇拝していたし、いろいろなアーティストからたくさんの刺激を受けていたので。いまとなっては「あの時代じゃないと生まれなかった音楽だったんだな」と思うけど、憧れは非常に強かったです。ファッションもマネしてましたからね。ロングヘア、髭、ダンガリーっていう。(アメリカには)いまはぜんぜん憧れないですけどね(笑)。誰しも同じだと思うけど。
ーー確かにそうですね。
細野:あの時代の人たちが、僕を含めて、どんどん高齢になっていて。そのことに対しては、ちょっと寂しいですけどね。ライ・クーダーの新作も聴きたいし、ドクター・ジョンはどうしてるかな? とかね。音楽だけじゃなくて、映画にしても、20世紀はどんどん消えていきますよ。そう思うと、いま、『HOCHONO HOUSE』みたいなアルバムを作れるのはラッキーですよね。このアルバムのアイデアがなければ、この数年やっていたことを続けて、フェイドアウトしようと思っていたので。真っ直ぐ行くはずだったのに、急にカーブして、見知らぬ場所に来ちゃった(笑)。
ーー“この数年やってきたこと”というのは、つまり、20世紀の音楽を再解釈して現代に伝える活動ということですよね?
細野:そうですね。それはこれからも続けたいと思っているし、この間から話しているように、音響の次元が変わっていることにも興味があって。そのふたつをどうつなぐか? という興味もあるしね。いまはね、いろんな音楽がおもしろいんですよ。打ち込みだけじゃなくて、本当におもしろい音楽が多い。ブライアン・フェリーの新作(『Bitter-Sweet』)も良かったな。古くさいジャズやカントリーをやってるんだけど、音がおもしろいんですよ。そういう作品を聴くと「やっぱり今は“音のおもしろさ”が大事なんだな」と。
ーー前回のインタビューに大きな反響があったのも、世界的に音質が変化していることを無意識のうちに感じていたリスナーが多いからだと思います。特に“バーチャルな低音”という指摘に反応してる人が多くて。
細野:あれもね、どうしてそうなってるのかわからないんだよね。音の変化はみんなが認知しているんだけど、おそらく音のアルゴリズムみたいなものが存在していて、それが表に出ていない。たぶん、意図的なものではなくて、自然現象に近い現象じゃないかと思いますね。理由がわからないまま、みんながそっちの流れに近づいていますから。音楽に限らず、レコーディングに関わっている人は。
ーー日本のポップスも、ここから大きく音が変わりそうですね。
細野:うん。映像にたとえると、1970年代後半に『STAR WARS』や『未知との遭遇』が公開されて、SFX技術の高さにみんなビックリしたんですよ。日本の映像関係者も「この技術にはかなわない」「これは日本ではできない」と思ってたんだけど、いまはテクノロジーの発達によって、その技術を共有している。そうなると問題なのは物語の作り込み、つまり「脚本が大事だ」ということになるんですよ。音楽もまったく同じですよね。いまは新しいサウンドが出てきて、「これはどうなってるんだろう?」と、音のおもしろさだけに興味が向いてる時代だなと。次は音楽の中身が問われるようになると思いますね。
ーーやはり過渡期なんですね、いまは。そう考えると、『HOCHONO HOUSE』も2019年だから生まれた作品だなと。
細野:そうなんですよ。確実に言えるのは、去年とはまったく違う音だということ。“2019年前半の音”ですね、『HOCHONO HOUSE』は。
ーー5月後半にはアメリカ公演もありますね。
細野:ニューヨークとロサンゼルスで3公演やって、その後、ひとつイベントに出て。それで今年はおしまい、何もないんですよ(笑)。その後はやっと落ち着いて、新しい機材で何か作り始めるんじゃないですかね。どんなものを作るかはわからないけど、僕自身も非常に楽しみです。
(取材・文=森朋之)
■リリース情報
『HOCHONO HOUSE』
発売:2019年3月6日(水)
価格:¥3,000(税抜)
<収録曲>
1. 相合傘~Broken Radio Version~
2. 薔薇と野獣
3. 恋は桃色
4. 住所不定無職低収入
5. 福は内 鬼は外
6. パーティー
7. 冬越え
8. 終りの季節
9. CHOO CHOO ガタゴト・アメリカ編
10. 僕は一寸・夏編
11. ろっかばいまいべいびい
■ライブ情報
『Circle’19』
5月19日(日)福岡・海の中道海浜公園
『Haruomi Hosono Concerts In Us』
5月28日(火)Gramercy Theatre, New York, NY
5月29日(水)Gramercy Theatre, New York, NY
6月3日(月)Mayan Theater, Los Angeles, CA

