ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」総合監修は日比野克彦
ステージ
ニュース
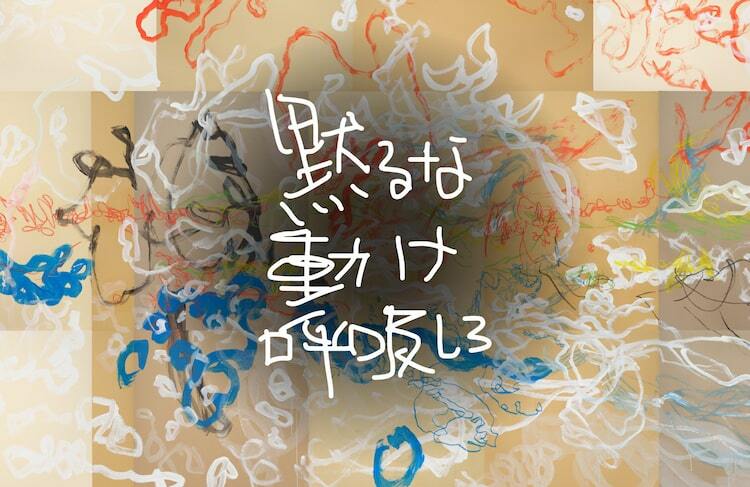
TOKYO FORWARD 2025 文化プログラム ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」キービジュアル
TOKYO FORWARD 2025 文化プログラム ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」が、来年11月29日に東京・東京文化会館 大ホールにて上演される。
これは、「東京2025世界陸上」と「デフリンピック」が東京で開催される2025年に、「東京2020大会」のレガシーを継承・発展させて展開する“多様な参加者とつどい・つながり・つくりあげる”3つのアートプロジェクト「TOKYO FORWARD 2025 文化プログラム」の一環として行われる公演。本公演では、“ろう者と聴者、それぞれ言語、生活環境の異なる表現者たちが出会い、前代未聞の舞台制作へと挑む”ことを目指す。
総合監修を手がける日比野克彦は、上演に向けて、「ステージは一回公演ですけども、我々のビジョンとしては世界中どの地域にも、ろう者も聴者もいますから、国内にとどまらず海外でも、中学生や高校生が、『うちの地域でもそれを再演したい!』と言っていただけるように、またろう学校の子どもたちと聴者の子どもたちとの交流プログラムとしてやってみたいなど、今後再演性のあるものに仕立てていきたいと思ってます。そういったものにするべく、今みんなで頑張っているところです」と意気込みを述べた。
日比野のコメント全文と、構成・演出の牧原依里、演出・出演の島地保武、ドラマトゥルクの雫境と長島確によるコメントは以下の通り。詳細は今後の発表を待とう。
日比野克彦コメント
僕は、7年前に初めて「ろう文化」というものがあると牧原さんから聞いて、何それ?って知るところから始まりました。
世の中に障害者やハンディ等の言い方があり、オリンピックにもパラリンピックがありますが、そういうものではなくて、例えばヨーロッパ的な文化やアジア的な文化など、様々な地域文化があるけれども、それと同じように「ろう文化」というのがあるということを認識しまして、ぜひ「TOKYO FORWARD 2025 文化プログラム」の中で発信していきたいと思い、スタートしました。
いまミーティングを重ねている真っ最中なんですけれども、本当に気づきが多いミーティングばかりです。
例えば、単純に台本は必要だよね、音響があるよねという前提でいると、これはやはり聴者の世界のデフォルトなんです。
ろう者からしてみると台本や声を出して本読みをしましょうということが適わない、音響も振動はあるけども音って何?というところから始まるので、そこでじゃあ、どう表現していくのか等、根本的な部分から話し合っています。
文化というものは、歴史が証明するように、違う価値観を持った人が川のほとりに集まってきて、そこから文化や文明というのもが生まれてきます。だから、違う価値観を持っているということは、これはお互いにとっても次への気づきを教えてくれる、示唆してくれる大きな大きな宝物なんです。なので、これがただ単なるエンターテインメントや表現のプログラムではなくて、本当に今社会が求めている多様な社会を築いていこうという時にエポックになるような、そんな舞台というか、観客含めて体験できる時空間というものにしていきたいなと思ってます。
ステージは一回公演ですけども、我々のビジョンとしては世界中どの地域にも、ろう者も聴者もいますから、国内にとどまらず海外でも、中学生や高校生が、「うちの地域でもそれを再演したい!」と言っていただけるように、またろう学校の子どもたちと聴者の子どもたちとの交流プログラムとしてやってみたいなど、今後再演性のあるものに仕立てていきたいと思ってます。
そういったものにするべく、今みんなで頑張っているところです。
楽しみにしていてください。
牧原依里コメント
作品の物語や内容を考える「構成」、そしてろう者を中心に「演出」をやらせていただくことになりました。
今回の作品は今までにない初めての試みになります。ろう者にとっての「オンガク(ろう者の音楽)」とはなんなのか、ろうコミュニティやろう者の今までの歴史の中で培ってきた身体や手話から自然に溢れるオンガクのようなものとはなんなのかを議論し、刺激を受けている日々です。また聴者とも意見を交わしていくことで、2つの世界の相違点、共通点などといった発見があり、音楽/オンガクの本質や人間について考えさせられています。
この作品が、人間の芸術をさらに発展していくための後押しになるのではないかと期待しています。
聴者の世界とろう者の世界が共生するとはどういうことなのか。
ぜひみなさんに舞台をご覧いただき、一緒に考えていけたら嬉しく思います。
島地保武コメント
今回のプロジェクトは一言で言うと、かなり一筋縄ではいかないだろうと今から思っています。
自分にとって当たり前だったことがどんどん覆されていくような感じがして。それは怖いことですけど、同時に楽しみでもあります。
僕はダンサーで、ダンスはコミュニケーションなので、そのコミュニケーションの幅が、どう変容していくのかに非常に興味があります。
何よりもやはり人と人との関わり合いなので、ドキュメンタリーじゃないですけど、僕が接していくことによって、そのこと自体がストーリーになっていけば良いなと考えています。
また出演と同時に演出もしていかなければいけないのですが、心がけていることは“嘘つかない”そして“無理をしない”ですね。
我慢はしますけど、しっかりお互い伝えられるという関係を築いていくのが、大事かなと。
この作品は舞台上でも更新されていくような、その場、その時のコミュニケーションというのが、見どころになるのではないかなと思います。
そして、この作品をご覧になる方々にとっても、舞台を観て終わりではない、自分にとっても“よい作品ができた、やった、終わり。”ではない、次へのきっかけになるような作品になったら嬉しいです。
雫境コメント
私は、ドラマトゥルクという演出家に助言やサポートをする役割を担います。
この作品で表現したいことですが、昔からろう者の手話には音楽のような動きがあります。それらは手話や手型、非言語的表現などで、時々見ることができます。そのような動きの中に、私たちは「オンガク(ろう者視点での音楽)」というものを感じることができます。
舞台では「オンガク」をどのように表現し、広めていくことができるのかを考えたいと思っています。
今はろう者だけで集まって手話表現の中に見られるオンガク的な表現、舞台上での新しい表現とはどういうものがあるのかなど話しています。公演当日はオンガクと聴者の音楽の協働について、一緒に考え新しい表現をみんなに広めていけたらと思います。
ぜひ劇場にお越しください。
長島確コメント
ドラマトゥルクというのは、いろんな立場の人が集団創作をしていく中で、いろいろ交通整理をしたり、文脈を作ったり、リサーチをしたりして、作っていくプロセスを助けていくような仕事です。
今回もまさにそういう形で入っていますが、異言語、異文化のとても重要なコラボレーションだと理解しています。
なので自分自身も今まで知らなかったこと、全然気がついてなかったことが山のように出てきていて、ものすごく勉強をしながらいろいろなことを進めています。考えさせられることも多く、その分アウトプットが全体として豊かになると思いますし、まだ今の時点でお名前が出ていない方たちも含めて、とてもよいチームが出来上がりつつあるので、ぜひ楽しみにしてください。
ゴシャッとしたすごいものができると思います。
%play_2366_v1%※初出時、公演日程に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。


