箏奏者LEO「自分自身の音楽を表現する挑戦」 アルバム『microcosm』リリース記念ライブ開催!
クラシック
インタビュー
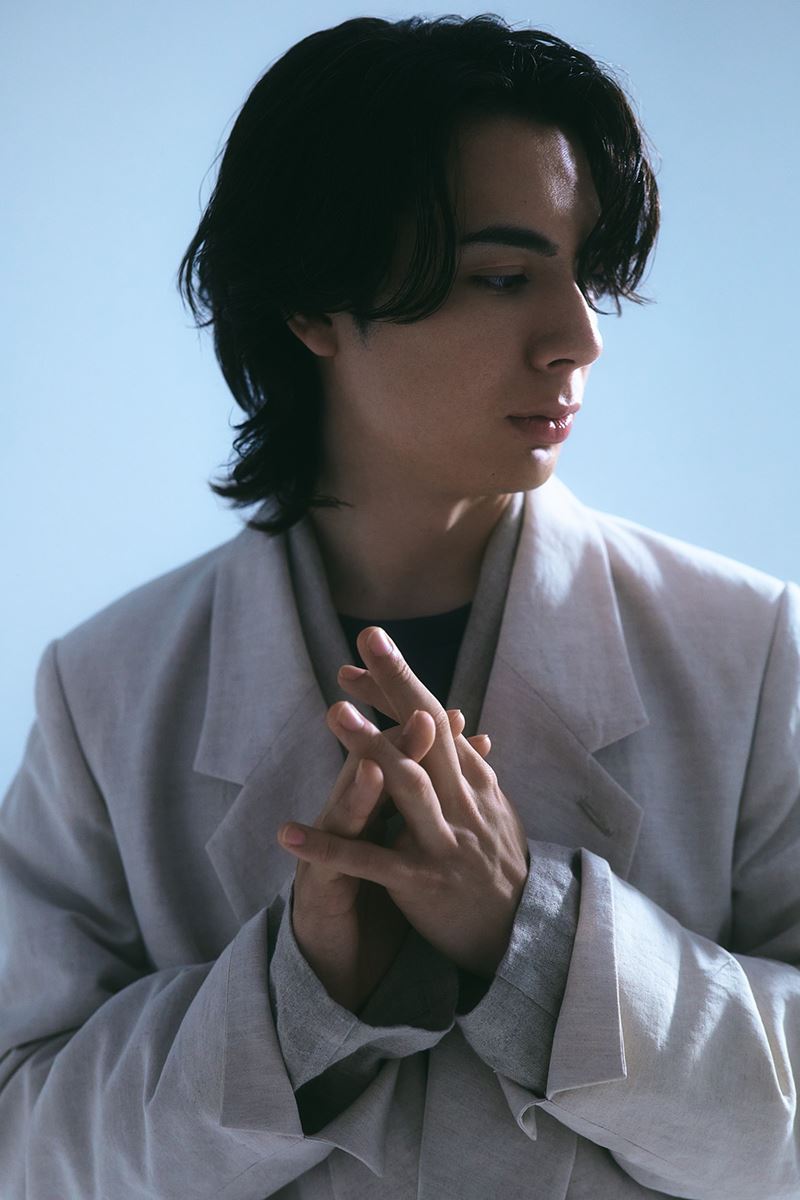
LEO
続きを読むフォトギャラリー(3件)
すべて見る箏奏者・LEOが7作目となるアルバム『microcosm(マイクロコズム)』をリリースした。これまで「箏」という楽器を表現の中心に据えてきた彼が、今回は自らその枠を外し、自身の音楽観を前面に押し出した意欲作だ。ジャズやエレクトロ、ポップスの要素を取り入れ、多彩なアーティストとのコラボレーションで生まれた“音の小宇宙”。その背景にある想いと、11月に控えるリリース記念ライブへの意気込みを聞いた。
――アルバム『microcosm』は“小宇宙”という意味です。音楽のジャンルにとらわれない、和楽器のイメージを覆した実験的な作品になっています。
LEO これまでのアルバムは常に箏を中心に据えて、「どうしたら箏という楽器が輝くか」を考え、コラボする楽器も箏との相性の良さをメインに選んでいました。でもそれは逆に表現の幅を狭めているのではないか……と思うところがあり、“箏が中心”の考えを一度手放したんです。自分が音楽ファンとして純粋に好きなアーティストに声をかけ、フラットな気持ちで制作しました。結果的に“箏奏者”というより、“自分自身が発信源”の作品になったと思います。
――LEOさんにとって大きなターニングポイントですね。
LEO 僕は19歳でメジャーデビューしたのですが、応援してくださる方々の「箏の可能性を広げてほしい」という期待に応えていきたいと思い続けていた部分がありました。でも今回は、自分の奏でたい音楽を忖度なしに届けることができた。ある意味、『microcosm』は自分にとって新たなファーストアルバムだと言えるかもしれません。
――アルバム制作ではどんな挑戦がありましたか。
LEO 一番大変だったのは、エレクトロニクスと和楽器の融合ですね。テクノポップユニットの「LAUSBUB(ラウスバブ)」との制作では、彼女たちが楽譜を使わずにPCで音楽を作るので、僕も新しい言語を学ぶような気持ちで取り組みました。また、今回は録音後の音の編集やエフェクトをつける作業にも参加したので、最後まで自分の音楽の面倒を見てあげられたなと思います。
――伝統楽器の箏をエレクトロニクスと組み合わせる。そこにはどんな魅力があるのでしょう。
LEO エレクトロニクスでは、余韻を持たせる“静”と、感情をのせて盛り上げる“動”の振り幅が一気に広がります。箏だけだと“0から10”の音量しか出せなくても、電子音を加えることで“0から30”までの音量が出せる。その振り幅を自在に操ることができるのが魅力です。例えば、シンセサイザーの爆音で盛り上げた後に、音がパッと消えて、箏の「ポンッ」という一音が静かに響く。すると聴き手はその一音に強烈に集中する。そんなドラマチックな演出もできるんです。
――新しい音楽表現のアプローチですね。
一人で一つの楽器を弾いているというより、いろんな音を同時に扱える“指揮者”のような感覚です。表現の幅がすごく広がって、単純に楽しい。今の時代にも合った音楽だと思っていますし、若い人にも届いてほしいです。

――とはいえ、PCでカチッと作り上げた音をライブで再現するには苦労もあるのでは?
LEO そうなんです。ライブは同期音源(PCで作った音)を流しながら演奏するので、即興で「ここの音をもっと伸ばしたい」と思っても、その場では変えられない不便さもあります。ただ一方で、絶対に生音だけでは出せない表現も可能になる。良い部分と難しい部分が共存しています。11月のライブでは、予定調和と即興がせめぎ合うような、ライブならではの熱量を届けたいです。
――“バンドを組んだ”感覚ともおっしゃっていました。
LEO 個性豊かなミュージシャンたちと一緒に音を作っているので、僕の箏が中心というより、バンドの一員になっている感じです。アルバムタイトル『microcosm(小宇宙)』のように、一人ひとりのアーティストとのコラボが、それぞれ違う小さな宇宙を生み出していく。やがてそれが銀河のようにつながっていくイメージです。ライブでは、その小宇宙がさらに広がっていく様子を感じてもらえるはずです。
――11月のライブは「新宿FACE」で開催されますが、邦楽やクラシックのパフォーマンスは数少ないですよね。
LEO 普段、箏やクラシックに馴染みのない、ポップスやテクノを聴くような人たちにも足を運んでいただきたいと思って、あえて会場に選びました。ライブハウスやクラブに音楽を聴きに行くようなテンションで来ても楽しめるライブにしたいなと。
――かなり斬新ですね。
LEO 新しいことばかりですが、これまでの積み重ねがあってこの表現方法に辿り着いているので、僕のなかでは一貫したストーリーがあります。今回のライブでは従来の伝統音楽・古典やクラシックの音楽観を背景に持ちつつ、今新たに取り組んでいるエレクトロ的なアプローチと融合させ、進化した姿をお見せしたいです。
――箏との向き合い方に変化はありましたか。
LEO 自分オリジナルの世界観を作品にできたことで、一つの壁を乗り越えたというか、自信がつきました。心の余裕が生まれて、最近は純邦楽にも改めて取り組んでいます。伝統と挑戦の両方を延ばしていけたらいいなと思っていて、音楽活動がすごく充実しています。
――最後に、ライブに来るお客さまにメッセージをお願いします。
LEO ライブに参加してくださるゲストミュージシャンたちのスケジュールが合うことが奇跡的で、この組み合わせでのライブは二度とないかもしれません。これまで応援してくださっていた方も、初めて僕、そして箏のライブを体験される方も、必ず新しい発見があるはずです。ぜひ、この特別な一夜を見逃さないでください。
取材・文=北島あや
<公演情報>
「LEO-microcosm-」
日程:11月5日(日)
会場:東京・新宿FACE
チケット情報:
https://w.pia.jp/t/leo-microcosm/

LEO 『microcosm』
日本コロムビア COCB-54380 ¥3,500(税込)
★高音質CD「UHQCD」採用
[収録曲]
01.Cotton Candy
02.Vanishing Metro
03.ぽたぽた
04.moments within
05.Night Scape
06.Microcosm Session
07.GRID // ON
08.moments between
09.音の頃 w/ LAUSBUB
10.Rays of Light
11.落葉
【LEO プロフィール】
9歳より箏を始め、カーティス・パターソン、沢井一恵の両氏に師事。16歳でくまもと全国邦楽コンクールにて史上最年少・最優秀賞・文部科学大臣賞受賞。一躍脚光を浴び、その後東京藝術大学に入学。「情熱大陸」「題名のない音楽会」「徹子の部屋」など多くのメディアに出演。セバスティアン・ヴァイグレ、井上道義、沖澤のどか、東京フィルハーモニー交響楽団、京都市交響楽団などと共演。鈴木優人指揮・読売日本交響楽団との共演で、藤倉大委嘱新作・箏協奏曲を2021年に世界初演。2024年にはヨーロッパに招聘され同作品をウィーン・コンツェルトハウス、スロヴァキア・フィルハーモニーでも好演を果たしている。箏奏者として初めてブルーノート東京や、SUMMER SONICにも異例の出演を果たすなど、箏の新たな可能性を広げる活動に注目と期待が寄せられている。出光音楽賞、神奈川文化賞未来賞、横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。
【ゲストミュージシャン・プロフィール】
網守将平(Shohei Amimori):Synth
東京藝術大学音楽学部作曲科卒業。同大学院音楽研究科修士課程修了。2013年日本音楽コンクール作曲部門1位及び明治安田賞受賞。大貫妙子、原田知世、Daokoなど多くのアーティストの作編曲を担当。映画『8番出口』のサウンドトラックや、NHK Eテレ『ムジカ・ピッコリーノ』の音楽監督を担当。23年には自身のキャリア初となるバンド・QUBITを結成。
大井一彌(Kazuya Oi):Dr
電子音楽と肉体性の融合を探求する新世代のドラマー。DATS、yahyelに所属し、アイナ・ジ・エンド、UA、AAAMYYY、odol、木村カエラ、GLIM SPANKY、THE SPELLBOUND、Dos Monos、YOASOBI他多数のアーティストのライブ&レコーディングに参加。アート展示やCM等への楽曲制作も行い、幅広いフィールドで活動している。
町田 匡(Tadashi Machida):Vn
ヴァイオリニスト。3歳よりヴァイオリンを始め、東京藝術大学を卒業、日本フィルハーモニー交響楽団に所属。近年ではtofubeats、パソコン音楽クラブ、in the blue shirt、MON/KU、ウ山あまね等多くのトラックメイカー/プロデューサーにストリングス提供を行うなど、クラシック音楽を軸足としポップスからクラブシーンに至るまで様々な音楽シーンを横断しながら活動を展開している。
中川裕貴(Yuki Nakagawa):Vc
関西を拠点に活動する音楽家/演奏家。チェロを独学で学び、そこから独自の作曲、演奏活動を行う。2022年よりgoat、YPYでも活動する音楽家・日野浩志郎とのDUOプロジェクト「KAKUHAN」をスタートさせ、以降、同ユニットではヨーロッパの主要な実験音楽フェスティバルに参加している。2025年には初となるソロアルバムをリリース予定。令和6年度京都市芸術文化特別奨励者。
フォトギャラリー(3件)
すべて見る
