マーヴィン・ゲイが歴史的名盤の後に目指したサウンドとは? 柳樂光隆の『You’re The Man』分析
音楽
ニュース
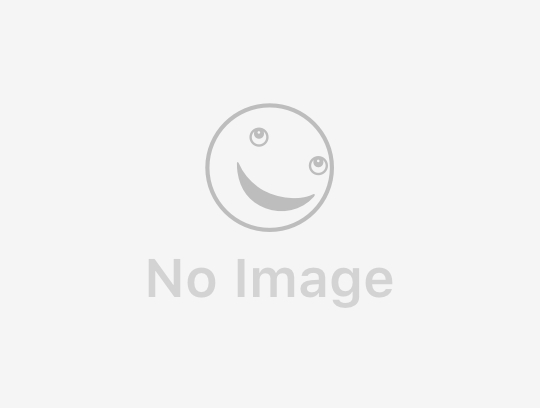
1972年にマーヴィン・ゲイがリリースする予定だった音源が『You’re The Man』という名前で陽の目を見ると言われて、気にならないリスナーはいないだろう。
マーヴィン・ゲイのディスコグラフィーで言うと、1971年に『What’s Going On』、1973年に『Let’s Get It On』をリリースしているので、音楽史に残る名盤2枚の間に発表されるはずだったもの、ということになるか。
そして、その内容があまりに素晴らしく、アルバムとして発表され広く届いていたら間違いなく人気曲になっていたであろう曲がいくつもあり、曲単位で言えばどれもこれもリリースされていてもおかしくないクオリティーだ。例えば、冒頭の2曲「You’re The Man」「The World is Rated X」だけでもかっこよすぎてびっくりしてしまったし、個人的にはこれだけのために買おうと思ったくらいだ。その後もバラエティに富んだアレンジの曲が続き、どれも凄まじいクオリティーばかり。とはいえ、そこでリリースされなかった理由がわかってくる。
曲は粒ぞろいなのだが、『What’s Going On』や『Let’s Get It On』で聴かれたようなアルバム一枚を通した世界観が見えてこない。冒頭のファンキーだったり、エッジーだったりする2曲があったと思ったら、ウィリー・ハッチが手掛けた楽曲群は『What’s Going On』以前=ニューソウル以前のモータウンのサウンドを思わせるポップなサウンドだったり、かと思えば、美しいバラードがあったりと、悪く言えばバラバラなのだ。繰り返すが、曲ごとのクオリティは申し分ない。「I’m Gonna Give You Respect」や「You’re That Special One」あたりと通じそうな、ジャクソン5『Third Album』やハニー・コーンの『Soulful Tapestry』などの作品が1970~71年なので時代と合わないわけでもない。ただ、マーヴィン・ゲイが当時やろうとしていた作品はもはやその手のポップソングではなくなっていて、『What’s Going On』以降の内省的でセクシーなサウンドとメッセージ性のあるサウンドを志向していたこともこのアルバムがお蔵入りになった原因としてあるだろう。『What’s Going On』と『Let’s Get It On』が地続きであることから逆算すると本作は「無し」だったのだろう。
ただ、マーヴィン・ゲイはその2作の間で1972年に映画のサウンドトラックとして『Trouble Man』をリリースしていて、これだけは同時期の作品と少し雰囲気が違う。彼らしい内省的な雰囲気があるものの、ブラックムービーのサントラであることも影響したのか、ギターのカッティングなどファンクの要素も多めでビートも重い。カーティス・メイフィールド『Super Fly』やロイ・エアーズ『Coffy』といったブラックムービーのサントラがそうであるように、インストゥルメンタルのジャズファンクで、この音楽性に関しては映画との兼ね合いもあるので必ずしもマーヴィン・ゲイだけで考えたわけではないと思うが、そんなサウンドもやっていたのは事実だ。前置きは長くなったが、冒頭の「You’re The Man」を聴くと、『Trouble Man』の時期で、そこに近いサウンドともいえるので、矛盾があるわけではない。ただ、そのファンクモードで作れる曲がこれだけだったのかもしれない。
とはいえ、ここに収められた「You’re The Man」の「Original Mono Single Version」「Alternate Version 2」、そして、2001年にリリースされた『Let Get it On』のデラックスエディションに収められた「Alternate Version 1」(※AppleMusicやSpotifyで聴けます)を聴き比べるととても面白い。「Original Mono Single Version」はファンキーなギターのカッティングとパーカッションが印象的なファンクだが、「Alternate Version 2」ではもっとギターもベースも自由に動き、空間も多めでジャズ的な即興の要素が聴こえてくる。例えば、1970年のダニー・ハサウェイ『Everything is Everything』収録の「The Ghetto」あたりを思わせるような自由さとスペースがあり、ニューソウルの中でもマーヴィン・ゲイが実践してきたこととは違う路線も試してはいたことがわかる。試行錯誤の末、最後にファンクにしてからシングルとしてリリースしてアルバムには未収録になったわけだが、この経緯はなかなか面白い。ちなみに最終バージョンがダントツでかっこいい。
そして、個人的には今回の目玉は「The World is Rated X」だと思っている。曲自体は『What’s Going On』に収録されている「Inner City Blues(Make Me Wanna Holler)」とかなり近く、そのリメイクのような部分もあるが、「The World is Rated X」ではテンポも上げて大胆なファンクになっている。ただ、この曲の最大の魅力はアレンジが異常に凝っていることにある。
前半部ではアコースティックのピアノを印象的に使っているが、いわゆるピアノ的に和音を乗せたり、ソロを弾いたりする役割で使うのではなく、パートとして使っていて、短いフレーズの繰り返しの使い方があまりに刺激的で気が利いている。かと思えば、後半からは全く異なるアレンジになり、ホーンやギターが使われ、即興の比率が高まってくる。そして、ストリングスも曲が進むにつれて、アレンジが変わってくる。まるで組曲のようなアレンジなのだ。スティーヴィー・ワンダーか、リロイ・ハトソンかというような作りに驚く。
バックバンドは即興性が高く、どんどん抽象的になっていき、マーヴィン・ゲイはどんどんエモーショナルになっていき、まるでアジテーションのような雰囲気になっていく。こんな暑苦しいマーヴィン・ゲイは他にない。1968年にキング牧師が暗殺され、再び公民権運動が盛り上がっていった時代で、ソウル的にはマーヴィン・ゲイやスティーヴィー・ワンダー、カーティス・メイフィールドらによりいわゆるニューソウルが台頭し、ジャズの周りで言うと70年代頭にはギル・スコット・ヘロンが現れ、ロイ・エアーズがユビキティを結成し、マイルス・デイヴィスは『Bitches Brew』をリリース。<ストラタ・イースト>や<ブラック・ジャズ>といった黒人たちによるインディペンデントレーベルが生まれ、ジャズがファンクやアフリカ音楽と接近していった時代だ。
ここでのマーヴィン・ゲイのボーカルはギル・スコット・ヘロンを彷彿とさせるようなエネルギッシュなものだ。内省的に世情を歌い上げるこの時期のマーヴィンのイメージとは別物で、音楽の世界観だけでなく、アジテーション的な態度や振る舞いも含めて、この時期の彼のアルバムにはそぐわなかったのだろう。とはいえ、当時の強面な側のブラックミュージックのようなサウンドも試してはいた、けど、選択しなかったという事実はとても面白い。ちなみに「Checking Out(Double Clutch)」もギル・スコット・ヘロンっぽいポエトリーリーディングとファンクの組み合わせでかっこいい。
実は本作はジャズとの繋がりがある音源が収録されているのも面白い。チャレンジングなサウンドをいろいろやっているマーヴィン・ゲイだが、スティーヴィー・ワンダーやダニー・ハサウェイのようなわかりやすいジャズとの接点は見当たらない。本作に収められた「Where Are We Going?(Alternate Mix 2)」と「Woman of The World」がその2曲。ちょっと変わったアレンジのこの2曲は、フレディー・ペレンとフォンス・ミゼルの2人が手掛けている。二人ともモータウンの専属の作曲家で、名曲を生み出しているが、それよりも重要なのはフォンス・ミゼルがラリー・ミゼルとセットでミゼル・ブラザーズと呼ばれていて、彼らはスカイ・ハイ・プロダクションというプロダクションチームを結成し、数々の名曲を生み出し、レアグルーヴ以降、再評価されたヒップホップにとって重要な存在であるということ。
中でも有名なのはラリー・ミゼルのハワード大学時代の教師だったジャズトランぺッターのドナルド・バードがハワード大の生徒を中心に結成したバンドともにジャズの名門<ブルーノート>からリリースした1973年の『Blackbyrds』以降の作品群だ。そこからドナルド・バードは『Street Lady』『Stepping Into Tomorrow』『Spaces and Places』と傑作を次々にリリースしていくが、それらはすべてミゼル・ブラザーズが手掛けている。それ以外にもボビー・ハンフリー、ジョニー・ハモンド、ゲイリー・バーツなど、ジャズとソウル/ファンクの挟間のような独自のサウンドを生み出していく。そして、フレディー・ペレンもその作品群に関わっていた。
「Where Are We Going?(Alternate Mix 2)」はドナルド・バード『Blackbyrds』にも収録されていて、2014年のレコードストアデイではこの2曲を収めた12インチのバイナルがリリースされている。マーヴィン・ゲイのバージョンの時点で、ドナルド・バードのバージョンにかなり近く、曲自体はすでに完成されている。
「Woman of The World」はエドワード・ゴードンの作曲で、フレディーとフォンスがプロデュース。動きの激しいエレピも含めて、かなりジャジーなアレンジで明らかにマーヴィン・ゲイの曲というよりは、イメージとしては『Extension of A Man』の頃のダニー・ハサウェイが歌いそうな曲とも言える。これは後に1973年にドナルド・バードが『Street Lady』で再演している。
これらの曲はアルバムとしては形になっていなかったわけだが、マーヴィン・ゲイが様々なチャレンジをしていて、その中から最終的に既存の名作に収録された曲がセレクトされた、ということがわかる。ニューソウル勢の中ではジャズやファンクとの、特にジャズとの繋がりが希薄なマーヴィンだが、チャレンジはしていて、質の高い音源は残していたのだ。メロウなインストの「Christmas in The City」もジャズ的な要素という視点で見るとまた聴こえ方が変わるかもしれない。
そういう意味では『You’re The Man』はジャズやレアグルーヴを聴くリスナーにはあまりにも興味深い音源であると言えるだろう。
ちなみにヒップホップ/R&Bシーンの名プロデューサーで、ハイエイタス・カイヨーテやエイミー・ワインハウスを手掛けたサラーム・レミがミックスを施したほぼネオソウルというか、ほぼヒップホップと言える最高の楽曲も収録されているので、現代ジャズ~ネオソウル~フューチャーソウルのリスナーも必聴である。
■『for Marvin Gaye”You’re The Man” by Mitsutaka Nagira』Mitsutaka Nagira
URLはこちら
■柳樂光隆
1979年、島根・出雲生まれ。音楽評論家。元レコード屋店長。21世紀以降のジャズをまとめた世界初のジャズ本「Jazz The New Chapter」シリーズ監修者。共著に後藤雅洋、村井康司との鼎談集『100年のジャズを聴く』など。カマシ・ワシントン、サンダーキャット 、フライングロータス、ロバート・グラスパー、くるりなどライナーノーツ多数。若林恵、宮田文久と編集者やライター、ジャーナリストを活気づけるための勉強会《音筆の会》共催。
■リリース情報
アルバム『You’re The Man』
発売:5月8日(水)
UICY-15825 ¥2,700(税抜)
<CD>
01. You’re The Man / Pts. I & II – Single Version
02. The World Is Rated X – Alternate Mix
03. Piece Of Clay – “The Master 1961-1984” Version
04. Where Are We Going? – Alternate Mix 2
05. I’m Gonna Give You Respect
06. Try It, You’ll Like It
07. You Are That Special One
08. We Can Make It Baby
09. My Last Chance – SalaAM ReMi Remix
10. Symphony / SalaAM ReMi LP Mix
11. I’d Give My Life For You – SalaAM ReMi LP Mix
12. Woman Of The World
13. Christmas In The City / LP Mix & Edit
14. You’re The Man – Alternate Version 2
15. I Want To Come Home For Christmas – LP Mix & Edit
16. I’m Going Home – “The Master 1961-1984” Version
17. Checking Out (Double Clutch) – “The Master 1961-1984” Version
アーティスト写真:Photo by Jim Britt


