syrup16gの音楽には乾いたユーモアがある 過去作品配信解禁を機に考えるバンドの魅力
音楽
ニュース
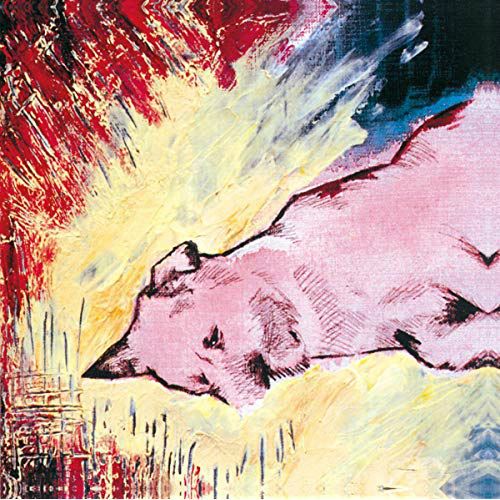
去る6月1日、syrup16gの過去作品群の音楽ストリーミング配信とダウンロード販売が解禁された。それと同時に公開された特設サイトには、石毛輝(the telephones、Yap!!!)、江沼郁弥、木下理樹(ART-SCHOOL)、小林祐介(THE NOVEMBERS)、ホリエアツシ(ストレイテナー)といったアーティストたちや、メンバーである中畑大樹、キタダマキ、元メンバーの佐藤元章、さらに、そのほか関係者によるレビューも公開されている。さらにさらに、その特設サイトはそれぞれの作品に対し誰でも自由にレビューを書きこめる仕様になっており、ちょっとしたお祭り騒ぎだ。2000年代のはじめ、アルバムやシングルを生き急ぐようにリリースしまくっていた頃のsyrup16gを体感していた身としては、案外、お祭り騒ぎも好きなバンドなのだろうと思うが、作品自体は、そんな周りの喧騒とは関係のない静けさの中に佇んでいるようでもある。
(関連:syrup16gの復活が支持される理由とは? 一貫した音楽的特徴を分析)
NUMBER GIRL、くるり、SUPERCAR、中村一義といったアーティストたちを指して「98年世代」と呼ぶことがあるが、syrup16gが最初のミニアルバム『Free Throw』をリリースしたのが、1999年。この年は、他にBUMP OF CHICKEN『FLAME VEIN』や、GOING STEADY『BOYS&GIRLS』、THE BACK HORN『何処へ行く』といった作品がリリースされている。MONGOL800の1stアルバム『GO ON AS YOU ARE』が沖縄でリリースされたのもこの年だ(全国リリースは2000年)。こうしてみると1999年には「ゼロ年代」へと突入していく起点となるような作品が多くリリースされていることがわかる。ゼロ年代の日本のロックシーンは音楽の中でも「歌」に重きを置くバンドが多く登場した時代であったが、しかし、中でもsyrup16gは異質な存在だった。彼らの音楽には溺れてしまいそうなほどのメロウネスがあり、その中でうたわれる歌は、若者が大きな声で、声を合わせてうたうような歌ではなく、人生を重ねた人が部屋でひとり紡ぐような、疲弊した人の歌だった。
syrup16gの音楽には「平等」という視点があった。例えば1stフルアルバム『COPY』に収録された「負け犬」は、映画『アウトレイジ』のキャッチコピー「全員悪人」ばりの勢いで、「全員負け犬」を突きつける。
程なく 人生を
そつなく終えれば
ヤクザも官僚も
ロックのロクデナシも
みんな負け犬でしょう(「負け犬」)
それは、とても平等で、優しい歌だった。「負け犬」は今でも、僕にとってsyrup16gのベストトラックだ。どれだけ金を稼ごうが、貧乏だろうが、モテようがモテなかろうが、この世に生まれ、生きて、死んでいく。それだけで全員、負け犬でしょう?――『COPY』というアルバムには、他の作品にはない、くぐもった密室感がある。歌詞はほとんど引き籠りの内省と夢想のようなもので、〈そこで鳴っているのは目覚まし時計〉(「生活」)、〈時計壊れた 後の責任は放棄〉(「君待ち」)と、いくつかの曲の歌詞に登場する「時計」というモチーフは、曲の主人公と「世界」がいかに断絶しているかを物語っていた。
2000年代のはじめ、自分が一番syrup16gを熱心に聴いていた10代の頃は、なぜ自分がこのバンドに惹かれているのかはわからなかったが、身の周りにあるすべてが退屈で、大嫌いで、くだらない自意識に雁字搦めになりながらも「とにかく、この世界から飛び出してしまい」という衝動を抱えながら鬱鬱と日々を過ごしていた、当時の自分の気持ちをすっぽりと収めることができるポケットのような存在がsyrup16gの音楽だったのだろう。「こんなにも傷だらけの歌をうたう大人がいる」という事実が、なによりの希望であり、彼らに対する信頼の種だった。当時は、テレビのニュースをつければ、同時多発テロを発端に戦争に乗り出していくアメリカの姿や、あるいは小泉純一郎やホリエモンの顔が頻繁に映し出されていた(こういう状況は、今と少し似ているかもしれない)。別に社会派な子供でもなかったが、10代は10代なりに、世界を感じ取りながら生きているのだ。あの頃の僕は、syrup16gの音楽を聴きながら、孤独で無力で平等な、このポケットの中にいたいと思っていた。人生はピカピカのプラモデルではなく、人生は人生でしかないということを教えてくれる大人が、syrup16gだった。
syrup16gの音楽には、「失くしたもの」の奥から「あったもの」を拾い上げるような逆説的な形で、生きることの美しさを証明するような力がある。それは、10代だった頃の自分にとってはロマンと共に生きる指針となり、そして30歳も過ぎ、近所に美味しいお蕎麦屋さんを2軒見つけるくらいにはおっさんになった今の自分にとっては、ひとつの「生き延び方」として、とても切実かつリアルに納得できるものだ。
今になって思う、生きることは「失うこと」の連続なのだと。飯を食い、仕事をし、恋に落ち、そして、失う。どんな幸福な景色も、一分一秒と時間が過ぎれば、それはすべて過去となり、失われる。人は失う。失って失って失って、失い続ける。しかし、人は「ない」ものを失うことはできないのだ。「ある」ものしか、人は失うことができない。syrup16gの曲には、すでに失われてしまったかもしれない、しかし、そこにたしかに「あったもの」の美しさが刻まれていた。たとえば、「センチメンタル」の切なくも甘美な旋律は、青春期の身を焦がすような恋に身を投げ入れたことのある人間にしか生み出しえないものだ。「My Song」のライナスの毛布にくるまれるような穏やかさは、愛する人と裸で身を寄せ合う、その刹那の安堵を知っている人にしか表現しえないものだ。『HELL-SEE』に収められた「シーツ」や「吐く血」といったストーリーテリングの才が際立つ名曲は、人が人を失うことの悲しみの奥から、「個人」の生の、小さくて尊い光を浮かび上がらせるようだ。それらすべての美しさが、たしかに、そこには「あった」のだ。
生まれたからには負け犬で、それでも美しいと思える瞬間がたしかにあって、それを結晶のようにして時折眺めながら、擦り切れて、失って、疲れて、汚れて、生きていく。迷いながら、戸惑いながら、手のひらから零れてしまいそうな「明日」を、なんとかすくい上げていく。正しくなかろうが、生産性がなかろうが、そうやって生きていく。そんな生き方を、あなたは笑うだろうか、どうだろうか。
しかしまぁ、笑われたっていいのだ。syrup16gの音楽にはいつだって乾いたユーモアがあって、それがなによりの魅力になっている。この十数年の間に、いろんな人たちとsyrup16gの話をしたが、このバンドを「あの深い絶望が~、闇が~」と語るおセンチな人たちとは友達になれなかったが、「シロップって、笑えるからいいよね」と語り合える人たちとは友達になれた。この原稿を書くことになり、Spotifyの画面にずらっと並んだsyrup16gのアルバムを聴き返す行為は、自分がこれまでどうやって生きてきて、そしてこの先、どうやって生きていくのかを改めて見直すような作業で、嬉しいような情けないようなで笑ってしまった。(天野史彬)


