SPECIAL OTHERS ACOUSTICのライブで感じた、アンサンブルという名の“テレパシー”の凄み
音楽
ニュース
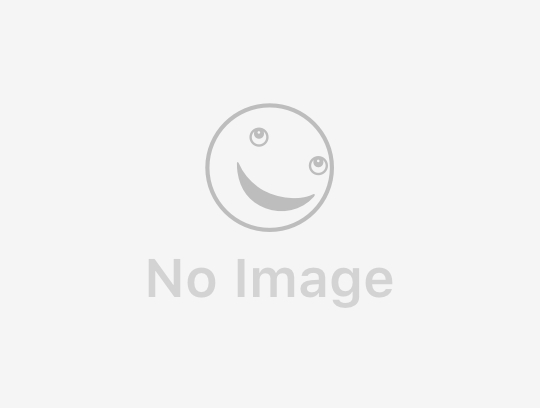
小さな声で話をしよう。大事な話を。余計な場所にまで届かないように、小さな声で。でも、私とあなたには絶対に届くような、小さな声で。
SPECIAL OTHERS ACOUSTIC(以下、SOA)の音楽は、まるでそんなことを私たちに提案しているかのようだ。武道館でワンマンライブを成功させ、野外フェスでは大ステージを担うインストゥルメンタルバンドであるSPECIAL OTHERS。彼らのアコースティック編成によるプロジェクト「SOA」は、バンドミュージックの持つ魅力とは、なにも複数の人間が集まって「大きなもの」を見せることだけにあるのではない、と証明している。「小さなもの」を取り零さないこともまた、その尊い力なのだと。彼らは音楽による、とても繊細な対話を私たちに聴かせてくれる。
今年、SOA名義で約3年半ぶりにリリースされたアルバムは、そんな彼らの音楽の力を象徴するかのように『Telepathy』と名付けられた。そのリリースツアーの東京公演、7月11日に恵比寿LIQUIDROOMで行われたライブを観た。
ささやかな電飾によって照らされ、観葉植物が飾られたステージの上、メンバー4人全員が椅子に腰かけての演奏。SOAは4人それぞれがひとりで複数の楽器を操るが、芹澤優真は主にグロッケンシュピールと鍵盤ハーモニカ、又吉優也は主にベースとマンドリン、宮原良太はドラムとギター、柳下武史はギターとベース、と、全員が一人でリズム楽器とメロディ楽器の両方を奏でている。これはSPECIAL OTHERSというバンドの「メンバー全員が平等にバンドの主役であり、同時に屋台骨であり、誰もが楽曲に奉仕する」という関係性をよく表している。特にSOAはアコースティック楽器による演奏ということもあって、それぞれの楽器の音が非常に繊細だ。だからこそ、音と音が潰し合わないように、それぞれの音がしっかりと響き合うように、メンバー4人が細かく呼吸を合わせながら音を重ね、絡み合わせていく必要があるだろう。曲によって楽器を変え、あるいは、1曲のなかで複数の楽器を操りながら演奏していくステージ上の4人。
芹澤はグロッケンシュピールと鍵盤ハーモニカを奏でながら、時にはカウベルのようなものを叩いたりと、細やかに楽曲のポップな輪郭を彩っていく。精巧なドラミングを見せる宮原は、曲によってはギターを弾きながら足元でドラムのシンバルとキックを鳴らす、という離れ業もやってのける。又吉はベースで曲にどっしりとした力強さを与えてみせたかと思えば、マンドリンでは曲を華やかに浮上させる。そして柳下は、時にメインに、時にサイドに回りながら、「ギターを弾く」という行為の中にある多様なスタイルを見せる。そんな4人の多彩かつ多才な演奏姿は、見ていてホレボレするほどだった。
アンコールで演奏された「ローゼン」に、この曲と縁の深いシンガーのLeyonaがゲストボーカルで参加するというスペシャルな瞬間があったが、本編は基本的にゆっくりと、じっくりと、淡々と進んでいった。穏やかな波の満ち引きを楽しむような時間、とでも言おうか。個人的にとても印象に残ったのは、アルバム『Telepathy』の1曲目を飾っていた「WOLF」。構造的に、この曲よりもダイナミックな曲は他にあるのだが、ただ、人と人、音と音の繊細な息遣いを堪能できるという点で、この「WOLF」という曲はSOAの真骨頂を見せるような曲なのである。「WOLF」では、宮原はドラムに加えギターを、又吉はマンドリンを奏でる。メンバー4人の鳴らすメロディが絡み合い、リリカルな情景を生み出していくところから曲は始まる。そして、そこから徐々にドラムが加わっていき、躍動感が生み出されていく。美しい旋律が続く曲の中で、後半、芹澤と宮原によるハンドクラップが鳴るタイミングがある。ミニマルに響く、心地いい、ふたりぶんのハンドクラップだ。しかし、この芹澤と宮原によるハンドクラップは、実際のところ、ずっと同じタイミングでは鳴り響いているわけではない。拍が徐々に、微妙にズレていく。もちろん、この「ズレ」は意図的に生み出されたもので、ナタリーに掲載されたインタビューにおいて、芹澤は「ちょっとスティーブ・ライヒを意識した」と語っていた。いわば、これまで多くの音の「重なり」を生み出してきたSOAの4人が、意図的に生み出した「重ならない」瞬間……それが「WOLF」のハンドクラップなのだ。そして、このハンドクラップの「ズレ」が生まれる瞬間に、私はどうしようもなく感動してしまう。何故なら、このハンドクラップのズレはまるで、「人と人とは簡単に、ひとつにはなれないんだ」と、伝えているようだから。このズレはまるで、初めは一緒だったふたりの人間が、いつしか、離れ離れになっていく……そんな情景を思い起こさせるから。

この日のMCで、宮原が、予告編のように映画のタイトルを言うのが上手いという話になり(どういう話だ!)、宮原と芹澤が同時に「君の名は!」と言う瞬間があった。思えば新海誠監督の『君の名は』は、若き少年少女の、時空を超えた心と心の繋がり……まるで「テレパシー」の存在を描いているような映画だった。2016年の夏は、私もあの映画を観に行き、大いに感動したのだが、しかし現実の生活の中で、あのようなダイナミックなテレパシー的な出来事というものは、そう起こらない。伝わらないこと、わかり合えないこと……そんな他者との「ズレ」を抱えながら毎日生きていくだけだ。しかし、そんな毎日の中で、人は誰かに気持ちを伝えたいと思い、誰かの気持ちをわりたいと思い、細やかな思いやりを重ねながら生きていく。
もし、この世に「偶然」ではない、真の意味での「テレパシー」というものが存在するのであれば、結局それは、気を遣い合ったり、声をかけ合ったり、視線を投げかけたりするような、そんな具体的で繊細な心と体のやり取りを出発点にして生まれるものなのだろうと思う。SOAのアルバムに何故、『Telepathy』と名付けられたのか? きっと、このタイトルが意味するのは、何もせずとも心が通じ合うような、そんなファンタジックな「テレパシー」ではない。丁寧に、丁寧に、音と言葉と心のやり取りを重ねることによって生まれる実際的な力としての「テレパシー」なのだ。
この日、「WOLF」の演奏中、宮原と芹澤に続き、フロアにいるオーディエンスからもハンドクラップが巻き起こった。もちろん、そもそもが精密に刻まれているこのハンドクラップを、LIQUIDROOMに集まった大人数が同じタイミングで叩けるわけもなく、会場に響く手と手の音は、ぎこちなく、バラバラにズレていく。でも、それでいい。だからこそ私たちは、「ズレ」すらも血肉化したSOAの4人の、徹底した鍛錬と実力による「アンサンブル」という名のテレパシーの凄みを感じることができる。「WOLF」における、ふたりのズレたハンドクラップに、徐々にそれぞれの楽器の音が重なっていき、ギターの旋律に戻り、再び4人の一体感のあるアンサンブルへと向かっていく……このクライマックスは圧巻だった。

(文=天野史彬/写真=中河原理英)

