SATANIC CARNIVAL プロデューサーI.S.Oが語る、フェスでストーリーを生み出すロマン
音楽
ニュース

2014年の初開催から6回目を迎えた『SATANIC CARNIVAL’19』が、幕張メッセ 国際展示場9-11ホールで6月15日、16日に開催された。2017年の『SATANIC CARNIVAL’17』では2デイズでの開催に規模を拡大。パンク、ラウドロック、ハードコアのシーンの居場所、入り口を作るべく、多くのバンドやファンの支持を受けながら開催してきた。
今回リアルサウンドでは、同フェスのプロデューサーであるI.S.O氏にインタビュー。ブッキングだけではなく、イベント制作まで全て自らの手で作り上げてきた彼が当初から描いてきたSATANIC CARNIVALの理想、回を重ねる毎に表れてきたバンドのストーリーがもたらすフェスとシーンの活性化、これからの課題について聞いた。(編集部)
アーティストごとの成長曲線を見せる
ーーSATANIC CARNIVALは「シーンの居場所を作ろう」というコンセプトから始まりましたけど、そこは今も同じですか。
I.S.O:そうですね。気持ちは変わらずやれてます。たぶん、コアな人から見れば「もうちょっと深いところをフォローアップできたらいいのに」って思うのかもしれないですけど、入り口としての役割、それがあの会場でできる形なのかなっていうところで続けてますね。
ーー歴史を振り返ると、2014年に始まったサタニックは、3年目から2デイズに発展します。
I.S.O:単純に重ねていくと、出たいバンド、出したいバンドが増えていって。そうなると一日じゃ収まらなくなってくる。僕らは自分たちでレーベルとマネージメントをやってるので、やっぱりピザ(PIZZA OF DEATH)のバンドだけじゃなくて、出演してるアーティストをプロモーションするにはどうするかっていうことに主眼があって。アーティストごとの成長曲線をちゃんと見せる必要が出てくるんですよね。若手のバンドが初登場して、最初はマキシマム ザ ホルモンだったりKen Yokoyamaの前に出ていたのが、トリに上がっていくみたいな。できる限りそういうストーリー性を見せていきたいなと。
ーー若手には夢や憧れが生まれますよね。
I.S.O:そう。去年に引き続きTHE NINTH APOLLOのハルカミライやTrack’sに出てもらって。あとBACK LIFTには久々に出てもらったけど……しつこすぎて(笑)。毎年毎年KICHIKU(小林‘KICHIKU’辰也/Ba&Vo)から電話来てたんですよ。
一一「出たい」と。そういうバンドも多いでしょうね。
I.S.O:そう。BACK LIFTには2回目に初登場で出てもらって。もっと遡ると1年目は若手枠で「BACK LIFTか04 Limited Sazabysのどっちに声を掛けようか?」って考えていたんです。ウチのスタッフに相談したら「いや絶対フォーリミでしょう」となって(笑)。KICHIKUもすごい悔しがってましたけど、それで次の年にBACK LIFTに出てもらった。でも、そのあとからBACK LIFTがブレたんですよ。もうこれ周知の事実ですけど。
一一ははは。続けてください!
I.S.O:もともと「90年代パンク好きです」って言いながら英語でメロディックやってたはずなのに、なんか日本語のポエトリーリーディングみたいなのを入れ始めたりして、そっからはずーっと出さなかったんです。格好よくないからっていう理由で。なんだけど、最近は自分たちがブレたことを自覚して、もがきながら奮起してて。で、良い作品も作って、先輩のバンドにも認められるようになってきた。で、その間も毎年開催前にKICHIKUは電話してくるんです。「出たい」と。いい加減根負けして。根負けしたんですけど、自分としては、根負けするだけのことを彼らが諦めずにやったんだなって。
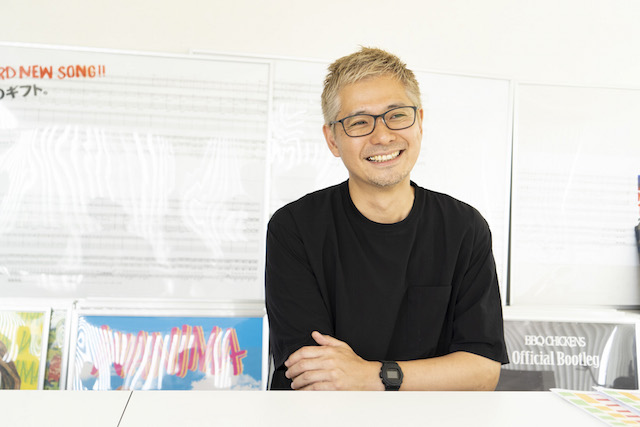
一一今の話が示唆的ですけど、格好いい奴は出す、格好良くないことしたら出さない、その線引きがすごくはっきりありますよね。
I.S.O:はい。僕も人間なんで。やっぱり見たこと、触れたことのあるバンドですよね。あと全部を見続けることはできないので、仲間の声。さっき言ったTHE NINTH APOLLOの旭くん(渡辺旭/レーベル代表)やライブハウスの店長に相談して、「このバンドどう?」「若手誰がいい?」「今だったらこの2バンドだね」「じゃあやってみよう」っていう感じで。だから若手には「出たい」ってどんどん言ってほしい。言ってくれれば気になるし、情報をチェックするし、ライブ行けたら見に行くし。線引きっていうのはその程度ですね。
一一触れられれば、交流が生まれる。そうなれば出演してくれるバンド全部をプロモーションしていく、という意識も生まれる。
I.S.O:そう、その気持ちは変わらないです。ただ出すんじゃなくて、出ることに何か意味があるっていうのはどのバンドも意識してますね。「なんでこのバンド出したの?」って言われたときに答えられないアーティストはいない。それはもう、少しでもバンドにとってプラスになることをしたいから。あとマガジンサイト(SATANIC ENT.)もやってるから、伝えたいことがある人たちに関しては、サイトのほうで対談とかインタビューで出てもらう。できる限りのことはしてます。
一一つまり、このフェス自体がひとつのメディア機能を持っている。
I.S.O:あぁ、そう感じてもらえたら一番嬉しいですね。最初、それこそ立ち上げて2年目のインタビューで「やっぱり発信力が大事だ」って話してました。それこそ今はお客さんとバンドが直接繋がることもできる時代なので、「あぁやっぱりサタニックに出てよかったな」ってバンドが思えるかどうかって、イベントの発信力にかかってると思う。
一一フェスが発信力を持つには、何が必要なんでしょうか。
I.S.O:どうだろう? 特化することじゃないですか? これだけ情報過多になったら、「僕たちこうです!」って特化するのが一番わかりやすい気がしますね。そのほうが目につくし。ただ……他のフェスがそうやってパンク/ラウド系のバンドを固め打ちにするっていう戦法を覚えちゃったから最近ややこしいんですけど(笑)。
一一あぁ、ありますね。この日だけラウド並び、みたいな。
I.S.O:そう、これ僕は声を大にして言いたいんですけど、サタニックの1~2年目、ちゃんとお客さんが集まってソールドしてから、他のフェスが3日間の1日だけそういうパンク・ラウド系のバンドで固めだしたり。そういうのを見るとイラッとします(笑)。まぁいいんですけどね。結果、このシーンのバンドの価値を分かってもらえたり、いろんな人に見てもらうチャンスを得られるのであれば、サタニックはすごくいい役割を果たしているなと思う。
一一いい効果だと思います。とはいえ、今回、横山健さんが「来年はない」ってステージで言ってましたが。
I.S.O:そう。来年はないんです。それはオリンピックで会場が使えないから。でもちょうど良かったですね、自分の中でもいろいろ見直せるし。毎年続けることって、いい面もあるけど、どうしても既視感が出てくるから。やり続けたい反面、こうやって一回休むことで見直して、何か新しい見せ方がないかなって。まぁ現状だけでもけっこうパンパンなんですけどね。

「どっちか論」じゃないといけないのか?
一一ブッキングだけじゃなく、イベント制作もI.S.Oさんひとりで担っているわけですよね。相変わらずイベンターは入れずに。
I.S.O:はい。入れてないです。自分で書類書いて。この部屋はこうやって使います、みたいな計画書を書いて。あと消防の申請とかも。
一一イベンターから「そろそろウチを挟みませんか」みたいな声がかかることはないんですか。
I.S.O:それはないです。普段、PIZZA OF DEATHはイベンターさんとやっているけど、そこに筋通して「直接自分たちでやらせてもらっていいですか?」って頼むところから始まってる。そこに今さら「ひとつ噛ましてください」って言ってくるのは馬鹿げてますよ(笑)。お互いの守備範囲もわかってるし。今さら「楽したいですか? お金くれるなら楽させますよ」って言ってこないですよね (笑)
一一ははは。実際は全然楽じゃないと思うけど、楽しめるくらいには回せるようになっている。
I.S.O:うん、そうですね。
一一ただ、さっきの既視感の話でいえば、続けることはマンネリと背中合わせですよね。特にサタニックは毎回同じバンドがよく出ている。
I.S.O:うーん、そこはスペースの限界なんですよね。ライブハウス感っていうのは、あれくらいの会場じゃないと味わえないし。野外でパーンとやっちゃうと違ってくる。だから、マンネリしないように自分なりに工夫はしてます。「やっとこのバンドがメインステージに」っていうストーリーもそうだし、メインステージの最後の3バンドに関しては独自の演出を付けるようにしていて。その瞬間だけはワンマンライブを作る、ぐらいのテンションで綿密に打ち合わせするんです。だからメインステージに行けるかどうかもストーリーだけど、ケツの3バンドに入れるかどうかっていう流れもあって。2段階どころか3~4段階あるんですよ。
一一4段階?
I.S.O:まずはEVIL STAGEに出る、EVIL STAGEのトリをやる、SATAN STAGEに移る、最後の3バンドに入る、最後にトリをやれるか、っていう。フォーリミとかまさにそうですね。EVILの一番手から始まって、毎回出演時間が遅くなっていって、遂に今年はメインのトリ。始まる前も、今までの映像を全部ビジョンに流しながら「……遂に!」っていう演出があって。そうやって見てると感慨深いものもある。ちゃんとしっかり掴んでいったなぁって思う。あとアツいのはNOISEMAKER。
一一どんなストーリーがあるんでしょう。
I.S.O:最初に出てもらった時から「NOISEとフォーリミは絶対行くだろう」っていう見込みだったんですよ。1回目に出てもらった時、彼らはもうA-SKETCHと契約してて。なんですけど、契約してからのNOISEが意外とうまく行かなかったんです。客観的に見ても、好きだけど誘えないなぁって。で、2017年に久しぶりに出演してもらったんですけど、その後「事務所とレーベルの契約が終わった」って聞かされたんです。でも、その厳しい状況下で彼らはめちゃくちゃ格好いい曲を自主で出したんです。「SADVENTURES」っていう曲。これは誘うしかないと思わされて。で、2018年にはEVIL STAGEのトリで素晴らしいライブをやって。その後、リリースしたミニアルバムもまた良くて。ジャケットのアートワークも、海外のWK Interactっていうストリートアーティストを日本に呼んで、渋谷のでっかいビルの壁にペイントさせるっていうのを実現させてたんですよね。そういうのを一通り見てるから、今、SATAN STAGEでやる価値のあるバンドだって思えて、今年SATAN STAGEに出てもらったら……まぁ余裕のライブでしたね。ステージの大きさもバンドに見合っていて。やっとバンドが立つべきステージに辿り着いた感じでした。

一一もうバンドの波乱万丈な歴史に完全に寄り添ってますよね。それはPIZZA OF DEATHの仕事なのかって言われたら、答えはYESなんですか。
I.S.O:いや、PIZZA OF DEATHの仕事じゃないですよね。だからSATANIC CARNIVALはPIZZA OF DEATHのイベントじゃない。それは最初に明言してる。その気持ちでやってるから、たまたまそういうストーリーが生まれると自分にもすごい相乗効果があるんですよ。
一一このフェスがあり、バンドとの交流を続けることで、I.S.Oさん個人に得るものがあると。そうなるとメンツはさらに固まりがちになると思うんですけど、それでも若手枠を用意して、初登場の若手バンドを出していくことは大事ですか。
I.S.O:絶対出したいですね。そもそもシーンが続いていってるわけで、若い子にはストーリーってあんま必要ないじゃないですか。「やべぇ!」みたいな勢いのほうが大事だったりする場合がある。だからこそ「え、お前ら出れるんだったら俺らも出れんじゃね?」みたいな感覚も若いバンドマンには持ってほしいし。自分に可能性を感じられるって、いいことじゃないですか。どうせ無理だよ、とは思ってもらいたくない。そうなると意識的に若手を誘いたくなるんですね。あと今回かなりチャレンジだったのがw.o.d.。
一一うん、サタニックにハマるのかってびっくりしました。
I.S.O:そう。「すごく格好いいけど、サタニックとは合わないかなぁ」って躊躇してたけど、お互いに刺激になればと思って誘ったら「出たい」って言ってくれたから。ただ、ハードコアとかオルタナ的なバンド、そこを触るか触んないかはサタニックにとってなかなか難しいところで。もちろん好きですよ? このシーンがもっと多種多様で深いこともわかってます。
一一たとえば、自分が好きなバンドを全部ごちゃまぜにして「どうだ!」って見せる方法と、あくまでみんなが喜ぶ、ちゃんと客が入るメンツっていうものがあるとして。I.S.Oさんはどっちを選ぶんですか。
I.S.O:……それ「どっちか論」じゃないといけないのか? って思います。「どっちか論」でやらないで、自分のバランス感覚でいいとこ取りしてやろうと思ってる。で、ハードコアのバンドが難しいのは、こういうメンツの中に出ていくと逆に目立つ、刺激になる反面、それこそ「怖ぇ」で終わっちゃうこともあるからで。サブステージと言っても6000人規模のフロアだし、そこで伝わるライブをやらなきゃ意味がなくて。どこまで届けられて、人を巻き込めていけるかっていうのも必要なんですね。
一一確かに、そのバンドに似合う規模、似合う会場ってありますよね。
I.S.O:そう。それこそゴリゴリのハードコアバンドをかっこ良いと思って、誘いたいと考えたても、それがバンドにとって良い見せ方にならないなら誘わない。ハードコアの仲間にも相談して「そうだよねぇ」って言ってたけど(笑)。だからそういうバンドに出会う機会は、サタニックのその先にあればいいかなって思う。サタニックきっかけで何か好きなバンドができて、試しにライブハウス行ってみたらたまたまゴリゴリのハードコアバンドがいたり。そういう出会いでいいと思う。俺も、せっかく出てもらうのに客にポカーンとさせるようでは意味がないじゃないですか。だからお客さんの感性も育てなきゃいけないし、育った人はライブハウスに行けばいいんだし。出演バンドたちもそれをわかってるから「ライブハウス来いよー」ってみんな言うわけですよね。だから、なんでもかんでもフェスに求めようとするのはナンセンスかなって僕は思う。
一一だからこそ、サタニックは入り口であると。ほんとにバンドのメリットを第一に考えてますね。
I.S.O:これって結局レーベルの人間だから、ですよね。バンドを駒として見てないですから。……あ、バンドをただの駒としてて見てるイベントが多いって言いたいわけじゃないですよ!
一一(笑)。わかりました。来年はひとまずお休み、そして2年後に次があることは確かなんですよね。
I.S.O:はい。そのつもりでやってます。難しいですけどね、続けるのは。自分なりにいろいろストーリーはあるけど、いろんなお客さんがいて。メンツだけ見て「あー、今年も一緒な感じじゃん」っていう人も当然いるだろうし。
一一ただ、私がフロアで見ていた限り、かなりのお客さんがサタニックのストーリーを共有していたと思いますよ。
I.S.O:あぁ。そう言ってもらえると救われます。やっぱりこのシーンは強いなって思います。なんだかんだでパンク・ラウド系は活気ありますよね。相変わらず若手もどんどん出てくるし。
一一同時に、中年になってもファンが離れない。子連れのお客さんがすごく多いのも印象的でしたね。これは20年前にはなかった光景。
I.S.O:そうですよね。僕ら世代がみんな親になりだして、今は僕らの後輩に小さな子どもが生まれてるような時代で。90年代から始まったシーンがあって、お客さんがみんな年齢を重ねていって、新たな家族ができたり、彼らの子どもがライブに来たり、また新たなバンドが登場したり。そうやって世代が繋がっていくのはロマンティックだなと思うし、そのロマンの一端を担えているのは、すごくやりがいがありますね。
(取材・文=石井恵梨子/写真=中村ナリコ)
SATANIC CARNIVAL ’19 オフィシャルサイト


