浜田麻里が語る、音楽的快感を作品に求める理由「同じ自分で居続けるのが面白くない」
音楽
ニュース
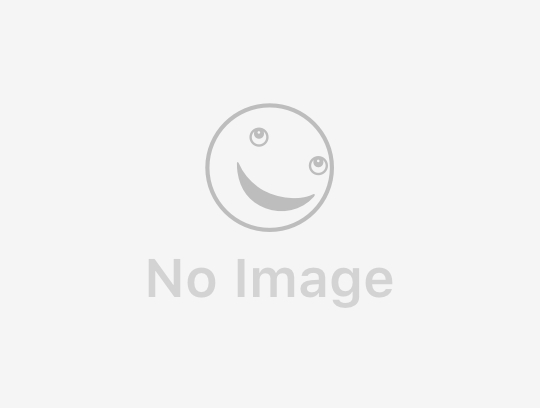
浜田麻里のニューアルバム(通算26作目)『Gracia』が凄まじい。ここ数作続いていたヘヴィメタリックな音楽性をさらに突き詰めた、究極とも言えるハードでヘヴィでアグレッシヴでパワフルなロックアルバムに仕上がっているのだ。仕掛けと展開の多い恐ろしくテクニカルで変則的な楽曲を、マイケル・ランドウ、ポール・ギルバート、クリス・インペリテリ、ビリー・シーン、グレッグ・ビソネットといったLAの超一流ミュージシャンが正確無比に演奏。さらに強烈なのは浜田のボーカルだ。技巧の限りを尽くしたパワフルなハイトーンのボーカルが時にソロで、時に多重録音による分厚いコーラスで突き抜けるように駆け上がっていく様子は「快感」以外の何ものでもない。そして彼女のもうひとつの持ち味でもあるメロディアスでメランコリックでスケールの大きなバラードもたっぷり聴ける。ハードなロックとソフトな楽曲のバランスが完璧だ。
今年デビュー35周年を迎えたベテランなのに、歳を重ねて丸くなったり渋くなったり枯れてきたりする様子は全くない。むしろそれどころか、キャリアを重ねるにつれさらに攻撃的に、エネルギッシュに、挑戦的になっている。声は昔から衰えるどころかどんどん凄くなっている。音域など昔よりも広くなってると思えるほどだ。女性ロックシンガーとして、浜田麻里は世界的に見ても前人未踏の域に達している。
間違いなくここ最近の浜田麻里の最高傑作であるばかりか、今年を代表するアルバムになるのは間違いない。しかしいざ話をしてみれば、ギラギラした欲や威圧感など全く感じさせない、おっとりとして穏やかな話しぶりは相変わらずだった。(小野島 大)
“今の自分にしか作れないもの”にしたい
ーー凄いインパクトでした。これ、大傑作だと思います。浜田麻里をよく知っている人もそうでない人も驚くと思います。
浜田麻里(以下、浜田):そうですか。ああ良かった!
ーー2年7カ月ぶりの新作が、古巣・ビクターレコードに28年ぶりに復帰しての一作になりますね。
浜田:そうですね。初期のビクター所属の時代から結構時間がたってるので、自分としては新たなところに移籍する感覚で選ばせてもらったんですけど、でも戻ってきたらやっぱり昔の匂いもあるし、安心感もおぼえますね。
ーービクターへの移籍はいつごろ決まってたんですか。
浜田:正直いうと、アルバムの制作の開始の方が先ですね。レコーディングのブッキングをやりながら心を決めたというか。
ーーなるほど。今回の作品の制作はいつごろスタートしたんでしょうか。
浜田:徳間ジャパンの最後の作品がライブのブルーレイだったんですけど(『Mari Hamada Live Tour 2016 “Mission” 』2016年2月発売)、その編集が終わってから取りかかって、約1年半ぐらいで制作しました。
ーーこういうものにしたい、という構想はあったんでしょうか。
浜田:デビュー35周年記念盤でもありますし、“今の自分にしか作れないもの”にしたいという気持ちはまず、ありました。
ーー集大成というよりは、今の浜田麻里を表すもの。
浜田:そうですね。
ーー今回は完全LAレコーディングという形になるわけですか。
浜田:ほぼそうなんですけど、日本でもいっぱい作業してますんで。昔みたいに何カ月も行きっぱなし、みたいなレコーディングではなく、行ったり来たりしながら。日本のエンジニアにお願いしているところもあります。高崎(晃)さんや増崎(孝司)君のギターは日本で録りましたし、歌は自分のプライベートスタジオで録ってますから。
ーーでも音の抜けやクリアさが前作とはかなり違う印象を受けました。
浜田:そうですね、はい。
ーーやはりアメリカ西海岸の音という感じがします。乾いていてスカッとしていて、とてもいい音で鳴っている。
浜田:ありがとうございます!
ーーミュージシャンのブッキングもご自分でなさったそうですね。
浜田:基本的には自分でやってます。まとめは、アメリカのエンジニアに委ねることもありましたけど。後半のオファーは一部、ビクターの窓口から。私の担当が洋楽のトップにいた方になったので、ミュージシャンの連絡先を調べてコンタクトしてもらい、私が引き継いで、そこからは直でやりとりしてます。
ーーそこまでご自分でやられてるんですね。ここ数作のレコーディングは同様の態勢ですか?
浜田:やり方自体はほぼ同じですけど、今回はほとんどのミュージシャンが外国人になってますね。
ーーあえて海外のミュージシャンを起用する理由があったわけですね。
浜田:世界視野で、今自分の作品に誰が必要かっていうところで選ばせていただいたんです。おこがましいですけど(笑)。高崎さんや増崎君も、日本人だからというより、ワールドワイドな視点で考えて、自分にとってベストなミュージシャンとして選択させていただきました。
ーー今作は「今の浜田麻里」を表現した作品で、ミュージシャンも「今の浜田麻里」を表すのに適任な人材を選んだということですね。「今の浜田麻里」とはどういうモードなんでしょうか。
浜田:ここ10年ぐらいなんですけど、結構ハードというかエッジィな感じになってたので、今回もよりハードに、というのが第一です。でもそれだけでは私じゃないので、幅も持たせて、対極にあるような曲も作っていく。より広がりを持たせつつ、ハードなところはよりハードに、というところでしょうか。基本的にはギターサウンドで、よりハードに、よりテクニカルに。
ーーお言葉通り、今作はハードロック/ヘヴィメタルといっていい内容だと思いますが、ご自分の指向がそうなってきた理由を改めて教えていただけますか。
浜田:周りからの影響とか、そういうのは全くないんですね。やっぱり“内なる自分”がなんかこう、攻めの姿勢になってるというか。その精神性を強く表現した曲をどうしても作りたい、という気持ちの流れの中から自然に出てきたんですよね。
ーー自分の精神性を強く表現したい。
浜田:そうですね。“強めのタッチ”の表現。歌のスタイルもそうですし、サウンド傾向もそうですし、歌詞の内容も含めて。そうなるとどうしてもハードなサウンドの曲が作りたくなってくる、ということですね。
ーー「強く表現したい」と思うようなものが、ご自分の中に湧き上がってきている?
浜田:そうですね……うまく言葉が見つけられないですけど、今の社会状況の中で、少し攻撃的な気持ちにはなってる気がします。
ーーあまり雑に一般化するのは良くないですが、アーティストは年齢を重ねキャリアを積むと、だんだん練れてきて丸くなり、表現も柔らかくなっていく傾向が強いと思うんです。でも麻里さんは逆にどんどん尖ってハードになっている。
浜田:(笑)。そうなんですよ。おかしいんですよ。
ーーそれだけ燃え上がるようなものがなにかあるんでしょうか。
浜田:なんでしょう?(笑)。ほんとに自然なんで、原点回帰しようとか、気をてらったものにしたいとか、そういう感覚もなく。
ーーヘヴィメタリックになっているとは言っても初期の感じとは全然違いますよね。
浜田:違いますね。初期はわりとシンプルな……今から考えれば、ですけど。でも作品を重ねるにつれ、もっともっと、という気持ちになって、どんどん演奏もメロディの幅も広いものになっていきますからね。どんどんビルドアップしてる感じですね。


より気持ちを入れられて、より質の高いものを
ーー今回すごくテクニカルな曲が多いですよね。演奏面もそうですし、ボーカルアレンジも凝っていて、めちゃくちゃ高いハードルでやっている。
浜田:そうですね。結果的にはそうなりましたけど、でも自分としてはそんなに苦労はないんです。ただ幅は広いと思いますね。ハードな歌や、すごく広い音域のメロディに自然になっちゃう。プラスして、ハードなものだけではなく繊細なタッチのアカペラとか、自分の得意なクラシカルなコーラスアレンジみたいなものをベーシックに入れてみたりとか。
ーーライブでやるのは結構大変そうですね。
浜田:コーラスも結構厚いですし。いつも厚いんですけど、最終的に補助的な感じまで(音量バランスを)下げてリードを立たせようとするんですけど、今回はちょっと上げめにして、よりハードに聞こえるように、とか。オクターブ上下のコーラスを入れるとか、いっぱいいろんなことをしてるので。それはそのままライブでは再現できないので、新たな取り組みとしてやることになると思います。
ーーそういうボーカルアレンジは当然全部ご自分で考えて、ご自分のプライベートスタジオで録るわけですよね。
浜田:そうですね。
ーーそれは完全におひとりの作業?
浜田:そうです。
ーー孤独な作業ですね。
浜田:孤独ですし……やってること自体は私にとって全然難しいことじゃないんですけど、時間がかかるんですね。アカペラのところも一本一本キレイにやっていって、それを2重にしたり3重にしたりして、それにまた3度上、もっと上、下と加えていくので。時間と根気は要りますね。
ーーそれは最初から完成形のイメージが頭にあって、それに近づけていくという作業なのか、それともやっていくうちに積み重なっていって、複雑で予測のつかないものになっていくのか。
浜田:だいたい想定はしてますけども、録っていくうちに新たなアイディアが出てきたりとかはあります。7割ぐらいは元から頭の中にあるものを具体化していくって作業ですね。プラス3割は、それができた上で、カウンター的に入れてみたりとか。演奏面では、今回ミュージシャンたちは全てハイレベルだったので、そんなに苦労した点はなかったんですけど、ドラムの編集からやるのでその点は結構大変でした。
ーー録ったドラム音源のエディットまでご自分でやられるんですか?
浜田:はい。ドラム、ベースはいつも先に録るので、ギターダビングの前に全部やります。
ーーそれはすごく時間がかかりそうですね。
浜田:すっごくかかります。ひとりでコツコツコツコツやっていかなきゃいけない。
ーーこういうこと聞いたら失礼ですが、そういう作業楽しいですか?
浜田:(笑)。いやあ〜疲れるなあと思うことはありますけど、基本的には好きですし、それで生きてきたんで。苦ではないですけど。
ーーそういうスタジオのコツコツした作業とライブと、どっちが性に合ってます?
浜田:……難しいですね(笑)。普通だったらライブってすぐ答える人が多いと思うんですけど、私の場合、もともとプロのキャリアがスタジオシンガーから始まったということもあるので、レコーディング自体にすごく価値を感じるタイプなので……作品作りもすごく楽しんでますし、ライブはまた全然違った感覚ですかね。いいものができて、お客さんとの一体感を得た時にはほんとにハッピーな気持ちになりますし、思うようにいかないと、うーっとなっちゃうし。
ーーメロディはすべて麻里さんが考えてるんですね。
浜田:基本的にはそうですね。掴みのあるメロディが浮かんだ時点で、その曲が採用となる……そんな感じです。
ーー楽曲を仕上げていく過程で自然にメロディが生まれてくると。そこで「今度はこの音域に挑戦しよう」とかそういう気持ちで作ることはあるんですか。
浜田:そういうの、全然ないんです。自然にできてきたメロディが結構なところにいっちゃうというか(笑)。
ーーなるほど。今作の楽曲はすべて日本人の作家が書いてますね。せっかくこれだけのミュージシャンに演奏してもらってるわけだし、楽曲も海外の作家に頼んでも面白そうな気がしますが。
浜田:うーん……今は結構“書きたい”と言ってくれるミュージシャンが周りにたくさんいてくれますんで、身近なところで発注するので全然足りてるというか。外国人とのコラボも過去にはやりましたけど、細かい煮詰めとかはやはり日本人同士の方が楽といえば楽ですし、データを使ったやりとりも、日本人の方が繊細にやれるんです。もちろん海外の作家でも、これという人が出てくれば全然ありえますけど。
ーー今作の楽曲の発注はどういう形でやられたんですか。
浜田:周りのミュージシャンに発注するんですけど、その人ごとに、この人にはこういう曲を書いてほしい、この人にはこういう曲を書いてほしい、という風に自分で決めて、発注するんです。それぞれの得意な傾向を考えて。一回目にできてきたものをそのまま使うことはまずないので、それをいろいろ組み替えてみたり書き換えてみたりして、何度もやりとりしながら最終形に持っていくんですね、アレンジも含めてです。歌詞はそこから考えます。
ーーじゃあお任せみたいな感じで丸投げするんじゃなく、麻里さんの方から「こんな感じの曲を」とリクエストする。
浜田:そうですそうです。
ーーたとえば1曲目の「Black Rain」という曲はかなりインパクトのあるテクニカルなヘヴィメタルチューンですが、どういう形で発注されたんでしょうか。
浜田:そうですね……まあ聴いてもらったまんまなんですけど(笑)、スピードチューンで、リフがかっこよくて、タッピングがメインになってる、という。
ーーああ、そこまで細かく指定するんですね。
浜田:そうですそうです。
ーー麻里さんの中で、こういうものを表したいということが、それだけ明確になっていた。
浜田:そうですね。毎回そうですけど、今作は特にそうでした。
ーーアルバム全体の構成を考慮して、さまざまなタイプの楽曲を考えて、ふさわしい作家に発注する。
浜田:曲順は最終的に錬るので、これが1曲目とか最初から明確に決まってるわけじゃないですけど、だいたいの読みとしてはあります。
ーー実際に曲ができる前に、どういうアルバムにするか、はっきりとしたビジョンが頭にあるわけですね。
浜田:そうですね。ただ、相手方のシチュエーションにもよるし、できてくるものにもよるので、最初から完全に確定してるわけじゃないですけど、やりとりの中でより近づけていくというか。
ーーだいたい向こうも意図をわかってすぐ書いてくれるものなんですか。
浜田:うーん……まあそういう人もいるし、なかなかうまく伝わらない人もいます。だいたいいつも同じような人たちが残っちゃいますね。特に頑張ってくれた人の曲をもっと良くしてあげたいからなのかもしれないですけど。実際はもっとたくさんの人たちが書いてくれてるんです。
ーーこのアルバムのために用意した曲は何曲ぐらいあるんですか。
浜田:数えてないのでわからないですけど……一時期はそれこそ何百曲も来る時代もありましたけど、今は数十曲ぐらいです。昔はデモテープだけで400曲ぐらい聞いたこともありましたね。やっぱり書きたいと思ってくださる方が多いんですよ、有難いことに。
ーー曲によってはアレンジャーが別につきますね。
浜田:そうですね。基本的には作者がアレンジすることが多いですけど、私の曲(今作では「Lost」「Dark Triad」)は大槻(啓之)さんや増田(隆宣)君に発注しています。大槻さんは私の曲を噛み砕く能力にすごく長けている方なので、これは大槻さんだなと。
ーー「噛み砕く能力」とは、麻里さんの曲の意図をくみ取って、的確に形にしてくれるということですか。
浜田:私の意図も感じてくださってると思いますし。経験が少ない人と比べると、一時代、ヒットソングを一緒に作ってきた感覚というものがありますから。プロデュース感覚に近いものですね。クオリティが高く、かつ掴みのある曲にアレンジしてくれることを期待して。
ーー最近は若い作家も起用されて、だいぶ刺激を受けてるんじゃないですか。
浜田:そうですね。自分の世代とは違う感覚も大事です。最終的に残ってる人は数人ですけど、準備段階ではもっとたくさん若い人に発注してるので。
ーーなるほど。そうして集まった楽曲からさらに厳選したものを煮詰めて完成させたものがこの11曲というわけですね。その楽曲をLAに持っていって現地のミュージシャンにプレイしてもらうわけですが、その時はどういう指示の仕方をするわけですか。
浜田:ベタ付きで(笑)。デモの段階でほとんど決め込んでいっちゃうので、ほぼ完璧なデモを作っていく。それを、各ミュージシャンの個性も出していただきつつ、より良いものにするという形ですね。
ーーデモテープを聴かせて、このまま弾いてくださいと。
浜田:そのまんまが絶対いいと思ってる時は、そう言います。ここは完全にフリーで、その人に任せたいという所はそうお願いして。
ーーデモの通り弾くということであれば、日本で日本人のミュージシャンと録っても大して変わらないのではないかとシロウト考えでは思うわけですが、LAに行って現地のミュージシャンに演奏してもらうことで、何が変わるんでしょうか。
浜田:そうですねえ……自分のお付き合いの範囲の中ではその人がベストだと思うからお願いしてるだけで、それがたまたまアメリカ人でロサンゼルスにいるっていうことなんですね。私のアルバムの核になっているのがグレッグ・ビソネット(デイヴ・リー・ロス、サンタナ、リンゴ・スター、ラリー・カールトン等に参加したこともあるベテランのセッションドラマー。『Sur lie』(2007年)以降の浜田の全アルバムに参加)で、彼に対する信頼感はすごく強いので、やはり彼だな、と。だから“人”ですね。アメリカに行くというよりも。
ーーマイケル・ランドウ(Pink Floyd、マイルス・デイヴィス、ロッド・スチュワート、ジェームス・テイラーなどに参加経験のあるベテランギタリスト)とも付き合いが長いですね。麻里さんにとって初の海外レコーディングとなった『In the Precious Age』(1987年)以来、欠かさず参加しています。
浜田:マイクは完全に安心感もありますし、マイクだったら絶対これ以上のフレーズが出てくるだろうという確信をもって預けて、実際に現場で期待通りのプレイをしてくれる。そういう絶対的な信頼感はあります。
ーーたとえば持っていったデモテープから大きく形が変わったとか、そういうことはありましたか。
浜田:そんなに大幅に変わった曲はないですけど、最後の「Mangata」は、ジェフ・ボーヴァ(ビリー・ジョエル、エリック・クラプトン、ハービー・ハンコック等に参加経験のあるベテランキーボード奏者)のプレイがすごく良かったんです。今回は結構濃密にコラボして、思った上のオーケストラアレンジになりました。それで世界観が広がったというのはあります。曲のテーマを細かく訊かれるので、お話ししたら共感してくれて、静かな波、そして人の葛藤と意志を連想するような素晴らしいアレンジをしてくれました。
ーーLAのミュージシャンのいいところってどこにあるんでしょう。レコーディングの環境も含めて。
浜田:うーん……そうですねえ……単純に技量が、特にドラム/ベースの場合は優れているというのはあります。特にグレッグ・ビソネットは、なんでもできるんですね。ドラマーですが、譜面の細かいニュアンスなんかも初見で読み取ってしまうような、基本的な音楽のアビリティがとても高いんです。ドラマーに特化してるというより、あらゆる意味で音楽的に信頼できる。今回の「Disruptor」なんかも変拍子満載でポリリズムがバースに入っていたりする。作曲したISAO君のアレンジなんですが、これを誰が叩けるんだろうって考えて。やっぱりこれはグレッグかなと思ってオファーしたら、全然苦もなくプレイしてくれました。グレッグ自身は「大変だった、こんなに難しい曲は滅多にやったことないよ」って言ってましたけど(笑)。こなすだけでなくグルーヴ感のあるプレイで、やっぱり凄いなと。(海外のミュージシャンは)そういう単純な能力やタイム感が、特にドラムに関しては高い人が多いかな、と思います。
ーー今回はテクニカルな曲が多いですからね。
浜田:そうなんです。もう1人のドラマーはマルコ・ミネマンというドイツ人ですけど(ポール・ギルバート、ジョー・サトリアーニなどに参加)、もう本当に超絶的なテクニックなんです。手も足も。その辺でよりテクニカルに聞こえるというのはありますね。
ーー麻里さんの楽曲は一時はかなりポップな、あるいはしっとりとした方向に行っていた時期もありますが、ここにきてアレンジも演奏も歌唱も非常に複雑な技巧を凝らしたテクニカルな楽曲が増えていますね。
浜田:うーん……なんて言えばいいんですかね(笑)。難しいことをしたいという発想ではないんですけど、より気持ちを入れられて、より質の高いものを、と目指しているうちに、だんだんそうなってきちゃったんです(笑)。ただもともと変拍子系とか転調とかがすごく好きで。シンプルキャッチーな良さとは対極の音楽的快感としてありえるので。かっこいいと思えるんですね。


自分の在り方のベーシックは主観性と客観性のバランス
ーーこれを聴いて、いろんな意味で限界に挑戦してる感じが凄いと思いました。麻里さん自身は「挑戦」なんてつもりはないかもしれないけど、でもここまでハードルを上げて、しかもそれを楽々と飛び越えていく感じというのは、一種の快感だなと。凄いですよこのアルバム。
浜田:(笑)。ありがとうございます。そうですね。確かにハードルがどんどん高くなっているのとイコールかもしれないですね。
ーーシロウトには絶対立ち入れないプロの領域ですね。カラオケで歌われることを前提として曲を作ってないというか。
浜田:(笑)。してないんですよねえ。カラオケで歌ってもらってナンボとか、そういう風潮が90年代とかありましたけど、ちょっと……いや“だいぶ”ですね。だいぶ違和感を感じてて。歌っていただくことはすごく嬉しいことなんですけど、歌っていただくための曲を作るって発想はまったくないんですよね、私の場合。それは昔から変わらないですね。なので90年代はすごく居心地が悪かった。
ーープロのボーカリストのプライドとして、ちゃんと技術を見せたい、というような。
浜田:技術を見せたい、というよりは、作品ですかねえ。なんか……エンターテインメントとしてシンガーをやっているというよりも、作品をひとつひとつ作っているという感覚が強いかもしれません。
ーーエンタテイナーではなくアーティストであるということですね。自分が納得のいく作品を作るために、自分の歌唱技術やミュージシャンの技術も含めて高いものが要求される。
浜田:そうですね、そういう風になってきてます。高いものにする、という前提があって何かをするのではなく、自然にそうなってきたんですね。
ーーボーカリストの進化とか成長の仕方はいろいろあると思うんです。テクニカルな方向に進化していく場合もあるし、表現力とか味わいみたいなものを深めていくという方向性もある。麻里さんの場合は、どちらかと言えば技術的な面を追求するという方向なんでしょうか。
浜田:結果として確かにそっち系になってるなと思いますね。ラフさとかそういうタイプではないだろうなと感じます。
ーーでしょうね。荒っぽさが味になったりかっこ良さになったりするタイプではない。
浜田:それとはむしろ対極……でもないですけど、わりときっちりと積み重ねていくみたいな。たとえば体調の悪さを反映してるような荒れた声色も一種の情緒感として良しとするような、昔ながらのロックとかブルースみたいなのとはちょっと違いますね。多重録音で緻密に積み重ねていったり、そういうのが好きですし得意だというのはあります。少しずつ重ねて作品にしていくので、きっちりしないとぐちゃぐちゃになっちゃうので。音数もすごく多いタイプなので、一個一個キレイにやっていかないと作品として成り立たなくなっちゃうんですよ。演奏も含めてですけど。
ーーよくギタリストの人が、「昔はとにかく速弾きを追求してたけど、今は速さよりも味わいの方を求めるようになった」と口にするのを聞きますが、麻里さんはそういうタイプではない。
浜田:ギターについては声と同じようにトーンというものがあって、年齢や環境で好みは変わると思いますね。たしかにそういう味わい深さに憧れもありますし、全然ありえると思うんですね。ですけど……まあそうですね……ちょっと逃げでもあるかなと(笑)。そういうミュージシャンの発言っていうのは。
ーーああ、ついていけなくなった人が負け惜しみで言ってるみたいな。
浜田:(笑)。同業者としてはそう思いますけど。
ーー手厳しいですね。でもそれでこそ浜田麻里だと思います。むしろそう言ってほしかった(笑)。麻里さんほどのベテランが未だにそう言えるのは素晴らしいと思います。ではご自分の将来像として、渋いブルースやジャズをしっとり歌うような、そういうビジョンは全くない?
浜田:将来像にはないですけど、でも全くありえなくはないと思います。将来自分がどういう心境になっていくかわからないですけど、たとえばレジェンドなボーカルが亡くなる直前ぐらいに録ったような、ガラガラの鬼気迫る声の歌がすごくかっこいいとか、あるじゃないですか。
ーービリー・ホリデイとか。
浜田:はい。そういうのもありえるかなとは思ったりはします。その瞬間でしか録れないような。そういう壮絶なものには、緻密に作り上げるものは負けてしまいますよ。
ーーでもそれは技術云々ではなく、そのボーカリストの人生とか生き様の問題ですよね。
浜田:そうですね。結果としてそうなるという。
ーー麻里さんは自分の人生や生き様みたいなものは、そんなに強く音楽に反映させるタイプではないようにお見受けしますが……。
浜田:でも、この歳まで女ひとりで仕事に生きてきたことに対しては誇りを持ちたいと思うんです。使える時間のほぼ全てを音楽に使って作品を作ってますから、やはり私の人生とイコールだと思うんですよね。
ーー今回の歌詞を拝見すると、ハードでヘヴィメタリックな曲はちょっと文語調の歌詞で、いかめしい勇壮な感じで怒りや憤りを表しているように聞こえる。でも残りの半分の、バラードっぽい曲やメロディアスな曲は平易な口語調の歌詞で、すごくパーソナルな感じで、しかもすべて別れの歌なんですよね。
浜田:そうなんですよね、うふふふ……。
ーーどうしてこういう歌詞になったんでしょう?
浜田:元々あまりハッピーな曲って歌ってこなかったと思うんです。「Return To Myself」(1989年)などで明るい印象を持たれている方もいるかもしれないですけど、もともと私は結構ダークな世界の方が得意なんで。どちらかといえばウエットでダークな歌詞。
ーー歌詞にはご自分の体験とか、そこから導き出される個人的な感情はどれぐらい反映してるんでしょうか。
浜田:音楽との連動で歌詞の世界を構築していくわけですけど、うーん……ベーシックな匂いだったりは……そうですねえ……70から80%ぐらいは自分じゃないですかね(笑)。今作は完成までに苦しい別れを多く経験して現在に至っているので。いろんな意味で自分の精神的な立ち位置をどう方向づけようかとか、もちろん移籍も含めて、いろんなことがこの2〜3年あったんです。デビュー30周年(2013年)が終わった頃から、もうひとつ自分の壁を超えるためにどういう風な環境で自分はいればいいだろうとか、どういう人たちと仕事をすればいいのか、すごく考え始めて。その結果、この2年は多くの選択をして、あえて別れを選んだ時期にあたります……それをそのまま書いてるわけじゃないにしても、自然に出てきちゃうのかもしれません。今は、それを越えて新たに歩み出していますけどね。
ーーなるほど。
浜田:あとはマイナーコードの曲だとどうしてもそういう世界観が浮かんできちゃうというのもあると思います。音楽的に、マイナーでウエットな哀愁系が自分のひとつのアイデンティティだと思ってますから。曲を書くときも基本的にすべてマイナーコードで、要所要所でメジャー感を入れていくという作り方で何作もきてますね。
ーーふむ。そのダークでウエットな世界は、ご自分の内面の反映なのか、それともご自分の周りの世界の反映なんでしょうか。
浜田:両方ありますね。音がハードになってきたってことと少し繋がるかもしれないですけど、なんらかのフラストレーションみたいなものがきた時に、爆発する。ハードなサイドに寄って、言葉も強くなりダークになる、ということは客観的に見てあるかと思います。やはり音楽は自分の内面の昇華なのかもしれませんね。
ーーさきほど、今回は少し攻撃的な気分になているという話もありましたが、今回のハードな曲の歌詞は、昨今の社会状況や世界情勢への怒りや憤りや不安がすごく反映されていると感じます。
浜田:そうですね。そうした、ふだん考えていることを歌詞に散りばめていくのは、大人のアーティストとして、しなきゃいけないことなんじゃないかと思います。表現者のひとりとして。問題提起を日常的に言葉や文章でするのは私がやるべきことではないと思うんですよね。あくまでも作品の中に時代感を投影していきたいんです。
ーー今「大人のアーティストとして」という言葉が出ましたけど、やはり若いころとはそのへんの意識が変わってきた?
浜田:うーん、そうですね。20代後半ぐらいから徐々にそういう傾向が出てきましたけど、でもここ最近より顕著にはなってきてますね。普通に日本人の大人として、考えるようなことを入れ込んでいきます。ふだん外国人と接しているっていうのもあって、日本人の高潔な民度ってものがすごく好きなんですね、私は。自分もそうでありたいと思うので。そういう意味でのフラストレーションみたいなものを感じる今の日本の匂いっていうのがあって。なのでどうしても書きたくなっちゃうんですよね。日本人としての美しさ、美徳を取り戻したいし、自分はそれをいつまでも持っていたいという思いが出てきちゃう。
ーーここ最近の日本からはそうした美しさが失われている。
浜田:そうですね、結構不思議に感じることが多いかな……たとえばメディアリテラシーみたいなものが、こんなに日本人って低いんだ。みたいに感じたりとか。
ーーメディアといえば、4年ぐらい前にインタビューしたとき、いわゆるソーシャルメディア、TwitterのようなSNSは自分に合わないからやらない、とおっしゃってましたけど、いつのまにか始めてますね(笑)。
浜田:(笑)。そうなんですよ。
ーー浜田麻里というと、メディアやインターネット上での露出が極端に少ないこともあって、やはり神秘のベールに包まれた謎多きアーティストというイメージがありますが、心境が変わってきたんでしょうか。
浜田:いえ、根本は全然変わってないんですけど、あまりにも情報が少なすぎるとみんなに言われるので(笑)。オフィシャルとして情報を流しつつ、たまに個人で書いたりしてます。呟きというよりも、オフィシャルの情報発信のひとつとして。あるいは、誰かが私のことを話題にしてくれたら、それにお応えする、ぐらいの程度ですけどね。
ーーそれでも以前と比べて開かれてきたことは確かだと思うんですが、それによって変わってきたものってあります?
浜田:特には……基本的に私は周りに左右されるタイプの人間ではないので(笑)、でも応援してくださる方々の喜怒哀楽を直接的に、リアルタイムで知ることができる手段なんだなと思いました。
ーーそれによってお客さんが自分に対して何を求め期待してるのか、考えることはありますか。
浜田:日常的にそれは考えますけど、だからといって“求められる自分でいる”ことを良しとしてないというか。
ーー昔からですか。
浜田:そうですね。自分の在り方のベーシックになってるものは何かと考えると、主観性と客観性のバランスだと思うんです。自分の視点、自分個人の情動と、それを俯瞰して見ている眼というか。そのへんのバランスをとるのは、私たちみたいな仕事をする人間には必要だと思いますね。
ーー俯瞰して見ると今の浜田麻里ってどういう状況ですか。
浜田:うーん……何かに迎合する姿勢はあまり似合わないとか……意思の強さは伝わり始めたかなとは思います。見た目と中身が違う。ただその頑なさがネックでもある(笑)。
ーーなるほど。ヒットチャート上の話なんですが、2010年の『Aestetica』以降、アルバムの売り上げがどんどん上昇していて、前作の『Mission』はついに11位まで上がってきてます。2000年代以降ちょっと伸び悩んだ時期もあったと思うんですが、こにきて右肩上がりに上昇している。ご自分でそういう状況の変化みたいなものは実感されてますか。
浜田:そうですね……自分のスタンスとしてはあまり変わってないのでそれほど実感はないんですけど……でも、もっとやらなきゃなと思ってます(笑)。
ーーまだまだもっと、ということですね。
浜田:全然満足してないんで。でも、歳を重ねても、いろんな意味でクオリティを下げることなくやれてきてるかなとは思います。それに対する皆さんの驚きみたいなものはよく読むんですけど……自分としては当たり前のことなんで。あとは……良くも悪くも自分を貫いてきたことがやっと歳を重ねることによって、色眼鏡で見られることなく、普通にフラットな視線で認識していただけるようになったのかなと。ずっと誤解をされていたタイプだと思うので……歳を重ねてお仕事はすごくやりやすくなったと思います。
ーーここ最近メディアでの露出が増えたこともあって、浜田麻里は健在である、健在どころか昔よりも凄くなっていると、みんな改めて認識して驚いたというのがあると思うんです。それが素直に数字に反映している。
浜田:そうですか。じゃあ今度も(メディア露出を)やらなきゃダメですかね。うふふふ。
ーーいや、あまり出過ぎるのも有り難みが薄れるんで、適度なバランスってことですかね。
浜田:そうですね。「Heart and Soul」(1988年)ぐらいの時ですけど、それまでコンサート動員がすごく多かったんです。一般の印象でいうとまだ(浜田の存在は)マイナーだったんでしょうけど、アルバムは結構売れてたし、動員も毎回増え続けていたんです。それで「Heart and Soul」で結構テレビに出だしたんですね。
ーーあれ、NHKのソウルオリンピックのテーマ曲だったんですよね。NHKのオリンピック中継にテーマソングが使われるようになったのは、「Heart and Soul」が最初だったと聞いています。
浜田:そうなんです。そのおかげでもちろんアルバムはもっと売れるようになったしシングルも売れたんですけど、動員は一回下がったんです。ガーンと行くと思ったら、一瞬だけど下がった。それで「Return to Myself」(1989年)でまたがーっと売れたんですけど、そういう難しさがあるんですよね。
ーーどうして動員が減ったんですか。
浜田:“いつでも見られる”って感覚ですね。そういう経験は35年のキャリアの中でいろいろあるので、わりと慎重というか出過ぎないように気をつけるタイプですね。
ーーある程度消費されないと売れないと思うんです。でも消費されすぎると飽きられるのも早くなる。その加減が難しいということでしょうか。
浜田:そうなんですよね……。
ーーでも失礼ながら浜田さんぐらいのキャリアのアーティストがここに来てぐんぐん売り上げを伸ばしているというのは珍しい例だと思います。しかも音楽的に全く妥協することなく、さらにカッティングエッジな音楽をやっている。
浜田:若い時は、この歳でこんな音楽をやっててこういう気持ちでいる、というのを想像できなかったんです。そういう意味では……想像を超えた感じではありますね。
ーー若い頃は、30年後、35年後にどういうシンガーになってると思ってました?
浜田:スタジオシンガーに戻ってるだろう、とか……もしかするとジャズとか、そっちに行ってるんじゃないかぐらいに20代の頃は……30代でもそうかな……思ってましたね。歌は歌ってるだろうなとは思ってましたけど。
ーーああ、でも若くて勢いのある時期は、怖い物なしというか、いつまでもこのイケイケの時期が続くと思ってしまうものじゃないんですか。
浜田:あんまりそういう感覚はなかったんですよ。子供の頃から音楽活動面では結構苦労が多かったんで(笑)。なのでその状況に有頂天になったりすることはまったくなかったですね。それに、その時の自分がすごく売れてたとしても、同じ自分で居続けるのが面白くないんですよね。脱皮してまた違う自分になろうとする。そのつど(それまでの自分を)壊してきた気がするんですね。いつも“破壊と再生”って言ってるんですけど。ある程度満足されてしまうと、それを壊してもう一回いちから積み上げていこう、みたいな。
ーーなるほど。今作は一聴してのインパクトが強いしアレンジも楽曲も歌唱もバラエティに富んでいて、しかも非常に攻めている。ここ数年で浜田麻里がやってきたことの完成形という感じもあります。でも今のお話だと、その完成した自分の音楽をさらに打ち壊して前に進んでいくこともありえると。
浜田:私の性格だと十分ありえると思います……。今は考えていなくても。
ーー今作は自分の音楽の理想に近いと言えますか。
浜田:いつも一生懸命作ってはいますけど、かなり手応えとしては高い方ですね。ただ100%満足っていうのはないんです、私の性格は。もうちょっと時間があれば良かったな、と今も思ってます。ミックスまで自分でやるので、ミックスのところとか。十分やったつもりではあるんですけど、やっぱり〆切というのがあって。もう一カ月ぐらいあったら良かったのに、と思いますけど。
ーー今作の曲はライブでやりがいがありそうですね。
浜田:そうですね。ライブではずっとファミリー的なバンドできましたけど、今回は半分ぐらいメンバーチェンジすることを自分で決断しまして、新たなミュージシャンでやります。まだリハーサルに入ってないので、今みんな一生懸命練習してますけど(笑)。ツアーの最終日は東京公演になる予定なんですけど、まだ会場が決まってないんです。できれば武道館に戻りたいんですけど、会場が取れるかどうかわからないんです。武道館に限らず、今都内で会場を抑えるのは大変なんです。前回は東京国際フォーラムで2日間やりましたけど、今回はフォーラムも一切取れなかった。
ーー今全体的に会場不足とは言われてますね。
浜田:はい。作品よりもライブにシフトするアーティストが増えてるって状況と、あとは単純に会場が足りない。それから東京オリンピックの影響もかなりあるみたいで。ほんと大変です。一時期……5年ぐらいの間、武道館を中心に毎回やってた時期があるんで、そこに戻ってきたとなると、ファンの人もきっと喜ぶし、自分のマインドにも結び付いていくんじゃないかという期待もありますし。やるんだったら今しかないかなと思ってたんですけど、状況が許すかどうか。35周年のアニバーサリーなのでなんとかやりたいんですけどね。

(取材・文=小野島大/写真=池田真理)
■リリース情報
『Gracia』
Produced & Directed by Mari Hamada
発売:2018年8月1日
価格:【通常盤】¥3,000(税抜)
【初回限定盤】¥4,200(税抜)
※CD + ボーナス・トラック入CD + DVDの3枚組、スリーブケース入り
〈収録曲〉
1.Black Rain
2.Disruptor
3.Orience
4.Zero
5.No More Heroes
6.Lost
7.Melancholia
8.Right On
9.Heart Of Grace
10.Dark Triad
11.Mangata
初回限定盤付属CD
1.Seventh Sense
初回限定盤付属DVD
1.「Black Rain」Music Video
2. Music Videoのメイキング
〈参加ミュージシャン〉
Drums:Gregg Bissonette, Marco Minnemann
Bass:Leland Sklar, Billy Sheehan, Philip Bynoe
Guitar:Michael Landau, Akira Takasaki, Paul Gilbert, Chris Impellitteri, Michael Romeo, Chris Broderick, Takashi Masuzaki
Keyboards:Jeff Bova, Derek Sherinian, Michael Romeo, Takanobu Masuda, Masafumi Nakao
Engineered by Bill Drescher

