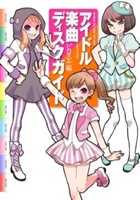ザ・ピーナッツからBABYMETALまで……11人の論者がアイドル楽曲の43年史を語る
音楽
ニュース

 イベントは、新宿ロフトプラスワンにて行われた。
イベントは、新宿ロフトプラスワンにて行われた。3月15日。新宿ロフトプラスワンにて、『アイドル楽曲ディスクガイド』(アスペクト)の刊行を記念するトークイベントが開催された。
ハロプロ楽曲大賞、アイドル楽曲大賞の主催者として知られるピロスエ氏が編者となった「アイドル楽曲ディスクガイド」は、1950年代から現在の2010年代までのアイドルとアイドル的な女性歌手のシングル850枚+アルバム100枚の950タイトルのレビューを収録したものとなっている。
2010~12年からはじまり、50年代から2000年代までの歴史を振り返りながら、間に井上ヨシマサ、tofubeatsのインタビューを挟み、最後に2013年を振り返るというボリュームのある構成の本書を読むと、アイドルという概念がいかに幅広く、様々なものを内包していて、その全貌を捉えることがいかに困難なのかがよくわかる。
トークイベントは二部構成でアイドル史を振り返るものとなっており、ピロスエ氏と本書に執筆したライター諸氏が登壇。雑多で混沌とした戦後のアイドル史を時系列順に語ることで歴史的な流れを整理する談話となった。
第一部では50~60年代のプレアイドル期から80年代後半まで。第二部では90年代から現在まで語られた。以下はその簡単な概要である。
さやわか「敷居の高さが今のアイドルとは違う」
第一部 登壇者 ピロスエ、岡島紳士、さやわか、栗原裕一郎、原田和典、岩切浩貴、【VJ】fardraut films
●1950~60年代(美空ひばり、江利チエミ、中尾ミエ、奥村チヨ、黛ジュン、吉永小百合、山本リンダ、ザ・ピーナッツ etc)
原田:この時代は、いわばスターの時代で、テレビに出る歌手は天上人だった。
栗原:テレビ放映 が53年。59年に「ザ・ヒットパレード」という歌番組が開始される。ロカビリー歌手だったミッキー・カーチスや長澤純、当時デビューしたばかりのザ・ピーナッツが出演していた。そこでカバーポップスの時代になって洋楽のカバーを歌う番組がヒット。そこからアイドルの概念が生まれたのではないか? 一方で当時は映画の時代で、吉永小百合はそこから出てきた。
さやわか:敷居の高さが今のアイドルとは違う。
栗原:『山口百恵→AKB48 ア・イ・ド・ル論』(宝島社新書)の北川昌弘さんは「アイドルとはテレビのものである」と言っている。テレビが登場したことでアイドルが登場した。また、当時の女性歌手は譜面が読めた。プロのミュージシャン。 進駐軍の外国人相手に歌っていたような人たちだった。
原田:英語の歌が日本でヒットしてたのは、今、考えると凄い。
●70年代前半(南紗織、天地真理、山口百恵、麻丘めぐみ、アグネスチャン、太田裕美、キャンディーズ etc)
ピロスエ:アイドルの歴史は南紗織の「17才」からスタートした。
栗原:彼女のデビューは71年、沖縄本土返還の一年前だった。政治情勢が変わると歌手の傾向も変わる。
岩切:この頃から、ポップスを書ける人が増えてきた。カバーを繰り返す内に和製ポップスが成熟していく。専属作家制度が崩壊したことが大きい。
ピロスエ:太田裕美はアイドルなのか?
栗原:この曲までは自分でピアノを弾いていて、他のアイドルに楽曲を提供していた。でも歌うのは他の人が提供した曲で自意識はシンガーソングライターだった。「木綿のハンカチーフ」ではじめてハンドマイクで歌った。
ピロスエ:あとは、後のグループアイドルに影響を与えるキャンディーズが73年に登場する。
●70年代後半(ピンクレディー、岩崎宏美、大場久美子、石川ひとみ、榊原郁恵 etc)
ピロスエ:デビュー年で分けているけど、70年代後半に人気が絶頂だったのは山口百恵。
さやわか:子どももいるし、セクシーもあるし、宇宙人もいるし、70年代後半になると、今のアイドルの概念に近くなる。
岩切:当時のアイドルファンは大学生以下で、小中学生から上は高校生まで。
栗原:いい年過ぎてアイドルを聴いていると、頭悪いんじゃないのと思われてたんじゃないですかね?
原田:大場久美子はピアノで表現できないフィーリングがいいですよね。僕は北海道出身でNHKと民放が数局しかなくて全部、後追いだった。地方によって受信できたテレビ番組の違いが大きかった。
岩切:当時は歌番組自体が細分化されていて、アイドルはワイドショーや天気予報でも歌っていた。
栗原:フォークもありニューミュージックもあり、音楽的にも充実していた時代。テレビを見ていたら様々な歌が流れていて、ポストモダン状態だった。
岡島「おニャン子がいろんなものを壊した」
●80年代前半(松田聖子、松本伊代、伊藤つかさ、薬師丸ひろ子、原田知世、岡田有希子、中森明菜、小泉今日子 etc)
栗原:前年の79年は暗黒の時代だった。誰一人残ってない。
岩切:中森明菜は山口百恵のフォロワー。
栗原:レコード業界は百恵的なものを売り出したかったが、松田聖子の登場で空気がガラッと変わった。
さやわか:今まで百恵的なものだったアイドルが聖子のぶりっ子的なものに傾いた。
栗原:薬師丸ひろ子や原田知世は角川映画の女優。
岩切:だから角川の雑誌「バラエティ」が独占していた。
栗原:角川春樹は映画とテレビと全部使って、本を売ろうとしていた。メディアミックスの走り。しかし、角川映画にとって、アイドルは副産物だったのではないかと思う。
さやわか:小泉今日子の「なんてったってアイドル」(作詞:秋元康)でアイドルがメタ化。そして、おニャン子クラブで素人化。この二つがこの時期に同時進行している。
●80年代後半(オールナイターズ、おニャン子クラブ、斉藤由貴、南野陽子、浅香唯、中山美穂、森高千里etc)
栗原:おニャン子で「もう、いいや」と思った。今までのアイドルは親衛隊文化(ヤンキー)だった。おニャン子以降、ファン層がヤンキー的なものからオタク的なものになっていった。
岡島:おニャン子がいろんなものを壊した。おニャン子から入った人と離れた人がいる。
さやわか:うしろゆびさされ組はアニメ『ハイスクール!奇面組』とのタイアップ。『スケバン刑事』(斉藤由貴、南野陽子、浅香唯)、『ママはアイドル』(中山美穂)などテレビ番組主導になっていて、アニソンやテレビドラマの番組タイアップが増えていく。
ピロスエ:南野陽子は、今の楽曲派の人たちにも評価されそうな感じがありますね。
栗原:森高千里の「17才」(南紗織のカバー)で歴史が一巡する。ただ、当時はアイドルとは思っていなかった。
岩切:森高は系譜としては太田裕美に近い。
栗原:Winkや森高千里は現代アートみたい。昭和の終わりで時代の変わり目。小泉今日子以降、アイドルがメタ化して、ベタなアイドルは成立しない。80年代後半はメタアイドルの時代。
岩切:音楽史的には作家がそろった時期。ロック系の人が増えた。おニャン子にはライダーズ系が入っている。楽曲的には豊かで小室哲哉も出てくる。みんな面白いことをやろうとしていた時代で、お金もあった。
●第一部 まとめ
岩切:アイドルポップスはなんでもあり。80年代までは、日本の景気と並走している。
さやわか:その後、経済とエンタメは反比例していき、社会の動きとシンクロしなくなっていく。これ以降、音楽産業はバブルを迎えることになる。
宗像「元号を広末にしたい。1997年は広末元年」
第二部 登壇者 ピロスエ、岡島紳士、鈴木妄想、田口俊輔、DJフクタケ、宗像明将、坂本寛、【VJ】fardraut films
●90年代前半(東京パフォーマンスドール、乙女塾、高橋由美子、ねずみっ子クラブ)
ピロスエ:おニャン子が解散して以降、「アイドル冬の時代」になったと言われているけど、本当にそうだったのか疑問視している。
鈴木:グループ数自体は減っていない。ただ、単純にメディア露出がガクンと減った。
田口:音楽シーンがバンド寄りになったため、相対的に露出が減った。その影響はある。
坂本:アーティストの方がスターやアイドルよりもカッコよくなってきたのがバンドブーム以降。その流れを踏まえて小室哲哉が活躍する。
岡島:おニャン子で素人化してアイドルが壊れて、森高とかWinkでメタ化した末期感というか何でもアリ感は今に通じる。
鈴木:東京パフォーマンスドール(TPD)は、おニャン子のカウンター。原宿で定期ライブをやっていた。
岡島:TPDはCDセールスこそ振るわなかったけど、日本武道館と横浜アリーナでコンサートを成功させた。今のライブアイドル全盛の流れに続いています。
坂本:おニャン子は一般まで巻き込んでいたけど、乙女塾は一回り落ちて、おニャン子の出がらし的に見られていた。TPDも今聴くとカッコイイけど、当時としては先鋭的で、一般のリスナーには受けが悪かった。
ピロスエ:この頃から、グループアイドルが増えていく。
坂本:完全なソロで成立していたのは森高千里までで、それ以降は松浦亜弥までいない。
フクタケ:その中で、当時の高橋由美子は特別な位置づけ。最後のアイドルと言われていて、一人で支えていた。
宗像:ねずみっ子クラブは、おニャン子以降の試行錯誤の始まり。このあとAKB48まで、中々爆発しない。
●90年代後半(安室奈美恵、MAX、SPEED、吉川ひなの、広末涼子、モーニング娘。etc)
坂本:SPEEDが当時の小学生に与えた影響は凄かった。安室奈美恵やSPEEDは、アイドルだけどアーティスト寄りの売り方をしていて、アイドルと呼ばれたくないみたいなところはあった。今と真逆。
フクタケ:吉川ひなのは、ちょっとメタでキャラ先行。「ハート型の涙」は、彼女のキャラを朝本浩文が面白がって作ったもの。
宗像:この時代、広末がいかに俺たちを救済したか。
ピロスエ:歌手デビューは97年。この年は『新世紀エヴァンゲリオン』の劇場版もあっていろいろとエポック・メイキングな年。90年代後半は、エヴァンゲリオン、広末、モーニング娘。など、僕たちの青春時代ということを差し引いても激動の時代だった。
宗像:元号を広末にしたい。1997年は広末元年。今は広末17年を生きている。僕と岡島さんは当時、広末のメーリングリストに登録していた。広末の影響で今がある。
ピロスエ:宗像さんと岡島さんが広末で人生が変わったのなら、僕と坂本さんはモーニング娘。の影響が大きい。
坂本:インターネットも絡んでいて、テキストサイト更新者から商業ライターへという流れがあった。
宗像:取材をしているとアイドルを目指したきっかけがモーニング娘。というアイドルはすごく多い。
坂本「渋谷系以降聴くものがなかった人が『LOVEマシーン』で転んだ」
●00年代前半(タンポポ、プッチモニ、ミニモニ。、松浦亜弥、Whiteberry、ZONE、dream、杏さゆり、星井七瀬 etc)
岡島:ハロプロ勢の勢いが凄い。ファンのコミュニケーションがネットを通じて盛んになった。
宗像:Webカルチャーの面から見てもハロプロは凄かった。違法ダウンロードが広まった時期だったけど、それでもCDは売れていた。また、ゼティマはCCCDを最後までやらなかった。その辺のストロングスタイルも素晴らしい。
岡島:アイドルに興味がない人がハロプロの音楽から入ってきた。
坂本:渋谷系以降聴くものがなかった人が「LOVEマシーン」で転んだ。それ以前のモーニング娘。はダサかったが「真夏の光線」くらいから評価が変わったけど、売上は伸びなかった。ダンス☆マンが参加することで当時の音になっていて、「LOVEマシーン」で吹っ切れた。
フクタケ:DJ文化が東京周辺へ定着した時期だった。一方で、ポストSPEED的なものを模索したavexは、後に残るものを育てている。
宗像:BEE-HIVE(アミューズ出身のアイドルグループの総称)は報われなかった。毛色の違うPerfumeだけが生き残った。
フクタケ:00年中盤は杏さゆりや乙葉といったグラビアアイドルがアイドルの代表の時代だった。
●00年代後半 (Perfume、AKB48、Berryz工房、℃-ute、真野恵里菜、中川翔子 etc)
ピロスエ:世間的にはハロプロのピークが過ぎた時期。それでもハロプロにこだわるか他のアイドルへ推し変するのかファンは迫られた。
宗像:Perfumeは「ポリリズム」のブレイクによって報われた。ここに至るまでが長かった。
岡島:中川翔子の功績は色々と多い。ネットランナーがBLOGをやらせた。
坂本:AKB48は「スカート、ひらり」の頃に劇場で見た。当時は「また、パンツ見せてるのか」って感じだった。
宗像:陸海空の自衛隊の協力で作られたAKB48の「RIVER」のPVは震災前(09年)だからできたもの。平和じゃないと作れない。
フクタケ:この頃の秋葉原はカオスだった。歩行者天国のいたるところでライブがおこなわれていた。
岡島:ホコテンのアキバ系アイドルによるストリートライブの熱狂が、ディアステージ、そしてでんぱ組.incにつながっている。
フクタケ「ブルーオーシャンはミュージカルや舞台」
●2010年代初頭(ももいろクローバー、東京女子流、9nine、乃木坂46、でんぱ組.inc、BABYMETAL、BiS、アップアップガールズ(仮)、天野春子「あまちゃん」etc)
ピロスエ:他の時代に較べて多様性がありますね。
宗像:「潮騒のメモリー」は2013年を意識した80年代オマージュとしてよくできている。
フクタケ:ロコドルやアジアといった中心じゃないところから、いいものが生まれている。その一方で、中央が空いていてドーナツ化現象が起きている。
岡島:地方にいてもいい作品が作れる環境が整った。ロコドルでもアジアでも場所に関係なく、いいものが出てくる。
坂本:それと引き換えに音楽が安く作られているという問題もある。売れるもの程、多様性がなくなっている。
宗像:今は現場が多い。スケジュールカレンダーを見ないと、自分の好きなアイドル以外の動向がわからなくなっている。
●全体 まとめ
坂本:楽曲が流行りものの形態に規定されているのを感じる。カラオケや着メロの影響によって楽曲の作り方が変わってくる。
栗原:カラオケ以降、コミュニケーションツールとしての役割が強くなっている。
岩切:お金がないとできることとできないことがある。昔の歌謡曲やアイドル楽曲のレコーディングはお金があるからできたことがたくさんあった。それは大きい。
宗像:ずっと見ているとアミューズの大里会長は怖い。そのアミューズがソロアイドルの武藤彩未を売り出しているということはグループからソロへというゆり戻しの流れが来くる兆候かもしれない。
フクタケ:ブルーオーシャンはミュージカルや舞台。新生TPDや乃木坂46がやっているけど、その流れができてくれればと思う。
岡島:BABYMETALがビルボードのチャートに入ったけど、接触なしでも、他と差別化されたコンセプトを固めてコンテンツがしっかりしていてライブが楽しければ受け入れられる。AKB、ももクロがブレイクして、ハロプロに勢いが戻りつつあり、BABYMETALらも後に続いている。要はアイドルの市場がそれだけ拡大し、安定し始めたということ。今後も握手会は安価で始められるので基本として進んでいくのだろうが、楽曲のバリエーションは、これからも増えていくと思う。さっきの多様性の話と繋がるけれど、CDの売り上げ自体の落ち込みが進む中では、チャートの上位曲だけを見ていてもアイドル楽曲全体のシーンは把握して行けなくなる。ライブアイドルはCDの売り上げだけでなく、ほとんどはチェキや握手を含む物販で回しているから。ビジネスとして最低でも数年は回っていたり、数百人規模のワンマンができるグループであるなら、無視はできないはず。そうしたグループが無数に出現して行けば、単に個人で「アイドル楽曲シーン全体を把握すること」が難しくなるだけで多様性は進んで行くし、もう既にその流れは始まっている。
フクタケ:運営の母体の基礎体力が重要になってきている。育成も含めて時間をかけられるところが残っていく。ロコドルは、やっている方の情熱で回っている側面もあるけど、ビジネスにならないという所は引いてきている。
宗像:不景気だけど、アイドルのマーケットは金を使うので、なんでも有りの盛り上がりがある。ただ、チャートに見えているのは上澄みの部分で、ライブの方はもっとグチャグチャなことになっている。アングラで揉め事が起きているのを見ていると、バンドブームの末期に似ている。とはいえ、バンドブームの時よりはマーケットが固まって広まっている。この本が出るのもその証明で、そこまで悲観的になる必要はないと思う。
ピロスエ:まとめとしては、「俺達の戦いはまだまだはじまったばかりだ!」ってことで。個々のヲタ活をがんばってきましょう。
(取材・文=成馬零一)
■書籍詳細情報
ピロスエ・編『アイドル楽曲ディスクガイド Idol Music Disc Guide 1971-2013』
発売日:2014年2月27日
発行・発売:株式会社アスペクト
判型:A5判(オールカラー256ページ)
定価:2500円+税