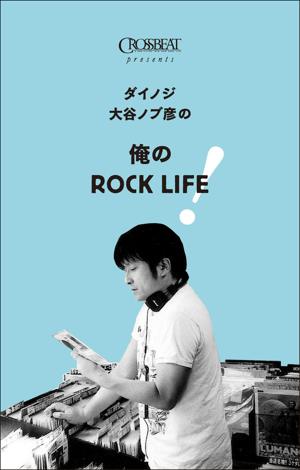ダイノジ大谷がロックを語り続ける理由「こっちだっていい曲だ、バカヤローって足掻きたい」
音楽
ニュース

 取材前夜は『オールナイトニッポン』の放送日だったにも関わらず、熱く語ってくれた大谷ノブ彦氏。
取材前夜は『オールナイトニッポン』の放送日だったにも関わらず、熱く語ってくれた大谷ノブ彦氏。お笑い芸人として数多くの番組・舞台に出演しつつ、ロックを軸としたポップ・ミュージックへの造詣の深さで活動の場を広げる、ダイノジの大谷ノブ彦氏。最近では人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』(水曜・第一部)のパーソナリティとして、音楽の”評論芸”やインタビューにも力を注ぐ大谷氏が、洋楽専門誌『クロスビート』誌の連載コラムをまとめた書籍『ダイノジ大谷ノブ彦の 俺のROCKLIFE』を上梓した。音楽のジャンル・嗜好が細分化する今、大谷氏が情熱的にロックを語り続ける理由とは何か。インタビュー前編では、自身のリスナー遍歴を踏まえた音楽シーン分析、音楽評論に対する考えを大いに語った。
――今回の著書『ダイノジ大谷ノブ彦の 俺のROCKLIFE』は『クロスビート』の連載コラムが元になっていますが、連載中はどんなことを意識して執筆していましたか。
大谷ノブ彦(以下、大谷):基本的に、音楽そのものの評論とか批評は自分にはできないので、これまでの体験を通して、好きな音楽について語るだけなんですよね。ただ、読者がそこで紹介しているアーティストやエピソードを知らなくて、その音楽を聞いたことがなくても、本を読み終わったらなんとなく聴いてみたいな、と思える感じは目指しています。何を聴いていいかわからない人たちに、専門用語以外の言葉を使って、良い音楽をわかりやすくシェアするということですね。さらに、この本が音楽の評論とか批評の入り口になれば、なお嬉しいです。
――『ロッキング・オン』などでは昔から体験談を交えた批評文を投稿するコーナーがありますが、大谷さんの文章はそのようなタイプの音楽ガイドとしても成立しているように思います。
大谷:実は僕、過去に3回くらいロッキング・オンに載っているんですよね。エレファントカシマシについて書いて。山崎洋一郎さん、兵庫慎司さん、鹿野淳さんなどが中心となって執筆していた時代はかなり読みました。
――投稿コーナーに代表されるような「音楽を語る」文化は脈々とブログなどでも続き、最近は個人が発信する時代になってきました。
大谷:その中で、個人の感想と作品のクオリティのバランスが崩れてきている気はしますね。良い作品でも、なかなか素直に受け入れられる環境がないというか。たとえば、先日ラジオで対談した銀杏BOYZの新しいアルバム『光のなかに立っていてね』のラストには、「僕たちは世界を変えられない」という曲があって、そのイントロがスーパーで流れている音楽なんですよ。また、MGMTの「kids」という曲は、カラオケのトラックを流して、3流ポップスのパロディをやったら、バンドの代表曲になっているんですね。音楽って、そういうふうにある意味ではチープな表現をクールなものとして解釈することもできて、それはとても素敵なことだと思うんです。ただ、そういう感覚を今の中学生の男の子とかに言葉で伝えるのはすごく難しい。個人の発信が増えた分、そういった文脈の深い作品が正当に評価されにくくなっていて、表層的にわかりやすいものが受けやすくなっているというか。
――大谷さん自身は、音楽に詳しくどっぷりハマっている人というより、音楽にハマりかけている人に語りかけようとしていると?
大谷:そうですね。僕は何度かフェスにDJとして出させてもらっていて、そこでもそういったアプローチを心がけています。邦楽のDJブースって昔と違っていろんな曲がかからないんですよ。盛り上がる曲が決まっていて、リスナーも知っている曲で盛り上がりたいという人が多い。DJはそのためのツールみたいになっていて、同じ曲を何回もかける傾向になっていく。ハイスタの「Stay Gold」何回かかるんだ?みたいな(笑)。だから、「Stay Gold」をかけるにしても、違う聴かせ方できないかとか、今のアークティックモンキーズとかをどうやって入れて、「いいじゃん」って思わせるかっていうことを考えている。でも、終わったあとは結局、Twitterで「やばかった Stay Gold」とかしか書かれないんですよ。アクモンかけたってことはだれも評価してくれない。でも、そこは足掻きたい。「こっちだっていい曲だ、バカヤロー」って言いたい。
――それは、ラジオでリスナーと向き合う時に、大谷さんがあえて普通はかけないような曲をぶつける感じと通じますね。
大谷:罠をしかけて、かかったら「この曲もいいじゃん」って思わせたいです。たとえば僕は、twitterで時々、ジャニーズのことを音楽的に評価するんですね。そうすると、ものすごくRTされるんですよ。だから、RTを増やしたかったら、 ずっとジャニーズのことをつぶやけばいいんです。でも、それをやったら僕じゃなくなるし、逆にジャニーズの音楽を冒涜することになると思う。本当に真面目に聴いているのなら、彼らがどういうイメージでその音楽を作っているかというところまで向き合わないとだめだから。罠っていうと語弊があるかもしれないけど、どの音楽もフラットに聴いてもらって、そこから普段は聴いていない曲のかっこ良さを発見してもらえたらいいなと思います。
――なるほど。ここからは、本のテーマにもなっている大谷さんの音楽遍歴を探ってみたいと思います。そもそも音楽にハマったきっかけは?
大谷:中3の時にバンドブームが来るんですよ。クラスのみんなBOOWYやレベッカなんかを聴いていた。で、その頃に生まれて初めて友達の家に泊まりに行って、友達にパンクロックを教えてもらったんです。純粋に「こういうやり方あるんだ!」ってびっくりしました。全然、歌うまくないし、テレビで流れてる歌謡曲の方が芸として優れているのに、すごくかっこいい。で、みんなが好きだっていってるバンドじゃなくて、自分だけのバンドがほしくなった。それが自分のパンク的な活動になると思って。だからエレファントカシマシとか群馬のROGUEとか聴いて、これみんな好きにならないだろうから俺のバンド、っていう感じで、変わったバンドが好きになっていったんです。さらに、そのアーティストたちが影響を受けた洋楽を聴くようになって、 誰かがエルヴィス・コステロのことをレコメンドしていたんですね。スーツにメガネかけて漫才師みたいな格好しているのに、パンクロックで渋かった。で、これも俺のもんだなって思って、そこから一気に、スリッツとかトーキングヘッズとかどんどん掘り始めて、もう音楽が楽しくてしょうがなくなっていった。それが高校生の時くらいですね。
――かなり掘り下げていますね。大学時代はどうでしたか?
大谷:僕、大学で全然しゃべらなかったんですけど、唯一仲良かった2人がいて。ひとりが福岡出身でベタな博多人なんですよ。いまどきリーゼントみたいなやつで、めんたいロックとか教えてくれて。もう一人は東京の吉原が実家で、見かけはちょっとしょぼいやつなんだけど、とにかく音楽がすごく好きで。当時、彼に対して、「プリンスはあんまり好きじゃない」っていったら、すごい剣幕で怒ってきたんですよ。
――はははは。
大谷:そこから彼は音楽の師匠という感じになっていきました。エレファントカシマシのライブもそいつと行った。僕が持っているものと彼が持っているものを交換しあうようになったりして、そのうち授業のたびに「これ聴いた?」みたいな感じになりましたね。それから、御茶ノ水のレンタル屋のジャニスに行ったり、渋谷の中古レコード屋を回ったり……。20代前半は、お笑いライブとレコードとライブ、あとは映画館。わかりやすいですね(笑)。
――当時の自分を含めた同世代を振り返ると、ロックにしても文学にしても映画にしても、命がけといった心持ちでカルチャーに向き合っていたような気がします。90年代前半という時代性もあったのでしょうか。
大谷:あの時代の人たちは、世界を変えてやろうって気概で、楽器を持ったり、映画を撮ったり、文章を書いたりしていました。ただ、95年にオウムの事件があってからは、明らかに風潮が変わったと思います。というのも、オウムの人たちの精神性って、サブカルチャーにハマる人たちと、実はそれほど差がなかったのではないかと。彼らは世界を変える方法として、ロッキング・オンや映画ではなく、麻原を信じたことで、結果的に人殺しをしてしまった。あれ以来、カルチャーに向き合っていた人たちにとっても、今まで信じていた言葉が一気に重くなってしまいました。スチャダラさんが、 ものすごくシリアスなアルバム出したりとか、そういう風に変わっていった。ただそんな中、小沢健二だけが天使の羽つけて、すごいアホなふりをしてテレビに出て、自分を王子様とか言ったりしていました。あれは、カルチャーに煌びやかな世界を取り戻そうっていう意味合いがあって、「life is coming back」ってことなんだろうと思います。それってすごくコメディ的ですが、熱いですよね。一見バカみたいに見えるけれど、実は鋭い批評性がある。そういう人だけが時代を変えられるような気がします。
――大谷さん自身、90年代後半から芸人として活動されていく中で、音楽との距離感はどう変わりましたか。
大谷:95年以降は1回「自分がやってきたのはオウムと同じことだった」という風になっちゃったんです。そんな中、北海道を拠点に活動していたブラッドサースティ・ブッチャーズやイースタン・ユースが、東京のライブハウスで演っているのを観る機会があって。当時はバンドブームも終わったところだったし、ほとんど人がいなかったんですよ。でも、僕にはものすごい衝撃だったんです。90年代の後半くらいから、ギターウルフとかハイ・スタンダード、ブラフマンとかが出てきました。ストリートで洋楽のコンプレックスとは別のところで生まれているユースカルチャーが、ライブハウスで一気に生まれてきたんですね。そのうちフジロックが始まりました。
――そこで大きな変化を感じたと。
大谷:舞台が変わった感じですね。フジロックはある種の夢みたいなものが叶っちゃったという感覚もあった。やはり1回目、2回目のフジロックの衝撃はすごかったですね。
後編:ダイノジ大谷が提言する、これからの音楽サバイバル術に続く
(取材=神谷弘一/編集協力=梶原綾乃)
■書籍情報
『ダイノジ大谷ノブ彦の 俺のROCK LIFE!』
価格:1,400円(税込み定価1,470円)
発売日:12月20日
人気ラジオ番組『オールナイトニッポン』(水曜・第一部)や『Good Jobニッポン』(月〜木)のパーソナリティを務める大谷ノブ彦(漫才コンビ、ダイノジの一人)の、クロスビート誌(現在は休刊)の連載「俺のROCK LIFE!」をまとめた一冊。単行本化に当たり、大谷がロックと向き合う姿勢に迫ったインタビューや、本人による「人生の10枚」の選盤/解説なども収録。