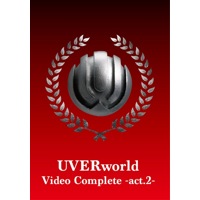UVERworld、マニピュレーター加入の意義とは? バンド編成から読み解くロックシーンの変化
音楽
ニュース

正式メンバーにサックス/マニピュレーターの誠果を加え、6人体制となったUVERworldが4月1日、渋谷duo MUSIC EXCHANGEにてライブを行った。
誠果がステージに登場すると、会場からは大きな歓声が。ボーカルのTAKUYA∞はライブ終盤のMCで、「俺と誠果は、UVERworldと同時にボーカル、サックス・マニピュレーターを始めて、UVERworldと一緒に成長してきた。誠果が戻ってくるって発表したあの日、俺たちはうれし泣き出来るくらい幸せな事だった」と、14年前にバンドを組んだ当時のことを述懐した。
 当日のライブは、700人という限られた観客の前で行われた。
当日のライブは、700人という限られた観客の前で行われた。2005年にメジャーデビューして以来、オーソドックスな5人編成のロックバンドとして活動してきたUVERworldだが、前身のSOUND極ROADでは誠果も正式メンバーだった。メジャーデビュー後、誠果はサポートメンバーというポジションで同バンドを支えてきたが、ここにきて再び正式メンバーとなった背景には、どんな事情があるのか。日本のロックシーンに詳しいライターの冬将軍氏は、次のように分析する。
「UVERworldのサウンドはいわゆるハードロックが土台としてあると思うのですが、ギターソロなどを重視するテクニカルな演奏ではなく、どちらかというとバンドとしてのアンサンブルを重視するタイプで、ミクスチャーロック的な色が濃い。そうなってくると、サウンドに彩りを与えるマニピュレーターの役割は大きくなってきます。マニピュレーターは基本、打ち込みのシンセサイザーやシーケンスなどをプログラミングする人ですが、コンピューターを扱うという部分から編曲やレコーディングエンジニア的なポジションも担う場合もあります。かつてライブでの同期モノと言えばリズムトラックを流し、それに対しバンドが合わせていくのが普通でしたが、昨今では逆に生バンドのライブ感に合わせてマニピュレーターがそういったシーケンスなどを制御していきます。バンドのテンションや、ライブの流れのタイミングを見計らっていく。エンジニア要素とバンドマン要素を持ち合わせなくてはならない重要な役割で、近年どんどん注目度を増しています。今回、同バンドにマニピュレーターが加えられたのは、バンドとしてのサウンドを拡げることと同時に、多くのリスナーがその役割の重要さを認識してきたことの現れなのかもしれません」
シンセサイザーやシーケンサーなど電子楽器は、古くは70〜80年代頃からニューウェーヴやテクノポップなどのジャンルで多用されるようになった。同氏によると、その後のMIDI機器やDTMの発達とともに、90年代にはhideやTHE MAD CAPSULE MARKETS、あるいはDragon Ashといったロックミュージシャンが積極的に電子楽器を導入してきたことが、マニピュレーターの存在感を高め、日本のロックシーンに新たな可能性をもたらしたという。さらに、UVERworldの場合、「誠果さん自身がプレイヤーとしての役割を果たしていることも見逃せない」と、同氏は指摘する。
 サックス/マニピュレーターの誠果。
サックス/マニピュレーターの誠果。「レコーディング現場はもちろん、ライブにおいても客席から見えない場所、ステージ袖やギターアンプの後ろなどにサポートとして参加しているマニピュレーターが実は多くのバンドにいます。ただ誠果さんの場合は、マニピュレーターであると同時にDJ的なポジションとして、サックスプレイヤーとして、ステージに立っていました。それゆえ、UVERworldの音楽に独自の色を添えると同時に、ライブにおける存在感と重要性がファンからも認知しやすかったという部分もあるでしょう。現場では、すでに第六のメンバーとして受け入れられていたのではないかと」
また、今回の増員には、ロックシーン自体の変化も感じるという。
「かつてロックバンドは、ギター、ベース、ドラムの最小編成が『かっこいい』とされてきた時代があり、逆にいえばそこに鍵盤楽器や打ち込みを導入することに抵抗がある雰囲気もありました。しかし、最近でいうとサカナクションやSEKAI NO OWARIなど、従来のロックバンドの編成とは異なるグループが目立っています。UVERworldがマニピュレーターを正式メンバーにしたのは、そういった時代の流れもあるのではないでしょうか」
5月からは全国ツアーを控えており、7月5日には京セラドーム大阪でのライブも決定しているUVERworld。盟友である誠果を正式メンバーに加えることによって、同バンドがさらに勢いを増すことを期待したい。
(文=編集部)