ニガミ17才、Tempalay、踊ってばかりの国……現代のサイケデリックな音楽たちがもたらすもの
音楽
ニュース
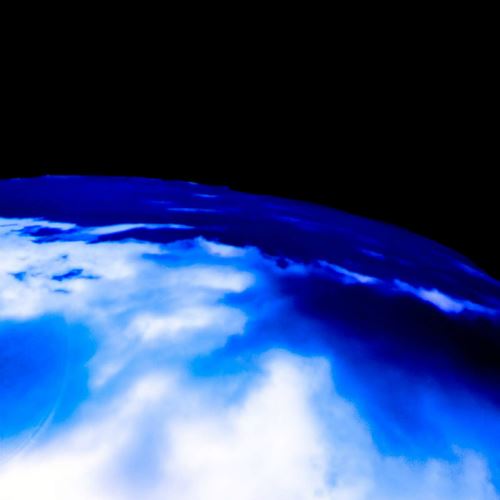
先日公開されていた、ニガミ17才の新しいMV「幽霊であるし」を観ていた。短髪になった岩下優介がカクカクくねくねと奇妙に体を動かしながらビルの中を這いずり回っていく映像はかなり猟奇的、というか、もはやホラーだ。バンドが世に出た当初には、芸人のデッカチャンが水を飲んでは吐き出すだけの「おいしい水」のMVも話題になっていたし、音楽、映像、ビジュアル、そういったすべてにおいて見せるユーモア混じりの奇怪なセンスは結成当初から相変わらずといえようが、「幽霊であるし」のビデオにおける岩下の異常な眼力と異様なダンスは、バンドがさらに化け物じみてきたことを如実に伝えるような、そんな凄みがある。実際、音楽的にはかなりの洗練が果たされていると言っていいだろう。
(関連:坂本慎太郎が若手アーティストに与えた影響ーーTempalay、東郷清丸の最新作より考える)
2018年の『ニガミ17才b』では、削ぎ落とされたシャープでダンサブルなサウンドを展開していたが、「幽霊であるし」はそれをさらに発展させたような異形のエレクトロニックポップを披露している。そのサウンドメイクは、もはや「4ピースバンド」という範疇に収まるものではない。そもそもニガミ17才は、岩下がかつて在籍していた嘘つきバービーも含めて、あぶらだこやゆらゆら帝国の意匠を継ぐサイケデリックロックの系譜に数えられることもあった。だが、「幽霊であるし」を聴くにつけて、ニガミは、そうしたサイケデリックロックの流れに対して、曲作りの手法も、「バンド」という形態もさらに多様化された現代ならではの新しい展開――それも、とても色っぽく、ポップなもの――を用意できるのではないかと期待してしまう。岩下優介という人間の感性は、JPEGMAFIAやセコイヤ・マレーのような、現代的かつ強烈な「個」を持ったアーティストたちに通じるものがあると個人的には思っているので、彼の「個」としての狂気やフェティシズムが、どれだけ形式や既成概念を突き破って我々の前に出てくるのか、この先もっともっと期待したいところ。
ちなみに、件の「幽霊であるし」のMVを作ったのは、King GnuやTempalayなどのビデオも制作しているクリエイティブチーム「PERIMETRON」なのだが、思えば、Tempalayが去年リリースしたアルバム『21世紀より愛をこめて』も、この国のサイケデリックポップの新しい地平を切り開くような快作だった。TwitterでBTSのメンバー・RMが反応したことでも話題になった「どうしよう」や「のめりこめ、震えろ。」など、一聴したら忘れられなくなるような、そのポップセンスをより一層開花させた楽曲を収録した本作。時代を射抜くような、鋭く批評的な眼差しと言葉を持ちながら、それをときにドロッと奇怪に、ときに美しくエモーショナルに、サイケデリックソングへと昇華する彼らの手腕が、あのアルバムでは見事に発揮されていた。
そもそも、「サイケデリック」と言われて「なんとなく意味がわからないもの」とか「現実離れしたなにか」といったものをイメージする人は多いかもしれないが、サイケデリックな音楽がもたらすものは、なにも非現実への逃避だけではない。社会や世間が「これは正しい」とか「これは正常だ」と断定する物事を、「本当にそうだろうか?」と疑う眼差し――それもまた、サイケデリック音楽が私たちにもたらすものだ。例えば、テレビやスマホの画面の中で政治家やコメンテーターが話す言葉と、ニガミ17才やTempalayが奏でる歪で奇妙な旋律や言葉は、果たしてどちらが明晰な景色を私たちに見せるだろうか? 本当に歪んでいるのはどちらだろうか? 私たちが見る風景や、私たち自身の心の中を表明するのに本当に適している言葉とはどんなものだろうか? 広告の見出しのように綺麗にコーティングされた言葉だろうか? それとも、意味すら超えた場所にある一見、理解不能な言葉だろうか?――そう、「正常」だとされるものが、本当に「正常」かどうかなんてわからない。そのぐらいこの世界は、私たちの心の中は、歪みながら、軋みながら、説明がつかないことばかりを抱えて、悲しくも滑稽に回っている。サイケデリック音楽は、便宜を図り合ったうえで生み出される、順風満帆に整理された「正しさ」にメスを入れる。「もっとちゃんと、世界を、心を見ようぜ」と私たちに問いかける。この混沌とした時代のなかで、押し付けられる「正しさ」に騙されないために。私たちが私たち自身を、人間を、より鮮明にこの世界に提示するために。この記事で紹介したニガミ17才やTempalayのようなバンドたちが今まさに認知を広げていることは必然といえるだろう。
そして最後に、筆者がこの10年間の日本の音楽シーンにおいて最も重要だと思っているサイケデリックバンド、踊ってばかりの国が、新作『私は月には行かないだろう』をリリースした。このアルバムタイトルは、お金持ちが月に行きたがるこの時代においての、自分たちの態度の表明だろうか? だとしたら、とても地に足がついている。もともと音楽性の豊かさに定評があっただけでなく、デビュー期から作品を重ねる毎に歌と言葉の精度を増してきたバンドだが、「ghost」や「光の中に」のような素晴らしく「いい歌」を朗々と響かせていた前作に比べ、本作はより、聴き手に話しかけるように親密で、かつ奥深い歌が聴こえてくるアルバムだ。曲の展開やメロディの響きは細部まで研ぎ澄まされながらも、全体的なプロダクションは決して重たくならず、むしろ軽やかに1音1音が鳴っている。おかげで一層、サウンドの風通しがよくなり、言葉も軽やかに、よく通る。1曲目「バナナフィッシュ」の歌い出しはこうだ。〈地球に突き刺さるビルや/陸を覆う光の群れ/あなたはその中で今日も/爪を噛んでいますか?〉――この時代、この社会に生きる、ほかならぬ私やあなたに向けられた言葉。アルバムはその後も、「時代」という狂気と、その中で生きる私たちの営みを愛おしみ、また同時に悲しむような歌が紡がれていく。かつて「世界が見たい」と歌ったバンドは、今、とても明晰な目で世界を見ている。2020年必聴の傑作である。(天野史彬)

