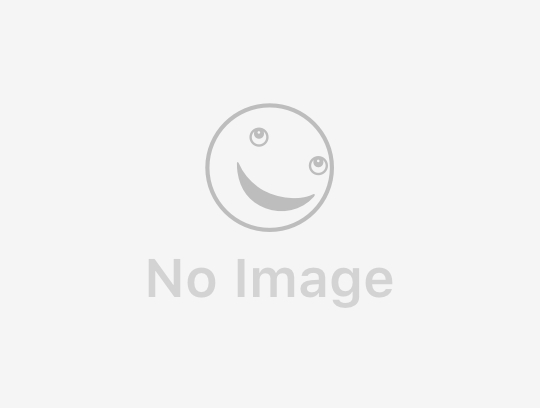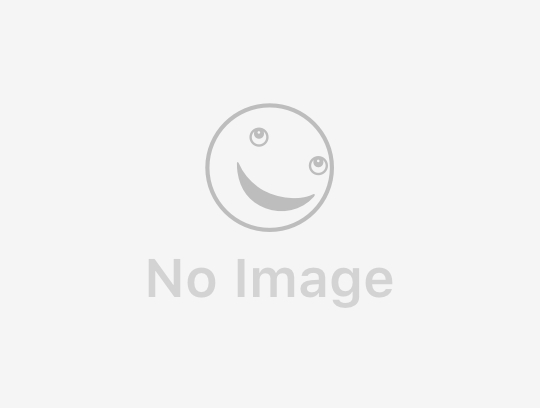2014年、父の故郷である徳之島や奄美大島の博物館で「芭蕉布(ばしょうふ)」を知った。沖縄や奄美群島など亜熱帯に自生する植物「糸芭蕉」を栽培し、糸からつくる織物だ。王族から庶民までの着物に愛用されてきたが、戦後一時衰退。その危機を救ったのが、沖縄県大宜味村(おおがみむら)喜如嘉(きじょか)生まれの平良敏子である。2000年には重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定された。
戦時中は「女子挺身隊」の一員として岡山県倉敷市で働き、戦後、倉敷紡績工場に就職。社長の大原總一郎の勧めで初代倉敷民藝館館長・外村吉之介に染織を学び、1946年に帰郷して芭蕉布の工房を開設。沖縄が日本に復帰した2年後の1974年、「喜如嘉の芭蕉布」が国の重要無形文化財に指定された。
展示されている約70点の手織物の中でも、琉球藍染や車輪梅染の色合い、絣柄や幾何形のモダンな展開が目を引く。例えば、古典柄の「鳥」をアレンジした燕のモチーフ「小鳥(トゥイグヮー)」に線を重ねると、柳の間を抜ける小鳥となる。シンプルな構成による定番と更新が、数学的でもあり詩的でもあるのだ。
地階で映像を見ると、栽培から糸にし、染色し、織るまでに大変な手間と根気のいる工程を喜如嘉の工房だけで成し遂げていて敬服する。民藝の主唱者、柳宗悦に「こんな美しい布はめったにない」と称賛された芭蕉布を若い世代にもぜひ知ってほしい。