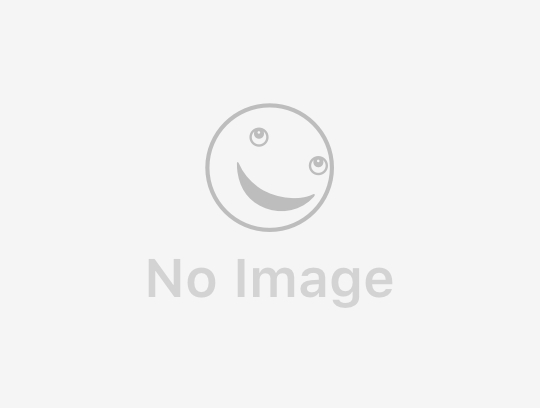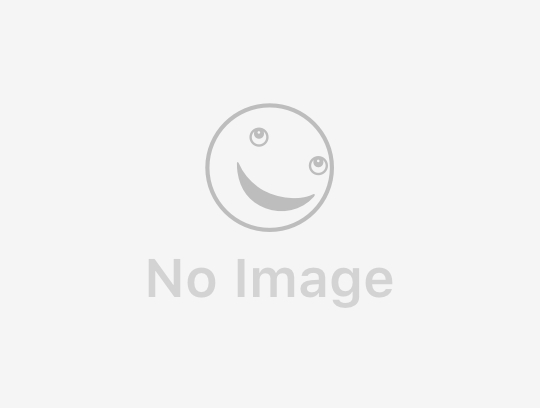ゴダールはいつだって、観る者をビギナーにしてしまう。
シネフィルを気どり、一端のことをつぶやきたがる輩こそ、ゴダールの前では初心者と化す。
それは、彼の映画が難解だからではない。いや、彼の映画が難解だったことはただの一度もない。退屈な映画も沢山ある。たが、それらもすべて、あっけらかんとしていて、どこかに一瞬きらめきがひそんでいる。
ゴダールは、目くばせをする。それは、映画マニアに向けた「知識の共有」という嫌らしい態度ではなく、どうだ、すげぇだろ、映画ってすげぇだろ、というウィンクである。おたくじゃなくても、なんだかわかんないけど、いまのかっこよかった! ゴダールがかっこいいのか? 映画がかっこいいのか? わかんないけど、かっこいいってことだけはわかる! そんふうにしてしまう。
みんなが、初心者になる。
ゴダール玄人もまとめて、初心者にしてしまう節操のなさが、ゴダールなのだ。
この映画は、ドキュメンタリーの形式をとった、ゴダールへのラブレターだ。
これ見よがしのアイコンタクトはしないけど、チャーミングなウィンクはする、案外素直な道化師ゴダール。その作品世界や遍歴ではなく、人間性そのものに、主に一緒に仕事をした女優たちの証言から、迫っている。
彼女たちは、彼の発明や偉業を賞賛なんてしない。
変わってる。けど、可愛いひとだったよね。
褒め称えることより、“わたしが知っているゴダール”を、宝石箱からお気に入りのジュエリーをチラ見せするように、教えてくれる。
四部構成で、時系列に沿っているので、ゴダールのキャリアの基本的なお勉強になる。そこは、文字通り、初心者向け。
たが、触れる者すべてをビギナーにしてしまうゴダールの魔法が、全編にふりかけられていて、愉しくなる。
きっと、芸術家になりたかったのであろうゴダール。でも、ゴダールは、あくまでも、ゴダールとして、愛され、鮮やかな幕切れを見せた。
世界中のひとびとに尊敬されるより、ゴダールって、やっぱりゴダールだよね、と微笑ませる人生。
ゴダールは、最後の最後まで、ゴダールを演じきった。そのことにニヤニヤさせられる、キュートな一本。