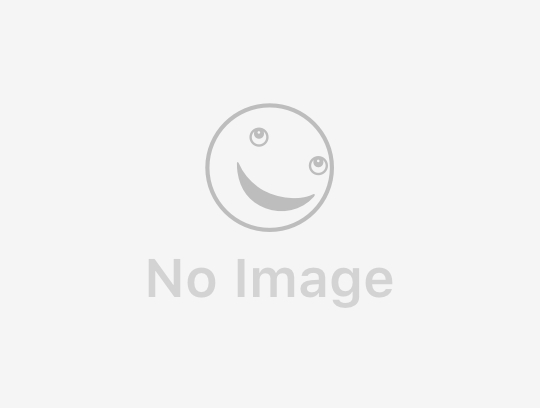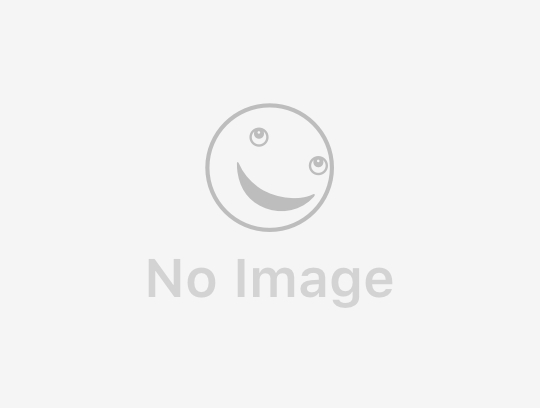1月7日の人日、3月3日の上巳、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の重陽の5つ日本の四季を彩る代表的な節句「五節句」の中でも3月の上巳の節句は、旧暦のこの頃が桃の花が咲くころであったため「桃の節句」とも呼ばれました。
現在では3月3日の節句は、女子の成長を願う「ひな祭り」として広く定着しています。ひな人形を飾るようになったのは江戸時代になってからのことです。人形の街として知られる埼玉県岩槻市にある岩槻人形博物館をはじめ、この時季になるとひな人形を紹介する展覧会が日本各地で開催されます。
世田谷の岡本から東京丸の内に建つ昭和9年竣工の明治生命館に移転してきた静嘉堂文庫美術館(静嘉堂@丸の内)でも、現在可愛らしいお雛さまの展覧会が開かれています。静嘉堂が所蔵している岩﨑家のお雛さまは、岩崎小彌太(三菱第4代社長・1879~1945)が、昭和の初め頃、孝子夫人のために、京都の丸平大木人形店に特注したものです。製作には3年の歳月を要したと伝えられ、まさに昭和初期の人形製作技術の粋を集めた美術工芸品と呼べる貴重なお雛さまです。
「岩﨑家雛人形」は白くつややかな丸いお顔が愛らしい稚児雛です。昭和4年(1929)に竣工した三菱家の邸宅・鳥居坂本邸(現在、跡地は国際文化会館港区六本木)の客間で披露されました。戦後、お雛さまは散逸してしまいますが、蒐集家・福喜世美氏が情熱をもって集め、静嘉堂文庫美術館において、受贈記念展(2019)などで紹介されてきました。
今回の展覧会では、「岩崎家雛人形」に加え、岩崎小彌太の還暦を祝し、丸平大木人形店に特注した61人に及ぶ「木彫彩色御所人形」や丸平文庫が所蔵する岩﨑家旧蔵の御所人形が里帰りを果たし当時の様子を伝える写真と共に展示されています。またギャラリー4では、国宝「曜変天目」と共に、岩﨑家ゆかりの「白綸子地松竹梅鶴模様打掛」が初公開されており見ごたえたっぷりの展覧会となっています。