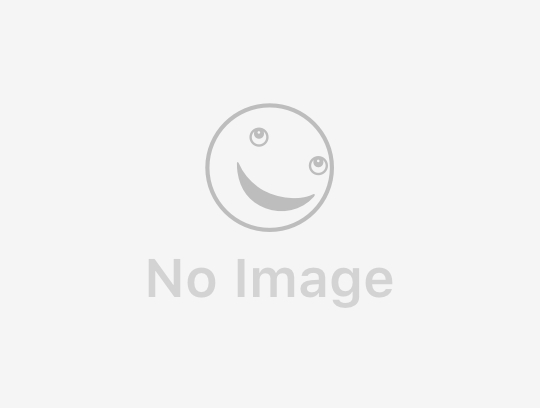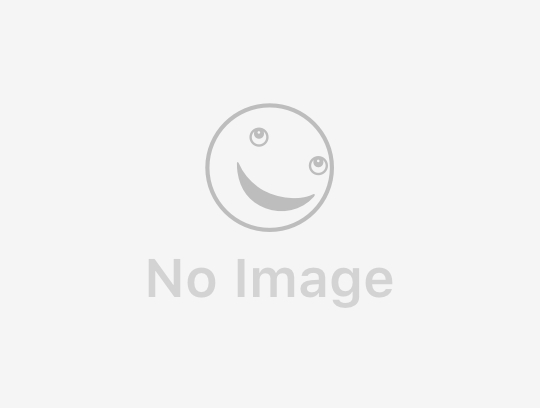アルノー・デプレシャンが映画と映画館との遭遇にはじまる極私的な映画史を語る一篇。そう聞くと濃すぎるシネフィル専用のアートフィルムなのかなと身構えかねないけれども、まるで心配には及ばない、むしろ裾野の広い素朴な味わいの小味な作品である。驚きはなにげなく言及、挿入される数々の思い出の映画だが、このラインナップからしてベルイマンやゴダールから『ダイ・ハード』『エイリアン』まで、アートフィルムから大エンタテインメントまで広大であるのが好ましい。ドラマ部分では『ママと娼婦』のフランソワーズ・ルブランが孫を映画館にいざなうおばあちゃん役で好演しているが、そんなジャン・ユスターシュの作品のような作家的な傑作ばかりを並べるのではなく『ターミネーター2』まで入って来てしまう気安さ、風通しのよさが、本作ひいては監督のシネフィルとしての豊かさを物語る。そして監督の投影である主人公は「観る少年」から「見せる大人」へと成長してゆくが、その表現も奥ゆかしく透明感があってみずみずしい。引用作のなかにはキン・フー『侠女』もあって嬉しかったが、最もしびれたのはエンディングテーマにトム・ウェイツのあの曲をもってきたところだ。ここには画はないのだが、やっぱりデプレシャンも『カルメンという名の女』のテレビの砂嵐のショットにはジンジン来たのだろうなと年も近い監督とクラスメート的会話をしたくなった。