植草信和 映画は本も面白い
もっと論じられるべき映画監督の全貌『岩井俊二』と、映画興行についての2冊『そして映画館はつづく』『映画人が語る日本映画史の舞台裏』。
毎月連載
第55回
20/12/25(金)

『岩井俊二 「Love Letter」から「ラストレター」、そして「チィファの手紙」へ』
『岩井俊二 「Love Letter」から「ラストレター」、そして「チィファの手紙」へ』(夏目深雪編/河出書房新社/1,800円+税)
1996年、NHKの『映像美の巨匠 市川崑』というドキュメンタリー番組で岩井俊二監督にインタビューした。その収録後に人をめったにホメないプロデューサーが、「岩井作品に起用される女優のときめきが分かるような気がした」と呟くように言った。その発言にいたく共感し、岩井がいかに周囲の人を惹きつける魅力的な映画監督なのかを理解した。
本書の編者である夏目深雪の「ロングインタビュー」を読んでいてそんな昔のことを思い出したのは、インタビュアーの岩井に対するリスペクト感が率直に感じられたからだ。本書全体にもその思いは貫かれている。編者の論考「村上春樹と岩井俊二」を始め、豊川悦司、中山美穂へのインタビュー、北川悦史子、行定勲のエッセイなど岩井の優れた仕事の数々を称揚、それらから日本映画を変えたといわれる岩井の業績が正当に評価されているとはいえないことがよく分かる。
構成は三部から成り、第一章『「Love Letter」から「ラストレター」、そして「チィファの手紙」へ』では『Love Letter』の東アジアでの人気、初の中国映画『チィファの手紙』などアジアとの関わり。第二章『ボーダレスな作家、岩井俊二』では小説など他ジャンルへの取り組みなどの活動。第三章『作品評+フィルモグラフィ』では、30年におよぶクリエーターとしての岩井の全貌を解明していく。
長年にわたって中国の映画人やファンに愛されてきた人気の秘密を考察した劉文兵の『岩井俊二監督作品は中国でどう観られてきたか』、『番犬は庭を守る』『ウォーレスの人魚』など岩井の小説に関する藤田直哉の評論『岩井俊二作品における「科学」と「神」』、同時期に東アジアでブームとなった村上春樹との比較で岩井監督の個性に焦点をあてた夏目の『村上春樹と岩井俊二 一人称の作家』など、異なった角度の論考は、人と作品を立体的に浮き彫りにしている。
ドラマ時代から数えるとその活動歴は30年を超える映画監督、クリエーター岩井俊二はもっと論じられなければならない存在だと、本書は教えてくれる。
『そして映画館はつづく―あの劇場で見た映画はなぜ忘れられないのだろう』(田中竜輔・沼倉康介編/フィルムアート社/2,000円+税)
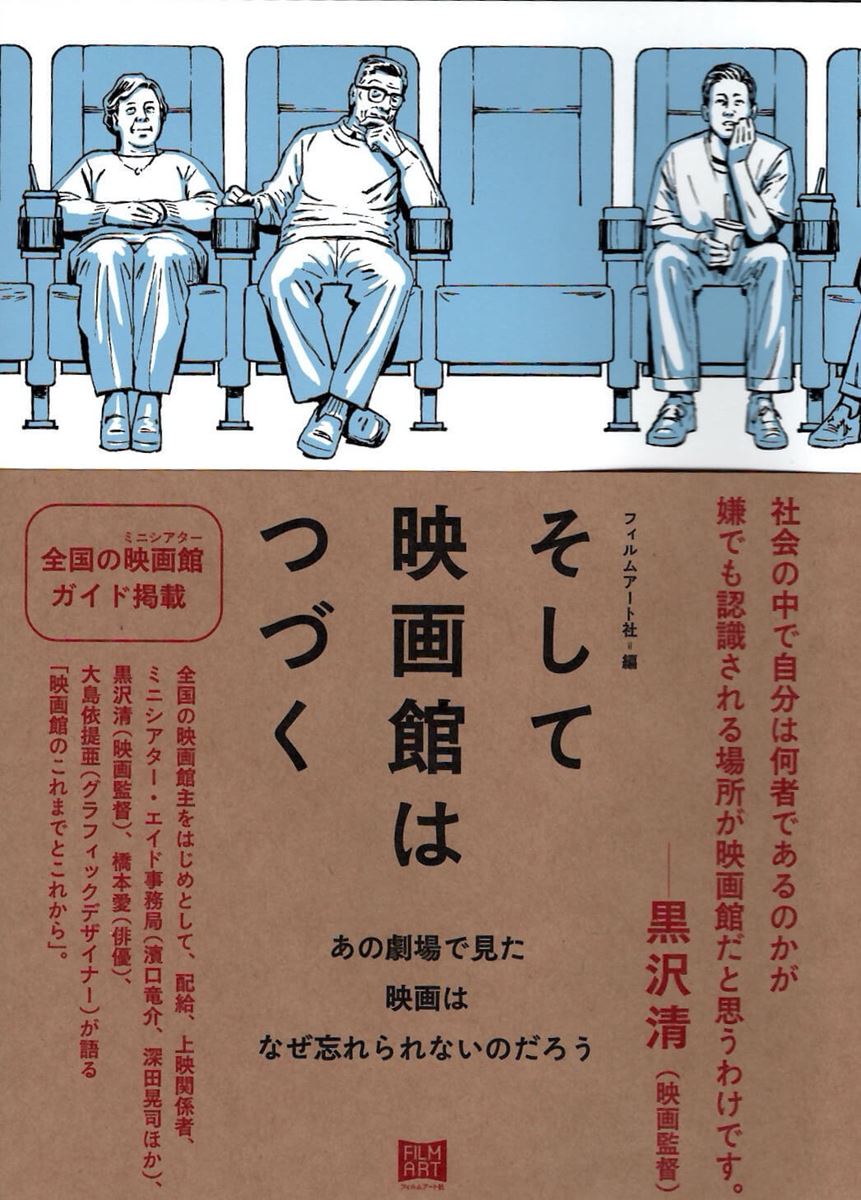
コロナ禍によって映画館産業は今、最大の危機に直面している。日本で最初の常設映画館が誕生した1903年以降、117年の歴史途上でかつて体験したことがない未曽有の艱難。大手シネコンに比して資本力の弱いミニシアターは、危急存亡の瀬戸際にあるといっても過言ではない。
当然のことながらその危機は映画館という場だけではなく、映画館へと作品を送る配給会社や映画を作る製作者とスタッフや俳優、そして観客にとっても地続きの問題だ。
本書は、北海道から沖縄までの全国12のミニシアターの支配人、番組編成担当者が自館の“これまで”と“これから”、さらにはコロナ禍がもたらした現象を語る第一章から始まる。以下、黒沢清、橋本愛、大島依提亜らが映画館体験と映画館への思いや期待を語る第二章、映画キュレーター、上映ディレクターらが映画の上映について語る第三章、濱口竜介、深田晃司両監督がいち早く支援に乗り出したミニシアター・エイド基金について語る第四章から成っている。現状報告的映画館考察書、といえばいいか。
コロナ禍によるミニシアター受難を訴えた緊急出版物のように受け取られ兼ねない本書だが、編集主体の〈フィルムアート社編集部〉はそうではないと言う。
「映画館について私たちはあまりに何も知らなさすぎるのではないかという思いもまた湧き上がってきました。今改めて〈映画館〉という場所について、あるいは〈上映〉という営為について考えたいと思ったのです」(はじめに)。
つまり、映画館という場をめぐる歴史的考察や今日的な課題を見つめ直し、あらためて映画館について考えさせられる本なのだ。「もし自分がどうしようもなくなってしまったときや本当に一人になってしまったとき、ちゃんとあなたをつつんでくれるような場所として映画館がある」(橋本愛)のだから。
『映画人が語る 日本映画史の舞台裏[配給興行編]』(谷川建司編/森話社/3.600円+税)
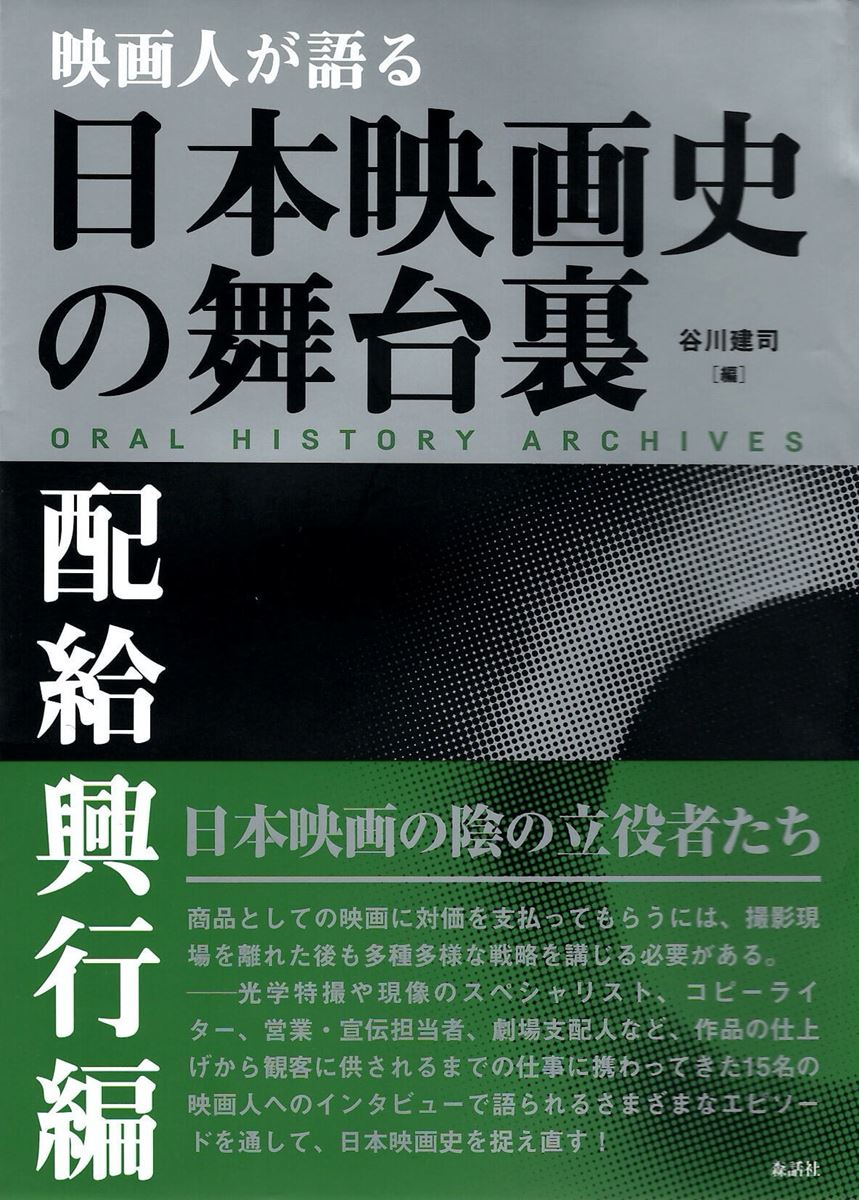
本書の編者である谷川建司は、洋画配給会社勤務から早稲田大学の教授に転じた映画研究者。長年にわたり、〈映画は資本の論理で成立しており作家論・作品論だけでは本質は掴めない〉という至極まっとうな理論を展開してきた。
彼はその持論を証明するために2014年、〈昭和戦後期における日本映画史の再構築〉を目的とした共同研究会を、京都の国際日本文化研究センター内に組織する。その研究成果は『戦後映画の産業空間──資本・娯楽・興行』(森話社/2016年)として結実。本書は、〈作品を仕上げる仕事〉〈作品を送り届ける仕事〉〈配給・興行の仕事〉に従事した映画人へのインタビューをまとめた、その続編ともいえる論考集。
本書の第Ⅰ部は〈作品を仕上げる仕事〉で、光学合成の中野稔、動画編集者の千蔵豊、現像技師の奥村朗らに聞き取り、以下、第Ⅱ部〈作品を送り届ける仕事〉はコピーライターの関根忠郎、芸能雑誌の小杉修造・高木清、第Ⅳ部「配給・興行の仕事」では配給の緒方用光、宣伝の原正人、映画館経営者の稲井峯弥ら15人に、研究会メンバーがインタビュー、各々の仕事と映画史について聞き書きしている(第Ⅲ部『企業の生き残りをかけて』は『大映』の社史裏面史)。
クレジットに名前も出ない、あるいは出たとしても瞬時に消えてしまうような映画のスペシャリストたちが語る、作品の仕上げから観客に供されるまでの製作秘話はどれもが傾聴に値する。そして面白い。いわば映画の黒子である彼らのような存在が映画産業を支え、映画史を形成していることを本書は証明している。
彼らが語る知られざるさまざまなエピソードを通して、「作家・作品中心の捉え方から解き放つ」チャレンジングな日本映画史研究書だ。
〈おしらせ〉連載「映画は本も面白い」は今回が最終回です。皆様、ご愛読ありがとうございました!(編集部)
プロフィール
植草信和(うえくさ・のぶかず)
1949年、千葉県市川市生まれ。フリー編集者。キネマ旬報社に入社し、1991年に同誌編集長。退社後2006年、映画製作・配給会社「太秦株式会社」設立。現在は非常勤顧問。著書『証言 日中映画興亡史』(共著)、編著は多数。
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内



