すべての地獄を生きる者たちよ、シコを踏めーー小川紗良の『菊とギロチン 』評
18/7/28(土) 12:00
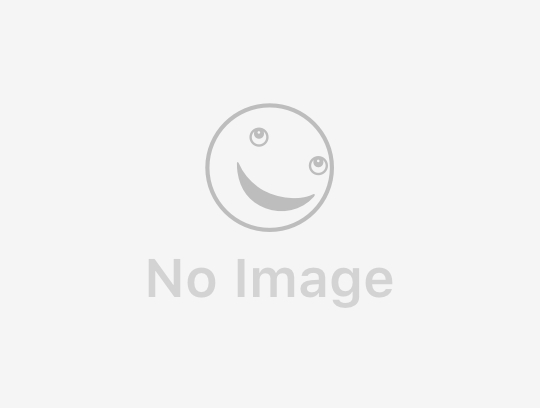
『リバーズ・エッジ』や『聖なるもの』『ウィッチ・フウィッチ』などの映画作品から、テレビドラマ『崖っぷちホテル!』(日本テレビ系)にも出演し、メジャー/インディーズを横断するかたちで、目覚ましい活躍を見せる女優・小川紗良。彼女は監督業でもアクティブな活動を見せ、手がけた作品の『最期の星』が「第40回ぴあフィルムフェスティバル」に入選、さらに『BEATOPIA』の劇場公開が決定している。女優として、監督として、瀬々敬久監督の最新作『菊とギロチン』を、小川はどう捉えたか。(編集部)
●映画を志したきっかけ
高校1年の春、教室で配られた自己紹介シートの「興味のあること」の欄に、私はなぜか「映像」と書いた。映像なんて作ったこともなかったのに。それから何日かして担任の先生に呼び出され、突然「ドキュメンタリーを撮ってみないか」と言われた。この一言が私を映像の世界に連れ出すことになる。それからの3年間、体育祭、文化祭、修学旅行など、私はあらゆる行事のドキュメンタリーを撮って過ごした。とにかく、楽しんでくれる友達の姿を見るのが好きだった。そして大学に入り、自分で脚本を書き仲間を集めて映画を撮った。今度は、まだ見ぬ誰かの心を動かしてみたいと。私の映画作りの原点には、無我夢中に学校行事を撮り続けていた高校時代がある。
私が映画を日常的に観るようになったのは、高校に入って女優業を始めてからだ。初めは好きな女優を追いかけて、そのうち好きな監督ができるとそこを掘り下げて……と、名画座に通いながら邦画を中心に観ていた。だからなのか、私は邦画の持つ空気感が好きだ。
先日韓国の映画祭に行って、「日本映画はガラパゴス化している」「原作ものが多すぎる」などの指摘を受けた。海外の映画祭では、こうして日本映画全体に対する意見も浴びることがあるのかと、新鮮な体験だった。確かに、韓国の方々のおっしゃる通りだと思う。日本の映画館に行けばいつも漫画原作映画が何本も上映されているし、それらのほとんどが国内興行で盛り上がって終わっていく。漫画やアニメの力が強い日本では、映画がそちら側に流れていくのも無理はないし、それで面白い作品ができて楽しむ人がいるのならば、それはそれで良いと思う。私も好きな漫画原作映画はいくつもある。
ただ、ときどき海外の素晴らしい作品を観ると、日本でもこういう作品をもっと観れないものかと、願わずにはいられないことがある。映画の芸術的価値が高く、監督の作家性が活かされ、それでいて多くの人に伝わる普遍性を持った作品が海外にはたくさんある。今の日本でそういった作品を作るには、2つの方法があると思う。1つは、日本映画界トップレベルの監督が作ること。そしてもう1つは、大手配給や制作会社を通さずにインディーズで作ることだ。後者は予算集めやスタッフィング、キャスティングなど多大な労力を要するが、それでも作り上げる監督の強い意志があれば、とても強度の高い作品が出来ると思う。『菊とギロチン』がその良い例だ。最近ではそういった作品がインディーズ映画界から出てきて、口コミで全国や海外映画祭へ広がっていくという例も時折見られる。「ガラパゴス化」と言われる日本映画界の突破口は、案外インディーズ映画にあるのかもしれない。
●大正の終わりと平成の終わりをつなぐ風穴
泣き顔が良いと言われたことがある。はらわたが煮えくり返るほど悔しい思いをしている時に。とても屈辱的だった。その相手以上に、泣き顔なんかを見せてしまった自分と、何も言い返せなかった自分に腹が立った。そして心の底から思った、「強くなりたい」と。
戦争、震災、貧困、労働、女性、暴力、朝鮮、琉球……『菊とギロチン』には様々な立場で地獄を見ながらも、「強くなりたい」と願う者たちがいる。これでもかと盛り込まれた“権力と弱者”の対立構造。いつもカメラは弱者の側にあり、彼らの見てきた地獄とその生き様を映す。「東京は地獄だ」「ここも地獄だ」。被災者も、自警団も、在郷軍人も、朝鮮人も、主義者も、小作人も、男も、女も、誰もがどこかで苦しいものを見ていた関東大震災直後の日本。どこにもいけない彼らはそれぞれの土俵でひたすらシコを踏みながら、「強くなりたい」と願うしかなかった。
映画の中で繰り返し使われる覗き穴のような画。その先には、女力士や主義者の様子が映される。あの穴を覗いているのは一体誰なのか?と思いながら映画を観ていた。そして最後まで観終わって、覗き見ていたのは紛れもなく平成を生きる私であることに気づく。『菊とギロチン』は明らかに、大正の日本を映すことで現代を語る映画だ。“主義者と女力士”という一見時代錯誤なモチーフを使いながらも、そこで問われているものは現代の労働問題や家庭問題、人種問題、ジェンダーに関する問題などに直結するものばかりだ。だから、平成を生きる私が女力士たちの姿を見て、「強くなりたい」と共鳴することができる。『菊とギロチン』は大正の地獄を描いたが、それを観る私たちがいるここもまた、案外地獄なのかもしれない。そうでなければ、この映画に心を動かされることなどなかっただろう。繰り返される覗き穴、あれはきっと大正の終わりと平成の終わりをつなぐ風穴なのである。
この映画には女力士たちが身体をぶつけ合いながら相撲をとるシーンがいくつもあるが、特に印象に残った試合がある。それは在郷軍人や自警団が会場から姿を消した直後の、梅の里(前原麻希)と羽黒桜(田代友紀)の試合だ。監視の目を離れ自由となった途端に、会場はそれまで以上に大きな盛り上がりを見せる。力士も、客も、勧進元も、皆が純粋に相撲を楽しみシコを踏み歓声をあげる。その試合の土俵はまるで、ほぼインディーズ体制で制作された本作の流れるスクリーンそのものであった。大きな組織に頼らずとも本当に作りたいものを、そして本当に良いものを作ろうとする監督・キャスト・ スタッフの圧倒的意思。そしてその画面に惹きつけられていく私たち観客。あの試合のシーンは、この映画自体のもつ構図とまるで同じであった。思わず「インディーズ映画」の意味を問い直したくなるほど、強度の高い映画である。
ところで、“シコを踏む”というのは力士の稽古や準備運動の他に「邪気を祓い清める」「地の神様を鎮める」といった意味があるという。相撲はもともと神前で行われていた競技であり、縁起の良いものだ。それにも関わらず、映画でも描かれている通り女が土俵に上がると神様が怒るのだという。また、女相撲は時に卑猥な目で見られ、力士の格付けにおいても男相撲に遠慮して「横綱」が存在しなかった。“女である”というだけで相撲のあり方がこうも違う。神を鎮める行為すら、女がやれば逆鱗に触れる。どんなに稽古したって、結局その辺の男に力で負ける。そんな矛盾をはらんだ女相撲のあり方も、この映画の中で印象的である。女が土俵に上がると神の怒りで雨が降るので、干ばつが起こるとその土地に女相撲が呼ばれたという。実際に映画の中でも雨が降るが、あの雨を降らせたのは本当に神様なのだろうか? 雨を降らせたのは、この矛盾に満ちた世に怒る作り手であり、そこに共鳴する我々観客ではないだろうか。
それでも、女力士たちはシコを踏む。主義者も、朝鮮人も、小作人も、それぞれの土俵で彼らなりのシコを踏む。『菊とギロチン』は絶えず「地獄だ」「弱いやつは何も変えられない」「結局ダメなんだ」「弱いやつは一生弱い」と、弱者の絶望を唱える。しかし映画のラストは、それでも土俵の上で戦い続ける女力士たちの姿で締められている。そのどん底の景色は、なぜか希望的に感じられた。最後に映されたのは「戦い続ければきっと変えられる」という彼女たちの希望である。「変えるために強くなりたい」という泥だらけの願望である。その光がわずかにでも見える限りシコを踏み続けるべきだと、この映画は鼓舞している。平成の終わり、すべての地獄を生きる者たちに、『菊とギロチン』はシコを踏めと叫んでいる。(小川紗良)
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内





