クドカン率いる『あまちゃん』チームが再集結! 『いだてん』落語を通した“笑い”の視点
19/1/6(日) 6:00
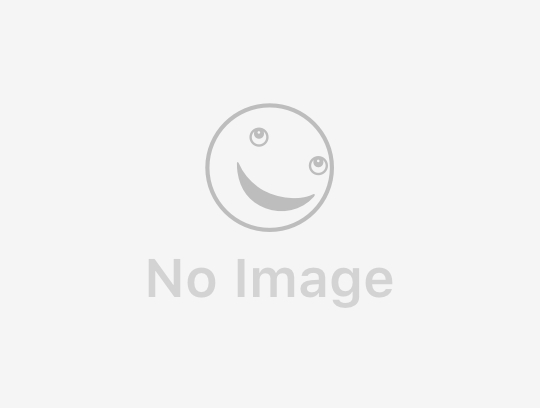
1月6日、新しい大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』(NHK)がスタートする。物語の主人公は、1912年に、日本人で初めてオリンピック(ストックホルム五輪)に出場した日本マラソンの父・金栗四三(中村勘九郎)と1964年に東京オリンピック招致に尽力した日本水泳の父・田畑政治(阿部サダヲ)の2人。物語は明治から始まり1940年の幻の東京オリンピックを挟んで、戦後復興の象徴としての1964年の東京オリンピックへと向かっていく。
写真:『いだてん~東京オリムピック噺~』第1話に登場する中村勘九郎の姿
脚本はクドカンこと宮藤官九郎、チーフ演出は井上剛、音楽は大友良英、プロデューサーは訓覇圭という2013年に大ヒットした連続テレビ小説『あまちゃん』(NHK)をヒットさせたチームが再結集し、東京オリンピックを描くのだから、プレオリンピック・イヤーにふさわしい大型企画だと言えるだろう。
『いだてん』は、あらすじを読むとオリンピック版『プロジェクトX』(NHK)とでも言うような硬派な作品に見える。“オリンピック”と“スポーツ”というモチーフは、“アイドル”と“芸能”を通して東日本大震災を描いた『あまちゃん』チームが取り組むにしては、ややミスマッチにも思える。確かに、“震災”と“アイドル”を描いた『あまちゃん』から、“東京オリンピック”と“スポーツ”を描く『いだてん』という流れは、現代を描くという意味において圧倒的に正しいのだが、ど真ん中過ぎて息苦しく感じ、何もこのチームでやらなくていいのではないかと、当初は思っていた。しかし、作品の語り手(ナレーション)を担当するのが、ビートたけしが演じる古今亭志ん生だと知ると、俄然興味が湧いてきた。
ホームページ等であらすじや人物相関図を見ても、単純なドラマではなさそうである。物語は明治から戦時下へと向かっていく前半と、東京オリンピック開催へと向かう戦後の二部構成。登場人物は、オリンピック招致を目指す東京都知事やジャーナリスト、金栗四三とその家族、金栗の盟友の三島弥彦(生田斗真)を中心とする三島家と金栗を応援する天狗倶楽部の人々、金栗の恩師にあたる嘉納治五郎(役所広司)の所属する東京高等師範学校・大日本体育協会の面々。そして、若き日の古今亭志ん生こと美濃部孝蔵(森山未來)をとりまく浅草の人々といった感じで、複数のコミュニティが同時に描かれている。つまり、視点が多数あるということだ。
クドカンドラマは元々、地方のスナックのような小さな共同体の狭い人間関係を延々と描くスタイルのものが多い。そのため、友達の知り合いの話を聞いているかのような心地よい狭さがあるのだが、家族の歴史や細かいサブカルチャーの引用を用いて“歴史のようなもの”を描いてきた。
それが顕著に出ていたのだが、現代を生きるヤクザが、落語という古典と出会い噺家となることで、疑似家族という自分の居場所を見つけていく『タイガー&ドラゴン』(TBS系)だろう。本作は『池袋ウエストゲートパーク』や『木更津キャッツアイ』(ともにTBS系)といったドラマで若者の風俗を描くことに長けた新鋭の若手脚本家というイメージが定着しつつあった宮藤が、幅広い視聴者が楽しめる普遍的な作品をはじめて作り上げた記念碑的作品だ。
『いだてん』に噺家が登場し、ストーリーに落語のモチーフが入ると知った時、真っ先に思ったのは『タイガー&ドラゴン』を発展させたような作品になるのではないかということだ。それはキャスティングからも伺える。主演の一人に宮藤と同じ大人計画に所属し、何度も宮藤のドラマや映画に出演した阿部サダヲがいることはもちろんのこと、峯田和伸、星野源、生田斗真といった宮藤の過去作に登場した俳優たちが多数出演し、古今亭志ん生を演じるのが、宮藤が尊敬し今の仕事を志すきっかけとなったビートたけしが名を連ねていること。
そして、若き日の志ん生の師匠・橘屋円喬を、宮藤の師匠にあたる大人計画・主催の松尾スズキが演じることも見逃せない。松尾は脚本を読んで、宮藤が円喬と孝蔵(志ん生)の関係を、「僕と宮藤君自身の関係に重ねていると感じました」と『NHK大河ドラマ・ガイド いだてん 前編』(NHK出版)の中で語っている。
狂言回しであり、おそらく宮藤の心情がかなり投影されるであろう、志ん生を中心とした落語家周辺の話には、宮藤の自伝的要素が入るのではないかと思う。
おそらく本作は、1940年の幻の東京オリンピックを挟んで、1964年の東京オリンピック向かっていく日本を通して、2020年の東京オリンピックへと向かう現在の日本を、照らし返すような作品になるのではないかと思う。その意味で、今後の日本を占うかのような、大きな構えの作品だと言えるが、そういった作品を描く際に落語という「笑い」の視点を用いるのは、実にクドカンドラマらしい。
戦国時代や幕末ではなく、明治から昭和にかけてという現代を大河ドラマで描くこと自体、画期的なのだが、それ以上に“笑える大河”が毎週放送されることが、何より楽しみである。
(成馬零一)
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内





