福嶋亮大が語る、パンデミック以降の倫理と表現 「隣人愛という概念は、改めて注目すべき」
20/5/20(水) 12:00

仏作家アルベール・カミュが1947年に発表した小説『ペスト』に再び注目が集まるなど、新型コロナウイルスの影響で書籍の消費動向にも様々な変化が生まれている。しかしながら、『復興文化論』『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』『百年の批評』などの著作で知られる気鋭の文芸批評家・福嶋亮大は、今回のパンデミックによる文化の内在的な変化はマイルドなものに留まると予想している。その一方で、各国のコロナ対策によって管理社会が到来することへの危惧から、キリスト教の「隣人愛」という概念に着目しているとのことだ。その真意とはいかなるものか。古今の書籍を参照に挙げながら、現状の認識を語ってもらった。(編集部)
新型コロナウイルスには表象的な貧しさがある
ーー新型コロナウイルスは多方面にさまざまな影響を与えています。文化に対してはどのような影響が出ると考えていますか。
福嶋:今回のパンデミックは経済的・政治的には大きな影響があるでしょうが、文化の内在的な変化は、マイルドなものに留まると思います。Netflixの興隆にせよ、Googleへの依存にせよ、西洋の凋落およびアジアの勃興にせよ、グローバリズムの終焉にせよ、パンデミック以前にさんざん語られてきたことであって、その内実は何も変わっていない。つまり、もともと勝っていたところがますます勝つようになった。コロナを文化史的な切断と考えるのは、おそらく過大評価だと思います。
そもそも、現代のネットワーク社会では、人間はウイルス的な挙動に憧れていたわけですね。「バイラル・マーケティング」なんて言葉があったくらいだから。創作者や文系の研究者も、ウイルスのように「拡散」し「越境」することに価値を認めてきた。先日ポン・ジュノ監督が『パラサイト』という映画でアカデミー賞をとりましたが、ウイルスはまさに不気味なパラサイトそのものです。ポン・ジュノはあらかじめウイルスから見た社会を撮っていたわけです。みんな潜在的にはウイルスになりたがっていたところに、本当のウイルスがやってきて、夢が悪夢的にかなえられたという感じでしょう。
結局、ここ数カ月の現象はすでに生じていた変化が加速しているだけです。想像力の更新は特段起こっていません。
--音楽ではライブ活動ができなくなったり、映画は軒並み公開延期になって映画館もいつ再開されるかはわからないという状況ではありますが、質的な意味で文化の革命みたいなものが起こるとは考えにくいと?
福嶋:1918年以降にパンデミックになったスペインかぜも、文化史にはたいして何も残していません。実際、我々は今年になるまで、この100年前の惨劇のことをほとんど忘れていたわけです。むしろ第一次世界大戦(1914年~1918年)の方が文化史的にははるかに大きな意味があった。
もちろん短期的に見れば、文化施設が廃業に追い込まれてしまうようなケースや、活動を諦めてしまうアーティストもいるでしょう。しかし、それはアートに限らず社会全体の問題であって、アート固有の問題ではない。加えて言うと、今回のパンデミックは表象的には貧しいものだと思います。
ーー表象的な貧しさ、というと?
福嶋:先日『ニューヨーク・タイムズ』で書いていた人がいたけれども(参照:Where Are the Photos of People Dying of Covid ?)、今回のコロナの報道では死者の映像はほとんど出てこない。我々が目にするのは空っぽになってしまった街の風景とか、ボール状のウイルスの画像とか、感染者数や死者数のグラフとか、そういうものですね。つまり、実際には悲惨なことが起こっているのに、妙にクリーニングされた表象がウイルスのように増えている。
その一方、これだけ連日報道されているのに、出来事の中心は空洞化したままです。たとえば、クルーズ船でウイルスがまん延した時も、クルーズ船の内部はろくに取材されなかったし、今もICUの状況をほとんど知ることができない。すでに3月に書いたことですが(参照:内なる敵と負の祝祭――震災とコロナウイルスのあいだで)、日本のマスメディアは「大本営発表」をやっているだけです。
あと、コロナウイルスそのものにも巧妙な自己隠匿性があって、ペストやエボラのように劇的な症状が出るわけではない。つまり、表象的に地味で発見しにくいからこそ、世界じゅうに拡大したし、リスクの測定も難しいわけです。いわば特徴がないのが特徴で、それが表象のクリーニングにも貢献している。これは表象文化論的には考察に値する問題だと思います。
ーー過去に疾疫が文化に影響を及ぼしたケースについても教えてください。
福嶋:今回のパンデミックと比較すべきは、やはり80年代のエイズ・クライシスでしょう。当時は多くのアーティストがエイズに対するアクションを起こした。それで、画家のキース・ヘリングならアクティビズムを、写真家のロバート・メイプルソープならばクラシシズムを、芸術家のフェリックス・ゴンザレス=トレスならミニマリズムをそれぞれ深化させていくわけで、エイズを契機にしてアートの語彙や表現技法が鍛え直されたところがある。HIV患者や同性愛者に対する差別があり、その差別への抵抗の形としてアートがあったわけです。
それに対して、今回のパンデミックは全世界的な問題であり、特定のコミュニティやセクシュアリティに負荷がかかったわけではない。そういう意味では、アートや文化が特別に活気づく気配はないと思います。ともかく、アーティストはどんな状況下でも、自分のイディオムのなかに外界を映し出すしかない。ゴットフリート・ライプニッツの「モナド」のようなものです。その点で、自分のイディオムを持っていないアーティストは、今後厳しくなるということはあると思います。
--アーティストが無料で配信した音源をリレーで繋いだりといったパフォーマンスが見られますが、そういう動きはどう見ていますか。
福嶋:いいことだと思いますが、ただそれはあくまでも一過的なものです。東日本大震災の直後と同じです。
ディザスターの本質的な影響というのは、必ずしもテーマとして直接的に出てくるものではなくて、えてしてズレを孕むものですね。たとえば、大正時代の関東大震災の後に出てきたのは「震災文学」というよりは、むしろ地震とは関係なさそうに見えるモダニズム(新感覚派)やプロレタリア文学でした。これは東日本大震災の後に、ポリティカル・コレクトネスが強くなったことと似ています。平たく言えば「地震と文学」ではなく「政治と文学」の時代になった。これがズレですね。
今後も「ウイルス文学」や「パンデミックアート」は多少出てくるでしょうが、それはたいして意味がなくて、むしろ深層で起こるズレのほうが重要です。ただ、さっきも言いましたが、僕はすべての変化をコロナに帰することには反対です。変化はそれ以前から起こっていたからです。
オルタナティヴな関係概念
--福嶋さんが注目している、文化領域とは異なる部分の変化は?
福嶋:政治的に危惧すべきなのは、家畜化=国内化(domestication)が進むことです。韓国や台湾におけるコロナ対策で、行動履歴をデータ化したりしていますが、そうした技術がさらに浸透すれば、例えば店やイベントスペースやビルに入るときに一定以上の熱があると入場できないとか、行動を強く制限することが可能になる。これは家畜の管理と同じです。場合によっては、そこに外国人の締め出しが加わったりするでしょう。
ここ数年EUでは、個人情報保護を規定する法としてGDPR(General Data Protection Regulation)が定められて、企業の大規模なデータ管理に抵抗してきましたが、実際にこのような状況になると、むしろ人権を気にしないアジアのやり方が効率的だということになって、超強力なバイオポリティクスと監視技術が合体したような制度が生まれる可能性があります。実際、ドイツはこの間プライバシー保全のために、分散型のコロナ追跡アプリを導入しようとした。ただ、それをやるとアメリカの巨大テック企業の支配力を強めることにもなりかねず、ジレンマを抱えているわけです(参照:Germany’s Angst Is Killing Its Coronavirus Tracing App)。
さらに、アジア型の制度が浸透すれば、感染者を隔離するという名目の下、当局が政治犯を監視することもできる。中国はそれを堂々とやるでしょうから、表面的にはクリーンだけど中身は相当ダークな社会になっていく。
ーー新しい価値観を模索する上で、例えば文学ではどのような方向性が考えられますか。
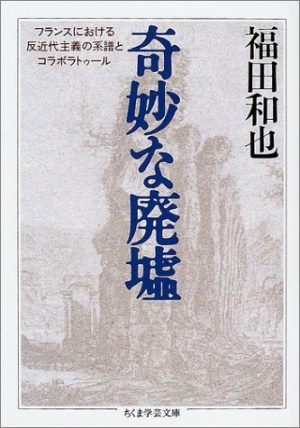
福嶋:昨今はアルベール・カミュの『ペスト』がよく読まれている。いいことですが、カミュはこの物語を留保つきの「勝利」で閉じたわけですね。しかし、彼自身、その地点には留まっていられず、やがて『転落』(1956年)のような「敗北」の文学を書くようになっていく。このあたりは福田和也氏のデビュー作『奇妙な廃墟』(2002年)でうまくまとめられています。読者が『ペスト』で自己完結してしまうと、カミュの屈折や陰影も見えなくなってしまう。
あと「文学と疫病」よりも前に、まず「宗教と疫病」というテーマが重要なんですね。いまは「濃厚接触」が忌避されているけれども、宗教の起源はまさに病者との濃厚接触にあったとも言える。なんといっても、イエス・キリストは病人を手で触れて治療したわけですからね。山形孝夫氏の『治癒神イエスの誕生』(2010年)によれば、それは当時の合理的な医療技術とは別のタイプの医療を推し進めることだったらしい。だからこそ、イエスの治療行為は社会的な軋轢も生んだのです。
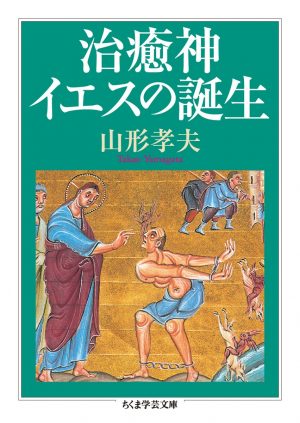
イエスは重度な病人を治療しながら、旅を続け「隣人愛」を説いた。しかし、考えてみると、疫病がまん延している世界での隣人愛や旅行は非常にリスキーなものです。しかし、だからこそそこには旧来の医療技術とは違うやり方で、コミューンを作る力もあった。このことが示唆するのは、管理社会的な状況を突破するのに、新しい形の宗教やそれに準ずる思想が求められるということです。
隣人愛という概念は、改めて注目すべきものだと思います。ユダヤ人哲学者・エマニュエル・レヴィナス(1906年~1995年)は「隣人」をモデルにして他者について考えた。レヴィナス的な隣人愛というのは、いわば自分の免疫力を下げてノーガードになるということです。自分のガードを下げて、存在への固執も手放して、あえてリスクを受け入れることで、初めて倫理が生まれるというのがレヴィナスの思想ですね。そのすべてを現実に落とし込むことは難しいとしても、レヴィナス的な思想がないと、管理社会の罠から逃れるのは難しいと思います。
ーー昨今では厚生労働省が「新しい生活様式」を提唱しています。これはいかにしてリスクを減らすかという発想のものだと思いますが、管理社会化から逃れるためには、あえてリスクを選択するような価値観も必要であると。
福嶋:たとえば、ソーシャルディスタンスは風通しのよい、明るい太陽の下で、他人とは適度な距離を保って接しなさいということですね。それはある意味ではとても「文明的」なんですよ。ハラスメントもおのずとなくなりますしね。しかし、文化というのは、そういう程よい距離を壊さないと成立しないところもある。特に、アングラ系の文化はそういうものですね。
ただ、ソーシャルディスタンスへの反対を声高に訴えても、理論的にはたいして面白くない。どちらかと言えば、近さや遠さという関係概念を、哲学や宗教の文脈で考えるべきではないでしょうか。隣人をモデルにしたレヴィナスや、テレコミュニケーションについて考えたジャック・デリダは、改めて読み直す価値があると思います。
いかにしてコナトゥスと戦うか
ーー距離を破壊するような価値観を提示するものとして、どんな表現が考えうるでしょうか。

福嶋:ちょっと間接的にお答えしますと、病気にも時代性があるんですね。特に平成後期には、うつや発達障害のように感染しないタイプの病気が目立つようになった。文学もそれに連動しています。たとえば、村上龍は平成前期には『ヒュウガ・ウイルス』(1998年)で感染症を描いたけれども、平成末期の『MISSING』(2020年)では抑うつ的な作家を主人公にしています。
韓国生まれのドイツの哲学者ビュンチュル・ハン(Byung-Chul Han)は『燃え尽き社会(Müdigkeitsgesellschaft)』(花伝社より刊行予定)という本で、病気のタイプとして感染(infection)と梗塞(infarction)を分けていて、現代社会ではうつや発達障害を含めて、後者が優勢になっていると述べています。平成後期の文学的想像力も、おおむね「梗塞」タイプですね。しかし、今回のパンデミックはそれをすっかり引っ繰り返したところがある。今後は感染と梗塞、この二つのタイプの交差するところで、面白い表現が出てくるかもしれません。
ただ、日ごろ批評を書いていて思うのは、小説というのはどうしても個人の内面的な「梗塞」に向かいがちで「感染」を捉えるのは難しいということです。逆に、映画は初期から「感染」を撮ってきた。セルゲイ・エイゼンシュテイン監督の『戦艦ポチョムキン』に「オデッサの階段」という有名なシーンがありますね。恐怖が伝染し、動作が伝染し、群衆がパニックになる。こういう場面は映画的にはうまく処理できますが、小説的に効果をあげるのは困難です。いずれにせよ、病気のタイプからジャンルの性質なり時代の特徴なりを考えるのは、批評のプログラムとして面白いと思います。
--文学は梗塞的な表現が得意とのことですが、特に象徴的だと考えている作品は。

福嶋:平成文学との関わりで言うと、意外に大正から昭和への転換期は面白い問題を含んでいます。この時期には、内向的に自分の異常性を発見するような小説が多い。例えば、肺結核を患っていた梶井基次郎や堀辰雄は象徴的だと思います。興味深いのは、彼らは1918年のパンデミックのことは眼中になく、結核の話しかしていないことです。そして、結核は感染症ですが、彼らの表現はむしろ内的な「梗塞」に近いように見えます。
ーーその大正時代の精神は、平成の精神にも近いものがあると。
福嶋:今夏に平成文学論の本を出すことになっていますが、僕はそこで大正と平成をアナロジー的に結んでいます。大正にはデモクラシーの運動があり、ユートピア文学があり、大震災があり、インターナショナリズムが唱えられた。平成もインターネットによるデモクラシーがあり、ディストピアのモチーフが流行り、二度の大震災があり、グローバリズムが唱えられた。逆に、昭和あるいは令和に入ると、インターナショナリズムあるいはグローバリズムの限界が言われるようになる。パンデミック後の世界恐慌の可能性が語られるという意味でも、令和初期は昭和初期と似ています。梶井は「桜の樹の下には死体が埋まっている」という言い方で、当時の不穏な世界情勢を暗示的に語っていたと思います。
--表現のアップデートを考える上で、参照にしたい本はありますか。
福嶋:社会学者のウルリッヒ・ベックが言っていることですが、気候変動であれテロリズムであれ金融恐慌であれ、現代のリスクに対応するためには、グローバルな法を作る必要がある。その主張の核にあるのは、国家が自国を守ろうとするならば、まずは自国の主権をある程度譲り渡さなければいけないというパラドックスです。これは先ほどいったレヴィナスの隣人愛にも通じる考え方ですね。現実には各国は防壁をどんどん上げているわけですが、それではグローバルな問題を解決できない。
付け加えると、レヴィナスが過激なのは、コナトゥス(自己自身を保全しようとする欲動や努力)を解除しないと、倫理は起動しないと言っていることです。レヴィナスはこのコナトゥス、つまり自己保存欲求を相対化するために、隣人愛をもってくるのです。これは別に自己犠牲を訴えるものではなく「存在すること」を第一目標としないような倫理が要るのだ、という話ですね。個人にせよ、集団にせよ、おそらく今後は自己保存の要求が露骨に出てくるでしょうし、国家もそこに便乗してくる。そうすると、極端な管理社会化にも抵抗できなくなる。その意味でも「コナトゥスへの抵抗」というレヴィナスの議論をどう引き継ぐかが、パンデミック後の大きなプログラムになると思います。
■福嶋亮大
1981年京都市生まれ。文芸批評家。京都大学文学部博士後期課程修了。現在は立教大学文学部文芸思想専修准教授。文芸からサブカルチャーまで、東アジアの近世からポストモダンまでを横断する多角的な批評を試みている。著書に『復興文化論』(サントリー学芸賞受賞作)『厄介な遺産』(やまなし文学賞受賞作)『辺境の思想』(共著)『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』『百年の批評』等がある。
新着エッセイ
新着クリエイター人生
水先案内





