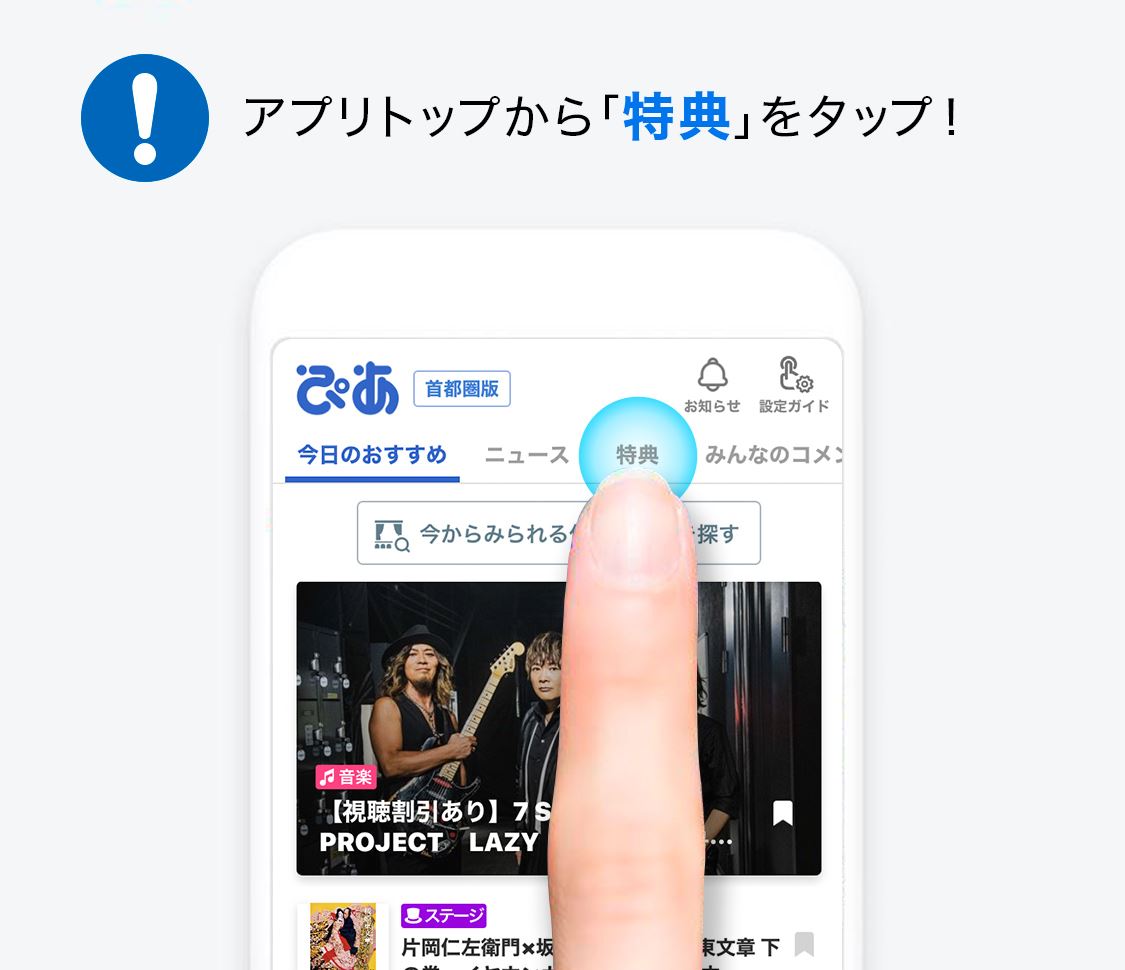中村倫也の才能論「自信なんてひとつもないです」
映画
インタビュー

中村倫也 撮影/友野雄
続きを読むフォトギャラリー(14件)
すべて見るこの世に才能なんてものがあるから、人は苦しむのかもしれない。
5月20日(金)公開の映画『ハケンアニメ!』は、アニメ業界で闘う者たちを描いた熱血エンタテインメント。その中で中村倫也は天才監督・王子千晴を演じている。
ものづくりに情熱を注ぐ人々の奮闘に胸が熱くなると同時に、己と才能という最も直視したくないものと限界まで向き合うさまは、どこか凄絶ですらある。
天才を演じた中村倫也は、才能というものについてどう考えているのだろうか。
自分を超える作業は、魂を雑巾絞りするようなもの

初監督作品『光のヨスガ』で社会現象を巻き起こし、一躍時代の寵児となった王子千晴。普段の飄々とした態度は、まさに天才そのもの。だが、その内側にはゼロからものを生み出すことへのプレッシャーと焦燥が渦巻いていた。
「僕と王子とでは置かれている状況のレベルが違いますけど、僕もエッセイを書いている中で『出ないなあ』というのは何度もあったので、そのへんの生み出す人の焦りはわかる部分もありました。そういう自分を超える作業って孤独だし、魂を雑巾絞りするようなものですからね」
部屋で大量の紙に埋もれながら、己の才能とひとり格闘する王子。演ずる中村が見せた怒りにも似た苦悶の表情は、今まで見ることのないもので、心を撃ち抜く強度がある。
「役者やっててもありますよ。たとえば台本を読んだとき、こいつのこの感情知らないなみたいなことは都度都度あって。そのときはやっぱり事前に家でそれを探さなきゃいけない。そのときはたぶん、あんな感じの顔を僕もしているんだろうなって。目、キマってるんだろうなと思います(笑)」
だが、王子は決してその苦悩を他人には見せない。中村倫也という俳優もまた創作過程における努力や苦労は易々と明かさない人に見える。
「見せるものじゃないんでね。手品師がタネを明かすのと一緒で。舞台とか如実にそうですけど、観客がこの役者頑張ってるなって思うのって物語に入り込むのを妨げる要因の一つになる。僕たちは観ている人たちを驚かせなきゃいけないし、役に説得力を与えなきゃいけない。この役者頑張っている、になっちゃいけないんですよね」
インタビューでも、時にはぐらかすように、わざと茶目っ気たっぷりのユーモアで核心を包み隠す。つかめそうで、つかめない。だから人はもっと中村倫也のことが知りたくなる。
「誤魔化し誤魔化しでやっていますね(笑)。そこは申し訳ないなと思いつつ。演技論なんて言った途端安くなるし、それを毎回毎回全部出してたらすぐゼロになる。だから、お互いwin-winの関係でいるためにも、ある程度はぐらかして、代わりに嘘も交えて、ギャグをかましつつみたいなことは、僕の『プロフェッショナル 仕事の流儀』です(笑)」


若い頃は、周りに突っかかることもありました

劇中では、アニメに懸けるさまざまな立場の仕事論が描かれていく。柄本佑演じる鬼プロデューサー・行城理は徹底的な数字主義者。中村もまた人気と共に責任ある役を多く任されるようになり、そこには当然数字や評価がつきまとうようになった。
「ぶっちゃけあんまり気にしてないんですよね。視聴率とか興行収入とか動員数とか、全部あるに越したことないと思ってるし、主演という立場をやらせてもらえるようになってるので、そのへんはもちろん背負わなきゃいけないんですけど。作品か数字かの二者択一で言えって言われたら、そんなことより現場でみんなが楽しんでる方がいいってなっちゃう。で、理想は二者択一じゃなくて両方やればいいじゃんっていうのが僕の考えです。極論ですけど」
一方、中村演じる王子の仕事論も印象的だ。「どれだけやろうが納得いかないものを世に出したらおしまいなんだよ」――アニメ放映に向けて周囲が着々と制作準備を進める中、その内容に納得がいかない王子は、そう言ってこれまで積み上げてきたものをひっくり返そうとする。はたから見れば、傍若無人。その一切妥協をしない姿勢は、一緒に働く分には困りものだけれど、どこか憧れる部分もある。
「僕は迷惑かけるタイプじゃないので王子みたいなことはしないですけど、でもなんか若い頃はね、ありましたよ。役者のくせに、この本、もっとこうしたら良くなるんじゃないかみたいに突っかかることも。だから僕のことを嫌いな演出家とかもいっぱいいると思うんですけど。でもそれはそのときの誠意だったんだよね」
それは、今の柔らかくてゆったりとした空気の中村倫也からは想像もつかない姿だ。
「まあそこは大人になりましたよね(笑)。うまく立ち回れるようになったというか。いつもものづくりをしてて思うのは、意見のすれ違いだったり、ちょっとした衝突だったり、なんやかんやあったとしても、結局みんなが良くしようと思ってやってるっていうのが大前提。そのへんのスポーツマンシップさえあれば、どんなことが現場で起こっても、わりと平気になりましたね。自分のことだけじゃなく」

なんでもかんでも誰かのおかげですって言う人は好きじゃない

時にワガママともとられる王子の言動に手を焼きつつ、彼が持てる才能をすべて発揮できるよう舞台裏で奔走するのがプロデューサー・有科香屋子(尾野真千子)だ。どんな天才も、どんなスターも、ひとりでものはつくれない。人の支えが、才能をさらに高くへ羽ばたかせるのだと感じさせてくれる作品でもある。
「作品として見たときに僕の心に残ったのはそっち側だったんですよね。王子だったり瞳(吉岡里帆)だったり、これをやりたいというものがある人のために、支えて動いてくれる人がいる。そこにぐっと来ました。それはきっと僕の中にもそういう経験があったりするからでしょうね。会社の人間もそうだし、現場の仲間たちもそうだし、別に自分のために動いてくれる。そんな大げさなことじゃなくても、誰かが何かを発して、それに周りが連動すること自体、美しいよなと思います」
だが、それこそ「若いとき」は、その美しさなど感じる余裕もなかった。
「もう自分自分です(笑)。それがいつのタイミングだったか詳しく覚えてないですけど、ひとりじゃ何もできないよなあと思えるようになって。と、同時にこうも感じたんですよ。自分の努力もないとできないよなって」
そう言って、中村は続ける。
「なんでもかんでも誰かのおかげですって言う人は好きじゃないんですよ。嘘つけって、お前が歯食いしばってやってきたからだろうって思う。たぶん日本人的な美意識がそんなに強くない方なんです、僕は。おかげさまでって言葉があんまり言えないタイプなんで(笑)」
耳心地の良い綺麗事だけで語らない。ちょっとひねくれた部分も厭わず見せる。そんなところもまた中村倫也のいとおしさだ。
「本当なら、他人のミスを自分の責任だと捉えて、自分の成功を他人の手柄だと思えたらいいんですけどね。でもそればっかだと、模範解答してんじゃねえよってなっちゃうので、僕みたいな性格の人間は特に(笑)。だから、誰かのおかげも自分のおかげも両方必要なんじゃないかなっていうのは、いつだったか同時に思いましたね」

旬や流行が過ぎ去ることは怖くない

天才監督・王子を演じた中村。芸能界という才能がひしめき合う世界で生きてきたからこそ、自分の才能にも他者の才能にも敏感なところはあるはず。この世に「天才」というものははたしているのだろうか。
「天才はいるんじゃないですか。僕の中で天才の定義があるんですよ。簡単に言えば、若くして周りがほっとかない人が、天才。その定義で言うと、自分は周りからいくらでもほっとかれていた若手時代だったんで、才能がないなっていうのは痛感いたしまして。だけど、そんな人間が今もこうしてやらせてもらえることから考えても、才能だけじゃないんじゃないのとは思う。真面目な話、才能なんてものは最初のスタートダッシュなだけで。才能があろうとなかろうと、それを持続できるガソリンというかね、向上心とか努力とか好きっていう衝動の方が、長い目で見たら大事だなって思いますね」
そう語る横顔に、先ほど彼が口にした「嘘つけって、お前が歯食いしばってやってきたからだろうって思う」という言葉がよぎった。中村倫也が世に出てきたのは、人の支えはもちろんある。でも間違いなく、スポットライトが当たらない場所で、彼が努力を積み重ねてきたからだ。
「僕の場合、役者として幸せになれる未来がまったく見えないスタートだったんで、まあ、おのずと必死こきますよね。そうすると、なんだよこの現場って思ったり、なんだよこの役って思うような役でも、自分の気持ちと姿勢次第で学べることが見つかる。たとえ1日に1カットも撮られない日があろうと、台詞が1行もない台本を渡されようと、どの出会いも無駄にしたくないなっていう想いだけは人一倍ありました。まあ、無駄にできない状況だったからですけど」

そして今、中村倫也という才能を多くの人が認めている。王子千晴は『光のヨスガ』という伝説のアニメを生み出すも次が続かず、8年もの間、表舞台から姿を消していた。光り輝く場所に立てば、今度は才能が消費される恐怖が生まれる。だが、その恐怖とは中村倫也はどうやら無縁のようだ。
「消費されることに対しては、特に何にも思っていないです。旬とか流行みたいなものは、そのうち過ぎ去るだろうなとは思ってたんで、別に怖くはないですし」
この達観とも客観とも言える姿勢。それは、流行が過ぎ去っても怖くないと思えるだけの、揺るぎない自信があるからなのだろうか。
「自信なんてひとつもないです。でも取り繕ったところで、自分は自分でしかないというか。明日、プロレスラーに喧嘩で勝てって言われても勝てないですし。その都度できることをやっていくしかない、って思っているから怖くないのかな。それより怖いのは、過去の自分と同じ表現をしちゃうこと。そうならないように、とは思っています」
一過性の人気や流行ではなく、向き合うべきは自らの表現。これだけ熱狂の渦にいても、まるで舞い上がったところが見えないのは、そう理解しているからだろう。
一度やった役をコピー&ペーストするような芝居はしない。作品ごとにまるで異なる顔を見せる中村倫也の演技は、そんな矜持に支えられていた。



(クレジット)
撮影/友野雄、取材・文/横川良明
フォトギャラリー(14件)
すべて見る