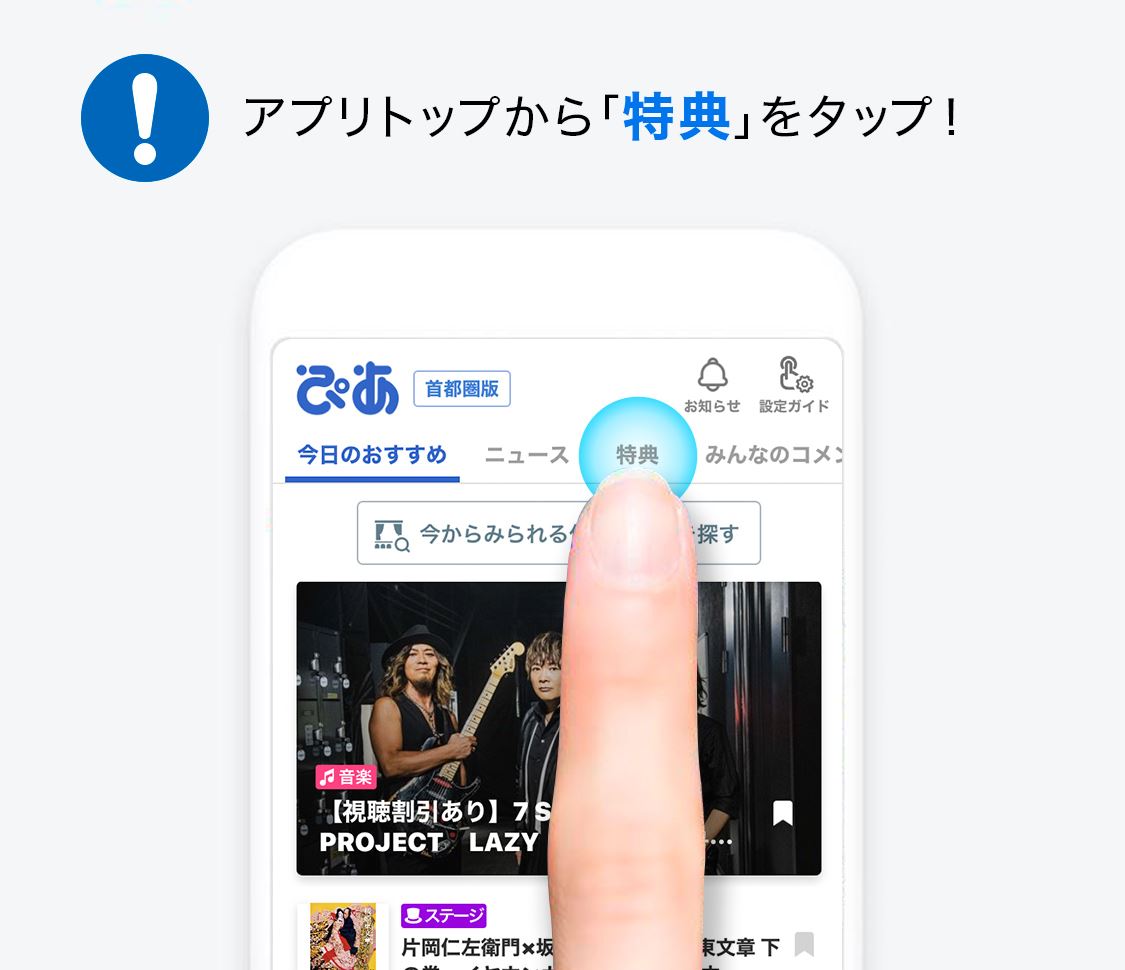横浜流星と藤井道人が不寛容社会に見る救い「信じられる人と一緒にいられればいい」
映画
インタビュー

左から)横浜流星、藤井道人 撮影:奥田耕平
続きを読むフォトギャラリー(13件)
すべて見る自ら「兄弟」と命名するほど固い絆で結ばれた俳優・横浜流星と監督・藤井道人が、渾身の新作を世に放つ。タイトルは『ヴィレッジ』。横浜にとって、藤井組の長編映画としては念願の初主演となる。
閉鎖的な“村”を舞台に、父親の汚名を背負い、村人から侮蔑の眼差しを向けられてきた男が掴んだ泡沫の幸福と、逃れられない転落。主人公・片山優の苦悶を、まるで皮膚から感情が裂け出てくるような抑制と放出の演技で横浜流星が見せている。
俳優・横浜流星の代名詞となるような1本はどのようにしてつくられたのか。その裏側を2人に語ってもらった。
ひとつの失敗も許してもらえないことに恐怖を感じる

――今作では、横浜さんの意見が脚本づくりに反映されていると聞きました。具体的にはどういう部分でしょうか。
横浜 脚本づくりをしていた1年前と今では状況はまた違いますけれど、当時、役者をやっていて感じていた恐れだったり戸惑いだったり怖さみたいなものを、監督にすべて伝えて、それを優に反映してくれました。
藤井 具体的に言うと、優がどんどん村の顔として祭り上げられていくところですね。光が射したように見えるけれど、結局のところ一寸先は闇。いつまたみんなに手のひらを返されるんじゃないかという恐怖が優には張りついている。笑っているんだけれど、決して本質的な笑顔ではないところや、実際に彼が転落してくくだりは、流星が俳優生活では味わえない感情を優に代弁してもらいました。
横浜 僕自身も、ほんの小さな失敗や過ちで転落していく人を近くで見てきたので。自分も同じような立場になったら、優のように転落していくんだろうなという恐怖はリアルに感じました。
――人間は誰しも過ちを犯すもの。なのに、失敗した人をもう這い上がってこられなくなるまで総叩きにするのが現代社会です。この過ちが許されない社会についてどうお感じになりますか。
藤井 人にはそれぞれ歴史があって、自分たちが歩いてきた道なので、そんなもの全部無視しちゃえよとは言えないんですけど、もっと寛容であるべきだとは思います。匿名性が増してきたからこそ、すごく不寛容の世の中になっている気がしていて。
横浜 特にこの仕事をしていると、ひとつの失敗も許してもらえない。その恐怖は感じます。
藤井 今って他者のいいところを探すことが下手くそになっている。それってカッコ悪いなと思うんです。「誰かを叩くことでしか村の立ち位置って上がらないんだっけ?」というのは常々疑問に感じるところで。綺麗事かもしれないですけど、もっと他者に優しくなれる村だったらいいのになと思うし、せめて自分たちくらいは他者に対して許しの眼差しを持っていたいと思います。

――横浜さんも藤井さんも社会的な立場があるからこそ、転落の恐怖はリアルに感じられるのかなと思います。
藤井 全然あるよね。
横浜 僕たちに限らず、表に出る人はみんなある種の息苦しさを抱えているんじゃないかなと思います。人間って怖いなって感じることが増えたというか。
藤井 生活とか、そういうことだけじゃなくて、作品に対してもより意識が高まっている部分はあります。『新聞記者』のときにプロデューサーの河村(光庸)さんがめっちゃ怒っている瞬間を見たことがあって。何があったかと言うと、ポスターのコピーやデザインに対して、こうじゃないんだと怒ってらっしゃったんですね。それまでの僕は宣伝に対して違和感を持っても、向こうもプロだしお任せしようって見て見ぬふりをしていたところがあって。でも、河村さんの熱意を見て、この人は売るまで責任をとる覚悟でやっているんだと思ったし、それがすごくカッコよかった。そこからは僕も、自分は監督なんで宣伝はお任せしますじゃなくて、ちゃんと熱意と責任を持って関わりたいと思うようになりました。
――横浜さんは一歩外に出れば、衆人環視的なプレッシャーに晒される毎日を送っているわけですが、どういうメンタルでその状況と向き合っているのでしょうか。
横浜 確かにいろんな人に何かを言われる仕事ではあるけれど、ちゃんと自分が信じられる人たちと一緒にいられればいいのかなって今は思っています。周りからどう見られるのかはわからないし、何がきっかけで評価が一変するかなんて、僕自身はどうしようもできない。でも、自分には信じられる人たちがいる。そしてその人たちがそばにいる。そこさえ失わなければ、何を言われても気にしなくていいのかなと。そういう意味でも、藤井組の現場は僕にとって救いです。またこの座組みで作品をつくることができる。それがあるから、頑張れているというのはあります。
藤井組には、自分の想像していなかった表情を引き出してもらえる

――監督は今の社会について「他者のいいところを探すことが下手くそになっている」とおっしゃいましたが、監督自身は人のいいところを見つけるのがお上手な印象です。監督と話していると、こちらもなぜか肯定してもらっているような気持ちになります。
藤井 人は否定されるより肯定された方が良い結果を生むと思うんですよね。自分もやっぱり人間なんで「馬鹿野郎」と言うときはあります。けど、愛のある「馬鹿野郎」でありたい。もちろん現場は安全が第一なので、事故の危険性があるときは強く注意します。人って、強く言われないと心にちゃんと残らないから。でも、強く言ったら、そのあとのケアが大事。あとで、どうしてあんなに強い言い方をしたのか、ちゃんと相手に説明します。俳優も、スタッフも、現場で萎縮させる必要はまったくないと思います。
横浜 藤井組で芝居をしていると、誰よりも自分のことを理解してくれていると信じられるんです。どの現場も、監督を信じて突き進む気持ちは同じです。でもやっぱりお芝居って正解がないから、やりながらわからなくなる瞬間があって。そのときに孤独を感じるんですけど、藤井組にはそれがない。だからこそ、毎回自分の知らなかった感情を引き出してもらえるのかなという気がします。
――そういう意味では、横浜さんが今回演じてみて、自分の知らなかった感情に辿り着いた場面はどこですか。
横浜 いちばんは、村長(古田新太)から「人生逆転するチャンスだ!」と言われるシーン。あそこは自分が想像していたものとはまったく違うものになりました。
藤井 あそこはたぶん今作でいちばんテイクを重ねたんじゃないかな。あの場面は、どん底にいた優がようやく蜘蛛の糸を掴んだ瞬間。だけど、家のことや自分自身の罪のことを考えると、簡単に「やった!」とは言えない。うれしさなのか、怯えなのか、簡単にカテゴライズできない複雑さを表情に乗せてほしいと流星に課したシーンでした。
横浜 やっていて、わけのわからない感情になりました。感情と表情は違う。僕の中で今までに感じたことのないものが渦巻いていて。まったく自分が想像していなかった表情を監督に引き出してもらったなっていう。

――テイクを重ねていくことで、どう変わったのでしょうか。
藤井 言葉が正しいかわからないですけど、解像度とか情報量の問題だと思っていて。古田さんが「人生変えるなら今だ、頑張れよ」と言う。これをピュアに受けちゃうと、安堵だったり、これからなんだ自分はという希望が湧き上がってくると思うんですよ。実際、脚本を読むとそうなっていて、流星の芝居も最初のテイクでは笑みが強かったんです。でもそれだと、この映画はハッピーな方向に行くんだという単純なサジェスチョンになってしまう。だから、もうちょっと複雑さを練り込みたいんだよねと話をして。うれしいんだけど、うまく笑えない。なぜなら、優は笑ったことがないから。そういうバックボーンをテイクごとに差し込みながら、徐々に複雑さや解像度を増していきました。
――そういったディレクションは、もともと監督の頭の中にある正解に俳優の芝居を近づけていくイメージなのか。あるいは俳優の芝居を見て、さらに監督の中でヴィジョンが膨らんでいくイメージなのか、どちらでしょう。
藤井 そのシーンに関しては「これがほしい」という明確なものがありましたね。もちろん一発目にやってくださるのは役者なんで、これが一発目に出るんだったら、さらにこれがあった方がいいかもと欲張りしちゃうこともよくあります。というか、もう毎カット欲張っております(笑)。
――横浜さんはそういったテイクを重ねて芝居を高めていくとき、間にインターバルを置くタイプですか。それとも、とにかくどんどん撮影していく中で、自分の中の感情を積み上げていくタイプですか。
横浜 僕は積み上げていくタイプです。というか、一度冷却しちゃうとダメになりそうで。
藤井 そんな時間も与えないしね(笑)。
横浜 そうそう。そもそも与えてくれないですし(笑)。
藤井 僕が流星と話をして、ベースに戻ろうとしたぐらいに、「監督戻られたら行きまーす」ってなる。
横浜 鬼です(笑)。
藤井 もちろん一旦冷却した方がいいときは時間を設けますけどね。
横浜 僕自身はちょっと時間を置いちゃうと積み上げてきたものをすべて崩してしまうような感覚になっちゃうんです。だったら、そのままやった方がいい。頭では整理しているつもりでも、まだ体までは追いついていないような。そういう状態でいった方が、結果的に自分の想像していなかったような表情を見られることが多い気がします。
横浜流星は、心の部分が鍛錬された俳優になってきている

――表情という意味では、あのベッドの上で朝日が射し込んでくるときの優の顔が、出力の高いお芝居が印象的だった中で、逆にすごく削ぎ落とされたものになっていて鮮烈に残りました。
横浜 あそこもいろんな思いがありました。それこそ、あんまり整理できていなかったとは思います。
藤井 あそこは能面に見えたかったんですよね。観客にここから優はどうなっていくんだろうと思わせたかった。そのためには、ああいう表情が必要でした。
――監督からは、現場でどんなオーダーをされましたか。
藤井 「瞬きしちゃだめ」って(笑)。最初に部屋に飾ってある能面を映して。そこから光が射して、優にトラックインするので、結構時間が長いんですよ。その間、瞬きをしないでほしいってお願いしました。そこは大変だったんじゃないかな(笑)。
横浜 ずっと感情に蓋をしていた優が、幼なじみの美咲(黒木華)と再会して、感情を放出できた。優にとって、美咲は光のような存在であり、ひとつ心が救われたシーンでした。だから、優、良かったなと思いました。顔は、あんな顔ですけれども(笑)。
――「感情と表情は違う」というお話がありました。内側にあるものとアウトプットが乖離しているのって技術的にすごく難しい気がするんですけど、どう成立させているんでしょうか。
横浜 難しいです。だから、1人ではできなかった。カットがかかるたびに、監督がいろんな言葉を投げてくれて。それを自分の中で咀嚼しながら、なんとかやっていったという感じです。最終的には、頭で考えてもわからないんです。だから、まずはやってみる。そこからまた考えようという繰り返しでした。

――6回目のタッグですが、俳優・横浜流星の成長を感じたところはありますか。
藤井 精神力がぐっと上がったと思うんですよね。組を信じる力だったり、本を深く読み解く力だったりが年々増してきて、心の部分が鍛錬された俳優になってきていると思います。だからこそ、自然と立っているだけで絵になるようになってきた。昔はもうちょいふにゃふにゃした兄ちゃんだったんですけどね(笑)。『流浪の月』の李(相日)監督とか、『春に散る』の瀬々(敬久)さんとか、いろんな監督や俳優と出会い、彼自身が真面目に誠実に取り組むことで得てきたものが絶対ある。それを感じられたのは今回一緒にやってすごくうれしかったですね。
――それは、どんな瞬間に感じるんでしょう。なんでもない話をしている瞬間なのか、やはりモニター越しなのか。
藤井 モニターを通して見たときですね。喋っているときは、お互いスウェットみたいな格好でダラダラしゃべってるだけなので、そこは昔とあんまり変わらない(笑)。
――横浜さんはどうでしょう。これだけ信頼し合える監督と出会えるのは、俳優として得がたい幸福だと思いますが、逆に馴れ合いになってはいけないという緊張感もありますか。
横浜 それはもちろんです。また藤井組に入るまでに、いろんなことを学んでこなくちゃいけないし、毎回成長したものを見せなきゃ一緒にやる意味がない。藤井組の現場は救いであると同時に、自分が学んできたものをぶつけに行く場でもあるんです。




取材・文:横川良明 撮影:奥田耕平
横浜さんヘアメイク:永瀬多壱(VANITES)
横浜さんスタイリング:伊藤省吾(sitor)
<作品情報>
『ヴィレッジ』
4月21日(金) 全国公開
配給:KADOKAWA/スターサンズ

フォトギャラリー(13件)
すべて見る