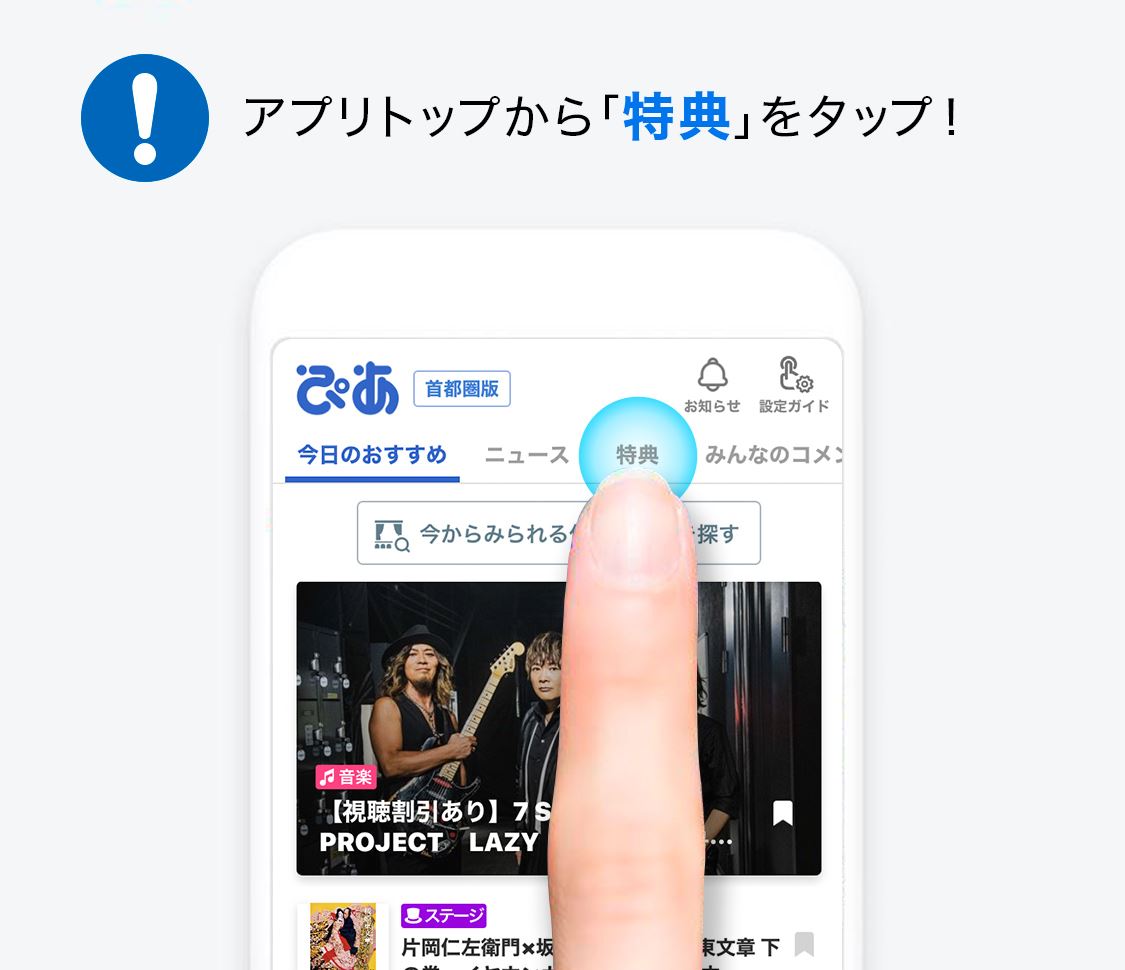監督・齊藤工、楽曲・yama 2人が作り上げた残酷な物語の中にある救い「パンドラの箱みたいな物語にyamaさんの曲が蓋をしてくれた」
映画
インタビュー

左から)齊藤工、yama 撮影:友野雄
続きを読むフォトギャラリー(9件)
すべて見る映画「スイート・マイホーム」が9月1日に公開となる。原作は2018年に第13回小説現代長編新人賞を受賞した神津凛子の同名小説だ。
舞台は長野。愛する妻と幼い娘たちのために一軒家を購入した清沢賢二(窪田正孝)。住宅の地下に巨大な暖房設備があり、家全体を温めてくれるというその住宅は「まほうの家」と謳われていた。しかし、幸せだった生活はある出来事をきっかけに、恐怖の時間へと転換していく。
監督を務めた齊藤工と、主題歌「返光(Movie Edition)」を歌うyamaに話を聞いた。
タブーとも言える出来事をどう描くか

何気ない家族の日常。しかし、その中でヒタヒタと恐怖が近づいてくるような作品だ。
今回の作品での表現において、齊藤監督はまずどのような点にこだわったのだろうか。
「賢二の実際の佇まいと、外から見える理想の夫像の間にあるものを、描きたいなと思っていました。原作もそうなんですけど、彼は決して褒められた人間ではありません。でも、彼を見放してしまうというか、切り捨ててしまうと多分、映画を最後まで観ることが苦痛になってしまう。ですのでこれが絶妙なラインだと思うし、窪田さんの配分の妙だと思うんですけど、ギリギリ彼を応援まではいかなくても、完全に切り離さないラインを探りました。原作だと、賢二以外にふたりの視点から同じ事象を描いているので、いろいろな見え方があり、豊かなんですけど、映画ではそれがない分、彼を嫌わせないようにすることは、すごく意識しましたし、窪田さんもご理解して演じてくださったことは、本当に生命線でした」
そして原作について「人間の究極のタブーが詰まった箱のような作品」と映画公式サイトでコメントしていた齊藤。
原作を読んだときは「継承や伝承という女性性、母性にまつわる物語だな、と思っていました」と言う。母性の奥にあるものを儀式的に伝承していく、という意味で、脚本開発のタイミングから「片目を隠した状態の女の子」の描写を物語の始まりと終わりに入れた。
そんな物語の中には、小さい命に対して起こる出来事としてはあまりにも残酷な描写がある。
そのシーンについて齊藤は「どう描写するのか、ということは撮影しながらも考えていた」と語る。しかし、それはこの作品において欠かせない場面でもあった。
「原作も、ゴール地点が残酷なまでに“そこ”だったので。子どもが悲惨な状態になってしまうということの捉え方と、どこまで描くか、ということが、撮影に協力してくれる赤ちゃんに対しても本当に繊細な部分だったんです。でも、僕らとしても現場的にはそこをマイルドに描いてしまうと、実写にする意味はなくなってしまう、と思って撮りました」
そんな作品について、yamaは「ジワジワと追い詰められるような、ずっと冷や汗をかいているような状態で観ていた」と振り返る。
「最後まで気が抜けない映画ではあったんですけど、すごく引き込まれました。
楽曲については、もちろん自分の作品でもあり、でも『スイート・マイホーム』という作品の世界観にも寄り添いたいと思っていたので、自分の色と映画の色をどこまで掛け合わせられるかな、とその中間のポイントを意識して表現はしています」
「パンドラの箱に蓋をする」yamaの楽曲

主題歌について、「yamaさんでなければ」と言う齊藤監督。普段の生活の中でもyamaの楽曲に触れていたというが、インタビューで挙げたのはアニメ「王様ランキング」のエンディングテーマ「Oz.」だ。
「yamaさんの曲が作品を浄化する、救済するという意味合いが素晴らしくて。むしろ、そのエンディングのために次の話も観るというぐらい」と絶賛した。
そして、今回の主題歌を依頼することになったとき、影響を受けた作品として挙げたのが、齊藤自身が主演を務めた『シン・ウルトラマン』のエンディングテーマ。米津玄師が歌う「M八七」。
「『君たちはどう生きるか』でもそうですが、物語を踏襲して、観ている人間にとってエンディングでいろんなものが着地していく。
エンドロールで最後にかかる楽曲は余韻の中、自分が観たものを振り返り、自分の生活と繋がっていく、そういうブリッジになってくれるようなものだと思うんです。
yamaさんと何度かラリーさせていただいて、早い段階で今の『返光』という楽曲にたどり着いたときに、見事に作品に寄り添ってくれながら、yamaさんの世界観になっていました。作中のどのキャラクター、と断定していないけれど、していないからこそ、観た方にとってそれが浄化や治癒に近い反応になっているんですよね。
本当にパンドラの箱みたいな物語ではあるんですけど、その蓋の仕方としては、もうこれ以上ない、本当に素晴らしい楽曲です」
一方、yamaは作品に寄り添うという点で、どのような点に気を配ったのか。
「楽曲の全体的な雰囲気としては、バラードですし、ちょっとスローテンポな温かい印象なんですよね。メロディも含めて懐かしさを感じるような、親しみやすい曲に聴こえるんですけれども、この作品らしさを入れるとしたら、優しく歌うだけではないのかもな、と思って。感情の波を変化させたり、不安定な心情が出るように気をつけたりしました。よく聴くと『おやおや?』と思うような、ちょっとした違和感を詰めてみたりしています」
パンドラの箱を閉じる、というある意味、重大な役割を担っているyamaの楽曲。映画の余韻を曲で包み込み、どのような思いで観客は帰路につくのか。その余韻の噛み締め方はさまざまなものになりそうだ。
音楽を通じて「芯の部分が似ているのかな、と感じた」

yamaについて、生活の中で楽曲に触れて知っていたという齊藤に対し、親交のあるACIDMANの大木伸夫から齊藤について聞いていた、とyama。大木と齊藤は20年来の仲だという。
大木に曲を書き下ろしてもらったことがあるyamaは「自分はACIDMANの世界観も、大木さんの考え方もすごく好き」と語る。
「……ということは、齊藤さんも素敵な方なんだろうな、ということはなんとなく感じていました。今回お話をもらったときに、自分が担当させていただけるならぜひ協力したい、と嬉しい気持ちではありましたね。音楽が好きという共通点があることで、齊藤さんとは少し芯の部分が似ているのかな、と勝手に感じていました」
そんなyamaの言葉に、齊藤も「合点がいきました」と大きく頷く。
「映画では、賢二の物語になっていて、この物語の中の“ある人物”の悲しみ、苦しみを本当の意味で浄化させるところまでは描ききれていないんですけど、yamaさんの主題歌によってその人物の情念は成仏してくれたな、と思うんです。
ACIDMANと僕の中では共通の、すごく本質的な部分をyamaさんの楽曲は表現してくださっているんですよね。この作品に必要だった、人物の1枚も2枚も奥にある感情を捉えて表現されているというか」
また、“ある人物”を演じた俳優とyamaは同じ回の試写で鑑賞していたそう。そのことを後日知った齊藤。「おふたりが話をされて、何か通じ合っているように見えた、と第三者から聞いたんですけど、ある種、モンスターとも言えるキャラクターを肯定してくれた2人だったので、その2人が繋がるということは、関わった人間としてはとても感慨深かったですね」と微笑んだ。
他者と対峙して生まれるものがある

そして話は「表現」について。
俳優・監督である齊藤、ミュージシャンのyamaはものづくりの際にどのようにインスピレーションを得ているのか尋ねると、齊藤はyamaの回答に対し「それは僕が聞きたい」と身を乗り出した。
yamaは「参考になるか分からないんですけど」と前置きしつつ、「人と話すこと」を挙げた。
「映画や小説、マンガとか、いろんな作品を見て刺激を受けることもあるんですけど、人の考え方や人生観、価値観を聞いたときが多いですね。曲を書き始めたのが本当に最近の話で、最初はひとりで煮詰まりながら自宅で制作していたんですけど、うまくいかないな、って。案外、人と話してコミュニケーションを取っていたほうがアイディアは浮かんできました」
一方、齊藤は写真家としての角度から自身を分析した。
「振り返ると、モノクロの写真をなぜか撮っていて。風景の写真って、もちろんそのときの天気とかあると思うんですけど、僕じゃなくても捉えられる景色だと思ってしまうんです。じゃあ僕にしか撮れないものは何か、と考えたときに、人の顔だったんですよね。その対象物と自分の関係値が如実に出るものだな、ということがわかって。だからyamaさんの話じゃないですけど、自分と違う生態系というか、心の生態系の差じゃないけど、その違いを知ることは己の輪郭を知るということじゃないですか。自分はここが足りないんだとか、自分はここにこだわってるんだ、みたいな輪郭が見えるんですよね。他者と対峙しているときに何か唯一無二のものが生まれるのはそういう瞬間だから、たぶん写真を撮ることを続けているんだな、話を聞いていて思いました」
yamaも「今の話を聞いて納得しました」と頷く。
「どうして人と話して曲ができるのかが分からなかったんですけど、そうなのかもしれない。人と話すことによって、自分とも対話してたんだな、と気づきました」
それぞれの、表現に対するパッション

一方、表現を続けていく上で重要になってくるのがパッションではないだろうか。この問いについて、yamaは「もともとパッションがない人間だった」という。
「誰かのライブに行ったこともないし、やったこともない状況で、完全に1人で音楽を完結させていたので、パッションという熱量に触れる瞬間がなかったんです。無機質なものとして音楽を捉えていたんですけど、上京して、メジャーデビューしてから、熱量を求められるようになって。ようやく最近ライブを通して、そこに触れたんですよね。
お客さんが目の前にいて、それぞれの人生がある。そこの会場に来てくれるまでに、もしかしたら本当に苦しくて、足を引きずりながら来た人もいるかもしれない。1人1人の物語を考えたときに、自分は何を歌えるだろうとか、その思いから出たときのその日の表現が結果的にパッションに繋がっているな、と最近は気づきました」
齊藤は過去に電車の中で会ったある女性について話してくれた。
「雨の日に、ずぶ濡れの女性が乗ってきたんです。なんでこんなに濡れているんだろうと思ったらベビーカーを押していたんです。突然の雨だったので、赤ちゃんが濡れないように傘をさしていたんでしょうね。だから彼女は濡れていて。赤ちゃんを守り、自分が濡れる。それが彼女にとって特別なことではない、ということにものすごくエネルギーを感じたんです。当たり前に優先順位の一位が自分ではない、という人の強さ。パッションって一時的な熱量というよりは、常日ごろ、その人に宿っている自覚が物を言うのかな、と。そのときお母さんがびしょ濡れになっている、けど平然とされてるということに、母という存在のパッションを感じて、敵わないな、と思いました。自分が何に心が動くのかをしっかり捉えていないと、いざそのパッションが必要な瞬間、その熱量の持続性がないな、と思いますね」
それぞれの中にある平熱が物を言う。だからこそ、「まさかが起きたときに本性が出るじゃないですか」と齊藤。もうひとつ、昔話をしてくれた。
「若いころ、ラクーアでガラにもなくデートをしたことがあるんです。
ずっと一緒にいる前提の2人だったんですけど、高いところから一気に落ちるアクションがあって……恥ずかしいんですけど、手を繋いで上まで行ったんですよ。でも、落ちた瞬間、お互いバッと手を離したんです。もう、我が、我がという感じで。それがお互いの本性であり、それが人間だと思うんですけど、帰りは無言でしたね。そのときに理想と現実は違うな、と思いました」
齊藤は明るく笑って話を締めくくったが、作中で、賢二たち家族を本田は「理想のご家族です」と言う。しかし、現実は……。
『スイート・マイホーム』の現実を全て知ったときに、どのような思いを抱くか。ぜひ映画館で確かめてほしい。


取材・文:ふくだりょうこ 撮影:友野雄
フォトギャラリー(9件)
すべて見る