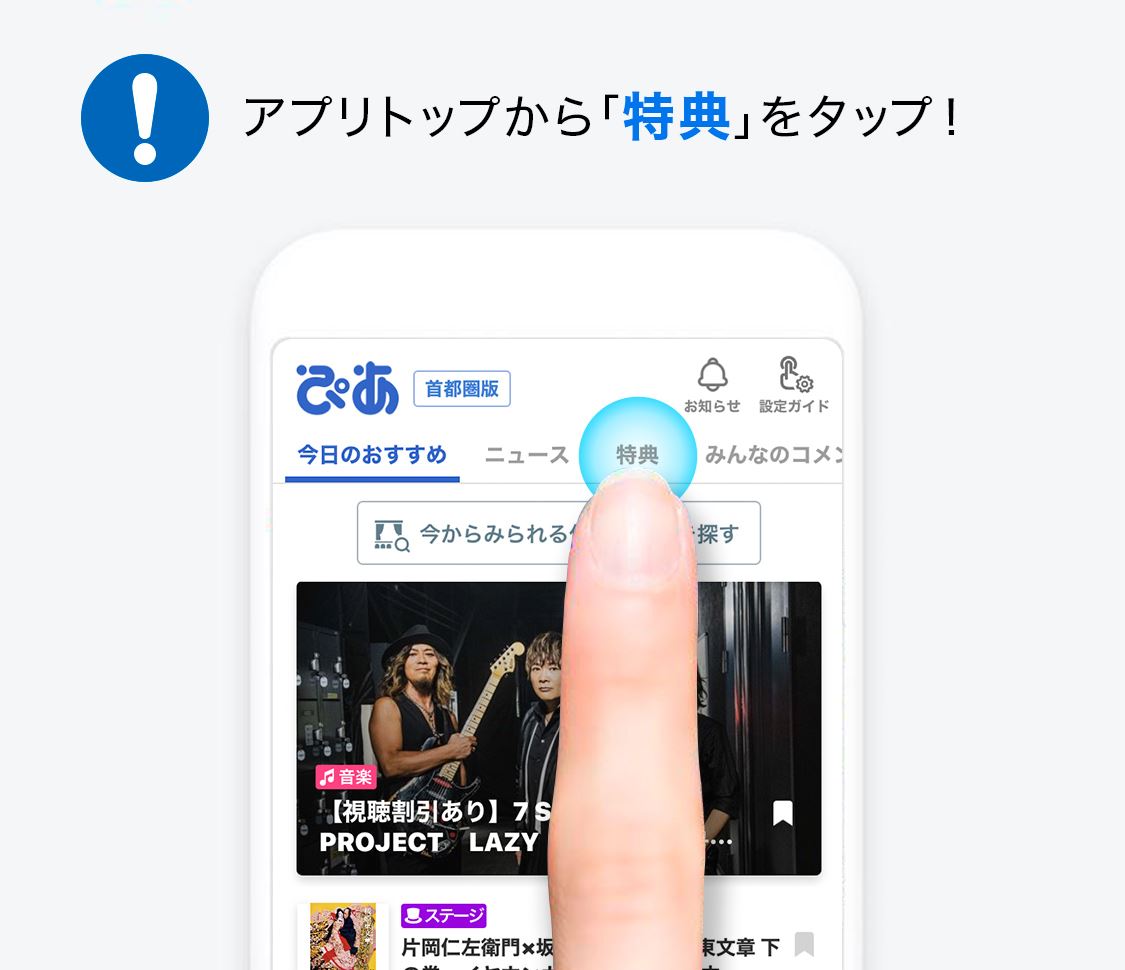矢崎広が世界恐慌の時代を生きる青年に「彼らはつらい経験もしているけど、同じくらい将来への夢もあった」
ステージ
インタビュー

矢崎広 撮影:You Ishii
続きを読むフォトギャラリー(8件)
すべて見る「幸せな演劇めぐりをさせてもらっている」と、矢崎広は言う。10代の頃に知り合った富岡晃一郎を通して「阿佐ヶ谷スパイダース」を知り、その作品を通して長塚圭史に憧れるようになった。だが長塚は自分よりも少し年長の俳優たちと組むことが多かったため、「先輩たちと作品創りをする方。自分たちは自分たちの世代で演劇を創っていくのかな」と、漠然と自分には縁のない、雲の上の人だと思っていたという。
しかし、演劇が紡ぐ縁は矢崎と長塚を結びつけた。今回、『アメリカの時計』で初めて長塚演出作品に参加することになったのだ。これまで出演してきた作品を共に創りあげた演出家たちから得たものを、矢崎は稽古場で活かして芝居を創り、長塚に提示。それを長塚が自身の創造性を通してさらに練り上げ、矢崎にフィードバックする。その循環がすごく良いものになっていると実感する、と矢崎は笑顔で語る。
そんな幸せな環境で稽古が進んでいる『アメリカの時計』は、20世紀アメリカを代表する劇作家のひとりである、アーサー・ミラーが1980年に発表した作品だ。

1920年代、アメリカは史上空前の繁栄を遂げていた。しかしその繁栄はいつまでも続くものではないと気づいたアーサー・ロバートソン(河内大和)はいち早く株から手を引き、親しい者たちに警告。だが、誰も耳を貸さなかった。果たして彼が予見した通り、1929年に株が大暴落。裕福な実業家だったモウ・ボーム(中村まこと)も財産を失ってしまい、妻のローズ(シルビア・グラブ)が宝石を現金に換えて暮らしている。そして息子のリー(矢崎広)は飢え苦しむ人々を目の当たりにしながら、自身の生き方を探すのだった……。
世界恐慌の時代のアメリカを生きる人々を描いた作品を上演するにあたって、キャスト陣には稽古開始前に長塚から課題が出されたという。第一次世界大戦後の情勢、ファシズム、株価など、各自が与えられたテーマについて調べ、皆の前で発表。キャスト・スタッフ共に知識を共有することによって、作品への理解を深めたという。

「僕のテーマは、すごく範囲が広いですが『第一次世界大戦後の光景』。図書館に行って本に目を通したりインターネットで検索したりして、第一次世界大戦とその被害、大戦後にアメリカが好景気になったのは何故か、敗戦国のドイツがとんでもない条約によって払うことになった賠償金を2010年にようやく払い終えたことなどを調べました。他の人が調べたこともおもしろかったし、そういう時間があったおかげですごく(作品に)入りやすかった。僕の中でどんどん、1920年代後半以降のアメリカの光景が本当に目の前に広がっているかのように濃くなっていると感じる。本当に面白い時代だと思いました」
話を聞くと、カンパニー各人が自身の知識と感性を総動員しているように感じる。実際、矢崎も稽古後の疲労が半端ないと打ち明ける。横浜の稽古場から都内に戻る時も、乗っていた電車の中で何度も寝過ごしてしまったそう。「『ここ、どこだ?』状態で、すごい所まで行っちゃったこともある」と思わず苦笑するのだった。

そうした経過を経ているだけに、カンパニー全体がまとまり、とても仲が良いという。しかも、稽古の合間も特に雑談はしないのだとか。「この戯曲に関連して、今の自分たちと重ね合わせた話が多いですね。『ここで起きている通貨のインフレって、これと似てますよね』と、歴史や経済の話になっているんです。もともとシルビアさん、河内さんや関谷春子さんとは面識がありましたけど、その人たちに限らず皆と話しています。大谷亮介さんも、すごく素敵な方なんですよ。ちょっと言葉で表現するのは難しい、存在自体がなんとも言えないおもしろさでいらっしゃる」と、大先輩とも良い雰囲気であることが窺える。
戯曲から受ける印象を遥かに超える舞台に
今回、矢崎が演じるのはリー・ボーム。裕福な家に生まれたが、大恐慌によって大学進学を断念することになる。「この時代を生き抜いたひとりの男として描かれていますが、彼が物語の語り手となって始まるので、彼の目線が観客と共有される。『僕は今こう感じたけど、皆さんもそう思いますよね?』という、ある意味では観客に一番近い存在かもしれません。それに対して、河内さんが演じるロバートソンが歴史的なことやいろいろな背景を述べて、リーはそれに反論することもある、という感じ」
複数の視点を観客に提供する、ある意味では象徴的な存在ともいえそうだ。だが、それでは終わらないところがこの戯曲のおもしろさだという。「物語の外にいて観客に語りかけていたはずのリーが、後半は物語の中に入っていく。どんどん感傷的になるとともに、語りの方は少なくなっていくんです。おもしろい造りだと思います」

大学入学前、つまり20歳前であるリー。矢崎は最近出演した舞台では16歳の息子をもつ父親役だったので、役柄上ぐっと若返ったことになる。「そうなんですよ(笑)。それが今、僕に求められている特徴なのかもしれないって最近思います。20歳前後から40代くらいまで幅広く演じられる役者としてとらえられていることは、とてもありがたい。そこは自分の武器として頑張っていきたいと思います」
1920~30年代のアメリカを舞台にしたシリアスな物語だけに、自然とメッセージ性も意識する。「世界恐慌を経てどんどん政策、つまり国が変わっていくなかで、彼らはどう生き抜いたのか。何を感じていたのか。まさに2023年の現在と置き換えて考えられるところが、この戯曲の魅力だと思います。『人の感情ってどう動くんだろう?』『いったい何が大切なんだろう?』と僕も考えていますし、観客の皆さんにも考えてもらいたい。リーたちはつらい瞬間もたくさん経験しているけど、同じくらい将来への夢もあった。そして必死に生き抜こうとしていた。その姿は、とても魅力的です」

そうしたつらい時代を描き、13人のキャストで50名以上の人物を演じ分ける物語。ミュージカルのように歌の力でエンタテインメントにする舞台ではないので、もしかしたら難解に感じる人もいるかもしれない。だが、矢崎はそれは心配していないという。「僕と同世代、あるいは下の世代の人が観に来ても『おもしろい』と思ってもらえる自信はあります。この戯曲が描いていることを、長塚さんが細かく分けて、その一つひとつを素晴らしいキャストが本当に濃く、当時の人間の姿を浮かび上がらせるように突き詰めながら、パズルを組み立てていくかのように積み重ねている稽古です。これが完成したら、戯曲を読んだ印象の数十倍もの面白さをもつ舞台になるはず。稽古場で僕はそれを体感しているし、自信があります。ぜひ、現代の世界情勢をこれから生きていこうとしている20~30代も含めて、多くの人たちに観ていただきたいですね」

カンパニーの挑戦は、どのような形で具現化するのか。ぜひ見届けたい公演は10月1日(日)まで、KAAT神奈川芸術劇場〈大スタジオ〉にて。
取材・文:金井まゆみ 撮影:You Ishii
ヘアメイク:ゆきや(SUNVALLEY)
スタイリスト:田中トモコ(HIKORA)
衣装協力:kujaku(03・6416・4109)
<公演情報>
『アメリカの時計』
作:アーサー・ミラー
演出:長塚圭史
翻訳:髙田曜子
出演:
矢崎広 / シルビア・グラブ/中村まこと/河内大和
瑞木健太郎/武谷公雄/大久保祥太郎/関谷春子
田中佑弥/佐々木春香/斎藤瑠希 /天宮良 大谷亮介
2023年9月15日(金)~2023年10月1日(日)
会場:KAAT神奈川芸術劇場<大スタジオ>
チケット情報
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2344784
フォトギャラリー(8件)
すべて見る