那須凜×串田十二夜×串田和美 6度目の上演アイルランドの喜劇『西に黄色のラプソディ』は原点回帰のような作り方で演劇の楽しさを
ステージ
インタビュー

左から)那須凜、串田和美、串田十二夜 (撮影:坂本彩美)
続きを読むフォトギャラリー(9件)
すべて見る串田和美が2023年に立ち上げたフライングシアター自由劇場の第六回公演『西に黄色のラプソディ』。演劇作品で大活躍の那須凜を、同劇団での好演が評判の串田十二夜が迎え、若き男女の恋と騒動を演じる。串田がこの作品を上演するのは今回で6度目。その魅力と、那須も驚く稽古場の様子を3人が語る。
大真面目にいい加減なことをいう、人間臭さが面白い
──この『西に黄色のラプソディ』は、串田さんにとっては6度目の上演になります。それほど魅了されている作品なんですね。

串田和美(以下、串田) 最初に上演したのが、1975年、六本木の自由劇場でした。狭いところでしたけど、いろんなやり方で3回くらいやったのかな。そのあと、2003年からまつもと市民芸術館で活動していた間に2回上演して(串田は2003~2023年の20年間、まつもと市民芸術館の芸術監督を務めた)。自分でもこんなにやっているのはなんでだろうなと思うんだけど。夢みたいな話で、嘘と意識しないで嘘ばっかりついているような人たちがいて、アイルランドの話だけど、日本でも江戸時代の話は大真面目にいい加減なことばっかりを言ってるから、きっと人間ってこんなものだったのかなと思ったりしてね。そういう人間臭いところが面白いなと思うんです。
──今回が初参加の那須さんは、戯曲を読んでどんな感想をお持ちになりましたか。
那須凜(以下、那須) 最初に読んだときにアイルランド独特の不毛の地の風景が浮かんできたんです。荒野が広がっていてその先に高い波が打ち付けている断崖絶壁があって、そこにポツンと酒場があるというイメージが。いろんな国でロングランで上演されているのもきっと、そういう景色を浮かべずにいられない魅力が色褪せないからかもしれないなと思いました。
──そして十二夜さんは、「フェスタまつもと2021」の一環として上演された5度目の同作に出演されています。再びこの作品に触れてどんなことを思われていますか。

串田十二夜(以下、十二夜) 今回を機に、過去の自由劇場での公演の資料を見てみたんです。すると、4年前の上演はわりと戯曲に忠実にやっていたんですけど、そこに昔のチラシに原作では出てこないはずの登場人物がいたり、みんなが悲しそうな顔をして笛を吹いている写真があったり、けっこう肉付けして遊んでいたんだなと思ったんです。それで、4年前はなぜオーソドックスにやったんだろう、6回目の今回はどうなるんだろうと思いながら稽古場にきたら、4年前とはかなり変わっていて。解釈もどんどん変えていこう、新しいものを見つけていこうとしていて、稽古の仕方も違うので、すごく面白いです。
“何もない”から始まる芝居づくり
──4年前とは違うものにしようと思われたのはどういうところからですか。
串田 キャストの顔ぶれ、劇場、予算、いろいろな条件を加味していくうちに変わりました。そもそも自由劇場時代は、狭くてお金もないなかでやっている期間が長くて、何もないところから作ることが身についていますからね。今の世の中、演劇界だけじゃなくいろいろなものが高騰して大変ですけど、そのなかでまた、「何もないのか、よしわかった」という感じがよみがえってきて。結局、困ったときのほうがいいものができるという実感も自分にはありますし。極端なことを言えば、「シメた」くらいに思ってやっています。

──その何もないところから、どんな稽古が始まっているんですか。
十二夜 一筋縄ではいかないようなことを言ってくる感じがあります(笑)。
那須 そうかもしれない(笑)。
串田 その通りです(笑)。
十二夜 何かこう、収まらないようにしてくるような。
那須 私は串田さんの演出を初めて受けるんですけど、確かに串田さんが言ってくださっているのは、このセリフはこういうふうに言ってくれというような指示ではまったくなくて。もっと大きくキャラクター性を捉えていくところから最初稽古に入って、ガツンと中身から何かを変えないといけない感じがするので、すごく疲れるんですけど(笑)、それが私は楽しいです。細かくタスクをこなしていく稽古とはまた感覚が違うので。

串田 僕は本当は、演出もしたくないんだよね(笑)。時々書くこともあるけど劇作家だとも思ってなくて、役者だけやりながら、みんなで集まって、「何やろうか」「こういう話どう?」って、ワイワイ言いながらできたらどんなにいいだろうと思っているんです。だから、役者がどういうふうに挑むかっていうことにはすごくこだわっていて。今回も、今までやったことないようにしたいなとか、戸惑いからいろいろなものが生まれるから、戸惑ったところからふわっとできたらいいなと思っています。自分も戸惑うようにやっていきたいし。何しろやっぱり芝居って役者が作るものであって、それをサポートするのが演出家じゃないかなと思うんですよね。
──中身から何かを変えて作っていくという意味では、今のところどういうものが自分のなかに生まれている手応えがありますか。那須さん演じるペギーンは酒場の一人娘で、十二夜さん演じる「父親を殺した」と語る謎の男クリスティに惹かれていきます。
那須 まだまだわからないです(笑)。ただ、串田さんがおっしゃるには、ペギーンも酒場を切り盛りしているけどまだ少女で若いから、この村で生きていくことに納得しているけれども、無意識下で違う人生もあったらいいなと思っていて、よそからやって来た若くて不思議な男の子にピュアに惹かれていく。だから、ただお父さんを殺したクリスティを英雄視する面白さだけではなくて、どこにどう惹かれていくのかというのは、作っていきたいなと思っています。
十二夜 クリスとしても、ずっとお父さんとふたりで暮らしていて、初めてよその村に行っていろいろな人に出会って、すべてが初めての経験なので。そこを自分の初めての体験を思い出しながら作っている段階です。
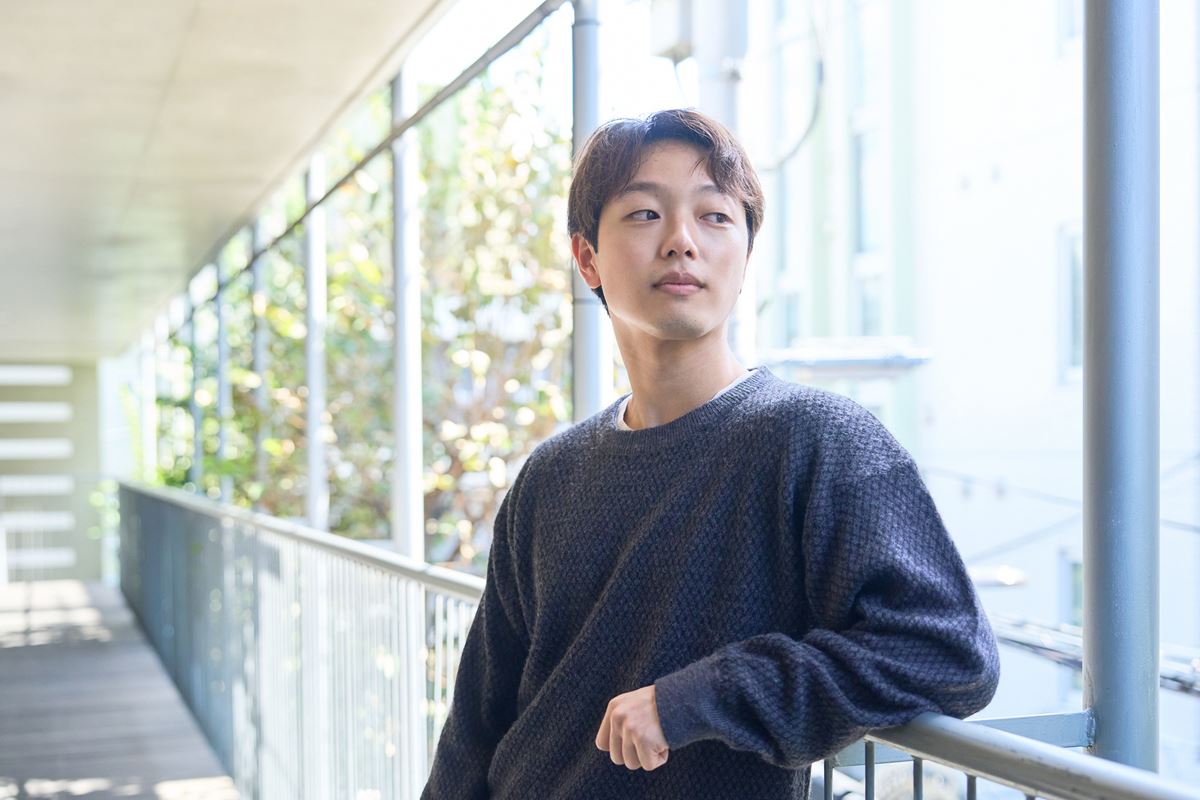
那須 最初読んだときは、お父さんを殺したというクリスが変な人だと思っていたけど、村の人たちも変なんですよね(笑)。クリスは意外とまとも……でもないけど。
十二夜 正直に生きているというか。
那須 素朴。
十二夜 だから、稽古が始まってから気づきました。クリスがベースとなるんじゃなくて、こんなにも周りの人間のリアクションに動かされ、環境でいろいろ変わってしまうんだって。その周りによってこの若い男女がどう成長していくのか、成長しないのかもしれないですけど、そんな青春的な要素もあるので。100年前に書かれたアイルランドの物語のクリスと、日本で生まれ育った2025年の自分とは全然違いますが、こんなときもあったなと、そこに面白さを出せそうな気がしています。
豊かな稽古場で「ノスタルジー」を感じられる芝居に
那須 串田さんが「ノスタルジーをテーマにしたい」とおっしゃっていましたね。
串田 そう。知らないことなのに、経験したことないのに、「懐かしいな」と感じることってあるじゃないですか。何百年も前の、もっと昔の、人間がまだちゃんとした哺乳類になる前から遺伝子のなかに持っているものが、ひゅっと出てきてゾクゾクとしたりして。たぶん、ノスタルジーのなかには、夢とか、嘘とか、もう少しのんびりしたいとか、証拠はないけどそんな人がいた気がするとか、本来の人間って何だったのかというようなものがあると思うんですけど。望むと望まざるとにかかわらずものすごい速さで科学的なものが進んでしまっている今だからこそ、そういうノスタルジーを感じられる芝居になるといいなと思っているんです。
──そのノスタルジーな空気は稽古場にもありますか。

那須 串田さんや大森博史さん、真那胡敬二さんといった先輩方がいろいろな話をしてくださるんです。俺たちの時代には、町に変なおじちゃんやおばちゃんがいたのが当たり前だったとか。それが作品の世界観のイメージを広げてくれて、個性的な村人たちも当たり前にいると思えてくるんです。ただ、そのお話が始まったときは、4時間くらい話続けていたのでびっくりしましたけどね。このまま稽古せずに雑談で終わるのかなって(笑)。
十二夜 最後ちゃんと演劇の話につながって良かったですよね(笑)。でも、この人たちには世間話と演劇が地続きで境界線がないんだ、それは豊かなことだなと感じました。
串田 僕の稽古場はそういうことがしょっちゅうあるんです。「そろそろ始めましょう」と言われるんだけど、「さっきからもう始まってるんだよ」と(笑)。そりゃあ戸惑うよね。
──串田さんが立ち上げられたこの「フライングシアター自由劇場」が、「飛ぶようにさまよいたい」というところから名付けられているのですから、さまよい戸惑いながら作られるのも当然と言えますね。
串田 さまよって、「行き場所どっちだっけ?」とか言っている感じが好きで。幕が開くまで毎回ダメかもしれないと思うんだけど、そのダメかもしれないものにしか興味がないというか、価値がないような気がするんです。設計図があってその通りに進むよりも。
十二夜 初めてフライングシアターに出た作品が仮面劇(『仮面劇・預言者』)だったんですけど、初日に僕仮面のなかで泣いちゃったんです。怖すぎて。今思い出しました。
那須 何が怖かったの?
十二夜 どうなっちゃうのか、本当にわからなくて。でも、「すごく好きだ」って言ってくれた人もいたので、やって良かったな、怖いのもいいなと思いました。
──若い世代は正解を欲しがると言われていますが、その点はいかがですか。
十二夜 答えがあることを用意されすぎて、逆にそれに抗いたい気持ちも今は大きいんじゃないかなと思います。例えば、Google MAPで行き方を示されすぎて、そうじゃない道を行きたいという気持ちはまた上がってきているんじゃないかなと。そういう意味では演劇は、観客として観ていても、正解もないし早送りもできないし、とても魅力的だなと思います。

──那須さんは改めて、今回の稽古からどんなものを得ておられるでしょうか。
那須 一言では言えないですけど。でも本当に、「ダメかもしれないけどそれがいい」みたいな気持ちになってきていて。例えば小道具も、用意されていてこれ使ってくださいではなく、この状況だったらどういう動きになったらいいのか、どういうものが欲しいのかということから考えていく。だから、ものづくりの、演劇の、原点に回帰している感覚に近いかもしれません。
串田 ただ、稽古の仕方も自分でルールを決めてしまいたくないから、次に誘ったときはまた違うやり方をするかもしれないよ(笑)。
──串田さんにとっての演劇の楽しさを最後にお聞きできたらと思います。
串田 だいたいいつも、幕が開いてお客さんがわーっと反応してくれたときに、こういう芝居だったんだと思うんです。霧が晴れて、あーこんな山の頂上にいたんだとか、こんな海のなかにいたんだと思う。霧が晴れるまでは怖いんですよ。どこにいるのかわからなくて迷子にもなる。でも、言葉も通じない国で迷子になったこともあとで笑い話になったりするのと同じ。迷って、そして霧が晴れて、「そうそう、最初からこうだったんだよ」と思う(笑)。それが全部楽しい。

取材・文:大内弓子 撮影:坂本彩美
<公演情報>
フライングシアター自由劇場 第6回公演
『西に黄色のラプソディ』
原作:J.M. シング『The Playboy of the Western World』
脚色・演出・美術:串田和美
出演:
那須凜/串田十二夜/内田健司
井内ミワク/竹口龍茶/反町鬼郎
さとうこうじ/真那胡敬二/大森博史
串田和美/銀粉蝶
2025年10月20日(月)~27日(月)
会場:東京・吉祥寺シアター
チケット情報:
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2559937
フォトギャラリー(9件)
すべて見る
