世界を席巻する映画『石門』は何を描くのか? 監督が語る

映画『石門(せきもん)』は、望まない妊娠をした女性リンの物語だ。彼女は診療所を営む両親が死産の責任を追求されて賠償金を迫られていることを知り、死産させてしまったという母の訴訟相手に、自分の子供を提供し“賠償金の代わり”にすることを思いつく。
先の読めない物語と、主人公の身体の変化、その痛みを描いた本作は、世界の映画祭を席巻し高評価を獲得している。監督を務めたホアン・ジーと大塚竜治は創作の過程で何を考えたのだろうか?
── この映画は、考えれば考えるほどに“不釣り合い”なことがたくさん起こる、観終わっても想像の膨らむ作品でした。劇中で主人公の両親は、死産の責任を追求されていますが、冷静に考えると“人間の命に見合う償い”は存在しません。しかし、主人公はその償いに自身の子を差し出そうとする。その一方で、彼女は身ごもり、自身の人生に大きな変化が生じています。このことで彼女がどれだけのものを失ったのか? それは両親の賠償に見合うものなのか? 経済の世界では、ふたつのモノの価値が“釣り合った”時に取引が成立します。しかし、彼女はそんな世界でずっと“不釣り合い”なやりとりに晒され続けています。
大塚監督 中国では日本と違って選択肢があまりないんです。単純に考えると選択肢が多い方が自由だと思うんですけど、中国だと選択肢がひとつしかない状態で、全員がそこに向かって進んでいくので“不釣り合い”が発生してしまう。日本だと、それぞれの人が置かれた状況に対応する選択肢が出てくる。選べるレールが次々に生まれ、選択肢が増えることで“不釣り合い”がなくなっていくんだと思います。
『石門』に登場する人たちも、みんな目的はひとつだと思うんです。いまの暮らしを楽しくしたい。幸福に安心して暮らしたい。でも、リンは妊娠をしてしまい、生まれてくる子をどうにかしなければならない。彼女の両親は賠償金を支払わなければならない状況にある。他に選択肢がない状況に追い込まれてしまうことで、“不釣り合い”が生まれてしまう。そう考えると、社会全体の状況が、この家族に凝縮されているような気がします。
ホアン監督 この映画を撮っている最初の頃、私は“主人公がどれぐらい稼ぐことができるのか?”そのお金の額を知りたいと思っていましたし、そのことを作品の中で表現したいと思っていました。でも、大塚さんはそうは考えていませんでした。
大塚監督 そうですね。

ホアン監督 彼は「それは重要なことではない。なぜなら、この映画は経済を語るものではないから」と言うんです。劇中で主人公の母を演じているのは、私の実の母なのですが、この母親は劇中でマルチ商法のようなことに手を染めていて、私は最初、この母親がそんな商売をするのはお金を儲けるためだと思っていました。
でも、私は大塚さんと話をしている時に気づいたんです。この母は単にお金を稼ぐためにマルチ商法をやっているのではなくて、自分の“楽しみ”のためにやっているんだと。
私たちはカメラの前でいま起こっていることに注目して撮影をします。それはつまり、あらかじめ設計されたものを撮る、最初に考えて、脚本に書いたものを撮るのではなく、目の前に思いがけないものがそこに現れて、それを捕まえることだと思うのです。
── おふたりが手がけた『卵と石』『フーリッシュ・バード』、そして『石門』もすべて経済的な繁栄やテクノロジーの発展が背景に描かれ、主人公の周囲の大人たちは“安定した結果が望める取引”や"予測を裏切ることのない数値をベースにした行為”を求めては裏切られる様子が描かれます。一方、主人公はいつも不安定で、先の見えない状況に置かれている。
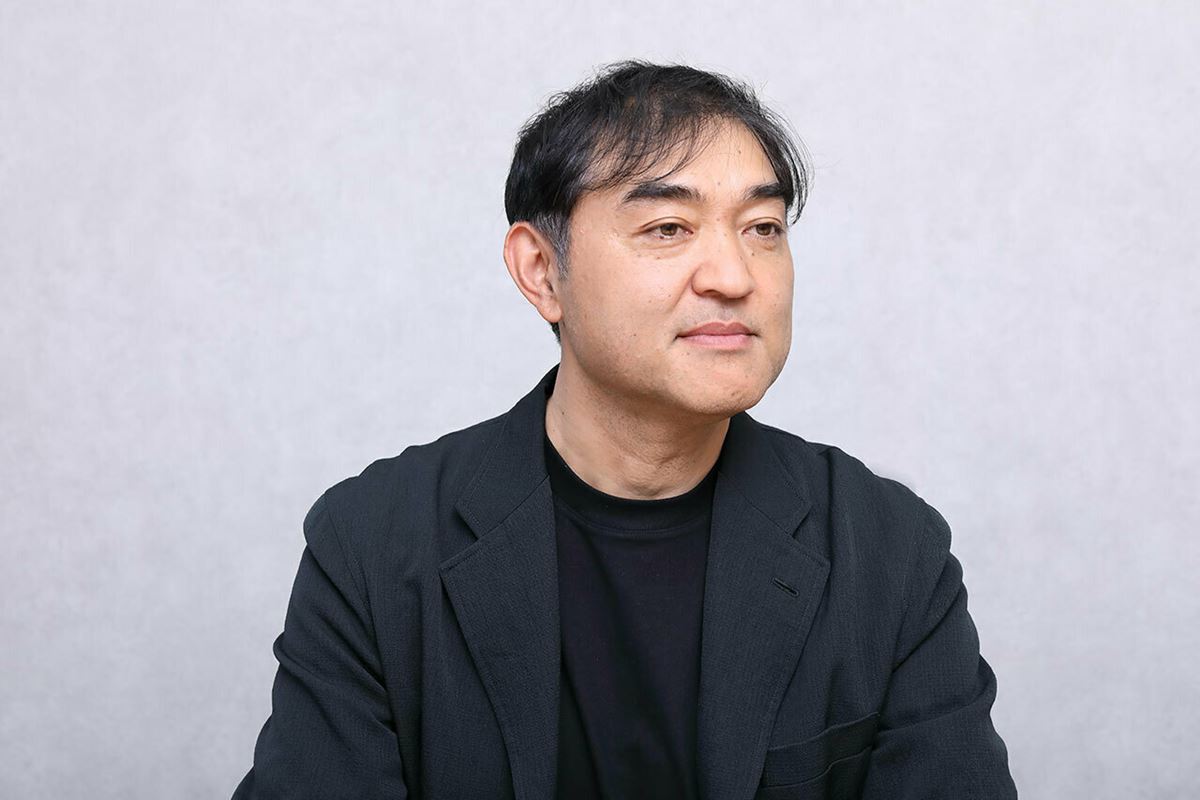
大塚監督 そのことは常に意識しています。中国では変化があまりにも早いので、安定というものが存在しないんです。テクノロジーの点でいうと、中国は各家庭に固定電話が普及するよりも先に、携帯電話が普及してしまった。
── 日本であれば固定電話が普及し、ある程度状況が“安定”した後に、携帯電話が個人に普及しました。
大塚監督 中国では一度も安定した状況がないままに携帯電話がやってきたわけですから、それは不安定ですよね。何かしらの答えが生まれるよりも先に 前提となる状況が変わってしまうわけですから。日本だとそんなことは起こらないですけど、中国にいるとその状況が目に見えてわかるので、可能な限り、その“不安定さ”は映画の中に取り入れていきたいと思っています。

── 主人公が不安定で、周囲から“はじき飛ばされている”感覚は、画面の構図にも現れています。『石門』では主人公のリンは常に広い空間の中にポツンと置かれていて、彼女の前や後ろを誰かが横切ったり、彼女のことなどお構いなしに行動していたりします。まるで彼女だけが取り残されてしまったようです。
大塚監督 そうですね。本作に関してはまず最初に“10か月撮影する”というプランがあったので、統一感を出すために固定カメラで、俳優と距離を置いて撮影しようと決めていました。というのも、10か月も撮影するわけですから、この先に何が起こるのかわからないわけです。だから俳優とは距離をとって、フルショットの空間の中に彼女を置く。カメラが彼女に寄ってしまうと、彼女の抱えている感情にも寄ってしまうことになるので。
僕たちは撮影すると、撮ったものをすぐに編集して、それを観ながら次のシーンについて考えるんですけど、そうした行為を積み重ねることで、彼女が“取り残されている”感覚が出てきました。さらに言うとこの映画では物語ではなく、主人公を演じたヤオ・ホングイの演技のリズムで編集しています。そのことでこれまで以上に彼女が“取り残されている”感覚が出てくることになりました。

ホアン監督 ふたりで監督している作品については画面づくりはすべて大塚さんにお任せしていて、私は演技指導などの面を担っています。『石門』については、私は俳優にカメラをもう少し寄せたいという気持ちがありました。撮影時、私たちとヤオ・ホングイ、そして彼女の両親を演じた私の両親は共に生活していましたから、私としては自分の身近な人間をもう少し寄って撮りたい、彼らを“美化”して撮りたいと思ったわけです。でも、そのアイデアは大塚さんに却下されました(笑)。
大塚監督 はい。しましたね(笑)
ホアン監督 彼は客観的な位置にカメラを置くことを主張したわけです。でも、映画が完成してわかりました。彼が正しかったんです。
── ヤオ・ホングイを主演に迎えた3作品は彼女の孤独感や、それを見つめる距離など共通するものを感じます。
ホアン監督 そうですね。ヤン・ホングイという俳優の向かっていく世界を同じ視点から見つめ続ける。それがこの3作品の変わらない姿勢だと思います。2012年に『卵と石』を発表し、2022年に『石門』を作り上げるまで10年かかりました。この10年というのは、オリンピック(2008年の北京五輪)を経験した中国に急激な変化が起こった時代です。そして、私たちはヤン・ホングイが12歳の時に最初の映画を撮影し、続いて彼女が17歳の時に2本目を、そして22歳の時に『石門』を撮影しました。この10年はヤン・ホングイが急激に成長し、変化していく時代でもあったわけです。
私は北京電影学院で映画を学んだのですが、そこでは“テーマがあるから映画をつくる”と教えられてきました。でも、私はテーマというのは、どこか説教くさいし、宗教の教えのようなイメージを抱いています。私はテーマよりも、日本語でいう……ソンザイ? 合ってる?
大塚監督 そう。「存在」
ホアン監督 「存在」という言葉が好きなんです。誰にも知られていない存在や、誰にも知られていなかった人、誰にも思われることのなかった感情、そういうものを発見することに興味があるんです。
大塚監督 それはふたりに共通する考えですね。

映画『石門』は、驚異的なスピードで変化していく社会や、そこで苦しむ人々、高い壁のようなものに囲まれてしまった女性の姿を描いているが、何かを訴えようとしたり、議論を挑んでくるような作品ではない。
本作が描くのは、苦境に立たされても何とか生きようと懸命に生きている女性の姿だ。選ばれた人間でも特別な人間でもない、客席にいる者と同じ毎日を一生懸命に生きている人間の姿。本作はそんな小さく、しかし力強い“存在”を鮮やかに描き出している。



