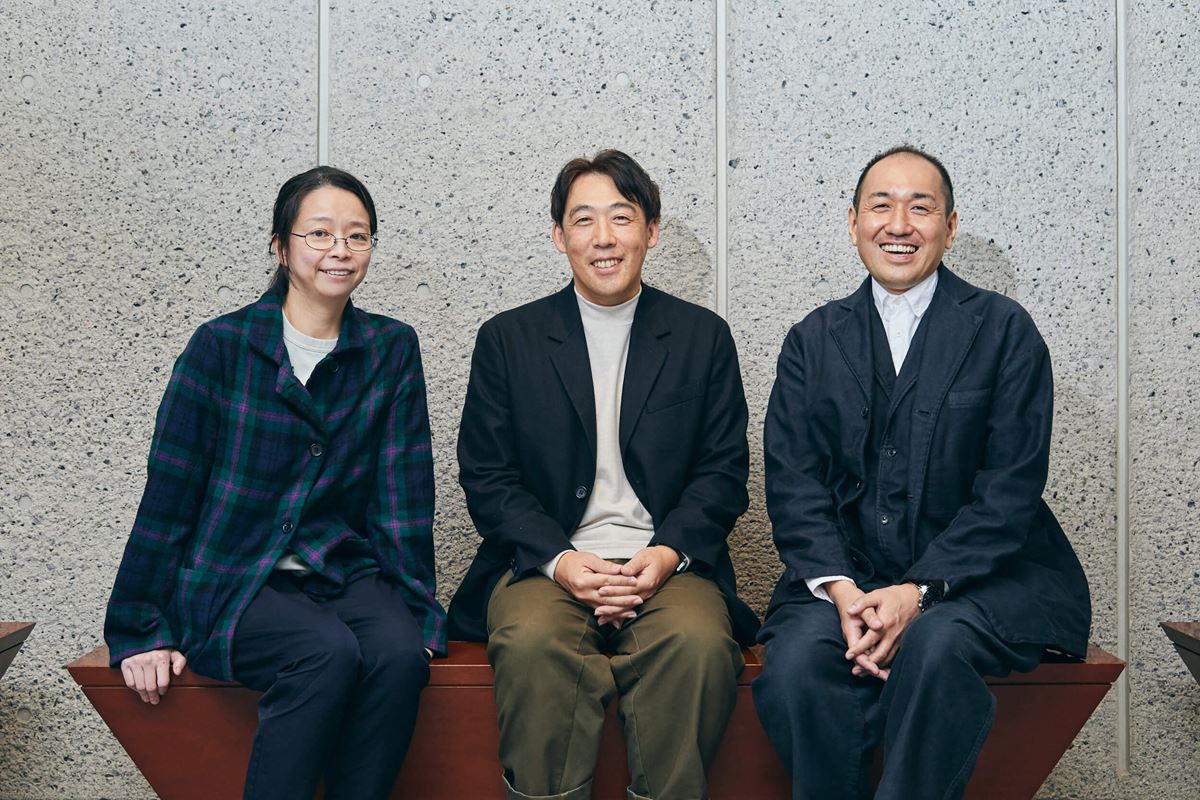『デカローグ』舞台化の裏側に迫る!
第2回:小川絵梨子×上村聡史×石川慶インタビュー【後篇】
ポーランドの鬼才クシシュトフ・キェシロフスキが遺した『デカローグ』の完全舞台化に向けて、演出を担う小川絵梨子と上村聡史、そして多くの映画ファン同様にキェシロフスキに魅了され、本作を「教科書のような存在」と話す映画監督・石川慶の3名が、本作の魅力や舞台化への期待、構想を前後篇に渡って語り合います! 【後篇】は、石川監督も大きく影響を受けたという「視点」について
絶望的な状況だからこそ、俯瞰した視点に救われる
── 原作では、時に理不尽とも言えるような出来事が、前触れや論理的な説明もなく描かれている部分が多いですね。
小川 1話の「ある運命に関する物語」の結末の部分で起こる出来事に関しても、脚本の第一稿の段階では「なぜ?」という部分が詳しく書いてあるんですけど、実際の映像ではカットされているんですね。おそらく、キェシロフスキが描きたかったのは「説明のつかない理不尽なことが起こりうる」ということだったんでしょうね。
石川 キェシロフスキがドキュメンタリー作家だったという部分も大きいのかもしれません。ただ家族の姿を撮っているだけで、いろんなことが起こるけど、それをいちいち説明しない。脚本家として「なぜ」という部分は書いても、彼自身はそこに興味はなかったんだろうなと。
小川 石川監督の作品もそうですよね。『ある男』(2022年)のラストに関しても、監督の中で答えがあるけど、それをあえて表現しないし、観る側も想像するのが楽しかったりもしますよね。
── 『愚行録』(2017年)でも、人間の欲望など、生々しい感情が描かれてはいるんですけど、それをどこか俯瞰した視点で見つめているように感じます。
石川 視点の置きどころという部分でキェシロフスキに影響を受けているところはすごくあると思います。『愚行録』も『ある男』も悲惨なことや絶望的なことが起きたりするけど、それをグーッと引いた視点で切り取る── 感情移入だけが正解ではなくて、どこかでスパンっと視点を変えるという意識はありました。

キェシロフスキは常にそういう視点を持っていて「安易に感情移入してちゃダメだ」「そんなんでわかった気になるなよ」と言われてる気がするんですよね。絶望的な状況に置かれている人間に対して、泣いて終わりじゃない。でも「意外とそこまで大した問題じゃないのかも……」という、ある種の救いというか、ちょっと気持ちが楽になったり、どこか温かささえも感じるものがあって、それは僕自身、物語を語る上で、大事な部分だと思っています。
小川 石川監督の作品は、引きの画面が冷たくないんですよね。決して「一度、引いて客観視しましょう」という感じではなく、持続した温かみを持っていて、それがすごく不思議なんです。
石川 その意味で『デカローグ』の1話の終わり方というのは、インパクトのある結末だけど、僕自身はすごく救いを感じるんです。
小川 1話のエンディングをどう見せるかというのは、すごく悩んでます(苦笑)。どこまで“手ざわり”の感触を伝えるべきか……。
石川 始まりの1話だからこそ、全てを見せなくてもいい気がして、あのモヤモヤが残る感じ──僕自身、ポーランドで1話を観た時は、自分が知っている物語というものとは違う何とも言えない変なものを見せられた感じがすごくあって、それが続きを見る原動力にもなった気がします。
── 「視点」ということに関して、上村さんは6話「ある愛に関する物語」の演出について、トメク(田中亨)とマグダ(仙名彩世)というふたりの主人公に加えて、トメクが一緒に暮らしている年配の女性(名越志保)の視点を新たに加えて描くとおっしゃっていました。
上村 トメクが向かいに住むマグダの部屋をのぞき見るという行為を通して、それがいつの間にか反転し、良心の呵責が愛へと変容していくお話です。原作では物語の途中でトメクの視点からマグダの視点に切り替わるんですが、この女性(※トメクの友人の母親)がその大事な架け橋になっている気がするんですよね。そこで原作脚本を読み返したら、この女性のシーンが映像ではカットされていたんです。舞台芸術として、“のぞき”から“愛”へとこの物語を結実させる上で、より深みを加えるために、そのシーンを復活させました。

演劇の強みって、やはり発語をお客さんがその場で感じ取れるという部分だと思うので、脚本でカットされたけど、面白い部分はそれ以外のエピソードでも復活させています。
小川 シーンを加えるということで言うと、私の担当の5話「ある殺人に関する物語」で、弁護を担当した青年の死刑判決を受けて弁護士がラストシーンで「I hate!(憎む)」と叫ぶんですね。これについて全く説明がないので「これは映像でしかできない」と思っていたんですが、実はあのシーンは草原で、死刑判決を受けた青年の妹が事故で死んだ場所を弁護士が訪れているという場面なんです。もし妹の事故がなかったら、彼は殺人を犯すことはなかったんじゃないか? という思いから、その理不尽さを憎んでいるんじゃないかと。
そこは脚本の須貝さんに「ここは草原なんです」とお伝えして、鳥のさえずりを加えるなど、解釈を踏まえて描くという形にしています。感情の部分ではなく、物語を伝える上で、演劇だとどうしても説明を加えなくてはいけない部分も出てくるので……。
上村 補助線を引くという感じですよね。
石川 そこはまさに映像と演劇の違いですごく面白いですね。映像はもう一度、観ることもできますからね。
上村 ただ、最初は「映像なら一発でわかるけど、それを演劇でどうやって描くのか……?」と悩んでいた部分も、それを逆手に取るというか、全く新しい発想が出てきたりもするんですよね。最近は、その作業がすごく楽しくなってきました(笑)。
20~30年は持つ「本棚に長く置ける作品」
── 映像メディアと演劇の表現の違いに関して、石川監督はどのように感じていますか?
石川 例えば映画『イニシェリン島の精霊』(2022年)のような、舞台出身の方(マーティン・マクドナー)が作った映像作品を見ると、ビジュアルによる解決法が、自分の引き出しとは全く違うところから出てくるような感じがあって、僕は演劇の人間が作る映像にものすごいジェラシーを感じますね。「フレームを切る」というのとは違ったビジュアライズをされている人間だからこその解決法なんだろうなと感じます。ふたりは、今回のように映像作品を舞台にする上で、映像が邪魔になることはないんですか?
小川 『デカローグ』に関しては、全然ないですね。言葉がしっかりと引き算されているので、映像があることで、むしろシーンが作りやすいです。ビジュアルに影響されたり「寄せよう」と考えるということはないんですが、シーンの理解という点で、先ほどの5話の弁護士の叫びもそうですけど、映像があることが助けになっていますね。

上村 舞台ならではの表現を目指したいので、あまり参考にすることはないのですが、ただ細かいディティールというか生活感みたいな、例えば当時のポーランドの牛乳を運ぶ箱ってどんな形だったのか? とか、そういうのは参考にはしています。
逆輸入パターンといいますか、『DUNE/デューン 砂の惑星』のドゥニ・ヴィルヌーヴが『灼熱の魂』という映画を撮っているんですけど、もともとはワジディ・ムワワドによる戯曲なんです。僕は日本版の舞台『炎 アンサンディ』(2017年)の演出をさせていただいたんですが、もとの戯曲では具象的なト書きや背景が一切書かれておらず、神話的なタッチや構成で描かれていている。でもヴィルヌーヴは映画を中東で撮影をして、その風情をしっかりと描いているんです。自分が舞台にする時は、映像の絵を参考にレバノンの雰囲気や砂漠の質感を表現するのにすごく助けになりました。
── 最後に演出のおふたりから『デカローグ』を楽しみにされているみなさんにメッセージをお願いします。
上村 長く自分の心に残ってくれる作品になると思います。日常の中で「もっと楽にいればいいんだ」とか「ここは流されちゃいけない」とかいろんなことを考えさせられて、20~30年は持つ作品、見応えのある、本棚に長く置くような作品になると思っておりますので、ぜひ劇場に足を運んでいただければと思います。
小川 ある種、実験的な試みですが、長期にわたり、素敵な俳優さんたちとじっくりと10話を作っていけることを嬉しく思っていますし、約3か月をかけてお客さまと一緒に『デカローグ』という旅をできるということは、本当に贅沢なことだと感じています。決して難しい話ではないので、人間に寄り添っていく10の物語を楽しんでいただけたらと思います。
取材・文:黒豆直樹 撮影:坂本彩美
『デカローグ 1~10』
2024年4月13日(土)~7月15日(月・祝)
会場:東京・新国立劇場 小劇場
https://www.nntt.jac.go.jp/play/dekalog/